
гҒӮгҖңгҒҠ

гӮўгғјгӮӯгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ(гҒӮгғјгҒҚгӮ”гҒүгғјгӮӢгҒЁ)
archivoltгҖӮйЈҫгӮҠиҝ«зёҒпјҲгҒӣгӮҠгҒ¶гҒЎпјүгӮўгғјгғҒгҒ®еүҚйқўгҒӘгҒ„гҒ—еҶ…йқўгҒ®з№°еһӢпјҲгғўгғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјүгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮзү№гҒ«гҖҒдёӯдё–гҒ®ж•ҷдјҡе ӮгҒ§гҒҜгҖҒжӯЈйқўжүүеҸЈгҒ®гӮўгғјгӮӯгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҒҜеҪ«еҲ»гҒ§иұҠгҒӢгҒ«йЈҫгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гӮўгғјгӮӯгғҲгғ¬гғјгғ–(гҒӮгғјгҒҚгҒЁгӮҢгғјгҒ¶)
architraveгҖӮгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮўгҒ®жңҖдёӢйғЁгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢж°ҙе№ігҒ®йғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«й–ӢеҸЈйғЁгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫз”ЁгҒ®жһ зө„гҒҝгӮ’гҒ•гҒҷгҖӮ

гӮўгғјгӮұгғјгғү(гҒӮгғјгҒ‘гғјгҒ©)
иӢұ/arcadeгҖӮжҹұгҒ§ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгӮӢйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгӮ„ гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҒқгӮҢгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹеҗ№ж”ҫгҒ—гҒ®йҖҡи·ҜгӮ„жӯ©йҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ
гӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ®гҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒЁгҖҢеҒҙе»ҠгҖҚгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢеҲ—жҹұзҫӨгӮ’гҖҢгӮ°гғ©гғігғүгғ»гӮўгғјгӮұгғјгғүгҖҚгҒЁвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ„гӮўгғігғүгӮҜгғ©гғ•гғ„йҒӢеӢ•(гҒӮгғјгҒӨгҒӮгӮ“гҒ©гҒҸгӮүгҒөгҒӨгҒҶгӮ“гҒ©гҒҶ)
arts and crafts movementгҖӮ19дё–зҙҖеҫҢжңҹгҒ«иӢұеӣҪгҒ§иҲҲгҒЈгҒҹе·ҘиҠёйҒӢеӢ•гҖӮW.гғўгғӘгӮ№гҒҜгҖҒе·ҘжҘӯз”ҹз”ЈгҒ®зө„з№”гҒ«жҠөжҠ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжүӢе·ҘдҪңгҒ®еҫ©жҙ»гӮ’дё»ејөгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҮӘгӮүP.S.гӮҰгӮ§гғғгғ–гҒЁе…ұеҗҢгҒ—гҒҰиҮӘе®…гӮ’гҒӨгҒҸгӮҠвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ«гғҮгӮіж§ҳејҸ(гҒӮгғјгӮӢгҒ§гҒ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Art DД“coгҖӮ1925е№ҙгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгғ‘гғӘдёҮеӣҪиЈ…йЈҫзҫҺиЎ“еҚҡиҰ§дјҡгҖҚгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«гҒ—гҒҰжөҒиЎҢгҒ—гҒҹж§ҳејҸгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒгҖҢгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгҖҚгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒ欧е·һгҒҠгӮҲгҒізұіеӣҪгҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгӮ’дёӯеҝғгҒ«1910е№ҙд»Јдёӯи‘үгҒӢгӮү1930е№ҙвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјж§ҳејҸ(гҒӮгғјгӮӢгҒ¬гғјгӮ”гҒүгғјгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Art NouveauгҖӮ19дё–зҙҖжң«гҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒ欧е·һгҒ®еҗ„ең°гҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹиҠёиЎ“ж§ҳејҸгҖӮгҒ“гҒ®еҗҚз§°гҒҜгҖҒ1896е№ҙгҒ«зҫҺиЎ“е•Ҷгғ“гғігӮ°гҒҢгғ‘гғӘгҒ«гҖҢгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгҒ®еә—гӮ’й–ӢгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢвҖҰвҖҰ

зӣёжұәгӮҠ(гҒӮгҒ„гҒҳгӮғгҒҸгӮҠ)
жқҝгӮ’ејөгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒд№ҫзҮҘгҒ—гҒҰгӮӮйҡҷй–“гҒҢгҒӮгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҡЈгӮҠеҗҲгҒҶжқҝгҒ®еҺҡгҒҝгӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢеҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮжҺҘеҗҲгҒҷгӮӢжңЁжқҗгӮ’еҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣёж¬ гҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гӮўгӮӨгғ«(гҒӮгҒ„гӮӢ)
aisleгҖӮеҒҙе»ҠгҖӮж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүж–јгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒ®дёЎеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢзҙ°й•·гҒ„е»ҠдёӢзҠ¶гҒ®йғЁеҲҶгҖӮ

й–јдјҪдә•еұӢгғ»й–јдјҪжЈҡ(гҒӮгҒӢгҒ„гӮ„гғ»гҒӮгҒӢгҒ гҒӘ)

жҳҺйҡңеӯҗ(гҒӮгҒӢгӮҠгҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)
зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢйҡңеӯҗгҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҢжҳҺйҡңеӯҗгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒҢгҖҒе…ғгҒҜгҖҢиЎқз«ӢпјҲгҒӨгҒ„гҒҹгҒҰпјүгҖҚгӮ„гҖҢиҘ–пјҲгҒөгҒҷгҒҫпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзӨҫж®ҝгҒ®дёЎи„ҮеҘҘгҒ«й…ҚгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢи„ҮйҡңеӯҗгҖҚгҒ«гҒқгҒ®еҗҚж®ӢгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
еҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒвҖҰвҖҰ

гӮўгӮҜгғӯгғҶгғӘгӮӘгғі(гҒӮгҒҸгӮҚгҒҰгӮҠгҒҠгӮ“)
akroterionгҖӮгғҡгғҮгӮЈгғҡгғігғҲгҒ®й ӮйғЁеҸҠгҒідёЎеҒҙгҒ®дёӢз«ҜгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢеҪ«еғҸгӮ„иЈ…йЈҫгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҸ°гҖӮгҒҫгҒҹеҪ«еғҸгӮ„иЈ…йЈҫгҒҠгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ

дёҠеңҹй–Җ(гҒӮгҒ’гҒӨгҒЎгӮӮгӮ“)
е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгҒҹй–ҖеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮ2жң¬гҒ®еҶҶжҹұгҒ®дёҠгҒ«еҶ жңЁгӮ’ж°ҙе№ігҒ«йҖҡгҒ—гҖҒз”·жўҒгҒЁеҘіжўҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеұӢж №гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒе№ігӮүгҒӘеұӢж №гҒ®дёҠгҒ«гҖҒеңҹгӮ’и’ІйүҫеһӢгҒ«д№—гҒӣеұӢж №еӢҫй…ҚгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮеұӢж №гҒ®дёЎз«ҜгҒ«гҒҜжҹ„жҢҜжқҝгҒҢгҒӨгҒҸгҖӮеҫҢдё–гҒ«гҒҜеӢҫй…ҚгҒ®з·©гҒ„жӘңвҖҰвҖҰ

жҸҡиҰӢдё–(гҒӮгҒ’гҒҝгҒӣ)
дё»гҒ«й–ўиҘҝгҒ®з”әеұӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒҝгҒӣгҒ®й–“гҒ®жӯЈйқўгғ»и»’дёӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҹұеӨ–еҒҙгҒ«и»ёеҗҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзёҒеҸ°гҖӮзёҒеҸ°гҒ®е№…гҒҜеҚҠй–“гҖҒй•·гҒ•гҒҜ1пҪһпј’й–“гҖӮзёҒеҸ°гҒ®и„ҡгҒҜеӨ–еҒҙгҒ®гҒҝгҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒзёҒеҸ°гӮ’гҒҫгҒҸгӮҠдёҠгҒ’гҒҹжҷӮгҖҒи„ҡгҒҢеҸ°иЈҸеҶ…гҒ«еҸҺгҒҫгӮӢгҖӮеӨ§жҲёгӮ„еҮәж јеӯҗгҒ®жЁӘвҖҰвҖҰ

и¶ій§„ж¬ (гҒӮгҒ—гҒ гҒҢгҒ’)

йЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜж§ҳејҸ(гҒӮгҒҷгҒӢгғ»гҒӘгӮүгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
ж•ҷ科жӣёзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒд»Ҹж•ҷдјқжқҘгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒдёӯеӣҪгҒ®е”җгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢе»әзҜүж§ҳејҸгҒҢж—Ҙжң¬гҒ«з§»е…ҘгҒ•гӮҢе§ӢгӮҒгҒҰгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§еӣҪйўЁеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸйҒҺзЁӢгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒз·ҸгҒҳгҒҰгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйЈӣйіҘгӮ„еҘҲиүҜгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҒ«гҒҜвҖҰвҖҰ

гӮўгӮ№гғҲгғ©гӮ¬гғ«(гҒӮгҒҷгҒЁгӮүгҒҢгӮӢ)
astragalгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘеҚҠеҶҶеҪўгҒ®зӘҒеҮәгҒ—гҒҹз№°еһӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҖҢгғҲгғ«гӮ№гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гӮўгғҶгӮЈгғғгӮҜ(гҒӮгҒҰгҒғгҒЈгҒҸ)
atticгҖӮеұӢж №гғ»дёҠеұӢгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«еұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгӮўгғҶгӮЈгӮ«гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒдё»иҰҒгҒӘ гӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў гҒ®дёҠйғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹдёӯпј’йҡҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйғЁеҲҶгҖӮ

гӮўгғҲгғӘгӮҰгғ (гҒӮгҒЁгӮҠгҒҶгӮҖ)
atriumгҖӮеҸӨд»ЈгғӯгғјгғһжҷӮд»ЈгҒ®дҪҸеұ…гҒ®дёӯеәӯгҒҜгҖҒзҺ„й–ўеҘҘгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹеәғй–“гҒ§гҖҒдёӯеӨ®дёҠйғЁгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгҖҢгӮігғігғ—гғ«гӮҰгӮЈгӮҰгғ пјҲеӨ©зӘ“пјүгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зёҒгҒҜпј”жң¬д»ҘдёҠгҒ®еҶҶжҹұгҒ§ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ«йӣЁгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҢгӮӨгғігғ—гғ«гӮҰвҖҰвҖҰ

гӮўгғ—гӮ№(гҒӮгҒ·гҒҷ)
apseгҖӮгғҗгӮ·гғӘгӮ« гҒ®еҶ…йҷЈйғЁгҒ®еҘҘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ–гҒ«еҚҠеҶҶеҪўгҒ«ејөеҮәгҒ—гҒҹйғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

йҳҝйғЁзҫҺжЁ№еҝ—(гҒӮгҒ№гҒҝгҒҚгҒ—гҖҒ1883пҪһ1965)
еӨ§жӯЈгҒӢгӮүжҳӯе’ҢжҷӮд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гғ»еңҹжңЁжҠҖиЎ“иҖ…гҖӮ旧姓гҒҜиҸ…еҺҹгҖӮж—Ҙжң¬жңҖеҲқгҒ®йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲй«ҳжһ¶йү„йҒ“гҒ®иЁӯиЁҲиҖ…гҖӮйҖҡз§°гҖҢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲпјҲж··еҮқеңҹпјүеҚҡеЈ«гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮеІ©жүӢзңҢдёҖй–ўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжңӯе№ҢиҫІеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҢ—жө·йҒ“еӨ§еӯҰпјүвҖҰвҖҰ

йӣЁиҗҪзҹі(гҒӮгҒҫгҒҠгҒЎгҒ„гҒ—)
йӣЁиҗҪгҒЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰең°йқўгҒҢеҮ№гӮҖгҒ®гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒйӣЁиҗҪгҒЎйғЁеҲҶгҒ«жҚ®гҒҲгҒҹзҹігӮ„гҒҫгҒҹгҒҜи»’дёӢгҒ«жІҝгҒЈгҒҰгӮҒгҒҗгӮүгҒ—гҒҹзҹізө„гҒҝгҒ®з·Ҹз§°гҖӮйӣЁжЁӢгҒ®гҒӘгҒ„жҷӮд»ЈгҒҜгҖҒеұӢж №гҒ®йӣЁж°ҙгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫйӣЁиҗҪзҹігҒ«иҗҪгҒЁгҒҷгҒӢгҖҒйӣЁиҗҪжәқпјҲгҒӮгҒҫгҒҠгҒЎгҒҝгҒһпјүгҒ§еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

дәңйә»зө„(гҒӮгҒҫгҒҗгҒҝ)
гҖҢз–ҺгӮүзө„пјҲгҒҫгҒ°гӮүгҒҗгҒҝпјүгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзҜүгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®зі»зөұгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгҖҒжҹұдёҠгҒ гҒ‘гҒ«гҖҢж–—ж ұзө„гҖҚгӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҖҒжҹұй–“гҒ®гҖҢдёӯеӮҷпјҲгҒӘгҒӢгҒһгҒӘгҒҲпјүгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢй–“ж–—жқҹпјҲгҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒҢпјүгҖҚгӮ„гҖҢиҹҮиӮЎпјҲгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹпјүгҖҚгӮ’й…ҚгҒҷвҖҰвҖҰ

йҳҝејҘйҷҖе Ӯ(гҒӮгҒҝгҒ гҒ©гҒҶ)
е№іе®үгғ»йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«жө„еңҹдҝЎд»°гҒҢжөҒеёғгҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰеӨ©зҡҮгғ»иІҙж—Ҹгғ»жӯҰеЈ«гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҜәйҷўеҶ…гӮ„йӮёе®…еҶ…гҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹд»Ҹе ӮгҖӮеҶ…йғЁгҒ«жҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®ж•ҷдё»гғ»йҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘеғҸгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮе»әзҜүзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеёёиЎҢдёүжҳ§е ӮгӮ’жәҗжөҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№вҖҰвҖҰ

гӮўгғЎгғӘгӮ«гғігғ«гғҚгӮөгғігӮ№(гҒӮгӮҒгӮҠгҒӢгӮӢгҒӯгҒ•гӮ“гҒҷ)
American RenaissanceгҖӮ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒзұіеӣҪгҒ®е…¬е…ұе»әзҜүгҒ§еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҒ§гҖҒд»ҸеӣҪгҒ®гӮЁгӮігғјгғ«гғ»гғҮгғ»гғңгӮ¶гғјгғ«гҒ§еӯҰгӮ“гҒ зұіеӣҪдәәе»әзҜү家гҒҢдёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүвҖҰвҖҰ

з¶ҫзӯӢ(гҒӮгӮ„гҒҷгҒҳ)

иҹ»еЈҒ(гҒӮгӮҠгҒӢгҒ№)
еҶ…жі•й•·жҠјгҒ®дёҠж–№гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиҹ»еЈҒй•·жҠјгҒЁеӨ©дә•гҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒ®дёҲгҒ®дҪҺгҒ„еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгҒҹеЈҒгҖӮеӨ©дә•гҒ®ж јзёҒгӮ„з«ҝзёҒгҒ®дҪҚзҪ®гҒҢжҹұгҒЁгҒҡгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢпјҢиҹ»еЈҒгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒЁгҒқгҒ®гҒҡгӮҢгҒҢзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

иҹ»з¶ҷгҒҺ(гҒӮгӮҠгҒӨгҒҺ)
жңЁжқҗжҺҘжүӢгҒ®дёҖгҖӮдёҖж–№гҒ®з«ҜгҒ«йғЁжқҗгҒ«йі©е°ҫзҠ¶пјҲиҹ»еҪўпјүгҒ®зӘҒеҮәзү©гҖҒд»–ж–№гҒ®з«ҜгҒ«еҗҢеҪўгҒ®з©ҙгӮ’жҺҳгӮҠзөҗеҗҲгҒ•гҒӣгӮӢгҖӮеј•ејөеҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҠөжҠ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖҒз°ЎеҚҳгҒ§еәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢжҺҘжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҹ»гӮҲгӮҠгӮӮеј•ејөгӮҠеј·еәҰгҒҢеӢқгӮӢгҒҢгҖҒжҺҘеҗҲй•·гҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢйҺҢзҠ¶гҒ®вҖҰвҖҰ

гӮўгғігғҲгғӢгғігғ»гғ¬гғјгғўгғігғү(гҒӮгӮ“гҒЁгҒ«гӮ“гғ»гӮҢгғјгӮӮгӮ“гҒ© Antonin Raymond 1888пҪһ1976)
гғҒгӮ§гӮіеҮәиә«гҖӮ
гғ—гғ©гғҸе·Ҙ科еӨ§еӯҰеҚ’гҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒЁе…ұгҒ«жқҘж—ҘгҒ—гҖҒеӣҪеҶ…гҒ«дәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮ
ж—Ҙжң¬дәәе»әзҜүгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖӮжҲҰеүҚгҒ«гҒҜгҖҒеүҚе·қеңӢз”·гҖҒеҗүжқ‘й Ҷдёү гӮүгҒҢгҖҒжҲҰеҫҢгҒ«гҒҜеў—жІўжҙөгӮӮгғ¬гғјгғўгғігғүдәӢеӢҷжүҖгҒ§еӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

гӮӨгӮӘгғӢгӮўејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ„гҒҠгҒ«гҒӮгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)
Ionic orderгҖӮе°ҸгӮўгӮёгӮўгҒ«з”ұжқҘгҒ—гҖҒжқұж–№гҒ«иө·жәҗгӮ’гӮӮгҒӨ гӮӘгғјгғҖгғјгҖӮзҙ°иә«гҒ®еҶҶжҹұгӮ’жңүгҒ—гҖҒгғүгғӘгӮ№ејҸгӮҲгӮҠи»Ҫеҝ«гҒӢгҒӨе„Әйӣ…гҒ§гҖҒжҰӮгҒ—гҒҰ гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжҹұй ӯгҒ®жёҰе·»иЈ…йЈҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«иӯҳеҲҘгҒ•гӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

жұ з”°и°·д№…еҗү(гҒ„гҒ‘гҒ гӮ„гҒІгҒ•гҒҚгҒЎгҖҒ1897пҪһ1956)
еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«дјқзөұзҡ„гҒӘеҜәзӨҫе»әзҜүгҒӘгҒ©гҒ®з§ҖдҪңгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжіүдҪҗйҮҺз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеёӮз«ӢеӨ§йҳӘе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеӨ§йҳӘеёӮз«ӢйғҪеі¶е·ҘжҘӯй«ҳзӯүеӯҰж ЎпјүеҚ’еҫҢгҖҒеӨ§йҳӘеәңеәҒгҒ«е…ҘеәҒгҖӮйҖҖиҒ·еҫҢгҖҒиҘҝеҢәгҒ«жұ з”°и°·е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжұ з”°и°·д№…еҗүиҮӘйӮёгҖҒвҖҰвҖҰ

зҹіе ҙе»әгҒҰ(гҒ„гҒ—гҒ°гҒ гҒҰ)
民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзӨҺзҹігҒ®дёҠгҒ«зӣҙжҺҘжҹұгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢе·Ҙжі•гҖӮжҹұгӮ’зӣҙжҺҘең°дёӯгҒ«еҹӢгӮҒгҒҰиҮӘз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢжҺҳз«ӢгҒҰе»әгҒҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘһгҖӮзӨҺзҹігҒЁжҺҘи§ҰгҒҷгӮӢжҹұдёӢз«ҜгӮ’зҹігҒ®еҗҲз«ҜгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮзҸҫеңЁгҒ®еҹәжә–жі•гҒ§гҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзҹігҒЁжҹұгҒ®ж‘©ж“ҰеҠӣгҒҢжңүеҠ№гҒ«еғҚгҒҸгҖӮ

зҹіжң¬е–ңд№…жІ»(гҒ„гҒ—гӮӮгҒЁгҒҚгҒҸгҒҳгҖҒ1894пҪһ1963)
еұұз”°е®ҲгҖҖгӮүгҒЁ еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ®ж§ӢжҲҗе“ЎгҒ®дёҖдәәгҖӮзҘһжҲёеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӨ§йҳӘгҒ®з«№дёӯе·ҘеӢҷеә—гҒ«е…ҘзӨҫгҖӮзҷҪжңЁеұӢгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’ж©ҹгҒ«йҖҖзӨҫгҖҒеҫҢгҒ«зҹіжң¬е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеұұеҸЈйҠҖиЎҢжқұдә¬ж”Ҝеә—гҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһзӨҫвҖҰвҖҰ

жқҝиҹҮиӮЎ(гҒ„гҒҹгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)

жқҝе”җжҲё(гҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ©)
жүүгҒ®жӯҙеҸІгҒҜгҖҒи»ҪйҮҸеҢ–гҒЁзөҢжёҲжҖ§гӮ’зӣ®жЁҷгҒЁгҒ—гҒҹжҠҖиЎ“ж”№иүҜеҸІгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮйЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®жүүгҒҜгҖҒйҮҚйҮҸгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒи»ёеҗҠгӮҠгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮӮгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮдёҠйғЁгӮ’гҖҢйј иө°гӮҠгҖҚгҖҢжҘЈгҖҚгҒ§гҖҒдёӢйғЁгӮ’гҖҢж•·еұ…пјҲй–ҫпјүгҖҚгҒ§еҗҠгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
жі•йҡҶеҜәвҖҰвҖҰ

жқҝжЈ§жҲё(гҒ„гҒҹгҒ•гӮ“гҒ©)

жқҝи‘ә(гҒ„гҒҹгҒ¶гҒҚ)
жңЁгҒ®жқҝгҒ§еұӢж №гӮ’и‘әгҒҸгҒ“гҒЁгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜи‘әгҒӢгӮҢгҒҹеұӢж №гҖӮжқүгғ»жӨ№гғ»ж —гҒӘгҒ©гҒ®иөӨе‘ігҒҢгҒЎгҒ®йғЁеҲҶгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖӮжҹҫеүІгӮҲгӮҠж°ҙгҒҢжөёйҖҸгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„е№ҙијӘжІҝгҒ„гҒ«еј•гҒҚеүІгҒЈгҒҹжқҝгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеҪўзҠ¶еҜёжі•гҒ«гӮҲгӮҠгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҺҡгҒ•3еҲҶпҪһ1еҜёгғ»е№…3пҪһ5еҜёгғ»й•·гҒ•вҖҰвҖҰ

дёҖжһҡжҲё(гҒ„гҒЎгҒҫгҒ„гҒ©)

дёҖж–Үеӯ—жЈҡ(гҒ„гҒЎгӮӮгӮ“гҒҳгҒ гҒӘ)

дёҖй–“зӨҫ(гҒ„гҒЈгҒ‘гӮ“гҒ—гӮғ)
зҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«иҲҺгҒ®жӯЈйқўжҹұй–“гҒ®ж•°гҒ§дҪ•й–“зӨҫгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжҹұй–“гҒҢдёҖй–“гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дёҖй–“зӨҫгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҳҘж—ҘйҖ гӮҠгҒ®зӨҫж®ҝгҒ®еӨҡгҒҸгҒҢгҒ“гӮҢгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҪўејҸгҒ®еҸӨгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢжҹұй–“гҒҢдәҢй–“гҒ®дәҢй–“зӨҫгҒ«гҒҜгҖҒеҮәйӣІеӨ§зӨҫгҒЁдҪҸеҗүеӨ§вҖҰвҖҰ

дјҠжқұеҝ еӨӘ(гҒ„гҒЁгҒҶгҒЎгӮ…гҒҶгҒҹгҖҒ1867пҪһ1954)
ж—Ҙжң¬жңҖеҲқгҒ®е»әзҜүеҸІе®¶гғ»е»әзҜүи©•и«–гҒ®й–ӢжӢ“иҖ…гҖӮзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮгҖҢжі•йҡҶеҜәе»әзҜүи«–гҖҚгҒӘгҒ©гҖҒжҳҺжІ»е№ҙй–“гҒ®е»әзҜүжҖқжҪ®гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸж–№еҗ‘д»ҳгҒ‘гӮӢж•°гҖ…гҒ®и«–ж–ҮгӮ’зҷәиЎЁгҖӮдҪң
е“ҒгҒҜгҖҒж©ҝеҺҹзҘһе®®пјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒе№іе®үзҘһе®®пјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒвҖҰвҖҰ

дјҠи—ӨжӯЈж–Ү(гҒ„гҒЁгҒҶгҒҫгҒ•гҒөгҒҝгҖҒ1896пҪһ1960)
еӨ§йҳӘеёӮе»әзҜүиӘІй•·гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӯҰж Ўж–ҪиЁӯгғ»зҫҺиЎ“йӨЁгҒӘгҒ©гӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гҒҹе»әзҜү家гҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺзүҮеІЎе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’зөҢгҒҰеӨ§йҳӘеёӮжҠҖеё«зқҖд»»гҖӮйҖҖиҒ·еҫҢгҖҒеӨ§йҳӘеёӮз«ӢеӨ§еӯҰ家ж”ҝеӯҰйғЁж•ҷжҺҲгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еӨ§йҳӘе•Ҷ科еӨ§еӯҰвҖҰвҖҰ

иұ•жү йҰ–(гҒ„гҒ®гҒ“гҒ•гҒҷ)
ж°ҙе№ігҒ®гҖҢж•·жЎҒпјҲиҷ№жўҒпјүгҖҚгҒ«гҖҢжү йҰ–з«ҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе·ҰеҸідәҢжң¬гҒ®ж–ңжқҗпјҲзҷ»жўҒпјүгӮ’еҗҲжҺҢеҪўгҒ«зө„гҒҝгҖҒгҒқгҒ®дёӯеӨ®гҒ«гҖҢжү йҰ–жқҹгҖҚгӮ’ж„ҸеҢ дёҠжҢҝгҒ—иҫјгӮ“гҒ еҪўејҸгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒ„гҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢжү йҰ–зө„гҖҚгҒ®дәҢзӯүиҫәдёүи§’еҪўгҒ§гғҲгғ©гӮ№гҒҜе®ҢзөҗгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢжү йҰ–жқҹвҖҰвҖҰ

зҢӘгҒ®зӣ®(гҒ„гҒ®гӮҒ)
гҖҢзҢӘгҒ®зӣ®гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒеҪўзҠ¶гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҖҢеҝғиҮ“еһӢпјҲгғҸгғјгғҲеһӢпјүгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж–Үж§ҳгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮе»әзү©гҒ®гҖҢеҰ»йЈҫгҖҚгҒ®гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгӮ„йҢәйҮ‘зү©гҒ®гҖҢе…ӯи‘үгғ»е…«еҸҢгҖҚгҖҒе·«еҘігҒ®жҢҒгҒӨгҖҢзҘһжҘҪйҲҙгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҖҢзҢӘгҒ®зӣ®вҖҰвҖҰ

зҢӘзӣ®жҮёйӯҡ(гҒ„гҒ®гӮҒгҒ’гҒҺгӮҮ)
гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒеұӢж №гҒ®еҲҮеҰ»йғЁеҲҶгҒ®й ӮзӮ№гӮ„гҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ®еӮҫж–ңгҒ—гҒҹз®ҮжүҖгҒ«еһӮдёӢгҒ•гҒӣгҒҹгҖҒиЈ…йЈҫжҖ§гҒЁйӣЁйҷӨгҒ‘гҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгҒҹеҪ«еҲ»гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҚз§°гғ»е®ҹдҪ“гҒЁгӮӮдёӯеӣҪгҒӢгӮүгҒ®зӣҙијёе…ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдҪ•ж•…гҒӢйҹ“еӣҪе»әзҜүгҒ«гҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгҒҜдёӢгҒҢвҖҰвҖҰ

иҢЁеһӮжңЁ(гҒ„гҒ°гӮүгҒ гӮӢгҒҚ)

д»Ҡдә•е…јж¬Ў(гҒ„гҒҫгҒ„гҒ‘гӮ“гҒҳгҖҒ1895пҪһ1987)
еҗҲзҗҶзҡ„гғ»ж©ҹиғҪзҡ„гҒӘгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒӢгӮүгҒҜи·қйӣўгӮ’зҪ®гҒҚгҖҒе»әзҜүгҒ«иҒ·дәәгҒ®жүӢжҘӯгӮ’ж®ӢгҒҷдҪңе“ҒгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҜҚж ЎгҒ®ж•ҷиҒ·гҒ«е°ұгҒҚй•·гҒҸеӢҷгӮҒгӮӢгҖӮпјҲж•ҷгҒҲеӯҗгҒ«жұ еҺҹзҫ©йғҺгӮүгҒҢгҒ„гӮӢпјүеёқеӣҪзҫҺиЎ“вҖҰвҖҰ

иҠӢзӣ®ең°(гҒ„гӮӮгӮҒгҒҳ)
straight jointгҖӮгӮҝгӮӨгғ«ејөгӮҠгӮ„ з…үз“Ұз©Қ гҒҝгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®ең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҠдёӢ2ж®өд»ҘдёҠйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹзӣ®ең°гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
иҰҸеүҮжӯЈгҒ—гҒҸдјёгҒігӮӢиҠӢгҒ®ж №гҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢз”ұжқҘгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж°ҙе№ігғ»еһӮзӣҙж–№еҗ‘гҒ®зӣ®ең°гҒҢдёҖзӣҙз·ҡгҒ«гҒӘгӮӢвҖҰвҖҰ

е…ҘжҜҚеұӢйҖ (гҒ„гӮҠгӮӮгӮ„гҒҘгҒҸгӮҠ)
гҖҖгҖҢжҜҚеұӢгҖҚгҒ®еҲҮеҰ»еұӢж №гҒ«гҖҒдёӢеұӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеәҮгҖҚгҒҢеӣһгҒ•гӮҢгҒҹеұӢж №еҪўејҸгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҚігҒЎгҖҢжҜҚеұӢгҒҢеҶ…гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹеұӢж №гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

е…Ҙеӯҗжқҝ(гҒ„гӮҢгҒ“гҒ„гҒҹ)

еІ©пЁ‘е№іеӨӘйғҺ(гҒ„гӮҸгҒ•гҒҚгҒёгҒ„гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1893пҪһ1984)
еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«еҘҲиүҜгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеҘҲиүҜзңҢеҗүйҮҺз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеҗүйҮҺе®ҹжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҘҲиүҜзңҢз«ӢеҗүйҮҺе·ҘжҘӯй«ҳзӯүеӯҰж ЎпјүжңЁе·Ҙ科е»әзҜүйғЁеҚ’гҖӮдәҖеІЎжң«еҗүгғ»жӯҰз”°дә”дёҖ гҒ«её«дәӢгҒҷгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеҗүйҮҺй§…иҲҺгҖҒж—§еҲ¶з•қеӮҚдёӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫз•қеӮҚй«ҳзӯүеӯҰж Ўпјүж ЎвҖҰвҖҰ

еІ©жң¬еҚҡиЎҢ(гҒ„гӮҸгӮӮгҒЁгҒІгӮҚгӮҶгҒҚгҖҒ1913пҪһ1991)
еӨ§йҳӘеәңгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮеӨ§йҳӘеёӮз«ӢйғҪеі¶е·ҘжҘӯй«ҳж Ўе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮз«№дёӯе·ҘеӢҷеә—гҒ«е…ҘзӨҫгҖҒе°Ҹжһ—дёүйҖ гҒ®жҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬е»әзҜүзҙ жқҗгҒ®иүІеҪ©гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒе»әзҜүгҒ«зөұдёҖж„ҹгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҢҒи«–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиҒ·дәәпјҲеӨ§е·ҘжЈҹжўҒпјүгҒ®дјқзөұгӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗе»әзҜү家гҒЁзӣ®вҖҰвҖҰ

еІ©е…ғзҰ„(гҒ„гӮҸгӮӮгҒЁгӮҚгҒҸгҖҒ1893пҪһ1922)
жӯҙеҸІдё»зҫ©гҒӢгӮүйӣўгӮҢгҖҒе»әзҜүгҒ®иҠёиЎ“жҖ§гӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹеӨ§жӯЈжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮй№ҝе…җеі¶зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’еҫҢгҖҒйҖ“дҝЎзңҒгҒ«е…ҘзңҒгҖӮпјҲеӨ§е·ҘдёҠгҒҢгӮҠгҒ§йҖ“дҝЎзңҒгҒ«еңЁзұҚгҒ—гҒҹ еұұеҸЈж–ҮиұЎ гҒҜгҖҒеІ©е…ғгҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢвҖҰвҖҰ

гӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒҶгҒғгғјгӮ“гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)
Wiener SezessionгҖӮ1897е№ҙгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®гӮҰгӮЈгғјгғігҒ«иҲҲгҒ•гӮҢгҒҹиҠёиЎ“йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҖӮ画家гҒ®G.гӮҜгғӘгғ гғҲеҸҠгҒіO.гғҙгӮЎгғјгӮ°гғҠгғјгҒ®ејҹеӯҗJ.M.гӮӘгғ«гғ–гғӘгғ’гҖҒJ.гғӣгғ•гғһгғігӮүгҒҢгҒқгҒ®дёӯеҝғгҖӮ
еҪјгӮүгҒҜгҖҒиӢұеӣҪгҒ®вҖҰвҖҰ

гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўгғіж§ҳејҸ(гӮ”гҒғгҒҸгҒЁгӮҠгҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Victorian styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ®гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўеҘізҺӢпјҲеңЁдҪҚ1837пҪһ1901пјүжІ»дёӢгҒ®зҫҺиЎ“гғ»е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮеҺіеҜҶгҒ«гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®еҪўж…ӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиЎЁзҸҫж§ҳејҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒеҗҢжҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҖиҲ¬зҡ„еӮҫеҗ‘гӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«зӨәгҒҷиӘһгҒЁгҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

гӮҰгӮЈгғӘгӮўгғ гғ»гғЎгғ¬гғ«гғ»гғҙгӮ©гғјгғӘгӮә(гҒҶгҒғгӮҠгҒӮгӮҖгғ»гӮҒгӮҢгӮӢгғ»гӮ”гҒүгғјгӮҠгҒҡ William Merrell Vories 1880пҪһ1964)
зұіеӣҪеҮәиә«гҖӮиӢұиӘһж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰжқҘж—ҘеҫҢгҖҒе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮиҝ‘жұҹе…«е№ЎеёӮгҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҖҒж•ҷдјҡгғ»еӯҰж Ўгғ»з—…йҷўгғ»еҖӢдәәе®…гҒӘгҒ©гӮ’иЁӯиЁҲгҖӮгғЎгғігӮҪгғ¬гғјгӮҝгғ гӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«еәғгӮҒгҒҹе®ҹжҘӯ家гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еҹәзқЈж•ҷеӣЈдә¬йғҪеҫЎе№ёз”әж•ҷдјҡгҖҒеҗҢеӨ§йҳӘж•ҷдјҡгҖҒвҖҰвҖҰ

гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ(гӮ”гҒүгғјгӮӢгҒЁ)
vaultгҖӮгғүгғјгғ гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮўгғјгғҒгӮ’еҹәжң¬еҪўгҒЁгҒ—гҒҹеұӢж №гҒ§гҖҒгӮўгғјгғҒгӮ’ж°ҙе№ігҒ«жҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҹгӮ«гғһгғңгӮігҒ®еҪўзҠ¶гҒ®еұӢж №гӮ’гҖҢгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеҚҳзҙ”гҒӘеҪўж…ӢгҒҜгҖҢзӯ’еһӢгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҖҚгҒ§гҖҒеҚҠеҶҶжҲ–гҒ„гҒҜ е°–й ӯгӮўгғјгғҒ гӮ’ж°ҙе№іж–№вҖҰвҖҰ

еҚҜз«Ӣ(гҒҶгҒ гҒӨ)
в‘ иҝ‘世民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе»әзү©гҒ®дёЎеҒҙгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹз“Ұи‘әзӯүгҒ®е°ҸеұӢж №д»ҳгҒҚиў–еЈҒгҖӮжң¬жқҘгҒҜиә«еҲҶгҒ®иұЎеҫҙгӮ’е…јгҒӯгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҳҺжІ»д»ҘйҷҚгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢиЈ…йЈҫгҒЁеҢ–гҒҷгҖӮйҳІзҒ«гӮ’е…јгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ
в‘Ўе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ®ж°‘家гҒЁгҒҸгҒ«з”әеұӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҰ»еҒҙгҒ®е°ҸеұӢвҖҰвҖҰ

еҶ…з”°зҘҘдёү(гҒҶгҒЎгҒ гӮҲгҒ—гҒӢгҒҡгҖҒ1885пҪһ1972)
жқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе…ғжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰз·Ҹй•·гҖӮдҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ гҒ®дёӢгҒ§е»әзҜүж§ӢйҖ еӯҰгӮ’з ”з©¶гҖӮж—Ҙжң¬гҒ®йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгғ»йү„йӘЁж§ӢйҖ еӯҰгҒ®еҹәзӨҺгӮ’зҜүгҒҸгҖӮгҖҢеҶ…з”°гӮҙгӮ·гғғгӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігғ‘гӮҝгғјгғігҒ®е»әзү©гӮ’еӨҡгҒҸиЁӯвҖҰвҖҰ

еҶ…и»ўгҒі(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒӘгҒ’гҒ—)

еҶ…жі•й•·жҠј(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҖ

еҶ…жі•иІ«(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒ¬гҒҚ)
гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢеҶ…жі•й•·жҠјгҖҚгҒ®еҫҢж–№гҒ«гҒӮгӮӢгҖҢиІ«гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҖҢеҶ…жі•иІ«гҖҚгҒҢжЁӘеҠӣгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж§ӢйҖ зҡ„еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҖҒгҖҢеҶ…жі•й•·жҠјгҖҚгҒҜеҢ–зІ§жқҗзҡ„гҒӘжүұгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒ„гҖӮе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢеҶ…жі•иІ«гҖҚгҒҜеЈҒгҒ®дёӯгҒ«еЎ—гӮҠиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘвҖҰвҖҰ

жө®йҖ гӮҠ(гҒҶгҒҘгҒҸгӮҠ)
гҖҖ

и…•жңЁ(гҒҶгҒ§гҒҺ)
гҖҖ

е…ҺжҜӣйҖҡ(гҒҶгҒ®гҒ’гҒ©гҒҶгҒ—)
гҖҖ

йҰ¬д№—гӮҠзӣ®ең°(гҒҶгҒҫгҒ®гӮҠгӮҒгҒҳ)
breaking jointгҖӮгӮҝгӮӨгғ«ејөгӮҠгӮ„ з…үз“Ұз©Қ гҒҝгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®ең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҠдёӢ2ж®өд»ҘдёҠйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹзӣ®ең°гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
зңҹйҰ¬иёҸгҒҝзӣ®ең°гҒЁзүҮйҰ¬иёҸгҒҝзӣ®ең°пјҲз ҙгӮҢзӣ®ең°пјүгҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

жў…йүўжҮёйӯҡ(гҒҶгӮҒгҒ°гҒЎгҒ’гҒҺгӮҮ)
жў…йүўзҙӢгҒҜдә”и§’еҪўгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒијӘйғӯгҒҢгҒ»гҒје…ӯи§’еҪўгҒ«иҝ‘гҒ„жӣІз·ҡгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢжў…йүўжҮёйӯҡгҖҚгҒЁе‘јгҒігҖҒжӣІз·ҡгӮ’з”ЁгҒ„гҒҡзӣҙз·ҡгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢеҲҮжҮёйӯҡпјҲгҒҚгӮҠгҒ’гҒҺгӮҮпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҖҢжӢқгҒҝгҖҚгҒ®з®ҮжүҖгҒ®гҒҝгҒ§гҖҢйҷҚжҮёйӯҡгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜз”ЁвҖҰвҖҰ

иЈҸз”І(гҒҶгӮүгҒ”гҒҶ)
гҖҖ

жөҰиҫәйҺ®еӨӘйғҺ(гҒҶгӮүгҒ№гҒ—гҒҡгҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1909пҪһ1991)
еІЎеұұзңҢеҖүж•·еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’еҫҢгҖҒеҖүж•·гғ¬гӮӨгғЁгғіпјҲзҸҫгӮҜгғ©гғ¬пјүгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҖҒ営繕йғЁй–ҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮе®ҹжҘӯ家еӨ§еҺҹз·ҸдёҖйғҺгҒ®еәҮиӯ·гҒ®дёӢгҒ«еҖүж•·е»әзҜүз ”з©¶жүҖпјҲзҸҫжөҰиҫәиЁӯиЁҲгҒ®еүҚиә«пјүгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—жөҰиҫәе»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖвҖҰвҖҰ

繧з№қеҪ©иүІ(гҒҶгӮ“гҒ’гӮ“гҒ•гҒ„гҒ—гҒҚ)
еҗҢзі»зөұгҒ®иүІгӮ’гҒјгҒӢгҒ•гҒҡгҒ«ж®өйҡҺзҡ„гҒ«иЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„гӮҚгҒ®жҝғж·ЎгҖӮж®өгҒјгҒӢгҒ—гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮйҖҡеёёгҒҜйқ’гғ»иөӨгғ»зҙ«гҒӘгҒ©дәҢиүІд»ҘдёҠгҒ®з№§з№қгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮжәҗжөҒгҒҜиҘҝеҹҹгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒе”җгҒ§жөҒиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢдјқжқҘгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒ繧з№қеҪ©иүІгҒЁз§°гҒ—гҒҰд»Ҹз”»гӮ„д»ҸеҜәвҖҰвҖҰ

жұҹе·қдёүйғҺе…«(гҒҲгҒҢгӮҸгҒ•гҒ¶гӮҚгҒҶгҒҜгҒЎгҖҒ1860пҪһ1939)
ж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүжҠҖеё«гҖӮзҰҸеі¶зңҢдјҡжҙҘиӢҘжқҫз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе®®еӨ§е·ҘгҒ®дҝ®иЎҢгҒ®еҫҢгҖҒеұұеҸЈеҚҠе…ӯгғ»еҰ»жңЁй јй»„гғ»д№…з•ҷжӯЈйҒ“гҒ«жҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘е»әзҜүжҠҖеё«гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеІЎеұұзңҢгҒ«и»ўд»»гҒ—гҖҒж•°гҖ…гҒ®е…¬е…ұж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯиЁҲзӣЈзҗҶгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж“¬жҙӢйўЁж§ҳејҸгҒҜгҖҢжұҹе·қејҸе»әзҜүгҖҚгҒЁгӮӮз§°вҖҰвҖҰ

гӮЁгғҮгӮЈгӮӯгғҘвҖ•гғ«(гҒҲгҒ§гҒғгҒҚгӮ…гғјгӮӢ)
aedikuleгҖӮе°ҸзҘӯеЈҮгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҸӨд»ЈгҒ®еҮұж—Ӣй–ҖгӮ„еёӮй–ҖгҖҒж•ҷдјҡе ӮгҒӘгҒ©гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҪ«еғҸгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹгҖҢгғӢгғғгғҒпјҲеЈҒйҫ•пјүгҖҚгҒ®е‘ЁгӮҠгӮ’еҶҶжҹұгҒЁ гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҘһж®ҝйўЁгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

гӮЁгғүгғўгғігғ»гӮӘгғјгӮ®гғҘгӮ№гғҲгғ»гғҗгӮ№гғҶгӮЈгӮўгғі(гҒҲгҒ©гӮӮгӮ“гғ»гҒҠгғјгҒҺгӮ…гҒҷгҒЁгғ»гҒ°гҒҷгҒҰгҒғгҒӮгӮ“ Edmond Auguste Bastien 1839 пҪһ1888)
д»ҸеӣҪгӮ·гӮ§гғ«гғ–гғјгғ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮиҲ№е·Ҙгғ»иЈҪеӣіиҒ·е·ҘгҖӮжЁӘй ҲиіҖиЈҪйү„жүҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮеҜҢеІЎиЈҪзіёе ҙпјҲеӣҪе®қпјүгҒ®й–ӢжҘӯеҪ“еҲқгҒ®дё»иҰҒгҒӘе»әйҖ зү©гҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гғҗгӮ№гғҶгӮЈгӮўгғігҒҢзўәе®ҹгҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒз№°зіёжүҖгғ»жқұзҪ®з№ӯжүҖгғ»иҘҝзҪ®з№ӯжүҖгғ»и’ёж°—вҖҰвҖҰ

жө·иҖҒиҷ№жўҒ(гҒҲгҒігҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)
гҖҖ

иқҰжқҹ(гҒҲгҒігҒҘгҒӢ)
гҖҖ

гӮЁгғ–гғ©гӮәгғһгғі(гҒҲгҒ¶гӮүгҒҡгҒҫгӮ“)
Д“brasementгҖӮеҹәжң¬гҖҒеЈҒж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜе»әзҜүгҒ®зӘ“гҒ®жҠҖжі•гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгӮ№гғӘгғғгғҲзӘ“гҒ®еҶ…йғЁгҒ«йҡ…еҲҮгӮҠгӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒе…үгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж–ңгӮҒгҒ«гӮ«гғғгғҲгҒ•гӮҢгҒҹйқўгҒҢеҸҚе°„жқҝгҒ®еғҚгҒҚгӮ’гҒ—гҖҒе®ӨеҶ…гҒ®еҘҘгҒ«гҒҫгҒ§жӢЎж•Је…үвҖҰвҖҰ

гӮЁгғӘгӮ¶гғҷгӮ№ж§ҳејҸ(гҒҲгӮҠгҒ–гҒ№гҒҷгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Elizabethan styleгҖӮиӢұеӣҪгӮЁгғӘгӮ¶гғҷгӮ№1дё–гҒ®ең°еӢўпјҲ1558пҪһ1603пјүгҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгғҶгғҘгғјгғҖгғјж§ҳејҸ гҒЁ гӮёгғЈгӮігғ“гӮўгғіж§ҳејҸ гҒЁгҒ®й–“гҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгҒҹйҒҺжёЎзҡ„ж§ҳејҸгҖӮ
гӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®еһӮзӣҙж§ӢйҖ гӮ’еҹәжң¬дҝҠгҖҒвҖҰвҖҰ

гӮЁгғігӮҝгӮ·гӮ№(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ—гҒҷ)
entasisгҖӮдёҖзЁ®гҒ®иғҙејөгӮҠгҖӮдёҠж–№гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰзҙ°гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҶҶжҹұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҹұиә«гҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢеғ…гҒӢгҒӘиҶЁгӮүгҒҝгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®гҖҢиғҙејөгӮҠгҖҚгҒҜгҖҒжҹұгҒ®дёӯзЁӢгҒ«жңҖеӨ§гҒ®иҶЁгӮүгҒҝгӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҖҒдёҠдёӢз«ҜгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰгҒқгҒ®ж–ӯйқўгҒҢвҖҰвҖҰ

гӮЁгғігӮҝгӮ·гӮ№(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ—гҒҷ)
гҖҖ

гӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ¶гӮҢгҒЎгҒҮгҒӮ)
entablatureгҖӮеұӢж №гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢж°ҙе№іеёҜгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ§гҒҜгҖҒгӮігғјгғӢгӮ№гғ»гғ•гғӘгғјгӮәвҖЈгӮўгғјгӮӯгғҲгғ¬гғјгғ– гӮҲгӮҠгҒӘгӮӢгҖӮ

еҶҶжҹұ(гҒҲгӮ“гҒЎгӮ…гҒҶ)
ж–ӯйқўгҒҢеҶҶеҪўгҒ®жҹұгҖӮж—Ҙжң¬е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҸӨжқҘз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӯдё–гҒ«й–“д»•еҲҮгӮҠгҒ«еј•жҲёгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҒи§’жҹұгҒҢе°ӮгӮүз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһгҒ®еҸӨе»әзҜүгҒ§зӣӣгӮ“гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹеҶҶжҹұгҒ«зёҰжәқпјҲиғЎйә»вҖҰвҖҰ

йҒ и—Өж–°(гҒҲгӮ“гҒ©гҒҶгҒӮгӮүгҒҹгҖҒ1889пҪһ1951)
зҰҸеі¶зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеҚ’жҘӯзҝҢе№ҙгҖҒе»әзҜүз•ҢгҒ®еӨ§еҫЎжүҖгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ иЁӯиЁҲгҒ®жқұдә¬й§…гҒ®жү№еҲӨгӮ’зҷәиЎЁгҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒ«её«дәӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗгҖӮе»әиЁӯиІ»з”ЁгҒ®и¶…йҒҺгӮ’зҗҶз”ұгҒ«и§ЈйӣҮгҒ•гӮҢгҒҹгғ©гӮӨгғҲгҒ®еҫҢгӮ’вҖҰвҖҰ

йҒ и—Өж–јиҸҹ(гҒҲгӮ“гҒ©гҒҶгҒҠгҒЁгҖҒ1866пҪһ1943)
ж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲжҠҖиЎ“гҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҒ§гҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®гғҡгғ¬пјҲгӮӘгғјгӮ®гғҘгӮ№гғҲгғ»гғҡгғ¬пјүгҖҚгҒЁгӮӮз§°гҒ•гӮҢгӮӢе»әзҜү家гҖӮй•·йҮҺзңҢжңЁжӣҪз”әгҒ®з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§жЁӘжөңжӯЈйҮ‘йҠҖиЎҢжң¬еә—пјҲзҸҫзҘһеҘҲе·қзңҢз«ӢжӯҙеҸІеҚҡвҖҰвҖҰ

гӮӘгғјгғҖгғј(гҒҠгғјгҒ гғј)
orderгҖӮе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгӮӘгғјгғҖгғјгҖҚгҒҜгҖҒеҸӨе…ёдё»зҫ©е»әзҜүгҒ®еҹәжң¬еҚҳдҪҚгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢзӨҺзӣӨпјҲжҹұеҹәпјүгғ»жҹұиә«гғ»жҹұй ӯгҖҚгҒӢгӮүгҒӘгӮӢжҹұгҒЁгҖҒж°ҙе№іжўҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғЈгғјгҖҚгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®йғЁжқҗзӣёдә’гҒ®з§©еәҸгҒӮгӮӢзө„еҗҲгҒӣгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮвҖҰвҖҰ

з¬ҲеҪў(гҒҠгҒ„гҒҢгҒҹ)
гҖҢз¬ҲпјҲгҒҠгҒ„пјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒй©ўйҰ¬пјҲгғӯгғҗпјүгҒ®иғҢгҒ®е·ҰеҸігҒ«жҢҜгӮҠеҲҶгҒ‘гҒҰиҚ·гӮ’зҪ®гҒҸгҒҹгӮҒгҒ®йҒ“е…·гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгҒ®йҖЈжғігҒӢгӮүд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҗҚз§°гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢиҰҒзҙ гҒ®дёҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӨ§з“¶жқҹпјҲгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢпјүгҖҚгҒ®е·ҰеҸігҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҒвҖҰвҖҰ

з¬ҲеҪўд»ҳеӨ§з“¶жқҹ(гҒҠгҒ„гҒҢгҒҹгҒӨгҒҚгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)
гҖҖ

жүҮеһӮжңЁ(гҒҠгҒҶгҒҺгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҢжүҮеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒеҺҹе§ӢдҪҸе®…гҒ«гӮӮгҒҷгҒ§гҒ«зҸҫгӮҸгӮҢгҖҒиҫІе®¶еұӢж №гҒ®гҖҢеһӮжңЁз«№гҖҚгӮ„гҖҢеӣӣйҳҝпјҲгҒӮгҒҡгҒҫгӮ„пјүгҖҚгҒ«гӮӮиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе®—ж•ҷе»әзҜүгҒ§гӮӮгҖҒжңҖеҸӨгҒ®гҖҢйҡ…жүҮеһӮжңЁгҖҚгҒ®дҫӢгҒҢеӣӣеӨ©зҺӢеҜәгҒ«йҒәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдёӯеӣҪгғ»йҹ“еӣҪгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҝгҒӘгҖҢвҖҰвҖҰ

з”·жўҒ(гҒҠгҒҶгҒӨгҒ°гӮҠгҖҒгҒҠгҒ°гӮҠ)
гҖҖ

еӨ§жұҹж–°еӨӘйғҺ(гҒҠгҒҠгҒҲгҒ—гӮ“гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1879пҪһ1935)
ж—Ҙе…үе»ҹпјҲжқұз…§е®®пјүеӨ§дҝ®з№•гҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰд»ҘжқҘгҖҒз”ҹж¶ҜгҒ«жёЎгҒЈгҒҰж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұе»әзҜүгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒдә¬йғҪиӮІгҒЎгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӯҗжҒҜгҒҢгҖҒе»әзҜү家гҒ®гҖҖеӨ§жұҹе®ҸгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжҳҺжІ»зҘһе®®е®қзү©йӨЁпјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒй«ҳйҮҺеұұйңҠвҖҰвҖҰ

еӨ§жұҹе®Ҹ(гҒҠгҒҠгҒҲгҒІгӮҚгҒ—гҖҒ1913пҪһ1989)
гғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұзҡ„ж§ҳејҸгҒЁгӮ’иһҚеҗҲгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢж··еңЁдҪөеӯҳгҖҚгҒ•гҒӣгҒҹе»әзҜүж„ҸеҢ гӮ’е®ҹи·өгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгҒҫгҒҹжі•ж”ҝеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гҒ®зӨҺгӮ’зҜүгҒ„гҒҹж•ҷиӮІиҖ…гҖӮз§Ӣз”°з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲзҲ¶гҒҜгҖҒе»әзҜү家гғ»еӨ§жұҹж–°еӨӘйғҺпјүжқұдә¬еӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’вҖҰвҖҰ

еӨ§еЈҒ(гҒҠгҒҠгҒӢгҒ№)
жҹұгҒҢиЎЁгҒ«зҸҫгӮҢгҒӘгҒ„ж§ӢйҖ гҖӮе’ҢйўЁжңЁйҖ е»әзҜүгҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘе·Ҙжі•гҒҜеЈҒгӮ’жҹұгҒЁжҹұгҒ®й–“гҒ«зҙҚгӮҒгҖҒжҹұгҒҢеӨ–йқўгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢзңҹеЈҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҹҺйғӯе»әзҜүгӮ„еңҹи”өгҒ§гҒҜгҖҒжҹұгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮи—ҒгӮ’е·»гҒҚд»ҳгҒ‘гҒҰеңҹгӮ’еЎ—гӮҠгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгӮӢеӨ§еЈҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еӨ§зҶҠе–ңйӮҰ(гҒҠгҒҠгҒҸгҒҫгӮҲгҒ—гҒҸгҒ«гҖҒ1877пҪһ1952)
営繕е®ҳеғҡгҒ®е»әзҜү家гҖӮе…¬е…ұе»әзҜүгҒ®дёӯеҝғзҡ„дәәзү©гҒ§гҖҒдёӯеӨ®и«ёе®ҳеәҒеҸҠгҒіең°ж–№еәҒиҲҺгӮ’ж•°еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеҰ»жңЁй јй»„гғ»зҹўж©Ӣиіўеҗү гҒ®еҫҢгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҖҒеӣҪдјҡиӯ°дәӢе ӮгҒ®е»әиЁӯгӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҹгҖӮжқұдә¬йә№з”әз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжЁӘжІіе·ҘвҖҰвҖҰ

еӨ§еҖүдёүйғҺ(гҒҠгҒҠгҒҸгӮүгҒ•гҒ¶гӮҚгҒҶгҖҒ1900пҪһ1983)
дә¬йғҪгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе®—е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгғ»дә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰ営繕гғ»еҸ°ж№ҫз·ҸзқЈйғЁжҠҖ師営繕гӮ’зөҢгҒҰгҖҒдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒ«е°ұд»»гҖӮеҫҢгҒ«еҗҢеӨ§еӯҰгҒ®еӯҰй•·гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе®—вҖҰвҖҰ

еӨ§жЈҹ(гҒҠгҒҠгӮҖгҒӯ)
еұӢж №гҒ®й ӮдёҠгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж°ҙе№ігҒ«иө°гӮӢдё»иҰҒгҒӘжЈҹгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеұӢж №гҒ®й ӮзӮ№гҒҜз“ҰгҒҢйҖЈз¶ҡгҒӣгҒҡйӣЁж°ҙгҒҢе…ҘгӮҠиҫјгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ«е№із“ҰгҒ®еҚҠеҲҶгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҖҒдёҠгҒ«дёёз“ҰгӮ’зҪ®гҒ„гҒҰйӣЁж°ҙгҒҢе…ҘгӮӢгҒ®гӮ’йҳІгҒҗгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’жЈҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҺҡжқҝгҒ§йһҚз®ұеҪўгҒ«дҪңгҒЈгҒҹвҖҰвҖҰ

еӨ§и°·зҹі(гҒҠгҒҠгӮ„гҒ„гҒ—)
е®ҮйғҪе®®еёӮеӨ§и°·иҫәгӮҠгҒ«з”ЈгҒҷгӮӢгҖҒзҹіиӢұзІ—йқўеІ©иіӘеҮқзҒ°еІ©гҒ§гҖҒж·Ўз·‘иӨҗиүІгҒ§еӨҡеӯ”иіӘгҖҒжұәгҒ—гҒҰиүҜиіӘгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒи»ҹзҹігҒ§еҠ е·ҘгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸе®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨ–иҰігҒ«жҜ”гҒ—гҒҰйӣЁж°ҙгҒ«иҖҗгҒҲиҖҗзҒ«жҖ§гҒ«е„ӘгӮҢгӮӢгҖӮеЎҖгғ»зҹіеһЈгғ»еҶ…иЈ…жқҗгҒӘгҒ©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

еІЎз”°дҝЎдёҖйғҺ(гҒҠгҒӢгҒ гҒ—гӮ“гҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1883пҪһ1932)
еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе’ҢжҙӢгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡжӯҙеҸІзҡ„гҒӘж§ҳејҸгӮ’йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲйҖ гҒ§е»әгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«е®ҡи©•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҢж§ҳејҸгҒ®еӨ©жүҚгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжқұдә¬иҠёеӨ§гғ»ж—©еӨ§гҒ§ж•ҷеЈҮгҒ«з«ӢгҒЎгҖҒд»Ҡе’Ңж¬ЎйғҺгғ»вҖҰвҖҰ

жӢқгҒҝ(гҒҠгҒҢгҒҝ)
гҖҖ

е°Ҹе·қе®үдёҖйғҺ(гҒҠгҒҢгӮҸгӮ„гҒҷгҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1882пҪһ1946)
дҪҗиіҖзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰж ЎпјҲзҸҫдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰпјүеӣіжЎҲ科еҚ’гҖӮдҪҸеҸӢ営繕гғ»еҶ…еӨ–жңЁжқҗе·ҘиҠёж ӘејҸдјҡзӨҫгғ»еӨ§жһ—зө„гҒ«еңЁзұҚгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫжё…ж°ҙзҢӣе•Ҷеә—гҖҒж—§жұ й•·зҫҺиЎ“йӨЁпјҲзҸҫзҘһжҲёеёӮж–ҮжӣёйӨЁпјүгҖҒж—§жұ й•·еӯҹйӮёгҖҒж—§и—Өдә•йӮёжҙӢйӨЁпјҲжқҫйўЁвҖҰвҖҰ

зҪ®еЎ©з« (гҒҠгҒҚгҒ—гҒҠгҒӮгҒҚгӮүгҖҒ1881пҪһ1968)
еӨ§жӯЈгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«й–ўиҘҝгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе…¬е…ұе»әзҜүгӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гҖҒгғҚгӮӘгӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸ гӮ’еҘҪгӮ“гҒ гҖӮйқҷеІЎзңҢеі¶з”°еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮйҷёи»ҚзңҒгғ»е…өеә«зңҢеәҒгҒ«еӢӨеӢҷгҒ®еҫҢзӢ¬з«ӢгҖӮзҘһжҲёй«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫзҘһжҲёеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁвҖҰвҖҰ

гӮӘгӮҜгғ«гӮ№(гҒҠгҒҸгӮӢгҒҷ)
oculusгҖӮзңјзӘ“гҖҒеҶҶзӘ“гҒЁиЁігҒҷгҖӮгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®гҖҢзӣ®гҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮгғӯгғјгғһгҒ®гғ‘гғігғҶгӮӘгғігҒ®гғүгӮҘгғјгғўй ӮйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгҖҒеҶҶеҪўгҒ®й–ӢеҸЈйғЁгӮӮгӮӘгӮҜгғ«гӮ№гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒ16дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҖҒеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢеҶҶеҪўзӘ“гҒҜгҖҒд»ҸиӘһгҒ®oeil de вҖҰвҖҰ

гӮӘгӮёгғјгӮўгғјгғҒ(гҒҠгҒҳгғјгҒӮгғјгҒЎ)
ogee archгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜеҫҢжңҹеҸҠгҒігӮӨгӮ№гғ©гғ е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҮёзҠ¶гҒ®жӣІз·ҡгҒЁеҮ№зҠ¶гҒ®жӣІз·ҡгҒ®зө„еҗҲгҒӣгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒзҺүи‘ұеҪўгҒ®гӮўгғјгғҒ

е°ҫеһӮжңЁ(гҒҠгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҢдәҢжүӢе…ҲгҖҚгҖҢдёүжүӢе…ҲгҖҚгҒЁзө„зү©гӮ’еҮәгҒҷгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰгҖҒгҖҢдёёжЎҒпјҲгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶпјүгҖҚгҒ®ж”ҜжҢҒгҒҢдёҚе®үе®ҡгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒи»’гҒҢдёӢгҒҢгӮӢжҮёеҝөгҒҢеў—гҒҷгҒ®гҒ§гҖҢе°ҫеһӮжңЁгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҜгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҖғжЎҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиҰӢгҒҰгӮӮгӮҲгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҖҢе°ҫеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒжҹұиҠҜгӮ’ж”ҜзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

иҗҪзёҒ(гҒҠгҒЎгҒҲгӮ“)
гҖҖ

й¬јз“Ұ(гҒҠгҒ«гҒҢгӮҸгӮү)
еӨ§жЈҹгҒҫгҒҹгҒҜйҷҚгӮҠжЈҹгҒ®з«ҜгҒ«йӣЁд»•иҲһгҒЁиЈ…йЈҫгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢз“ҰгҒ®з·Ҹз§°гҖӮжқҝгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜй¬јжқҝгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜи“®иҸҜж–ҮгӮ„зҚЈйқўгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜи§’гҒ®з”ҹгҒҲгҒҹй¬јйқўгҒёгҒЁеӨүеҢ–гҒ—зӣӣиЎҢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ民家гҒ§гҒҜй¬јйқўвҖҰвҖҰ

й¬јж–—(гҒҠгҒ«гҒЁгҖҒгҒ„гҒҢгҒЁ)
ж–—гҒ®дёҖгҖӮдёҠдёӢгҒ§пј”пј•В°йЈҹгҒ„йҒ•гҒЈгҒҹиӮҳжңЁгӮ’гҒҶгҒ‘гӮӢж–—гҒ§гҖҒйҖҡгӮҠиӮҳжңЁгҒӘгҒ©гҒ®дәӨгӮҸгӮӢйҡ…иӮҳжңЁгғ»йҡ…е°ҫеһӮжңЁгҒ®е…Ҳз«ҜгҒӘгҒ©гҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгҖӮжӯЈж–№еҪўгҒ§ж–№ж–—гӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮзү№ж®ҠгҒӘз№°еһӢгҒҢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дёӢйқўгҒҢиҸҠиҠұеҪўгҒ§гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иҸҠж–—гҒЁгҒ„вҖҰвҖҰ

жҠҳзҪ®зө„(гҒҠгӮҠгҒҠгҒҚгҒҗгҒҝ)
е°ҸеұӢжўҒгҒ®з«ҜйғЁгҒ®зҙҚгӮҒж–№гҒ®дёҖгҖӮжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«зӣҙжҺҘе°ҸеұӢжўҒгӮ’жһ¶гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«и»’жЎҒгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮеҸӨд»ЈгҒӢгӮүз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йҖҶгҒ§гҖҒжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«гҒҫгҒҡжЎҒгӮ’жёЎгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«е°ҸеұӢжўҒгӮ’гҒ®гҒӣгӮӢзҙҚгӮҒж–№гӮ’дә¬е‘Ӯзө„гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҒӢгҖңгҒ“

гӮ¬гғјгӮҙгӮӨгғ«(гҒҢгғјгҒ”гҒ„гӮӢ)
gargoyleгҖӮйӣЁж°ҙгҒ®жҺ’ж°ҙеҸЈгҖҒжҖӘйіҘгӮ„зҚ…еӯҗгҒӘгҒ©

иІқеҪў(гҒӢгҒ„гҒҢгҒҹ)
гҖҖ

иІқеҪўжҹұ(гҒӢгҒ„гҒҢгҒҹгҒ°гҒ—гӮү)
гҖҖ

иҹҮиӮЎ(гҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)
гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖҢиҹҮиӮЎгҖҚгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢдәҢжң¬гҒ®ж°ҙе№іжқҗгҖҚгҒ®й–“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёҠгҒ«гҖҢж–—пјҲгҒҫгҒҷпјүгҖҚгӮ’гҒ®гҒӣгҒҹгҖҒиӣҷпјҲиҹҮпјүгҒ«дјјгҒҹжӣІз·ҡеҪўгҒ®ијӘйғӯгӮ’гӮӮгҒӨе»әзҜүиЈ…йЈҫйғЁжқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҷӮд»ЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж§ӢйҖ дҪ“гҒЁиЈ…йЈҫж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁвҖҰвҖҰ

йҸЎеӨ©дә•(гҒӢгҒҢгҒҝгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)
еӨ©дә•еҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮж јзёҒгғ»з«ҝгҒӘгҒ©гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒжқҝгӮ’йҸЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е№іиЎҢгҒ«дёҰгҒ№гҒҰиІјгҒЈгҒҹгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӨ©дә•гҖӮиЎЁйқўгҒҢпј‘жһҡжқҝгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒпј‘жһҡгҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮзҹ§гҒҺзӣ®гҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’йҸЎжқҝгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйҺҢеҖүжҷӮд»Јд»ҘйҷҚзҰ…е®—ж§ҳе»әзҜүгҒ§гӮҲгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«вҖҰвҖҰ

дёёжЎҒ(гҒҢгҒҺгӮҮгҒҶгҖҒгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶгҖҒгҒҫгӮӢгҒ’гҒҹ)
еҜәзӨҫе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж–—ж ұгҒ®дёҖз•Әе…ҲгҒ®жүӢе…ҲгҒ®дёҠгҒ«гҒӮгӮӢжЁӘжқҗгҒ§еұӢж №е‘ЁгӮҠгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖӮеһӮжңЁгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢи»’жЎҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜж–ӯйқўгҒҢеҶҶеҪўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®з§°гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж–ӯйқўгҒҢи§’еҪўгҒ§гӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ®еҪўгҒ§жҷӮд»ЈгҒ®ж–°ж—§гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢвҖҰвҖҰ

жҺӣиҫјгҒҝеӨ©дә•(гҒӢгҒ‘гҒ“гҒҝгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)
иҢ¶е®ӨгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢеӨ©дә•еҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮеӨ©дә•гӮ’ејөгӮүгҒҡеҢ–зІ§еһӮжңЁгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢеҢ–зІ§еұӢж №иЈҸгҒЁе№іеӨ©дә•гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеӨ©дә•гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгҒ®еҢ–зІ§еұӢж №иЈҸгӮ’жҺӣиҫјгҒҝеӨ©дә•гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮе№іеӨ©дә•гӮҲгӮҠгҒ•гӮүгҒ«дҪҺгҒ„еӨ©дә•гӮ’иҗҪгҒЎеӨ©дә•гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

и‘ӣиҘҝиҗ¬еҸё(гҒӢгҒ•гҒ„гҒҫгӮ“гҒҳгҖҒ1863пҪһ1942)
иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒЁе»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’е…ұеҗҢзөҢе–¶гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮзӣӣеІЎеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеҚ—йғЁи—©еЈ«и‘ӣиҘҝ家гҒ®йӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮпјҲеҗҢжңҹгҒ«гҖҒжЁӘжІіж°‘иј”гғ»е®—е…өи”өпјүиҫ°йҮҺи‘ӣиҘҝиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§зӣӣеІЎйҠҖиЎҢжң¬еә—жң¬йӨЁвҖҰвҖҰ

й ӯиІ«(гҒӢгҒ—гӮүгҒ¬гҒҚгҖҒгҒҡгҒ¬гҒҚ)
жҹұй ӮйғЁгҒ«жёЎгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖҢиІ«гҖҚгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮйЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ§гҒҜгҖҒе»әзү©гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжЁӘеҠӣгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиҖғж…®гҒӣгҒҡгҖҒжҹұгҒ гҒ‘гҒ§иҮӘз«ӢгҒҷгӮӢж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«жЁӘжһ¶жқҗгҒҜзҙ°гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹд»•еҸЈгӮӮеҚҳзҙ”гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ§гҒҜвҖҰвҖҰ

зүҮеІЎе®ү(гҒӢгҒҹгҒҠгҒӢгӮ„гҒҷгҒ—гҖҒ1876пҪһ1946)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«еӨ§йҳӘгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®йҮҚйҺ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬йғҪеёӮиЁҲз”»з ”з©¶гҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮзҹіе·қзңҢйҮ‘жІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮж—Ҙжң¬з”ҹе‘ҪдҝқйҷәеүҜзӨҫй•·гғ»зүҮеІЎзӣҙжё©гҒ®е©ҝйӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮиҫ°вҖҰвҖҰ

зүҮеұұжқұзҶҠ(гҒӢгҒҹгӮ„гҒҫгҒЁгҒҶгҒҸгҒҫгҖҒ1853пҪһ1917)
жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„е®®е»·е»әзҜү家гҖӮзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰиҲҲйҖ 家еӯҰ科第1еӣһеҚ’жҘӯжҖ§гҖӮд»ЈиЎЁдҪңгҒҜгҖҒеҘҲиүҜеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҖҒдә¬йғҪеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҖҒжқұдә¬еӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁиЎЁж…¶йӨЁгҖҒж—§жқұе®®еҫЎжүҖпјҲиөӨйҳӘйӣўе®®пјүгҒӘгҒ©гҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘжҳҺжІ»ж§ҳејҸе»әзҜүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

и‘ӣйҮҺеЈ®дёҖйғҺ(гҒӢгҒ©гҒ®гҒқгҒҶгҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1880пҪһ1944)
й–ўиҘҝгӮ’дёӯеҝғгҒ«иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹд»–гҖҒйҹіжҘҪгғ»зөөз”»гҒ«гӮӮйҖ и©ЈгҒҢж·ұгҒҸгҒҫгҒҹеҘіеӯҗж•ҷиӮІгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮӢгҒӘгҒ©еӨҡж–№йқўгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеӨ§йҳӘеәңжұ з”°еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲе…ҲзҘ–гҒҜгҖҒз©әжө·жёЎе”җгҒ®йҡӣгҒ®йҒЈе”җеӨ§дҪҝгҒ§гҒӮгӮӢи—ӨеҺҹи‘ӣйҮҺйә»е‘Ӯпјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүвҖҰвҖҰ

йҙЁеұ…(гҒӢгӮӮгҒ„)
иҝ‘з•ҝең°ж–№гҒ®иҫІе®¶гҒ«гҒҜгҖҒдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸгҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдёҠеә§гҒ®еә§ж•·еҒҙгҒ гҒ‘гӮ’гҖҢй•·жҠје·»пјҲгҒӘгҒ’гҒ—гҒҫгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжҷ®йҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гҖҒеә§ж•·еҒҙгҒ®гҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгӮ’ж¬ гҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҖҢйҮҝеҗҚж —пјҲгҒЎгӮҮгҒҶгҒӘгҒӘгҒҗгӮҠпјүгҖҚгӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒе·Ұе®ҳгҒ§вҖҰвҖҰ

иҢ…иІ (гҒӢгӮ„гҒҠгҒ„)
гҖҖ

е”җеұ…ж•·(гҒӢгӮүгҒ„гҒҳгҒҚ)
гҖҖ

е”җз ҙйўЁ(гҒӢгӮүгҒҜгҒөгҒҶ)
гҖҖ

е”җж§ҳ(гҒӢгӮүгӮҲгҒҶ)
гҖҖ

жІіеҗҲжө©и”ө(гҒӢгӮҸгҒ„гҒ“гҒҶгҒһгҒҶгҖҒ1856пҪһ1934)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе»әзҜүеӯҰдјҡгҒ®еүҚиә«йҖ 家еӯҰдјҡеүөз«Ӣзҷәиө·дәәгҒ®дёҖдәәгҖӮжұҹжҲёжң¬жүҖз”ҹгҒҫгӮҢгҖҒе·ҘйғЁеӨ§еӯҰж ЎйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢз”ҹгҖӮе·ҘйғЁзңҒгғ»еҸёжі•зңҒгӮ’зөҢгҒҰжІіеҗҲе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖй–ӢиЁӯгҖӮй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®й•·иҖҒзҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

йӣҒжңЁжЈҡ(гҒҢгӮ“гҒҺгҒ гҒӘ)
гҖҖ

зңӢжқҝе»әзҜү(гҒӢгӮ“гҒ°гӮ“гҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸ)
еӨ§жӯЈ12е№ҙпјҲ1923пјүгҒ®й–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҖҒз„јгҒ‘йҮҺеҺҹгҒ«гҒҜгғҗгғ©гғғгӮҜпјҲе…өиҲҺгғ»д»®иЁӯе°ҸеұӢгҒ®ж„ҸпјүгҒҢе»әгҒҰгӮүгӮҢгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҢгғҗгғ©гғғгӮҜе•Ҷеә—иЎ—гҖҚгҒ®ж§ҳзӣёгӮ’е‘ҲгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒӘгҒӢгҒ«гҒҜе»әзҜү家пјҲйҒ и—Өж–°гғ»еҗүз”°дә”еҚҒе…«гғ»гғ¬гӮӨгғўгғігғүзӨҫгғ»еүҚз”°еҒҘдәҢвҖҰвҖҰ

гӮӯгғјгӮ№гғҲгғјгғі(гҒҚгғјгҒҷгҒЁгғјгӮ“)
keystoneгҖӮиҰҒзҹіпјҲгҒӢгӮ“гӮҒгҒ„гҒ—пјүгҖҒжҘ”зҹіпјҲгҒҸгҒ•гҒігҒ„гҒ—пјүгҖӮгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгҒ«е…ҘгӮӢжҘ”еҪўгҒ® иҝ«зҹігҖӮгӮўгғјгғҒгӮ’йҖ гӮӢе ҙеҗҲгҒ«жңҖеҫҢгҒ«жҢҝе…ҘгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®дҪҚзҪ®гҒ§д»–гҒ®иҝ«зҹігӮ’еӣәгӮҒгӮӢеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҖӮ
иЈ…йЈҫгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹгӮҠдёӢж–№гҒ«й•·гҒҸ延長гҒ—гҖҒвҖҰвҖҰ

жңЁиІ (гҒҚгҒҠгҒ„)
гҖҢдәҢи»’гҖҚгҒ®и»’иЈҸгҒ®ж§ӢжҲҗгҒҜгҖҒи»’жЎҒгҒӢгӮүгҖҢең°еһӮжңЁгҖҚгӮ’е·®гҒ—еҮәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®йј»е…ҲгӮ’е°‘гҒ—жҺ§гҒҲгҒҰгҖҢжңЁиІ гҖҚгӮ’йҖҡгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жәқгӮ’еҪ«гҒЈгҒҰгҖҢйЈӣжӘҗеһӮжңЁгҖҚгӮ’иҗҪгҒ—иҫјгҒҝжҢәеҮәпјҲгҒҰгҒ„гҒ—гӮ…гҒӨпјүгҒҷгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҢйЈӣжӘҗеһӮжңЁгҖҚгҒ®йј»е…ҲгӮ’е°‘гҒ—жҺ§гҒҲгҒҰгҖҢиҢ…иІ пјҲгҒӢгӮ„вҖҰвҖҰ

жңЁеӯҗдёғйғҺ(гҒҚгҒ”гҒ—гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1884пҪһ1955)
еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«е…¬е…ұе»әзҜүгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеҰ»гӮ«гғ„гҒ®зҲ¶гҒ®ж–°з”°й•·ж¬ЎйғҺпјҲж–°з”°еёҜйқ©иЈҪдҪңжүҖеүөе§ӢиҖ…пјүй–ўдҝӮгҒ®дҪңе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§жңЁеӯҗдёғйғҺйӮёгҖҒж—§ж–°з”°й•·ж¬ЎйғҺзҗҙд№ғжөҰеҲҘйӮёпјҲжё©еұұиҚҳпјүгҖҒж—§вҖҰвҖҰ

еІёз”°ж—ҘеҮәеҲҖ(гҒҚгҒ—гҒ гҒІгҒ§гҒЁгҖҒ1899пҪһ1966)
е»әзҜүеӯҰиҖ…гғ»е»әзҜү家гҖӮжҲҰеүҚгғ»жҲҰеҫҢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒе»әзҜүеҲҶйҮҺгҒ®йҖ еҪўж„ҸеҢ иЁӯиЁҲгҒ®жЁ©еЁҒгҖӮзҰҸеІЎзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҜҚж ЎгҒ«е…ҘиҒ·гҖҒеІёз”°з ”з©¶е®ӨгҒ«гҒҜгҖҒдё№дёӢеҒҘдёүгғ»еүҚе·қеңӢз”·гғ»з«ӢеҺҹйҒ“йҖ гғ»жөңеҸЈйҡҶдёҖгӮүгҒҢеңЁзұҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҪңе“ҒвҖҰвҖҰ

жңЁйј»(гҒҚгҒ°гҒӘ)
гҖҢжңЁйј»гҖҚгҒ®гҖҢйј»гҖҚгҒҜгҖҢз«ҜпјҲгҒҜгҒӘпјүгҖҚгҒ®ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгғ»иӮҳжңЁгғ»й ӯиІ«гғ»иҷ№жўҒгҒӘгҒ©гҒ®ж°ҙе№іжқҗгҒҢгҖҒжҹұгҒӘгҒ©гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰзӘҒеҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜзӘҒеҮәгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒӣгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚпјҲгҖҢжҺӣйј»гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶпјүгҒ®иЈ…йЈҫгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹеҪ«еҲ»гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҗҢйЎһгҒ«гҒҜгҖҒжҸЎгӮҠжӢігҒ®вҖҰвҖҰ

е®ўж®ҝ(гҒҚгӮғгҒҸгҒ§гӮ“)
гҖҖ

гӮӯгғЈгғҺгғ”гғј(гҒҚгӮғгҒ®гҒҙгғј)
canopyгҖӮеӨ©и“ӢеҪўгҒ®еәҮгҖӮеұӢж №зҠ¶гҒ®ејөгӮҠеҮәгҒ—гғҶгғігғҲгҖӮе•Ҷеә—гҒ®еә—е…ҲгӮ„гғӣгғҶгғ«гҒ®еҮәе…ҘгӮҠеҸЈгҒӘгҒ©гҒ«ж—ҘйҷӨгҒ‘гӮ„йӣЁйҷӨгҒ‘гҒ®зӣ®зҡ„гҒ§е·®гҒ—жҺӣгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеәҮгҖӮ

гӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«(гҒҚгӮғгҒҙгҒҹгӮӢ)
capitalгҖӮжҹұй ӯгҖӮиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«гҒҜдёҠгҒӢгӮүгҒ®еҠӣгҒЁгҒқгӮҢгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢеҠӣгҒЁгҒ®жҺҘзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸӨд»Јд»ҘжқҘгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°еҪ«еҲ»зҡ„гҒ«иЈ…йЈҫгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҪўгҒ«гҒҜгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®гҖҢгғ‘гғ”гғ«гӮ№жҹұгҖҚгӮ„гҖҢгғӯгғјгӮҝгӮ№жҹұгҖҚгҖҢгғ‘гғ«гғЎгғғгғҲжҹұгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӨҚзү©вҖҰвҖҰ

гӮ®гғЈгғ©гғӘгғј(гҒҺгӮғгӮүгӮҠгғј)
galleryгҖӮдҪҝз”ЁзҜ„еӣІгҒҢеәғгҒ„иӘһгҖӮеҒҙйқўгҒҢйғЁеҲҶзҡ„гҒҫгҒҹгҒҜе…ЁдҪ“гҒ«й–ӢгҒӢгӮҢгҖҒжҹұгҒ§ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҹеұӢж №гӮ’жҢҒгҒӨжӯ©иЎҢз”ЁгҒ®з©әй–“гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮзҙ°й•·гҒҸгҒҰзӢӯгҒ„е»ҠдёӢгӮ„е®ӨгӮ’жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҠҮе ҙгҒ®пј’йҡҺд»ҘдёҠгҒ®е®ўеёӯгӮ„гҖҒдҪ“иӮІйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®еҶ…еЈҒгҒӢгӮүзӘҒвҖҰвҖҰ

зөҢгғҺе·»(гҒҚгӮҮгҒҶгҒ®гҒҫгҒҚ)
гҖҖ

擬жҙӢйўЁе»әзҜү(гҒҺгӮҲгҒҶгҒөгҒҶгҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸ)
幕жң«гҒӢгӮүжҳҺжІ»жҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ®жҲ‘гҒҢеӣҪгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдё»гҒЁгҒ—гҒҰиҝ‘дё–д»ҘжқҘгҒ®жҠҖиЎ“гӮ’иә«гҒ«д»ҳгҒ‘гҒҹеӨ§е·ҘжЈҹжўҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢиҰӢгӮҲгҒҶиҰӢгҒҫгҒӯгҖҚгҒ§иЁӯиЁҲж–Ҫе·ҘгҒ•гӮҢгҒҹе»әзҜүгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮеҫ“жқҘгҒ®е’Ңж§ҳгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒЁгҒ—гҒҹе»әзҜүгҒ«гҖҒиҘҝжҙӢе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙзҡ„ж„ҸеҢ гӮ„гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜдёӯиҸҜйўЁвҖҰвҖҰ

йӯҡе°ҫеҪўжҮёйӯҡ(гҒҺгӮҮгҒігҒҢгҒҹгҒ’гҒҺгӮҮ)
гҖҖ

еҲҮжҮёйӯҡ(гҒҚгӮҠгҒ’гҒҺгӮҮ)
гҖҖ

еҲҮзӣ®зёҒ(гҒҚгӮҠгӮҒгҒҲгӮ“)
еӨ§еҫіеҜәеұұй–ҖгҒ®дёҠеұӨгҒ®гҖҢеӢҫ欄гҖҚдёӢгҒ®гҖҢзёҒгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢзёҒжЎҶгҖҚпјҲгҖҢжҺҫгҖҚгҒ®йј»е…ҲгҒ®жқҗпјүгҒ®гҒҝгӮ’еҺҡгҒҝгҒ®гҒӮгӮӢжқҗгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒгҒқгҒ“гҒ«зёҰгҒ®гҖҢеә•зӣ®ең°гҖҚгӮ’еҲҮгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҖҢеҲҮзӣ®зёҒйўЁгҖҚгҒ«иҰӢгҒӣгҒӢгҒ‘гӮӢзҙ°е·ҘгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгҒ°гҖҢгҒӘгӮ“гҒЎгӮғгҒЈгҒҰеҲҮзӣ®зёҒгҖҚгҒ§гҒӮвҖҰвҖҰ

еҲҮзӣ®й•·жҠј(гҒҚгӮҠгӮҒгҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҖ

е®®ж®ҝ(гҒҸгҒҶгҒ§гӮ“)
гҖҖ

ж«ӣеһӢгғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ(гҒҸгҒ—гҒҢгҒҹгҒәгҒ§гҒғгӮҒгӮ“гҒЁ)
segmental pedimentгҖӮеҶҶеј§еҪўгҒ® гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

еңӢжһқеҚҡ(гҒҸгҒ«гҒҲгҒ гҒІгӮҚгҒ—гҖҒ1879пҪһ1943)
еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеІҗйҳңзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒ«еңЁд»»дёӯгҖҒжңқй®®з·ҸзқЈеәңеәҒиҲҺгҒ®иЁӯиЁҲгҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҖӮ1919е№ҙеӨ§йҳӘгҒ«еңӢжһқе…¬еӢҷжүҖгӮ’и§ЈиӘ¬гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еӨ§йҳӘеәңиҫІе·ҘйҠҖиЎҢеӨ–иЈ…ж”№дҝ®гҖҒж—§е…«жңЁйҖҡе•Ҷжң¬зӨҫвҖҰвҖҰ

д№…йҮҺзҜҖ(гҒҸгҒ®гҒҝгҒ•гҒҠгҖҒ1882пҪһ1962)
е әеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮйү„йҒ“зңҒеҲқд»Је»әзҜүиӘІй•·гҒӘгҒ©гӮ’зөҢгҒҰд№…йҮҺиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮеҫҢе№ҙгҖҒжҲёз”°е»әиЁӯгҒ®зӣёи«ҮеҪ№гҒ«е°ұд»»гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеҚғи‘үзңҢз«ӢдҪҗеҖүй«ҳзӯүеӯҰж Ўж—§жң¬йӨЁгҖҒеҚ—жө·гғ“гғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјҲзҸҫй«ҳеі¶еұӢеӨ§йҳӘеә—пјүгҖҒж—§еҸӮе®®жҖҘиЎҢвҖҰвҖҰ

зө„еӢҫ欄(гҒҸгҒҝгҒ“гҒҶгӮүгӮ“)
гҖҖ

йӣІж–—гғ»йӣІиӮҳжңЁ(гҒҸгӮӮгҒЁгғ»гҒҸгӮӮгҒІгҒҳгҒҚ)
зҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®зө„зү©гҒҜгҖҒгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸжі•йҡҶеҜәгҒ®гҖҢйӣІж–—гғ»йӣІиӮҳжңЁгҖҚпјҲйӣІж–—ж ұпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзө„зү©гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҖҒж°ҙе№ігҒ«жҢәеҮәпјҲгҒҰгҒ„гҒ—гӮ…гҒӨпјүгҒ—гҒҹгҖҢиӮҳжңЁпјҲгҒІгҒҳгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«д№—гҒЈгҒҰж¬ЎгҒ®гҖҢиӮҳжңЁгҖҚгӮ„гҖҢдёёжЎҒпјҲгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶпјүгҖҚгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢвҖҰвҖҰ

йӣІж–—ж ұ(гҒҸгӮӮгҒЁгҒҚгӮҮгҒҶ)
гҖҖ

и”өз”°е‘Ёеҝ (гҒҸгӮүгҒҹгҒЎгҒӢгҒҹгҒ гҖҒ1895пҪһ1966)
еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ® е ҖеҸЈжҚЁе·ұ гӮүгҒЁзҹҘгӮҠеҗҲгҒ„еҗҢдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҖӮиЎЁзҸҫдё»зҫ© гҒӢгӮүгғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒҫгҒ§е№…еәғгҒ„ж§ҳејҸгҒ®е»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮеұұеҸЈзңҢиҗ©еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲе…ғгҒҜгҖҒжөңеІЎе‘Ёеҝ пјүе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰгҒ®еүҚиә«пјүеҚ’гҖӮжӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒӘгҒ©гӮ’вҖҰвҖҰ

гӮҜгғӘгӮўгӮ№гғҲгғјгғӘгғј(гҒҸгӮҠгҒӮгҒҷгҒЁгғјгӮҠгғј)
clerestorey windowгҖӮй«ҳзӘ“гҖӮжҳҺеұӨгҖӮе…ғгҒҜгҖҒж•ҷдјҡе ӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒ®еЈҒгҒ®жңҖдёҠйғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзӘ“гҒ®еҲ—гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҗҢж§ҳгҒ®ж–№ејҸгҒ«гӮҲгӮӢжҺЎе…үзӘ“гҒ®йғЁеҲҶгӮӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е‘јгҒ¶гҖӮж©ҹиғҪзҡ„гҒ«гҒҜвҖҰвҖҰ

еҲіжҠңиҹҮиӮЎ(гҒҸгӮҠгҒ¬гҒҚгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)
гҖҖ

жҰ‘зёҒгғ»жҰ‘жқҝ(гҒҸгӮҢгҒҲгӮ“гғ»гҒҸгӮҢгҒ„гҒҹ)
гҖҖ

гӮІгӮӘгғ«гӮ°гғ»гғҮгғ»гғ©гғ©гғігғҮ(гҒ’гҒҠгӮӢгҒҗгғ»гҒ§гғ»гӮүгӮүгӮ“гҒ§ Georg de Lalande 1872пҪһ1914)
зӢ¬еӣҪеҮәиә«гҒ®е»әзҜү家гҖӮж—Ҙжң¬гҒ§иЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮж—Ҙжң¬гҒ«гғҰгғјгӮІгғігғҲгғ»гӮ·гғҘгғҶгӮЈгғјгғ«пјҲгӮўгғјгғ«гғ»гғҢгғјгғҙгӮ©гғјпјүж§ҳејҸгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдҪңе“ҒгҒҜгҖҒгғҲгғјгғһгӮ№йӮёпјҲйҮҚж–Ү/йўЁиҰӢй¶ҸгҒ®йӨЁпјүгҖҒж—§гғӯгӮ·гӮўй ҳдәӢйӨЁпјҲеҮҪйӨЁеёӮжҷҜиҰіеҪўжҲҗжҢҮвҖҰвҖҰ

еӨ–йҷЈ(гҒ’гҒҳгӮ“)
гҖҖ

й–“ж–—гғ»й–“ж–—жқҹ(гҒ‘гӮ“гҒЁгғ»гҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒӢ)
гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёЎж–—ж ұй–“пјҲжҹұй–“пјүгҒ®гҖҢдёӯеӮҷпјҲгҒӘгҒӢгҒһгҒӘгҒҲпјүгҖҚгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёҠйғЁгҒ«гҖҢй–“ж–—пјҲгҒ‘гӮ“гҒЁпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢж–—гҖҚгҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖҢжқҹгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҢй–“ж–—жқҹпјҲгҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒӢпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ
гҖҢй–“ж–—гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢдёЎж–—ж ұгҒ®вҖҰвҖҰ

еҠҚе·ҙзҙӢ(гҒ‘гӮ“гҒЁгӮӮгҒҲгӮӮгӮ“)
гҖҖ

й–“йқўиЁҳжі•(гҒ‘гӮ“гӮҒгӮ“гҒҚгҒ»гҒҶ)
гҖҖ

гӮігғјгғҠгғјгӮ№гғҲгғјгғі(гҒ“гғјгҒӘгғјгҒҷгҒЁгғјгӮ“)
cornerstoneгҖӮгӮҜгӮ©гӮӨгғіпјҲд»ҸиӘһгҒ®йҡ…гҒ®ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгӮігӮўгғігҒӢгӮүеҮәгҒҹиӘһпјүгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮйҡ…зҹігҖӮз…үз“Ұз©Қ гҒҝгӮ„жҜ”ијғзҡ„е°ҸгҒ•гҒӘзҹігӮ’з©ҚгӮ“гҒ еЈҒдҪ“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҮәйҡ…йғЁеҲҶгҒ«йҡ…йғЁгҒ®иЈңеј·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮ„гӮ„еӨ§гҒҚгӮҒгҒ®зҹігӮ’гҖҒиЎЁйқўгҒҢеӨ§е°ҸдәӨдә’гҒ«вҖҰвҖҰ

гӮігғјгғӢгӮ№(гҒ“гғјгҒ«гҒҷ)
corniceгҖӮгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў гҒ®жңҖдёҠйғЁгҒ®и»’гғ»еЈҒйқўгӮҲгӮҠзӘҒеҮәгҒ—гҒҹиЈ…йЈҫж°ҙе№іеёҜгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜеЈҒдҪ“гҒ®дёҠйғЁгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒеҗ„еұӨгӮ’еҢәеҲҮгӮӢйғЁеҲҶгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘж°ҙе№іеёҜгӮӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮігғјгғӢгӮ№гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҖҢиӣҮи…№гҖҚгҒЁиЁігҒ—гҖҢи»’иӣҮвҖҰвҖҰ

гӮҙгғјгғ«гғҮгғігғ»гғ©гғҶгӮЈгӮӘ(гҒ”гғјгӮӢгҒ§гӮ“гғ»гӮүгҒҰгҒғгҒҠ)
golden ratioгҖӮй»„йҮ‘жҜ”гҖӮ1пјҡ1.618033гҖӮз·ҡеҲҶпјЎпјўгӮ’зӮ№пјЈгҒ§еҶ…еҲҶгҒ—гҖҒпјЎпјЈпјҡпјўпјЈпјқпјЎпјўпјҡпјЎпјЈгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒпјЎпјЈгҒЁпјўпјЈгҒ®жҜ”гӮ’й»„йҮ‘жҜ”гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
жңҖгӮӮз°ЎеҚҳгҒӘдҪңеӣіж–№жі•гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮв‘ жӯЈж–№вҖҰвҖҰ

槓жқҶ(гҒ“гҒҶгҒӢгӮ“)
гҖҖ

ж јзӢӯй–“(гҒ“гҒҶгҒ–гҒҫ)
гҖҖ

ж§ӢжҲҗдё»зҫ©(гҒ“гҒҶгҒӣгҒ„гҒ—гӮ…гҒҺ)
constructivismгҖӮ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҖҒгӮҪгғҙгӮЈгӮЁгғҲгҒ§иҲҲгҒЈгҒҹйқ©ж–°зҡ„гҒӘиҠёиЎ“йҒӢеӢ•гҖӮC.гғһгғ¬гғјгғҙгӮЈгғҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе§ӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖҢгӮ·гғҘгғ—гғ¬гғһгғҶгӮЈгӮ№гғ гҖҚгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжӣҙгҒ«жҠҖиЎ“жҷӮд»ЈгҒ®и«ёжқЎд»¶гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢзҫҺиЎ“ж–ҮеҢ–гӮ’еұ•вҖҰвҖҰ

еҗ‘жӢқ(гҒ“гҒҶгҒҜгҒ„гҖҒгҒ”гҒҜгҒ„)
ж—Ҙжң¬гҒ®зӨҫеҜәе»әзҜүгҒҜгҖҒеҸӨгҒҸгҒҜгҒқгҒ®е№ійқўгҒҢз°ЎеҚҳгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз«ӢйқўгҒ®жӯЈйқўгғ»иғҢйқўгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘе§ҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢе№іе®үжҷӮд»ЈеүҚжңҹгҒ“гӮҚгҒӢгӮүгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸдҪҸе®…зі»гҒ®дҪҸиҰҒжұӮгҒӢгӮүгҒӢгҖҒзҘһзӨҫе»әзҜүгҒ®зҘӯзҘҖдёҠгҒ®йғҪеҗҲгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒзҘһзӨҫжң¬ж®ҝеүҚвҖҰвҖҰ

еӢҫ欄(гҒ“гҒҶгӮүгӮ“)
гҖҢеұұй–ҖгҖҚгҒ®дёҠеұӨгҒ®зёҒе‘ЁгӮҠгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖҢеӢҫ欄гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе®ҹз”ЁгҒ«дҫӣгҒҷгӮӢй«ҳгҒ•гҒ®гӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹз”ЁгӮ’йӣўгӮҢгҒҰгҖҒж„ҸеҢ дёҠгҒӢгӮүгҖҢеӢҫ欄гҖҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒе»әзҜүгӮ’гҒҶгҒҫгҒҸгҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸӨгҒҸгҒӢгӮүиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮпјҲеұұеҸЈгҒ®гҖҢз‘ з’ғе…үеҜәдә”йҮҚеЎ”гҖҚгҒ®гӮҲвҖҰвҖҰ

иҷ№жўҒ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)
гҖҢдәҢйҮҚиҷ№жўҒејҸжһ¶ж§ӢгҖҚгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдёӢгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„ж–№гӮ’гҖҢеӨ§иҷ№жўҒгҖҚгҖҒдёҠгҒ®е°ҸгҒ•гҒ„ж–№гӮ’гҖҢдәҢйҮҚиҷ№жўҒгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҜәйҷўе»әзҜүгҒ®гҖҢеӨ–йҷЈгҖҚгҒ®гҖҢжҹұгҖҚгӮ’зңҒгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢжўҒгӮӮгҖҢеӨ§иҷ№жўҒгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҢз№Ӣиҷ№жўҒпјҲгҒӨгҒӘгҒҺгҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶпјүгҖҚвҖҰвҖҰ

иҷ№жўҒиҹҮиӮЎ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)
гҖҖ

иҷ№жўҒеӨ§з“¶жқҹ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)
гҖҖ

е°ҸеЈҒ(гҒ“гҒӢгҒ№)
гҖҖ

еӣҪйҡӣж§ҳејҸ(гҒ“гҒҸгҒ•гҒ„гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
International styleгҖӮгӮӨгғігӮҝгғјгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«ж§ҳејҸгҖӮиҝ‘д»Је»әзҜүгҒ®еӨҡж§ҳгҒӘеӢ•еҗ‘гҒ®гҒҶгҒЎгҒ§гҖҒеҖӢдәәгӮ„ең°еҹҹгҒ®зү№ж®ҠжҖ§гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒ«е…ұйҖҡгҒӘж§ҳејҸгҒёгҒЁеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮеҖӢгҖ…гҒ®е»әзҜү家гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дё»ејөгӮ„дҪңйўЁгҒ«е№ҫвҖҰвҖҰ

и…°й«ҳжҳҺйҡңеӯҗ(гҒ“гҒ—гҒ гҒӢгҒӮгҒӢгҒ„гҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)
гҖҖ

гӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸ(гҒ”гҒ—гҒЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Gothic styleгҖӮгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜгҒЁгғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒ®дёӯй–“жҷӮжңҹгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгҒқгҒ®ж§ӢжҲҗиҰҒзҙ гҒҜгҖҒгҖҢе°–й ӯеҪўгӮўгғјгғҒгғ»гғӘгғ– гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгғ»гғ•гғ©гӮӨгӮӨгғігӮ°гғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰҒзҙ иҮӘдҪ“гҒҜгӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®зҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮҙгӮ·вҖҰвҖҰ

и…°й•·жҠј(гҒ“гҒ—гҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҖ

еҫЎжүҖжЈҹй¬јжқҝ(гҒ”гҒ—гӮҮгӮҖгҒӯгҒҠгҒ«гҒ„гҒҹ)
гҖҖ

е°ҸеӨ©дә•(гҒ“гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)
дҪҷи«ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢе°ҸеӨ©дә•гҖҚгҒ®е‘јгҒіж–№гҒ«дјјгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢе°ҸеЈҒпјҲгҒ“гҒӢгҒ№пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖгҒ„ж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®д»–гҖҒе»әзү©гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҢе°ҸпјҲгҒ“пјүгҖҚгӮ’жҺҘй ӯиӘһгҒ«еҶ гҒҷгӮӢиЁҖи‘үгҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еҲ—иЁҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ
гҖҢе°Ҹз©ҙпјҲгҒ“гҒӮгҒӘпјүгҖҚгҖҒгҖҢе°ҸжқҝпјҲвҖҰвҖҰ

е°Ҹжһ—жӯЈзҙ№(гҒ“гҒ°гӮ„гҒ—гҒҫгҒ•гҒӨгҒҗгҖҒ1890пҪһ1980)
жҳҺжІ»жң«жңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒе®ҳеәҒ営繕гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮиҒ–еҫіиЁҳеҝөзөөз”»йӨЁпјҲгӮігғігғҡдёҖзӯүжЎҲпјүиЁӯиЁҲиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҶҶең°ж–ҮеӯҗйӮёгҖҒиӢҘ槻зӨјж¬ЎйғҺйӮёгҒӘгҒ©гҒ®дҪҸе®…дҪңе“ҒгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

е°Ҹй–“иҝ”гҒ—(гҒ“гҒҫгҒҢгҒҲгҒ—)
гҖҖ

гӮігғ©гғ (гҒ“гӮүгӮҖ)
columnгҖӮеҶҶжҹұгҖӮеҶҶеҪўж–ӯйқўгҒ®жҹұгҖӮеҸӨе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгғҷгғјгӮ№гғ»жҹұиә«гғ»жҹұй ӯгӮҲгӮҠгҒӘгӮҠгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°жҹұиә«гҒ«иҶЁгӮүгҒҝгӮ’жҢҒгҒӨгҖӮ

гӮігғӘгғігғҲејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ“гӮҠгӮ“гҒЁгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)
Corinthian orderгҖӮ йҗҳзҠ¶гҒ®жҹұй ӯгӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүпјҳгҒӨгҒ®гҖҢгӮўгӮ«гғігӮөгӮ№гҖҚгҒ®иҢҺгҒҢиіӘзҙ гҒӘжёҰе·»иЈ…йЈҫгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зӘҒгҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҹұиә«гҒҜдёҖиҲ¬зҡ„гҒ« гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гӮігғӯгғӢгӮўгғ«ж§ҳејҸ(гҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Colonial styleгҖӮжӨҚж°‘ең°ж§ҳејҸгҖӮ17пҪһ18дё–зҙҖгҒ«гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гғ»гӮ№гғҡгӮӨгғігғ»гӮӘгғ©гғігғҖгҒӘгҒ©гҒ®жӨҚж°‘ең°гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе»әзҜүгӮ„е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮзү№гҒ«гҖҒзұіеӣҪгҒ®жӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ®е»әзҜүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒиӢұеӣҪгҒ®еҸӨе…ёдё»зҫ©ж§ҳејҸгӮ’вҖҰвҖҰ

йҮ‘еүӣз•ҢжӣјиҚјзҫ…(гҒ“гӮ“гҒ”гҒҶгҒӢгҒ„гҒҫгӮ“гҒ гӮү)
гҖҖ

жЁ©ж®ҝ(гҒ”гӮ“гҒ§гӮ“)
гҖҖ

йҮ‘е Ӯ(гҒ“гӮ“гҒ©гҒҶ)
ж—Ҙжң¬жңҖеҸӨгҒ®гҖҢйҮ‘е ӮгҖҚгҒҜгҖҒиҒ–еҫіе®—гғ»з·Ҹжң¬еұұгҖҢжі•йҡҶеҜәгҖҚгҒ®гҒқгӮҢгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬жңҖеӨ§гҒҜгҖҒиҸҜеҺіе®—гғ»еӨ§жң¬еұұгҖҢжқұеӨ§еҜәгҖҚгҒ®гҖҢеӨ§д»Ҹж®ҝгҖҚпјҲжӯЈејҸгҒ«гҒҜгҖҢйҮ‘е ӮгҖҚгҒЁз§°гҒҷгӮӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жі•зӣёе®—гғ»еӨ§жң¬еұұгҖҢиҲҲзҰҸеҜәгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еәҰгҖҢдёӯйҮ‘е ӮгҖҚгҒЁгҖҢжқұйҮ‘е ӮвҖҰвҖҰ

гӮігғігғқгӮёгғғгғҲејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ“гӮ“гҒҪгҒҳгҒЈгҒЁгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)
Composite orderгҖӮгҖҢж··еңЁејҸгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҖҒгҖҢгғӯгғјгғһејҸгӮӘгғјгғҖгғјгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮжҹұй ӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮӘгғӢгӮўејҸгҒ®йЎ•и‘—гҒӘжёҰе·»иЈ…йЈҫгҒЁгӮігғӘгғігғҲејҸгҒ®гӮўгӮ«гғігӮөгӮ№гҒЁгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҖҒжңҖгӮӮиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҹұиә«гҒҜ гғ•гғ«гғјвҖҰвҖҰ
гҒ•гҖңгҒқ

еқӮеҖүжә–дёү(гҒ•гҒӢгҒҸгӮүгҒҳгӮ…гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1901пҪһ1969)
гғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§ гҒ«её«дәӢгҒ—гҖҒгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгӮ’е®ҹи·өгҖӮйғҪеёӮгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–ӢзҷәгҒӢгӮү家具гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеІҗйҳңзңҢзҫҪеі¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйғЁзҫҺеӯҰзҫҺиЎ“еҸІеӯҰ科еҚ’гҖӮжёЎд»ҸгҒ—гғ‘гғӘе·ҘжҘӯеӨ§еӯҰгҒ§е°ұеӯҰгҒҷвҖҰвҖҰ

жЎңдә•е°ҸеӨӘйғҺ(гҒ•гҒҸгӮүгҒ„гҒ“гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1870пҪһ1953)
ж—Ҙжң¬еҲқгҒ®иӢұеӣҪзҺӢз«Ӣе»әзҜү家еҚ”дјҡе»әзҜүеЈ«гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғӯгғігғүгғіеӨ§еӯҰе»әзҜү家еҚ’гҖӮжө·и»ҚжҠҖеё«гӮ’зөҢгҒҰдёүиҸұең°жүҖгҒ«е…ҘзӨҫгҖҒдёёгҒ®еҶ…гғ“гӮёгғҚгӮ№иЎ—е»әиЁӯгҒ«жҗәгӮҸгӮҠгҖҒеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§е‘үйҺ®е®ҲеәңеҸёд»Өй•·е®ҳе®ҳиҲҺпјҲе…ҘиҲ№еұұиЁҳеҝөйӨЁпјүгҖҒжқұжҙӢж–Үеә«гҖҒвҖҰвҖҰ

笹е·қж…ҺдёҖ(гҒ•гҒ•гҒҢгӮҸгҒ—гӮ“гҒ„гҒЎгҖҒ1889пҪһ1937)
ж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе»әзҜүйғЁжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҳӘзҘһй–“гҒ«зү№иүІгҒ®гҒӮгӮӢдҪҸе®…дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе°ҸеҮәжҘўйҮҚгӮ„еҜҢжң¬еҒҘеҗүгӮүзҫҺ術家гҒЁгӮӮдәӨжөҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҸӨзҫҺиЎ“и’җйӣҶ家гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮй«ҳеҗҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеІёжң¬з“Ұз”әйӮёгҒҢзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢгҖӮ

笹繰(гҒ•гҒ•гҒҗгӮҠ)
йЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгӮ„гҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢзҙ°йғЁж„ҸеҢ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠгҒ«д№—гӮӢгҖҒжүӢеүҚгҒЁжүӢе…ҲгҒ®гҖҢж–—гҖҚгҒ®й–“гҒ®гҖҒгҒқгҒ®дёҠз«ҜгӮ’гҖҒиҰӢйҷ„гҒҢгҖҢ笹гҒ®и‘үгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ«гҖҒж–ңгӮҒгҒ«жҠүгҒЈгҒҰиҰӢгҒӣгӮӢгҖҒз№Ҡзҙ°гҒӘзҙ°е·ҘгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮиӮҳгӮ’ејөгҒЈгҒҰжҢҒвҖҰвҖҰ

жҢҮйҙЁеұ…(гҒ•гҒ—гҒҢгӮӮгҒ„)
гҖҖ

жҢҮж•·еұ…(гҒ•гҒ—гҒҳгҒҚгҒ„)
гҖҖ

жҢҝиӮҳжңЁ(гҒ•гҒ—гҒІгҒҳгҒҚ)
жқұеӨ§еҜәеҚ—еӨ§й–ҖгҒ®ж–ӯйқўеӣігӮ’гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еӯ”гӮ’з©ҝпјҲгҒҶгҒҢпјүгҒЎжҢҝгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖҢжҢҝиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠгҒ«гҖҢж–—гҖҚгӮ’жҚ®гҒҲгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«гҖҢжҹұгҖҚгӮ’иІ«йҖҡгҒ—гҒҰдјёгҒігҒҰгҒҸгӮӢгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгҒҹгҖҢйҖҡиІ«пјҲгҒЁгҒҠгҒ—гҒ¬гҒҚпјүгҖҚгӮ’д№—гҒӣгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҢж–—гҖҚгҒ®вҖҰвҖҰ

жү йҰ–(гҒ•гҒҷ)
еұӢж №гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢе°ҸеұӢзө„гҒ®дёҖгҒ§гҖҒгҖҢж•·жЎҒпјҲиҷ№жўҒпјүгҖҚгҒЁзҷ»жўҒгҒ§гҒӮгӮӢдәҢжң¬гҒ®гҖҢеҗҲжҺҢпјҲжү йҰ–з«ҝпјүгҖҚгҒЁгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢдәҢзӯүиҫәдёүи§’еҪўгҒ®еҚҳзҙ”гҒӘгғҲгғ©гӮ№еҪўејҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҖҢж•·жЎҒгҖҚгҒ«гҖҢжү йҰ–з«ҝгҖҚгҒ®е…Ҳз«ҜгӮ’гҖҒж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҢжү гҒҷпјҲжҢҝгҒҷпјүгҖҚгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—вҖҰвҖҰ

жү йҰ–з«ҝгғ»жү йҰ–жқҹ(гҒ•гҒҷгҒ–гҒҠгғ»гҒ•гҒҷгҒҘгҒӢ)
гҖҖ

дҪҗз«Ӣдёғж¬ЎйғҺ(гҒ•гҒҹгҒЎгҒ—гҒЎгҒҳгӮҚгҒҶгҖҒ1856пҪһ1922)
й«ҳжқҫеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科第1жңҹеҚ’гҖӮе·ҘйғЁзңҒгғ»жө·и»ҚзңҒгғ»и—Өз”°зө„гғ»йҖ“дҝЎзңҒгғ»ж—Ҙжң¬йғөиҲ№гҒ«жүҖеұһгҖӮе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүйҖ 家еӯҰ科ж•ҷе“ЎгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдҪңе“ҒгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬ж°ҙжә–еҺҹзӮ№жЁҷеә«пјҲйҮҚж–ҮгҖҒзҸҫеңЁгӮӮе…¬зҡ„е»әйҖ зү©гҒЁвҖҰвҖҰ

дҪҗи—ӨеҠҹдёҖ(гҒ•гҒЁгҒҶгҒ“гҒҶгҒ„гҒЎгҖҒ1878пҪһ1941)
ж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гҒ®еүөе§ӢиҖ…гҖӮж ғжңЁзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҲ‘гҒҢеӣҪгҒ®е»әзҜүеӯҰдјҡгҒ®йҮҚйҺ®гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒҷгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе®®еҹҺзңҢеәҒиҲҺгҖҒж ғжңЁзңҢеәҒиҲҺгҖҒж»ӢиіҖзңҢеәҒиҲҺгҖҒж—ҘжҜ”и°·е…¬дјҡе ӮгҖҒж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰеӨ§йҡҲвҖҰвҖҰ

дҪҗи—ӨжӯҰеӨ«(гҒ•гҒЁгҒҶгҒҹгҒ‘гҒҠгҖҒ1899пҪһ1972)
е»әзҜүйҹійҹҝеӯҰгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ§гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгғҲгғӘгӮўгғ иЁӯиЁҲгҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…гҖӮеҗҚеҸӨеұӢеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪҗи—ӨеҠҹдёҖгҒ«её«дәӢгҖӮж—Ҙе…үжқұз…§е®®гҒ®жң¬ең°е ӮгҒ§иө·гҒ“гӮӢгҖҢйіҙйҫҚгҖҚгҒ®зҸҫиұЎгӮ’科еӯҰзҡ„гҒ«и§ЈжҳҺгҒҷгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰеӨ§йҡҲиЁҳеҝөи¬ӣе ӮвҖҰвҖҰ

дҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ(гҒ•гҒ®гҒЁгҒ—гҒӢгҒҹгҖҒ1880пҪһ1956)
ж—Ҙжң¬гҒ®ж§ӢйҖ еӯҰгҒ®зҷәеұ•гҒ«еӨҡеӨ§гҒӘиІўзҢ®гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҖӮеұұеҪўзңҢеҮәиә«гҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҒ®йғҪеёӮеҫ©иҲҲгҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»гҒ«еҫ“дәӢгҖӮеӣҪжҠҖйӨЁгҖҒжқұдә¬й§…гҖҒеҫ©иҲҲе°ҸеӯҰж Ўе»әзҜүеӨҡж•°гҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеәҒиҲҺгҖҒеӯҰеЈ«дјҡйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮ

йҜ–е°»(гҒ•гҒ°гҒҳгӮҠ)
гҖҖ

зҡҝж–—(гҒ•гӮүгҒЁ)
гҖҖ

жЎҹе”җжҲё(гҒ•гӮ“гҒӢгӮүгҒ©)
гҖҢжЈ§е”җжҲёгҖҚгҒҢжёЎжқҘгҒҷгӮӢйҡҸеҲҶгҒЁд»ҘеүҚгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҒе№…гҒ®зӢӯгҒ„з«ӘзҫҪзӣ®ејөгӮҠгӮ’иЈҸгҒ®жЈ§гҒ§жӯўгӮҒгӮӢгҖҒзүҮйқўејөгӮҠгҒ®гҖҢжқҝжЈ§жҲёпјҲгҒ„гҒҹгҒ•гӮ“гҒЁпјүгҖҚгҒҢеӨҡгҒҸдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе№іе®үжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ®е№ізӯүйҷўйііеҮ°е ӮгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜдёЎйқўејөгӮҠгҒ®з«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§вҖҰвҖҰ

дёүеҚҒз•ӘзҘһе Ӯ(гҒ•гӮ“гҒҳгӮ…гҒҶгҒ°гӮ“гҒ—гӮ“гҒ©гҒҶ)
гҖҖ

гӮёгӮ§гғјгғ гӮ№гғ»гӮ¬гғјгғҮгӮЈгғҠгғј(гҒҳгҒҮгғјгӮҖгҒҷгғ»гҒҢгғјгҒ§гҒғгҒӘгғј James McDonald Gardiner 1857пҪһ1925)
зұіеӣҪдәәе»әзҜү家гғ»ж•ҷиӮІе®¶гҖӮзұіеӣҪгӮ»гғігғҲгғ«гӮӨгӮ№з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҸгғјгғҗгғјгғүеӨ§еӯҰдёӯйҖҖгҖӮпјҲжң¬ж јзҡ„гҒӘе»әзҜүж•ҷиӮІгҒҜеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢпјүзұіеӣҪиҒ–е…¬дјҡдјқйҒ“еұҖгҒӢгӮүзҜүең°гҒ®з«Ӣж•ҷеӯҰж ЎгҒёгҒ®жҙҫйҒЈгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҖҒз«Ӣж•ҷеӯҰж ЎеҲқд»Јж Ўй•·гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮж Ўй•·йҖҖд»»еҫҢгҖҒжң¬вҖҰвҖҰ

ең°еҶҶйЈӣи§’(гҒҳгҒҲгӮ“гҒІгҒӢгҒҸ)
е№іе®үжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®еҹәжң¬гҒҜгҖҒдёЎж–№гҒЁгӮӮи§’жқҗгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒгҖҢең°и§’йЈӣи§’гҖҚгҒЁеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮеҸӘгҖҒеҸӨд»ЈгҒ®еҪўејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гӮӮгҒқгҒ®йҒ•дҫӢгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгҖҢең°еҶҶйЈӣи§’гҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒи–¬вҖҰвҖҰ

ж•·еұ…(гҒ—гҒҚгҒ„)
гҖҖ

иҢӮеә„дә”йғҺ(гҒ—гҒ’гҒ—гӮҮгҒҶгҒ”гӮҚгҒҶгҖҒ1863пҪһ1913)
жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ«й–ўиҘҝгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҒй–ўиҘҝгҒ®е»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгҒ®иҚүеҲҶгҒ‘зҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҖӮй•·еҙҺзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科е°Ӯ科еҚ’гҒ®еҫҢгҖҒе°јеҙҺзҙЎзёҫжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰе·Ҙе ҙзҸҫе ҙгӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеӨ§йҳӘгҒ«иҢӮе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе°јеҙҺвҖҰвҖҰ

з№ҒеһӮжңЁ(гҒ—гҒ’гҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҢз№ҒеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰж јејҸгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹе»әзү©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж јејҸгӮ’дёӢгҒ’гӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜдҪҸе®…зі»гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеһӮжңЁгҒ®гғ”гғғгғҒгӮ’еәғгҒ’гӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒжҳҺгҒҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҖҢз–ҺеһӮжңЁпјҲгҒҫгҒ°гӮүгҒ гӮӢгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҳҺгҒҚгӮ’еәғгҒ’вҖҰвҖҰ

йҢЈи‘ә(гҒ—гҒ“гӮҚгҒ¶гҒҚ)
гҖҖ

зҚ…еӯҗеҸЈ(гҒ—гҒ—гҒҗгҒЎ)
е„ҖејҸгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖҢй¬јйқўгҖҚгӮ„гҖҢй¬јжқҝгғ»й¬јз“ҰгҖҚгҒҢжҠҪиұЎеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгҒ®еҗҚз§°гҒ®з”ұжқҘгҒҜдёҚжҳҺгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ«гҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹжЈҹгӮ’гҖҢеҫЎжүҖжЈҹгҖҚгҒЁе‘јгӮ“гҒ гӮүгҒ—гҒҸгҖҒгҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гҖҢеҫЎжүҖжЈҹй¬јжқҝвҖҰвҖҰ

зҚ…еӯҗйј»(гҒ—гҒ—гҒ°гҒӘ)
гҖҖ

дёӢең°зӘ“(гҒ—гҒҹгҒҳгҒҫгҒ©)
гҖҖ

ең°еһӮжңЁ(гҒҳгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

дёғе®қжұ (гҒ—гҒЈгҒҪгҒҶгҒ„гҒ‘)
гҖҖ

йҺ¬(гҒ—гҒ®гҒҺ)
гҖҖ

еӣӣеҚҠж•·(гҒ—гҒҜгӮ“гҒҳгҒҚ)
гҖҢеӣӣеҚҠж•·гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣӣеҚҒдә”еәҰгҒ«жҢҜгӮүгҒҡгҖҒе»әзү©гҒЁе№іиЎҢгҒ«зўҒзӣӨгҒ®зӣ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж•·гҒҸе ҙеҗҲгҒҜгҖҢзўҒзӣӨж•·пјҲгҒ”гҒ°гӮ“гҒҳгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
ж–№еҪўгҒҫгҒҹгҒҜзҹ©еҪўгҒ®еҲҮзҹігӮ„ж•·з“ҰгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒдёҖж–№еҗ‘гҒҜзӣ®ең°гӮ’йҖҡгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒЁзҹ©жүӢж–№еҗ‘гҒ®зӣ®ең°гҒҜдәӨдә’гҒ«йҖҡгҒ—гҒҹгӮӮвҖҰвҖҰ

ең°иҰҶй•·жҠј(гҒҳгҒөгҒҸгҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҖ

жё…ж°ҙиӢұдәҢ(гҒ—гҒҝгҒҡгҒҲгҒ„гҒҳгҖҒ1895пҪһ1964)
зҘһжҲёеёӮеҶ…гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе…өеә«зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖҒжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮгғүгӮӨгғ„ иЎЁзҸҫдё»зҫ© гӮ’е§ӢгӮҒгҖҒгӮўгғјгғ«гғҮгӮігғ»еӣҪйҡӣдё»зҫ©пјҡгғӯгӮ·гӮў ж§ӢжҲҗдё»зҫ© гҒӘгҒ©еӨҡеҪ©гҒӘж§ҳејҸгӮ’жҠҳиЎ·гҒ—гҖҒйҳӘзҘһй–“гҒ®гғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒ«еҪ©гӮ’ж·»гҒҲгҒҹвҖҰвҖҰ

йҢ«жқ–еҪ«(гҒ—гӮғгҒҸгҒҳгӮҮгҒҶгҒјгӮҠ)
гҖҖ

гӮёгғЈгӮігғ“гӮўгғіж§ҳејҸ(гҒҳгӮғгҒ“гҒігҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Jacobean styleгҖӮиӢұеӣҪгӮёгӮ§гғјгғ гӮ№1дё–гҒ®жІ»дё–пјҲ1603пҪһ1625пјүгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе»әзҜүгғ»е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮеһӮзӣҙејҸгӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®гғўгғҶгӮЈгғјгғ•гҒЁгҖҒгҒ„гҒ•гҒ•гҒӢжҝ«з”ЁгҒҺгҒҝгҒ®еҸӨе…ёзҡ„иЈ…йЈҫгҒ®ж··еңЁгҒ«зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
е…ҲиЎҢгҒҷгӮӢ гӮЁгғӘвҖҰвҖҰ

гӮ·гғЈгғ•гғҲ(гҒ—гӮғгҒөгҒЁ)
shaftгҖӮжҹұиә«

дё»ж®ҝйҖ (гҒ—гӮ…гҒ§гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)
е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢеҜқж®ҝйҖ гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҜқж®ҝгҖҚгҒ®д»–гҖҢеҜҫгҒ®еұӢгҖҚгҖҢйҮЈж®ҝгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒе®ӨгҒ®ж§ӢжҲҗгҒҜгҖҢжҜҚеұӢгғ»еәҮгҖҚгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳзҙ”гҒӘе»әзү©гӮ’гҖҒеәғеӨ§гҒӘж•·ең°гҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’гҖҢжёЎе»ҠгҖҚгҒ§гҒӨгҒӘгҒҗеҪўејҸгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮҠзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгҖҢвҖҰвҖҰ

гӮ·гғҘгғ—гғ¬гғһгғҶгӮЈгӮ№гғ (гҒ—гӮ…гҒ·гӮҢгҒҫгҒҰгҒғгҒҷгӮҖ)
suprД“matismeгҖӮзө¶еҜҫдё»зҫ©гҖӮ1913е№ҙгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®C.гғһгғ¬гғјгғҙгӮЈгғҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе”ұгҒҲгӮүгӮҢгҒҹдё»зҫ©гҖӮзөөз”»гҒӢгӮүж–ҮеӯҰзҡ„гғ»иЁҳиҝ°зҡ„иҰҒзҙ гӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҒҰгҖҒзҙ”зІӢгҒ§зө¶еҜҫзҡ„гҒӘж„ҹжғ…гӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮгҒ“гҒ®жҠҪиұЎзҫҺиЎ“гҒёгҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

й ҲејҘеЈҮ(гҒ—гӮ…гҒҝгҒ гӮ“)
дёҠд»ЈгҒ®гҖҢй ҲејҘеЈҮгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢи–¬её«еҜәйҮ‘е ӮгҖҚеҶ…гҒ®зҷҪеӨ§зҗҶзҹігҒ®гӮӮгҒ®гӮ„гҖҒгҖҢе”җжӢӣжҸҗеҜәйҮ‘е ӮгҖҚеҶ…гҒ®иҠұеҙ—еІ©еЈҮдёҠз©Қж јзӢӯй–“пјҲгҒ“гҒҶгҒ–гҒҫпјүе…ҘгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжңЁйҖ гҒ§гҒҜгҖҢжқұеӨ§еҜәжі•иҸҜе ӮгҖҚеҶ…гҒ®е…«и§’дәҢйҮҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
е№іе®үвҖҰвҖҰ

гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгғіж§ҳејҸ(гҒҳгӮҮгғјгҒҳгҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Georgian styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ§гҖҒ18дё–зҙҖгҒӢгӮү19дё–зҙҖдёӯй ғгҒ«еҚідҪҚгҒ—гҒҹгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёпј‘дё–гҒӢгӮүпј”дё–гҒҫгҒ§гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹе»әзҜүгҒЁе®¶е…·гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіж§ҳејҸгҖӮгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜж§ҳејҸ гӮ„ гғӯгӮігӮіж§ҳејҸ гҒ«иҝ‘гҒ—гҒҸгҖҒжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢвҖҰвҖҰ

жӣёйҷўйҖ (гҒ—гӮҮгҒ„гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)
гҖҢеҜқж®ҝйҖ гҖҚгҒӢгӮүгҖҢжӣёйҷўйҖ гҖҚгҒёгҒ®з§»иЎҢгҒ«гҒҜгҖҒй•·гҒ„жҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгӮ’иҰҒгҒ—гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҪўејҸдёҠгҒ®жЁЎзҙўгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдә’гҒ„гҒ«еҪұйҹҝгҒ—еҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҖҢеәҠеҗҢжҷӮдёҰиЎҢзҡ„гҒ«йҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮд»ҘеүҚгҒҜгҖҒгҖҢжӯҰ家йҖ гҖҚгӮ„гҖҢдё»ж®ҝйҖ гҖҚгҒЁз§°гҒ•гӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

жӣёйҷўзӘ“(гҒ—гӮҮгҒ„гӮ“гҒҫгҒ©)

е®ҡиҰҸзӯӢ(гҒҳгӮҮгҒҶгҒҺгҒҷгҒҳ)

дёҠж®өгҒ®й–“(гҒҳгӮҮгҒҶгҒ гӮ“гҒ®гҒҫ)

жӯЈе Ӯ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒ©гҒҶ)

жө„еңҹеәӯең’(гҒҳгӮҮгҒҶгҒ©гҒҰгҒ„гҒҲгӮ“)
е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ«гҖҢжө„еңҹпјҲејҸпјүеәӯең’гҖҚгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ®зҰ…е®—зі»гҒ®еәӯең’гҒҢйҖ гӮүгӮҢе§ӢгӮҒгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒгҒ“гҒ®ең°жіүеҪўејҸгҒҢз¶ҷз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҢжң«жі•жҖқжғігҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӢҘе№Іиҝ°гҒ№гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮдјқж•ҷеӨ§её«жңҖжҫ„гҒҜгҖҢжң«жі•зҮҲжҳҺиЁҳгҖҚгҒ«вҖҰвҖҰ

иҸ–и’ІжЎҒ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒ¶гҒ’гҒҹ)

гӮёгғ§гӮөгӮӨгӮўгғ»гӮігғігғүгғ«(гҒҳгӮҮгҒ•гҒ„гҒӮгғ»гҒ“гӮ“гҒ©гӮӢ Josiah Conder 1852пҪһ1920)
иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ«еҗ‘гҒ‘гҖҒжҳҺжІ»ж”ҝеәңгҒҢиҝҺгҒҲгҒҹгҒҠйӣҮгҒ„еӨ–еӣҪдәәгҖӮе·ҘйғЁзңҒе·ҘдҪңеұҖжҠҖиЎ“е®ҳгҖӮ
ж—Ҙжң¬дәәе»әзҜүеҢ–гҒ®иӮІжҲҗгҒ«еҠӘгӮҒгҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒдёҠйҮҺеҚҡзү©йӨЁгҖҒй№ҝйіҙйӨЁгҖҒгғӢгӮігғ©гӮӨиҒ–е ӮгҖҒдёүиҸұдёҖеҸ·йӨЁгҖҒж№Ҝеі¶еІ©еҙҺйӮёгҖҒдёүдә•еҖ¶жҘҪйғЁгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гӮёгғ§гғігғ»гғҗгғігғ»гӮҰгӮЈгғ»гғҗгғјгӮ¬гғҹдәҢвҖ•(гҒҳгӮҮгӮ“гғ»гҒ°гӮ“гғ»гҒҶгҒғгғ»гҒ°гғјгҒҢгҒҝгҒ«гғј John van Wie Bergamini 1888пҪһ1975)
зұіеӣҪдәәгғҹгғғгӮ·гғ§гғізі»гҒ®е»әзҜү家гҖӮй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҖҒзұіеӣҪиҒ–е…¬дјҡгҒӢгӮүиҒ–и·ҜеҠ еӣҪйҡӣз—…йҷўйЎ§е•ҸжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢжқҘж—ҘгҖӮгҒқгҒ®зі»еҲ—гҒ®ж•°гҖ…гҒ®ж–ҪиЁӯиЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеӯҗжҒҜгҒҜгҖҢеӨ©зҡҮгҒ®йҷ°и¬ҖгҖҚгҖҢж•°гҒ®дё–з•ҢгҖҚгҖҢе®Үе®ҷгҖҚгҒ®и‘—жӣёгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢж•°еӯҰиҖ…гғ»зү©вҖҰвҖҰ

зҷҪдә•жҷҹдёҖ(гҒ—гӮүгҒ„гҒӣгҒ„гҒ„гҒЎгҖҒ1905пҪһ1983)
гғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒҢдё»жөҒгҒ®йўЁжҪ®гҒ«зӣёеҸҚгҒ—гҖҒе“ІеӯҰзҡ„гҒЁз§°гҒ•гӮҢгӮӢзІҫзҘһжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„йҮҚеҺҡгҒӘе»әзҜүгӮ’гҒ®гҒ“гҒ—гҒҹгҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰж ЎеӣіжЎҲ科пјҲзҸҫдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰйҖ еҪўз§‘еӯҰ科пјүеҚ’гҖӮжӢ…еҪ“ж•ҷжҺҲгҒҜ жң¬йҮҺзІҫеҗҫгҖӮе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒиұЎеҫҙзҡ„вҖҰвҖҰ

зҘһе®®еҜә(гҒҳгӮ“гҒҗгҒҶгҒҳ)
жҳҺжІ»з¶ӯж–°гҒ®зҘһд»ҸеҲҶйӣўд»ҘеүҚгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®—ж•ҷиҰігҒҜзҘһд»Ҹж··ж·ҶгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢдёҖеўғеҶ…гҒ«гҖҒгҒҠеҜәгҒ§гҒҜгҖҢйҺ®е®ҲзӨҫгҖҚгӮ’гҖҒзҘһзӨҫгҒ§гҒҜгҖҢзҘһе®®еҜәгҖҚгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеёёж…ӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжёЎжқҘгҒҷгӮӢе®—ж•ҷгӮ’гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒҜеҸ–жҚЁйҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеҸ—гҒ‘вҖҰвҖҰ

гӮ·гғігӮ°гғ«ж§ҳејҸ(гҒ—гӮ“гҒҗгӮӢгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
shingle styleгҖӮзұіеӣҪгҒ®жқұйғЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚ—еҢ—жҲҰдәүеҫҢгҒ®19дё–зҙҖеҫҢ
еҚҠгҖҒгӮўгӮ«гғҮгғҹгӮәгғ е»әзҜүгҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҰгҖҒдёӯиҰҸжЁЎдҪҸе®…гҒ«зӢ¬иҮӘгҒ®ж–°ж©ҹи»ёгҒҢжү“гҒЎ
еҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеЈҒгҒӢгӮүеұӢж №гҒҫгҒ§гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰжқүжқҗгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«пјҲжңЁиЈҪгӮҝгӮӨгғ«гғ»вҖҰвҖҰ

иә«иҲҺ(гҒ—гӮ“гҒ—гӮғ)

зңҹеҸҚгӮҠ(гҒ—гӮ“гҒһгӮҠ)

еҜқж®ҝйҖ (гҒ—гӮ“гҒ§гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)
е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®еҜәзӨҫгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳеҢ–гҖҚгҒҢйҖІгӮҖдёӯгҖҒзҡҮж—ҸгҒӘгҒ©дёҠжөҒгҒ®дҪҸе®…еҪўејҸгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮең°дҪҚгҒ«гӮҲгӮҠиҰҸжЁЎгғ»еҪўејҸгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒдёүдҪҚд»ҘдёҠгҒ®ж•·ең°гҒҜгҖҒдёҖз”әпјҲ121пҪҚГ—121пҪҚгҖҒ4430еқӘпјүгҒ§гҖҒе‘ЁеӣІгҒ«гҖҢзҜүең°еЎҖгҖҚгӮ’гӮҒгҒҗгӮүвҖҰвҖҰ

еҝғжҹұ(гҒ—гӮ“гҒ°гҒ—гӮү)

зёӢз ҙйўЁ(гҒҷгҒҢгӮӢгҒҜгҒөгҒҶ)

ж•°еҜ„еұӢйҖ (гҒҷгҒҚгӮ„гҒҘгҒҸгӮҠ)
е®Өз”әжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒӢгӮүе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»ЈгҒҜгҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢеӨ§еҗҚгҒҢзҫӨйӣ„еүІжӢ гҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҲҰд№ұгҒ«дјҙгҒҶзӨҫеҜәгҒ®з ҙеЈҠгҒЁеҫ©иҲҲеҶҚе»әгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜж–°иҰҸгҒ®еҹҺйғӯгӮ„еҹҺдёӢз”әгҒ®е»әиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…ЁеӣҪзҡ„гҒ«з©әеүҚгҒ®е»әзҜүгғ–гғјгғ гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йңҖиҰҒгҒ«еҝңгҒҲгӮӢе·ҘвҖҰвҖҰ

гӮ№гӮҜгғ©гғғгғҒгӮҝгӮӨгғ«(гҒҷгҒҸгӮүгҒЈгҒЎгҒҹгҒ„гӮӢ)
scratch tileгҖӮгӮҝгӮӨгғ«гҒ®иЎЁйқўгӮ’ж«ӣеј•гҒ®гҒ—гҖҒе№іиЎҢгҒ®жәқгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’з„јжҲҗгҒ—гҒҹзІҳеңҹгӮҝгӮӨгғ«гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒҢгҖҒеёқеӣҪгғӣгғҶгғ«пјҲ1890пјүгҒ«з”ЁгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢиүҜгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иӢҶеЈҒ(гҒҷгҒ•гҒӢгҒ№)

йҲҙжңЁзҰҺж¬Ў(гҒҷгҒҡгҒҚгҒҰгҒ„гҒҳгҖҒ1870пҪһ1941)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮйқҷеІЎеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮеҗҚеҸӨеұӢй«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҗҚе·ҘеӨ§пјүж•ҷжҺҲгӮ’зөҢгҒҰзӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ®йҒҺеҚҠгҒҢеҗҚеҸӨеұӢгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҖҢеҗҚеҸӨеұӢгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҹе»әзҜү家гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮеӨҸзӣ®жјұзҹігҒ®зҫ©ејҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

з Ӯж‘әгӮҠеӨ©дә•(гҒҷгҒӘгҒҡгӮҠгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)

з°ҖеӯҗзёҒ(гҒҷгҒ®гҒ“гҒҲгӮ“)

й Ҳжҹұ(гҒҷгҒ°гҒ—гӮү)

гӮ№гғ‘гғӢгғғгӮ·гғҘз“Ұ(гҒҷгҒұгҒ«гҒЈгҒ—гӮ…гҒӢгӮҸгӮү)
spanish roof tileгҖӮпјіеӯ—еҪўзҠ¶гҒ®ж–ӯйқўгӮ’жҢҒгҒӨжҙӢз“ҰгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒзІҳеңҹгҒ®з”ҹең°гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮ’з„јжҲҗгҒ—гҒҹиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢгҒҳиүІгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹйӯ…еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҡ…жүҮеһӮжңЁ(гҒҷгҒҝгҒҠгҒҠгҒҺгҒ гӮӢгҒҚ)

йҡ…延гҒі(гҒҷгҒҝгҒ®гҒі)
иҝ‘дё–гҒ®и»’гҒҜгҖҒжӯЈгҒ—гҒҸгҖҢйҡ…延гҒігҖҚгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҡгҖҒдёЎз«ҜгҒ гҒ‘гӮ’еҸҚгӮҠдёҠгҒ’гҖҒдёӯзЁӢгҒҜзӣҙз·ҡгҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁдёӯеӨ®гҒҢйҢҜиҰҡгҒ®гҒҹгӮҒзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгҒЈгҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒи»’йҡ…гҒ®еҸҚгӮҠдёҠгӮҠгҒҜз”ҡгҒ гҒ—гҒҸгҖҒжҖҘгҒ«йӢӯгҒҸе°–гҒЈвҖҰвҖҰ

йҡ…и“Ӣз“Ұ(гҒҷгҒҝгҒ¶гҒҹгҒҢгӮҸгӮү)
еҪ№зү©з“ҰгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»еұӢж №гӮ„зёӢз ҙйўЁпјҲгҒҷгҒҢгӮӢгҒҜгҒөпјүгҒ«жҺӣз“ҰгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒи»’е·ҙз“Ұгғ»йҡ…е·ҙз“Ұгғ»жҺӣе·ҙз“ҰгҒ®е°»йғЁеҲҶгҒ®жҺҘеҗҲзӮ№гӮ’иҰҶгҒҶз“ҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠжӨҖгҒҫгҒҹгҒҜйү„е…ңгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫгҒ®гҒӘгҒ„е®ҹз”Ёжң¬дҪҚгҒ®з“ҰгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«зЁ®гҖ…гҒ®еҪўвҖҰвҖҰ

дҪҸеҗүйҖ (гҒҷгҒҝгӮҲгҒ—гҒҘгҒҸгӮҠ)
зҘһзӨҫгҒ®жң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»йҖ гҒ§жЈҹгҒ«пј’жң¬гҒ®зҪ®еҚғжңЁпјҲгҒҠгҒҚгҒЎгҒҺпјүгҒЁ3жң¬гҒ®е …йӯҡжңЁпјҲгҒӢгҒӨгҒҠгҒҺпјүгӮ’зҪ®гҒҸгҖӮеҰ»е…ҘгӮҠгҒ§гҖҒжӯЈйқў2й–“еҲҶгӮ’1й–“гҖҒиғҢйқў2й–“гҖҒеҒҙйқў4й–“гҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒҜеүҚеҫҢгҒ«еӨ–йҷЈгҒЁеҶ…йҷЈгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮдё№еЎ—гҒ§еӣһгӮҠзёҒгҒҜвҖҰвҖҰ

гӮ№гғҜгғігғҚгғғгӮҜгғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ(гҒҷгӮҸгӮ“гҒӯгҒЈгҒҸгҒәгҒ§гҒғгӮҒгӮ“гҒЁ)
swan-neck pedimentгҖӮдәҢгҒӨгҒ®еҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгҒҶе№ігӮүгҒӘпјіеӯ—еҪўгҒ®жӣІз·ҡгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹ гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

ж•ҙеҪўеӣӣй–“еҸ–(гҒӣгҒ„гҒ‘гҒ„гӮҲгҒҫгҒ©гӮҠ)
民家гҒ®е№ійқўеҪўејҸгҒ®еҲҶйЎһгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеңҹй–“гӮ’йҷӨгҒ„гҒҹеұ…е®ӨйғЁгҒ®йғЁеұӢгҒҢз”°гҒ®еӯ—еҪўгҒ«4е®ӨдёҰгҒ¶гӮӮгҒ®гҖӮй–“д»•еҲҮгӮҠгҒҢзёҰжЁӘеҚҒеӯ—гҒ«гҒЁгҒҠгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢж•ҙеҪўеӣӣй–“еҸ–гҖҚгҖҒй–“д»•еҲҮгӮҠз·ҡгҒҢйҖҡгӮүгҒҡйЈҹгҒ„йҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜгҖҢйЈҹйҒ•гҒ„еӣӣй–“еҸ–гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеӨ§йҳӘиҝ‘йғҠгҒ§гҒҜ4вҖҰвҖҰ

жё…жҘјжЈҡ(гҒӣгҒ„гӮҚгҒҶгҒ гҒӘ)

иғҢиҝ”гҒ—(гҒӣгҒҢгҒҲгҒ—)

гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)
SezessionгҖӮеҲҶйӣўжҙҫгҖӮиӢұиӘһзі»гҒ§гҒҜгҖҢгӮ»гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ19дё–зҙҖжң«гҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгғүгӮӨгғ„гғ»гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ«иҲҲгҒЈгҒҹиҠёиЎ“гҒ®йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дё»гҒӘжҙ»еӢ•й ҳеҹҹгҒҜе»әзҜүгҒЁе·ҘиҠёгҖӮ
гҒқгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘдёӯеҝғең°гҒҜгҖҒгғҹвҖҰвҖҰ

ж‘ӮзӨҫ(гҒӣгҒЈгҒ—гӮғ)
зҘһзӨҫжң¬зӨҫгҒЁз”ұз·’гҒ®ж·ұгҒ„зҘӯзҘһгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжң¬зӨҫгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«зҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҘһзӨҫгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮжң¬зӨҫгҒ®з®ЎзҗҶгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮ еҗҢгҒҳеўғеҶ…ең°гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҢпјҲеўғеҶ…зӨҫпјүгҖҒеўғеҶ…ең°еӨ–гҒ«гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢпјҲеўғеӨ–зӨҫпјүгҖӮ

жҠҳиЎ·ж§ҳ(гҒӣгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶгӮҲгҒҶ)
йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ«ж–°жқҘгҒ®гҖҢеӨ§д»Ҹж§ҳгҖҚгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҖҒдёүж§ҳејҸгҒҢдёҰз«ӢгҒҷгӮӢеҪўгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж„Ҹиӯҳзҡ„гҒ«дёүж§ҳејҸгӮ’ж··еңЁгҒ•гҒӣгӮӢгҖҢжҠҳиЎ·ж§ҳгҖҚгҒ®жүӢжі•еҢ–гҒҢе®ҡгҒҫгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒҜгҖҒзӣёеҪ“гҒӘжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢиЁігҒ§гҖҒвҖҰвҖҰ

иҝ«зҹі(гҒӣгӮҠгҒ„гҒ—)
voussoirпјҲд»ҸгҖҒгғ–гғјгӮҪгӮўгғјгғ«пјүгӮўгғјгғҒгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢжҘ”еҪўгҒ®зҹігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

зҰ…е®—ж§ҳ(гҒңгӮ“гҒ—гӮ…гҒҶгӮҲгҒҶ)
йҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҲқгӮҒгҒ«гҖҢеӨ§д»Ҹж§ҳгҖҚгҒҢдјқжқҘгҒ—гҒҰй–“гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзҰ…е®—гҒҢж „иҘҝпјҲдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜгҖҢгҒҲгҒ„гҒ•гҒ„гҖҚгҖҒе»әд»ҒеҜәгҒ§гҒҜгҖҢгӮҲгҒҶгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁиӘӯгӮҖпјүзҰ…её«гӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҚ—е®ӢгҒӢгӮүдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒЁдёҖз·’гҒ«гҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸж–°гҒ—гҒ„е»әзҜүж§ҳејҸгҒҢијёе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®вҖҰвҖҰ

е°–й ӯгӮўгғјгғҒ(гҒӣгӮ“гҒЁгҒҶгҒӮгғјгҒЎ)
pointed archгҖӮгҖҢе°–гӮҠгӮўгғјгғҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒ®дёҖгҒӨгҖӮгӮ№гғ‘гғігҒ®й•·гҒ•гҒ«зӯүгҒ—гҒ„еҚҠеҫ„гӮ’жҢҒгҒӨдәҢгҒӨгҒ®еҶҶеј§гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰе°–й ӯеҪўгҒ«гҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮгҖҒжҹұгҒ®й–“йҡ”гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгҒ®й«ҳвҖҰвҖҰ

иҚүеәө(гҒқгҒҶгҒӮгӮ“гҒөгҒҶгҒЎгӮғгҒ—гҒӨ)
гҖҢиҢ¶гҖҚгҒҜгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ”гӮҚгҖҒгҖҢзЈҡиҢ¶пјҲгҒӣгӮ“гҒЎгӮғпјүгҖҚпјҲзЈҡгҒЁгҒҜз“ҰгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒЁз§°гҒ—гҒҰгҖҒиҢ¶и‘үгӮ’еӣәгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еүҠгҒЈгҒҰе–«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҫҢдё–гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«ж „иҘҝзҰ…её«гҒҢгҖҒеҚ—е®ӢгҒӢгӮүиҢ¶гҒ®зЁ®гӮ’жҢҒгҒЎеё°гӮҠгҖҒй«ҳеұұеҜәгҒ®жҳҺжҒөдёҠдәәгҒҢиҢ¶з•‘гӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢвҖҰвҖҰ

з·Ҹеҗ‘жӢқ(гҒқгҒҶгҒ“гҒҶгҒҜгҒ„)

е®—е…өи”ө(гҒқгҒҶгҒІгӮҮгҒҶгҒһгҒҶгҖҒ1864пҪһ1944)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҖҒй–ўиҘҝгҒ®е»әзҜүз•ҢгҒ®йҮҚйҺ®гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгғ—гғӯгғқгғјгӮ·гғ§гғігӮ„зҙ°йғЁж„ҸеҢ гҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ«гҒҷгҒҗгӮҢгҖҒжҠҳиЎ·дё»зҫ©е»әзҜүгӮ’еҫ—ж„ҸгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮжұҹжҲёз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮе®®еҶ…зңҒгғ»жө·и»ҚзңҒгғ»и—Өз”°зө„гӮ’зөҢгҒҰгҖҒеӨ§йҳӘгҒ«е®—е»әвҖҰвҖҰ

зӣёијӘ(гҒқгҒҶгӮҠгӮ“)
дёүйҮҚеЎ”гҖҒдә”йҮҚеЎ”гҒӘгҒ©гҒ®д»ҸеЎ”гҒ®жңҖдёҠеұӨеұӢж №гҒ®й ӮйғЁгҒ«з«ӢгҒӨгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒдёӢгҒӢгӮүйңІзӣӨгғ»дјҸйүўпјҲиҰҶйүўпјүгғ»и«ӢиҠұгғ»д№қијӘгғ»ж°ҙз…ҷгғ»з«ңи»ҠпјҲз«ңиҲҺпјүгғ»е®қзҸ гҒӢгӮүжҲҗгӮӢгҖӮеҝғжҹұгҒ®дёҠгҒ«йүӣзӯҶгҒ®гӮӯгғЈгғғгғ—гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӢгҒ¶гҒ•гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйқ’йҠ…гҒҫгҒҹгҒҜйү„гҒ§дҪңгӮүгӮҢгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

зӨҺзҹі(гҒқгҒӣгҒҚ)
е»әзү©гҒ®жҹұгҒ®дёӢгҒ«жҚ®гҒҲгӮӢзҹігҖӮжҹұгҒ®ж №е…ғгҒҢи…җгӮӢгҒ®гӮ’йҳІгҒҺгҖҒдёҠгҒ®иҚ·йҮҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҹұгҒҢең°йқўгҒ®дёӯгҒ«жІҲдёӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҹұгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҠӣгӮ’ең°йқўгҒ«дјқгҒҲгӮӢеҪ№зӣ®гӮ’гӮӮгҒӨгҖӮ

иў–еҲҮ(гҒқгҒ§гҒҚгӮҠ)
еҺҡгҒҝгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҖҢиҷ№жўҒгҖҚгӮ’гҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒҸд»ҳиҝ‘гӮ’ж–ңгӮҒгҒ«еҲҮгӮҠеҸ–гҒЈгҒҰзҙҚгӮҒгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢиў–еҲҮгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒҸд»ҳиҝ‘гҒ®дёҠж–№гҒ®еӯӨеҪўгӮ’гҒӘгҒҷеҮәејөгҒЈгҒҹйғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢйҜ–е°»пјҲгҒ•гҒ°гҒҳгӮҠпјүгҖҚгҖҒдёӢз«ҜгҒ«еҲівҖҰвҖҰ

жӣҪзҰ°йҒ”и”ө(гҒқгҒӯгҒҹгҒӨгҒһгҒҶгҖҒ1853пҪһ1937)
жұҹжҲёз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢдёҖжңҹз”ҹгҖӮеҫҢгҒ«гҖҒдёӯжўқзІҫдёҖйғҺпјҲ1868пҪһ1936пјүгҒЁе…ұгҒ«гҖҒжӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒдёёгҒ®еҶ…гҒ®дёүиҸұ3гҖҒ4гҖҒ6гҖҒ7еҸ·йӨЁгҖҒж…¶жҮүзҫ©еЎҫеӨ§еӯҰеӣіжӣёйӨЁгҖҒж—§ж—Ҙжң¬йғөдҫҝзҘһжҲёж”Ҝеә—гғ“гғ«гҖҒжҳҺжІ»еұӢгғ“гғ«вҖҰвҖҰ
гҒҹгҖңгҒЁ

еӨ§й»’жҹұ(гҒ гҒ„гҒ“гҒҸгҒ°гҒ—гӮү)
民家гҒ®е№ійқўгҒ®дёӯеӨ®д»ҳиҝ‘гҖҒзү№гҒ«еңҹй–“гҒЁеә§ж•·еўғгҖҒеңҹй–“гҒ®иЎЁеҒҙгҒЁиЈҸжүӢгҒ®еўғзӣ®гҒ«гҒӮгӮӢеӨӘгҒ„жҹұгҖӮ

еӨ§зӨҫйҖ (гҒҹгҒ„гҒ—гӮғгҒҘгҒҸгӮҠгҖҒгҒҠгҒҠгӮ„гҒ—гӮҚгҒҘгҒҸгӮҠ)
зҘһзӨҫгҒ®жң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»йҖ гҒ§жЈҹгҒ«пј’жң¬гҒ®зҪ®еҚғжңЁпјҲгҒҠгҒҚгҒЎгҒҺпјүгҒЁ3жң¬гҒ®е …йӯҡжңЁпјҲгҒӢгҒӨгҒҠгҒҺпјүгӮ’зҪ®гҒҸгҖӮеҰ»е…ҘгӮҠгҒ§гҖҒжӯЈйқў2й–“гҖҒеҒҙйқў2й–“гҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒҜдёҖй–“еҲҶгҒ®гҒҝеЈҒгҒ§еҢәеҲҮгӮүгӮҢгҖҒзҘһеә§гҒҜиҘҝгӮ’еҗ‘гҒҸгҖӮзҙ жңЁйҖ гӮҠгҒ§еӣӣе‘ЁгҒ«й«ҳ欄вҖҰвҖҰ

иғҺи”өз”ҹжӣјиҚјзҫ…(гҒҹгҒ„гҒһгҒҶгҒ—гӮҮгҒҶгҒҫгӮ“гҒ гӮү)

еӨ§ж–—(гҒ гҒ„гҒЁ)
ж–—зө„пјҲгҒҫгҒҷгҒҗгҒҝпјүгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒжңҖдёӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҢж–—ж ұгҖҚе…ЁдҪ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢжңҖеӨ§гҒ®гҖҢж–—гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜгҖҒжҹұй ӮйғЁгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢеҸ°ијӘгҖҚгӮ„гҖҢзҡҝж–—пјҲгҒ•гӮүгҒЁпјүгҖҚгӮ’йҡ”гҒҰгҒҰжҚ®гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҢж–—гҖҚгҒ®дёҠж–№гҒ®гҖҢиӮҳжңЁгҖҚгӮ’еҗ«гӮҖйғЁеҲҶгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®ж·ұгҒ•гӮ’гҖҢеҗ«вҖҰвҖҰ

еӨ§еЎ”(гҒ гҒ„гҒЁгҒҶ)

еӨ§ж–—иӮҳжңЁ(гҒ гҒ„гҒЁгҒІгҒҳгҒҚ)

еҸ°зӣӨжүҖ(гҒ гҒ„гҒҜгӮ“гҒ©гҒ“гӮҚ)
еҸ°зӣӨгҒЁгҒ„гҒҶйЈҹеҷЁйЎһгӮ’ијүгҒӣгӮӢи„ҡд»ҳгҒҚгҒ®еҸ°гҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰйЈҹдәӢгҒ®з”Ёж„ҸгӮ’гҒҷгӮӢе®ӨгҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®еҸ°жүҖгҒ®иө·жәҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеҸ°зӣӨгҒҜе№іе®үиІҙж—ҸгҒ®иӘҝеәҰе“ҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзҘһзӨҫгҒ®зҘӯе…·гҒЁгҒ—гҒҰзҸҫеңЁгӮӮз”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

еӨ§д»Ҹж§ҳ(гҒ гҒ„гҒ¶гҒӨгӮҲгҒҶ)
йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҲқгӮҒгҖҒжқұеӨ§еҜәеҫ©иҲҲгҒ«йҡӣгҒ—гҖҒеғ§йҮҚжәҗгҒЁе®Ӣдәәйҷіе’ҢеҚҝгҒҢгҖҒдёӯеӣҪзҰҸе»әзңҒгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҒЁдјқзөұзҡ„гҒӘгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«иҖғжЎҲгҒ—гҒҹж–°гҒ—гҒ„е»әзҜүж§ҳејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®жң«гҒ«гҖҒе№ійҮҚиЎЎпјҲжё…зӣӣгҒ®жң«еӯҗпјүгҒ«гӮҲгӮӢеҚ—йғҪз„јгҒҚиЁҺгҒЎгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҲҲвҖҰвҖҰ

еӨ§з“¶жқҹ(гҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)
йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«гҖҒе®ӢгҒӢгӮүдјқгӮҸгҒЈгҒҹгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢиЈ…йЈҫйғЁжқҗгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒдёҠйғЁгҒ«гҖҢж–—гҖҚгӮ’гҒ®гҒӣгҖҒгҖҢеҰ»йЈҫгҖҚ
гӮ„еҶ…йғЁгҒ®гҖҢиҷ№жўҒгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®йғЁдҪҚгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖҒ瓶еӯҗпјҲгҒёгҒ„гҒ—пјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўзҠ¶гҒ®гҖҢжқҹгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢжқҹгҖҚгҒ®зү№иүІгҒҜвҖҰвҖҰ

еӨ§з“¶й°ӯ(гҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒігӮҢ)

еҸ°зӣ®з•і(гҒ гҒ„гӮҒгҒ гҒҹгҒҝ)
гҖҢдёёзӣ®пјҲгҒҫгӮӢгӮҒпјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒиҢ¶гҒ®ж№ҜгҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢз”ЁиӘһгҒ§гҖҒз•ізёҒгҒ«жҺҘгҒҷгӮӢз•іиЎЁгҒ®гҖҢзӣ®гҒ®ж•°гҖҚгҒҢдёҖз•іеҲҶгҒҷгҒ№гҒҰжҸғгҒЈгҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҢеҸ°еӯҗпјҲгҒ гҒ„гҒҷпјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢжӣёйҷўгғ»еәғй–“гҖҚгҒ§гҒ®жӯЈејҸгҒӘиҢ¶гҒ®ж№ҜгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖҢжЈҡзү©гҖҚгҒ®дёҖвҖҰвҖҰ

еҸ°ијӘ(гҒ гҒ„гӮҸ)
жҹұй ӮйғЁгҒЁгҖҢеӨ§ж–—гҖҚгҒ®й–“гҒ«е…ҘгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒ§гҖҒгҖҢй ӯиІ«гҖҚгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж§ӢйҖ зҡ„еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶе№…еәғгҒ®еҺҡжқҝгҒ®йғЁжқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®гҖҢеӨҡйҮҚеЎ”гҖҚгҒ«гҖҒеҸӨгҒҸгҒӢгӮүгҒқгҒ®дҪҝз”ЁгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮжңҖеҸӨгҒ®жі•вҖҰвҖҰ

й«ҳж©ӢиІһеӨӘйғҺ(гҒҹгҒӢгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1892пҪһ1990)
иұӘеҘўгҒӘйӮёе®…гӮ„гғӣгғҶгғ«гҒ®иЁӯиЁҲгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮеҪҰж №еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ гҒ«её«дәӢгҖӮиҒ–еҫіиЁҳеҝөзөөз”»йӨЁпјҲеҺҹжЎҲ/е°Ҹжһ—жӯЈзҙ№пјүе®ҹж–ҪиЁӯиЁҲгҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеӯҰеЈ«дјҡйӨЁгҖҒеүҚз”°дҫҜзҲөйӮёжҙӢйӨЁгҖҒж—§ж—Ҙжң¬з”ҹе‘ҪйӨЁпјҲзҸҫй«ҳвҖҰвҖҰ

й«ҳеЎҖйҖ (гҒҹгҒӢгҒёгҒҘгҒҸгӮҠ)

жҠұжҺ§гҒҲ(гҒ гҒҚгҒігҒӢгҒҲ)

з«№и…°е»әйҖ (гҒҹгҒ‘гҒ“гҒ—гҒ‘гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1888пҪһ1981)
дҪҸеҸӢз·Ҹжң¬еә—еҮәиә«гҒ§гҖҒж—Ҙе»әиЁӯиЁҲгҒ®жҜҚдҪ“гҒ®й•·и°·йғЁз«№и…°е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ®еүөз«ӢиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮзҹіе·қзңҢйҮ‘жІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮзҲ¶гҒҜгҖҒеІ©жң¬й«ҳдҝҠз”·зҲөпјҲзҹіе·қзңҢзҹҘдәӢпјүгҒ§гҖҒе№јжҷӮгҒ«ж—§е°ҸеҖүи—©гҒ®з«№и…°е®¶гҒ®йӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰеҸҠгҒіиӢұеӣҪAAгӮ№гӮҜгғјвҖҰвҖҰ

жӯҰз”°дә”дёҖ(гҒҹгҒ‘гҒ гҒ”гҒ„гҒЎгҖҒ1872пҪһ1938)
еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҢй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®зҲ¶гҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮзҰҸеұұеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮ欧е·һз•ҷеӯҰгҒ§еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮўгғјгғ«гғ»гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгӮ„гӮјгғ„гӮ§гӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©ж–°гҒ—гҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«зҙ№д»ӢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰвҖҰвҖҰ

еӨҡйҮҚеЎ”(гҒҹгҒҳгӮ…гҒҶгҒЁгҒҶ)
гҖҢеӨҡйҮҚеЎ”гҖҚгҒҜгҖҒгҖҢдёүйҮҚеЎ”гҖҚгӮ„гҖҢдә”йҮҚеЎ”гҖҚгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҹәжң¬гҖҒе№ійқўгҒҜеӣӣи§’еҪўпјҲеӨҡи§’еҪўгӮӮгҒӮгӮӢпјүгҒ®з©әй–“гӮ’еҘҮж•°ж•°гҒ«йҮҚгҒӯгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жәҗжөҒгҒҜдёӯеӣҪгҒ®гҖҢжҘјй–ЈгҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҢеЎ”гҖҚгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҖҢеҝғжҹұгҖҚгӮ’жҚ®гҒҲгҖҒгҖҢеӣӣеӨ©вҖҰвҖҰ

еӨҡеұӨеЎ”(гҒҹгҒқгҒҶгҒЁгҒҶ)

еЎ”й ӯ(гҒҹгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶ)
еӨ§еҜәйҷўгҒ®ж•·ең°еҶ…гҒ«гҒӮгӮӢе°ҸеҜәйҷўгӮ„еҲҘеқҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒи„ҮеҜә (гӮҸгҒҚгҒ§гӮү)гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶ гҖӮзҰ…е®—еҜәйҷўгҒ®зӢ¬зү№гҒӘеҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ(гҒҹгҒӨгҒ®гҒҚгӮ“гҒ”гҖҒ1854пҪһ1919)
жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„е»әзҜү家гҖӮе·ҘеӯҰеҜ®йҖ 家еӯҰ科第дёҖеӣһеҚ’гҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢз”ҹгҖӮжқұдә¬й§…гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒиөӨгғ¬гғігӮ¬гҒ«зҷҪгҒ„еҫЎеҪұзҹігҒ®еёҜгҒ®гғ‘гӮҝгғјгғігҒҜгҖҢиҫ°йҮҺејҸе»әзҜүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮжқұдә¬еёқеӨ§е·Ҙ科еӨ§еӯҰй•·йҖҖе®ҳеҫҢгҖҒ1905е№ҙгҒ« зүҮеІЎе®ү гҒЁе…ұгҒ«вҖҰвҖҰ

з«ңеұұзҹі(гҒҹгҒӨгӮ„гҒҫгҒ„гҒ—)
е…өеә«зңҢй«ҳз ӮеёӮиҫәгӮҠгҒ«з”ЈгҒҷгӮӢгҖҒжөҒзҙӢеІ©иіӘжә¶зөҗеҮқзҒ°еІ©гҒ§гҖҒеҠ е·ҘгҒ«йҒ©гҒ—гҒҹеј·еәҰгҒЁзІҳгӮҠгӮ’жңүгҒ—гҖҒиҖҗзҒ«жҖ§гҒ«гӮӮе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®иүІеҗҲгҒ„гҒӢгӮүгҖҒйқ’з«ңзҹігҖҒй»„з«ңзҹіеҸҠгҒіиөӨз«ңзҹіпјҲзЁҖе°‘пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеҸӨгҒҸгҒҜгҖҒд»ҒеҫіеӨ©зҡҮйҷөгҒ®зҹіжЈәгӮ„е№іеҹҺе®®гҒ®зӨҺзҹігҖҒиҝ‘зҸҫвҖҰвҖҰ

з«Ӣзҹіжё…йҮҚ(гҒҹгҒҰгҒ„гҒ—гҒӣгҒ„гҒҳгӮ…гҒҶгҖҒ1829пҪһ1894)
幕жң«гҒӢгӮүжҳҺжІ»жҷӮд»ЈеүҚжңҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§е·ҘжЈҹжўҒгғ»е»әзҜү家гҖӮжқҫжң¬еҹҺдёӢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮ擬жҙӢйўЁе»әзҜү гҒ®е…ёеһӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢй–ӢжҷәеӯҰж Ўж ЎиҲҺпјҲеӣҪе®қпјүгҒҢд»ЈиЎЁдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

з”°иҫәж·іеҗү(гҒҹгҒӘгҒ№гҒҳгӮ…гӮ“гҒ„гҒЎгҖҒ1879пҪһ1926)
гҒҠгӮӮгҒ«еӨ§жӯЈжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜү科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒ«её«дәӢгҖӮжё…ж°ҙзө„пјҲзҸҫжё…ж°ҙе»әиЁӯпјүгҒ®жҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҠҖиЎҢгғ»еӯҰж Ўгғ»йӮёе®…гҒӘгҒ©гӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҖҒеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҖӮе»әзҜүгҒЁе·ҘиҠёгҒ®жҸҗжҗәгҖҒз”°ең’и¶Је‘ігҒӘгҒ©гӮўгғјгғ„гғ»гӮўгғігғүвҖҰвҖҰ

гғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гӮҜгғӯгӮ№гғ“гғјгғ»гӮ°гғӘгғјгғі(гҒ гҒ«гҒҲгӮӢгғ»гҒҸгӮҚгҒҷгҒігғјгғ»гҒҗгӮҠгғјгӮ“ Daniel Crosby Greene 1843пҪһ1913)
зұіеӣҪдәәгҒ®е®Јж•ҷеё«гғ»зү§её«гғ»е»әзҜү家гҖӮзұіеӣҪгғһгӮөгғҒгғҘгғјгӮ»гғғгғ„е·һз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҳгғңгғігғ»гғ•гғ«гғҷгғғгӮӯгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж–°и–¬иҒ–жӣёзҝ»иЁігҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҖӮеҫҢгҒ«еҗҢеҝ—зӨҫиӢұеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҗҢеҝ—зӨҫеӨ§еӯҰпјүгҒ§ж•ҷеё«гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж‘ӮжҙҘ第дёҖе…¬е ӮпјҲзҸҫж—Ҙжң¬еҹәзқЈж•ҷеӣЈзҘһжҲёвҖҰвҖҰ

и°·еҸЈеҗүйғҺ(гҒҹгҒ«гҒҗгҒЎгӮҲгҒ—гӮҚгҒҶгҖҒ1904пҪһ1979)
ж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұж–ҮеҢ–гҒ®з¶ҷжүҝгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒжӯЈзөұзҡ„гҒӘгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ«гҒқгӮҢгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹгҖҒз«ҜжӯЈгҒӘдҪңйўЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢе»әзҜү家гҖӮйҮ‘жІўеёӮгҖҒд№қи°·з„јзӘҜе…ғгҒ®е®¶гҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжқұдә¬е·ҘжҘӯеӨ§еӯҰгҒ§й•·гҒҸж•ҷйһӯгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮгҖҢеҚҡзү©йӨЁжҳҺжІ»жқ‘вҖҰвҖҰ

жүӢжҢҹ(гҒҹгҒ°гҒ•гҒҝ)
зҘһзӨҫе»әзҜүгҒӘгҒ©гҖҒдё»гҒ«еҗ‘жӢқжҹұгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«гҖҒеұӢж №гҒ®еһӮжңЁеӢҫй…ҚгҒ«жІҝгҒЈгҒҰе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҹгҖҒгҒ»гҒјдёүи§’еҪўгҒ®еҢ–зІ§жқҝгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҪ«еҲ»зү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗ‘жӢқжҹұдёҠгҒ®зө„зү©гҒЁеһӮжңЁгҒ®йҡҷй–“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒзҙҚгҒҫгӮҠгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

еӨҡе®қеЎ”(гҒҹгҒ»гҒҶгҒЁгҒҶ)
гҖҢеӨҡе®қеЎ”гҖҚгҒҜгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®еҜҶж•ҷзі»еҜәйҷўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢеӨҡе®қеҰӮжқҘпјҲйҒҺеҺ»дёғд»ҸгҒ®дёҖгҖӮе®қз”ҹеҰӮжқҘгҒЁгӮӮпјүгҖҚгҒЁгҖҢйҮҲиҝҰеҰӮжқҘпјҲдёҚз©әжҲҗе°ұеҰӮжқҘгҒЁгӮӮпјүгҖҚгҒ®дәҢгҒӨгҒ®д»ҸеғҸгӮ’дёҰгҒ№гҒҰе®үзҪ®гҒ—гҒҹгҖҢеЎ”гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢзңҹиЁҖеҜҶж•ҷ(жқұеҜҶ)гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒдёҖеұӨзӣ®вҖҰвҖҰ

гғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғгғҲгғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒ гӮӢгӮҖгҒ—гӮ…гҒҹгҒЈгҒЁгғ»гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)
Darmstadter SezessionгҖӮгҖҢгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғігҖҚгҒ«ж¬ЎгҒ„гҒ§зӢ¬еӣҪгҒ®гғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғгғҲгҒ«иҲҲгҒ•гӮҢгҒҹиҠёиЎ“йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҖӮгғҳгғғгӮ»гғіеӨ§е…¬E.гғ«гғјгғҲгғҙгӮЈгғ’гҒҢгҖҒиӢұеӣҪгҒ®иҝ‘д»ЈйҒӢеӢ•гҒ«еҲәжҝҖгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғвҖҰвҖҰ

дё№дёӢеҒҘдёү(гҒҹгӮ“гҒ’гҒ‘гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1913пҪһ2005)
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҢдё–з•ҢгҒ®гӮҝгғігӮІгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬дәәе»әзҜү家гҒЁгҒ—гҒҰжңҖгӮӮж—©гҒҸеӣҪеӨ–гҒ§гӮӮжҙ»иәҚгҒ—гҖҒиӘҚзҹҘгҒ•гӮҢгҒҹдёҖдәәгҖӮ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫ©иҲҲеҫҢгҒӢгӮүй«ҳеәҰжҲҗй•·жңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӣҪ家зҡ„гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹе»әзҜүз•ҢгҒ®гғҲгғғгғ—гғӘгғјгғҖгғјвҖҰвҖҰ

еҚҳеұӨ(гҒҹгӮ“гҒқгҒҶ)
жӯҙеҸІзҡ„е»әйҖ зү©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеұӢж №гҒ®йҮҚгҒӘгӮҠгҒҢгҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮйҡҺж•°гҒЁгҒҜеҲҘгҒ§гҖҒе»әзү©гҒҢ2йҡҺгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®йҡҺж•°гҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

йҒ•жЈҡ(гҒЎгҒҢгҒ„гҒ гҒӘ)
гҖҢйҒ•жЈҡгҖҚгҒ®зҷәз”ҹгҒҜгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ§гҖҒзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҢжқұеұұж®ҝпјҲж…Ҳз…§еҜәпјүжқұжұӮе Ӯгғ»еҗҢд»Ғж–ҺгҖҚгҒ®гҖҢд»ҳжӣёйҷўгҖҚгҒ«йҡЈгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгҖҢжЈҡгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒҫгҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҢең°иўӢгҖҚгӮ’ж¬ гҒҚгҖҢең°жқҝгҖҚгӮ’гҖҢжҠјжқҝгҖҚеҪўејҸвҖҰвҖҰ

еҚғйіҘз ҙйўЁ(гҒЎгҒ©гӮҠгҒҜгҒө)

дёӯжўқзІҫдёҖйғҺ(гҒЎгӮ…гҒҶгҒҳгӮҮгҒҶгҒӣгҒ„гҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1868пҪһ1936)
жӣҪзҰ°йҒ”и”ө гҒЁе…ұгҒ«жӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’дё»е®°гҒҷгӮӢгҖӮеұұеҪўзңҢзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҸҠгҒігӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёеӨ§еӯҰеҚ’гҖӮж–ҮйғЁзңҒиҫһиҒ·еҫҢгҖҒжӣҪзҰ°гҒЁжқұдә¬дёёгҒ®еҶ…гҒ«е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮжҳЁжҜ”委гҒ«гҒҜгҖҒжңӯе№ҢиҫІеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҢ—жө·йҒ“еӨ§еӯҰпјүжҳҶвҖҰвҖҰ

дёӯй–Җе»Ҡ(гҒЎгӮ…гҒҶгӮӮгӮ“гӮҚгҒҶ)

еёіеҸ°ж§Ӣ(гҒЎгӮҮгҒҶгҒ гҒ„гҒҢгҒҫгҒҲ)

жүӢж–§(гҒЎгӮҮгҒҶгҒӘ)

йҮҝзӣ®еүҠгӮҠ(гҒЎгӮҮгҒҶгҒӘгӮҒгҒ‘гҒҡгӮҠ)

йҺ®е®ҲзӨҫ(гҒЎгӮ“гҒҳгӮ…гҒ—гӮғ)

зҜүең°еЎҖ(гҒӨгҒ„гҒҳгҒ№гҒ„)
гҖҢзҜүең°еЎҖгҖҚгҒЁгҖҢз·ҙеЎҖгҖҚгҒҜгҖҒеүҚиҖ…гҒҢгҖҢеңҹгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢдёҖдҪ“йҖ гҖҚгҒӘгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҫҢиҖ…гҒҜгҖҢз“ҰгҖҚгӮ’гҖҢеңҹгҖҚгҒ§з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°гҖҢзө„з©ҚйҖ гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж§ӢйҖ гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҖӮдёЎж–№гҒЁгӮӮгҖҒиЎЁйқўгҒ«жјҶе–°гӮ’еЎ—гӮҠд»•дёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжјҶе–°вҖҰвҖҰ

гғ„гӮӨгӮ№гғҲгӮігғ©гғ (гҒӨгҒ„гҒҷгҒЁгҒ“гӮүгӮҖ)
twist columnгҖӮжҚ©гӮҢжҹұгҖӮеҶҶжҹұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҹұиә«гҒ®йғЁеҲҶгҒҢзё„гӮ’ж’ҡгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«еҪўдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮ

и№Іиёһ(гҒӨгҒҸгҒ°гҒ„)

д»ҳжӣёйҷў(гҒӨгҒ‘гҒҳгӮҮгҒ„гӮ“)

д»ҳжЁӢз«Ҝ(гҒӨгҒ‘гҒІгҒ°гҒҹ)
ж•·еұ…гҖҒйҙЁеұ…гҒӘгҒ©гҒ®жәқгҒ®еҮёйғЁеҲҶгӮ’жЁӢз«ҜпјҲгҒІгҒ°гҒҹпјүгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒж•·еұ…гӮ„йҙЁеұ…гҖҒз«Әжһ гҒӘгҒ©гҒ«жәқгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҰеј•гҒҚжҲёгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдёҠгҒ’дёӢгҒ’жҲёгҒӘгҒ©гӮ’е»әгҒҰиҫјгӮҖйҡӣгҖҒжәқгӮ’еҪ«гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйӣҮгҒ„жңЁгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжәқгӮ’дҪңгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®йӣҮгҒ„жңЁгӮ’вҖҰвҖҰ

еҺЁеӯҗдәҢйҡҺ(гҒӨгҒ—гҒ«гҒӢгҒ„)
иЎ—и·ҜеҒҙгҒ®е№іе…ҘеұӢж №гҒ®и»’й«ҳгӮ’дҪҺгҒҸжҠ‘гҒҲгҒҹ民家гҒ®гҖҒеұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢеҺЁеӯҗдәҢйҡҺгҖҚгҒЁз§°гҒҷгӮӢгҖӮгҖҢдёӯдәҢйҡҺгҖҚгҒЁиЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҚҳгҒ«гҖҢгҒӨгҒ—гҖҚжҲ–гҒ„гҒҜгҖҢгҒҡгҒ—гҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгӮҠгӮӮгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢеҺЁеӯҗгҖҚд»ҘеӨ–гҒ«гҖҢеӣіеӯҗгҖҚгҖҢиҫ»гҖҚгҒ®жјўеӯ—вҖҰвҖҰ

еңҹжөҰдәҖеҹҺ(гҒӨгҒЎгҒҶгӮүгҒӢгӮҒгҒҚгҖҒ1897пҪһ1996)
иҢЁеҹҺзңҢж°ҙжҲёеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲжЁӘеұұеӨ§иҰігҒҜеҸ”зҲ¶гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢпјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒ«её«дәӢгҖӮжёЎзұігҒ—гӮҝгғӘгӮўгӮ»гғігҒ«е…ҘжүҖгҖӮпјҲеҗҢеғҡгҒ«гҖҒгғӘгғҒгғЈгғјгғүгғ»гғҺгӮӨгғҲгғ©гҖҒгӮўгғүгғ«гғ•гғ»гӮ·гғігғүгӮўгғјгҒҢгҒ„гҒҹпјүеё°еӣҪеҫҢеӨ§еҖүеңҹжңЁпјҲзҸҫвҖҰвҖҰ

з№Ӣиҷ№жўҒ(гҒӨгҒӘгҒҺгҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)

еҰ»е…Ҙ(гҒӨгҒҫгҒ„гӮҠ)
е»әзү©гҒ®еҰ»еҒҙгҒ«дё»еҮәе…ҘеҸЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеҰ»еҒҙгҒЁгҒҜе»әзү©гҒ®еұӢж №гҒ®еӨ§жЈҹгҒЁзӣҙи§’гҒӘеҒҙйқўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨ§жЈҹгҒЁе№іиЎҢгҒӘеҒҙйқўгҒҜе№іеҒҙгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҰ»гҒЁгҒҜгҖҒз«ҜгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒеҲҮеҰ»еұӢж №гҒҜдёЎз«ҜгӮ’еҲҮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒқгҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

еҰ»жңЁй јй»„(гҒӨгҒҫгҒҚгӮҲгӮҠгҒӘгҒӢгҖҒ1859пҪһ1916)
жұҹжҲёж——жң¬гҒ®з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгӮігғігғүгғ«гҒ«её«дәӢгҖҒгӮігғјгғҚгғ«еӨ§еӯҰеҚ’гҖӮж•°еӨҡгҒҸгҒ®е®ҳеәҒе»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжқұдә¬еәңеәҒиҲҺгҖҒжқұдә¬е•Ҷе·Ҙдјҡиӯ°жүҖгҖҒжЁӘжөңжӯЈйҮ‘йҠҖиЎҢжң¬еә—пјҲзҸҫзҘһеҘҲе·қзңҢз«ӢеҚҡзү©йӨЁпјүгҖҒж—Ҙжң¬иөӨеҚҒеӯ—зӨҫжң¬зӨҫгҖҒж—Ҙжң¬ж©ӢгҖҒж—§еұұеҸЈзңҢеәҒиҲҺпјҲзҸҫеұұвҖҰвҖҰ

й¶ҙдәҖ蓬иҺұзҹізө„(гҒӨгӮӢгҒӢгӮҒгҒ»гҒҶгӮүгҒ„гҒ„гӮҸгҒҗгҒҝ)
дҪңеәӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёӯеӣҪгҒ®зҘһд»ҷжҖқжғігӮ’еҹәгҒ«гҖҒзҗҶжғійғ·гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢ蓬иҺұеі¶гӮ„й•·еҜҝгҒ®гӮ·гғігғңгғ«й¶ҙгӮ„дәҖгӮ’зҸҫгҒҷзҹізө„гӮ’жҚ®гҒҲгҒҰгҒқгҒ®дё–з•ҢгӮ’жҠҪиұЎзҡ„гҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒ«иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮзҘһд»ҷжҖқжғігҒЁгҒҜгҖҒеҸӨд»ЈдёӯеӣҪгҒ§гҖҒдәәгҒ®е‘ҪгҒ®ж°ёйҒ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҘһдәәгӮ„д»ҷдәәгҒ«иЁ—вҖҰвҖҰ

гғҮгғ»гӮ№гғҶгӮӨгғ«(гҒ§гғ»гҒҷгҒҰгҒ„гӮӢ)
De StijlгҖӮ1917е№ҙгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®гғ©гӮӨгғҮгғігҒ§T.v.гғүгӮҘгғјгӮ№гғ–гғ«гӮ°гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰзөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹйҖ еҪўйҒӢеӢ•гҒ§гҖҒеҗҢзӣҹгҒ®ж©ҹй–ўиӘҢгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢгӮ№гғҶгӮӨгғ«гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖиӘһгҒ§гҖҢж§ҳејҸгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ
йҒӢеӢ•гҒ«гҒҜгҖҒP.гғўвҖҰвҖҰ

еёқеҶ ж§ҳејҸ(гҒҰгҒ„гҒӢгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҠгӮ·гғ§гғҠгғӘгӮәгғ пјҲж°‘ж—Ҹдё»зҫ©гғ»еӣҪ家主зҫ©гғ»еӣҪж°‘дё»гҖҖзҫ©гғ»еӣҪзІӢдё»зҫ©гҒӘгҒ©гҒЁиЁігҒ•гӮҢгҖҒзЁ®гҖ…гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢз•°гҒӘгӮӢпјүгҒ®еҸ°й ӯгӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз„ЎеӣҪзұҚгҒҫгҒҹгҒҜеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘиҝ‘д»Јдё»зҫ©е»әзҜүгҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҰдё»ејөгҒ•гӮҢгҒҹж§ҳејҸгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮж§ӢйҖ вҖҰвҖҰ

йҰ¬и№„еҪўгӮўгғјгғҒ(гҒҰгҒ„гҒҰгҒӨгҒҢгҒҹгҒӮгғјгҒЎ)
horseshoe archгҖӮйҰ¬и№„гҒ®еҪўгӮ’гҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгҖӮеҚҠеҶҶгӮўгғјгғҒ гҒ®еӨүеҪўгҒ§гҖҒ4еҲҶгҒ®3еҶҶгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮдёёеһӢйҰ¬и№„еҪўгӮ„е°–гӮҠйҰ¬и№„еҪўгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

еҮәзө„(гҒ§гҒҗгҒҝ)
еұӢж №гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢи»’жЎҒпјҲдёёжЎҒпјүгӮ’еүҚгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҖҒжҹұеҝғгҒӢгӮүи»’е…ҲгҒҫгҒ§гҒ®еҮәгӮ’ж·ұгҒҸгҒҷгӮӢжүӢжі•гҒ®дёҖгҖӮжҹұдёҠгҒ®еҮәдёүж–—гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеӨ§ж–—гҒӢгӮүеЈҒйқўгҒЁгҒҜзӣҙи§’гҒ«жһ иӮҳжңЁгҒ®дёҖгҒӨгӮ’еүҚж–№гҒёзӘҒеҮәгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®дёҠгҒ«еЈҒйқўгҒЁе№іиЎҢгҒ«и»’жЎҒгӮ’жүҝгҒ‘гӮӢе№ідёүж–—гӮ’ијүгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮвҖҰвҖҰ

гғҶгғғгӮ»гғ©(гҒҰгҒЈгҒӣгӮү)
tesseraгҖӮе»әзҜүзү©гҒ®еәҠгӮ„еЈҒйқўжҲ–гҒ„гҒҜе·ҘиҠёе“ҒгҒ®иЈ…йЈҫгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгғўгӮ¶гӮӨгӮҜпјҲmosaicпјүеҲ¶дҪңгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжјҶе–°гҒ®дёӯгҒ«еҹӢгӮҒиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮөгӮӨгӮігғӯзҠ¶гҒ®е°ҸзүҮгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҫәгҒҢж•°гғҹгғӘгҒӢгӮү30гғҹгғӘгҒ»гҒ©гҒ§гҖҒеӨ§зҗҶзҹігғ»иІҙзҹігғ»гӮ¬гғ©вҖҰвҖҰ

гғҶгғҘгғјгғҖгғјгӮўгғјгғҒ(гҒҰгӮ…гғјгҒ гғјгҒӮгғјгҒЎ)
tudor archгҖӮгҖҢе°–й ӯгҖҚгҒЁгҖҢгӮӘгӮёгғјгҖҚгҒ®дёӯй–“гҒ®гӮўгғјгғҒгҖӮгҒӨгҒ¶гӮҢгҒҹеҪўгҒ®жүҒе№ігҒӘгҖҢе°–й ӯгӮўгғјгғҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮ

гғҶгғҘгғјгғҖгғјж§ҳејҸ(гҒҰгӮ…гғјгҒ гғјгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Tudor styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ®15дё–зҙҖжң«й ғгҒӢгӮү17дё–зҙҖеҲқй ӯгҒҫгҒ§гҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгҒ°гӮүжҲҰдәүгҒ®зөӮзөҗгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҫҢгҒ«гҖҢгғҶгғҘгғјгғҖгғјгҒ®е№іе’ҢгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжҷӮд»ЈгҒҢиЁӘгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒ1530е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜе»әзү©гҒ®ж§ҳејҸгҒҢгӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸгҒӢгӮүеӨүеҢ–гҒҢз”ҹвҖҰвҖҰ

гғҶгғ©гӮігғғгӮҝ(гҒҰгӮүгҒ“гҒЈгҒҹ)
terracottaгҖӮе…ғжқҘгҖҢзҙ з„јгҒҚгҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮе»әзҜүзү©гҒ®еӨ–иЈ…з”ЁгҖҒзү№гҒ«гғ‘гғ©гғҡ
гғғгғҲгғ»иӣҮи…№гғ»жҹұй ӯгҒӘгҒ©гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘжЁЎж§ҳгҒ®гҒӮгӮӢеӨ§еһӢгҒ®зІҳеңҹиЈҪе“ҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮж·ұ
гҒҝгҒ®гҒӮгӮӢиөӨиӨҗиүІгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒз…үз“ҰгӮҲгӮҠзЎ¬иіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҶгғ©гӮҫ(гҒҰгӮүгҒһ)
terrazzoгҖӮдәәйҖ зҹігҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒгғЎгғғгӮ·гғҘгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгғўгғ«гӮҝгғ«гӮ’дёӢеЎ—гӮҠгҒ—гҒҹдёҠгҒ«гҖҒеӨ§зҗҶзҹігғ»иӣҮзҙӢеІ©гғ»иҠұеҙ—еІ©гҒӘгҒ©гҒ®зІүз •зІ’гҒ«йЎ”ж–ҷгғ»зҷҪгӮ»гғЎгғігғҲгӮ’з·ҙгӮҠж··гҒңгҒҹгғўгғ«гӮҝгғ«гӮ’еЎ—гӮҠгҖҒзЎ¬еҢ–жҷӮгӮ’иҰӢгҒҜгҒӢгӮүгҒЈгҒҰиЎЁйқўгӮ’з ”зЈЁгҒ—гҖҒиү¶еҮәгҒ—гҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

з…§гӮҠиө·гӮҠеұӢж №(гҒҰгӮҠгӮҖгҒҸгӮҠгӮ„гҒӯ)

з…§гӮҠеұӢж №(гҒҰгӮҠгӮ„гҒӯ)

еӨ©и“Ӣ(гҒҰгӮ“гҒҢгҒ„)
д»ҸеғҸгҒ®й ӯдёҠгҒ«жҮёгҒ‘еҗҠгӮӢгҒ•гӮҢгҒҹи“ӢзҠ¶гҒ®иҰҶгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҺҹж„ҸгҒҜгҖҒеҚ°еәҰгҒ®иІҙдәәгҒҢеӨ–еҮәжҷӮгҒ«дҪҝгҒҶгҖҢи“ӢгҖҚгӮ’гҒ•гҒҷгҖӮгҖҢиЈӮпјҲгҒҚгӮҢпјүгҖҚгӮ’ејөгҒЈгҒҹгҖҢиЈӮи“ӢгҖҚгҒ®д»–гҖҒжңЁиЈҪгғ»йҮ‘еұһиЈҪгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮеӣӣе‘ЁгҒ®зёҒгҒ«гҖҢз“”зҸһпјҲгӮҲгҒҶгӮүгҒҸпјүгҖҚгӮ’еһӮгӮүгҒҷгҖӮпјҲз“”зҸһгҒЁгҒҜгҖҒеӨ§вҖҰвҖҰ

еӨ©зӢ—еһӮжңЁ(гҒҰгӮ“гҒҗгҒ гӮӢгҒҚ)

еӨ©з«әж§ҳ(гҒҰгӮ“гҒҳгҒҸгӮҲгҒҶ)
гҖҖ

еӨ©дә•й•·жҠј(гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶгҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҖ

гғҮгғігғҶгӮЈгғ«(гҒ§гӮ“гҒҰгҒғгӮӢ)
dentilгҖӮжӯҜйЈҫгӮҠгҖӮгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһе»әзҜүгҒ®гҖҢгӮігғјгғӢгӮ№гҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢе°ҸгҒ•гҒӘзӣҙж–№дҪ“гҒ®йҖЈз¶ҡиЈ…йЈҫгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгҒ®еҪўгҒ®жӯҜгҒҢдёҰгӮ“гҒ гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҗҚд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖӮиӘһжәҗгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®densгҒ§жӯҜгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

гғүгғјгғһгғјзӘ“(гҒ©гғјгҒҫгғјгҒҫгҒ©)
dormer windowгҖӮеұӢж №зӘ“гҖӮиҘҝжҙӢдҪҸе®…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒ«жҺЎе…үгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еұӢж №йқўгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹзӘ“гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬гҒ«еҲҮеҰ»гҒ®е°ҸеұӢж №гҒЁзҹ©еҪўгҒ®й–ӢеҸЈйғЁгӮ’жҢҒгҒӨгҖӮгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒеҶҶеҪўеұӢж №гҒЁгҖҢзүӣзңјзӘ“гҖҚгӮ’зө„еҗҲгҒҷдҫӢгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгғјгғһгӮ№гғ»гӮҰгӮ©гғјгғҲгғ«гӮ№(гҒЁгғјгҒҫгҒҷгғ»гҒҶгҒүгғјгҒЁгӮӢгҒҷ Thomas James Waters 1842пҪһ1898)
иӢұеӣҪгҒ®еңҹжңЁжҠҖиЎ“её«гҖӮ幕жң«жңҹгҖҒгӮ°гғ©гғҗгғјгҒ®зҙ№д»ӢгҒ§и–©ж‘©и—©гҒ®й№ҝе…җеі¶зҙЎзёҫжүҖгҒӘгҒ©гҒ®е·ҘдәӢгҒ«жҗәгӮҸгӮҠгҖҒй•·еҙҺгҒ«иЎҢгҒҚгӮ°гғ©гғҗгғјгҒ®е…ғгҒ§еғҚгҒҸгҖӮ1868е№ҙиІЁе№ЈеҸёгҒ«йӣҮз”ЁгҒ•гӮҢгҖҒеӨ§еҖүзңҒгғ»е·ҘйғЁзңҒгҒ«еңЁзұҚгҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҖҒеҸӨе…ёдё»зҫ©е»әзҜүпјҲгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгғівҖҰвҖҰ

гғүгғјгғ гғ»гғүгӮҘгӮӘгғјгғў(гҒ©гғјгӮҖгғ»гҒ©гҒ…гҒҠгғјгӮӮ)
иӢұ/domeгҖҒдјҠ/duomoгҖӮжҲ–гҒ„гҒҜдёёеұӢж №гҒҜгҖҒе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеұӢж №еҪўзҠ¶гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒеҚҠзҗғеҪўгӮ’гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгӮ’дёӯеҝғгҒ«ж°ҙе№ігҒ«еӣһи»ўгҒ•гҒӣгҒҹеҪўзҠ¶гҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгғүгғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гӮӮгӮўгғјгғҒгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиҮӘвҖҰвҖҰ

еңҹеұ…жЎҒ(гҒ©гҒ„гҒ’гҒҹ)
гҖҖ

еЎ”(гҒЁгҒҶ)
гҖҢеЎ”гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰд»Ҹж•ҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҹж§ӢзҜүзү©гҒ§гҖҒд»ҸйҷҖгҒ®йҒәйӘЁгӮ’еҘүе®үгҒ—дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«е–¶гҒҫгӮҢгҒҹиұЎеҫҙзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®гҖҢеў“гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢеЎ”гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еҸЈиӘһгғҗгғјгғӘиӘһгҒ®гҖҢгғҲгғ•гғҗгҖҚгҒҢдёӯеӣҪгҒ«дјқжқҘгҒ—гҖҢеЎ”е©ҶгҖҚгҒЁйҹівҖҰвҖҰ

йҠ…жқҝи‘ә(гҒ©гҒҶгҒ„гҒҹгҒ¶гҒҚ)
йҮ‘еұһжқҝи‘әгҒ«йҠ…жқҝгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮжұҹжҲёжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

иғҙејө(гҒ©гҒҶгҒ°гӮҠ)
гҖҢжӣІйқўгҒҢгҖҒеҗҢдёҖеҶҶеј§гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘд»®иӘ¬гҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮд»®иӘ¬гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӨңиЁјгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮпјү
гҖҢиғҙејөгҖҚгҒ®е ҙеҗҲгӮ’зӨәгҒҷгҖӮв‘ е…ҲгҒҡгҖҒжҹұгҒ®зёҰж–ӯйқўгҒ®зҹ©еҪўгӮ’д»®гҒ«жҸҸгҒҸгҖӮв‘Ўжҹұй ӮгҒ®жң«вҖҰвҖҰ

йҖҡгҒ—иІ«(гҒЁгҒҠгҒ—гҒ¬гҒҚ)

йҖҡиӮҳжңЁ(гҒЁгҒҠгҒ—гҒІгҒҳгҒҚ)

ж–—ж ұзө„зү©(гҒЁгҒҚгӮҮгҒҶгҒҸгҒҝгӮӮгҒ®)
жҹұй ӮйғЁгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒи»’гҒ®еҮәгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢжһ¶ж§ӢиЈ…зҪ®гҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҹәжң¬гҒҜгҖҒж–№еҪўгҒ®гҖҢж–—пјҲгҒҫгҒҷпјүгҖҚгҒЁгҖҢж ұпјҲгҒІгҒҳгҒҚпјүгҖҚпјҲгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘдәҢжқҗгҒ®зө„еҗҲгҒӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
е…ҲгҒҡгҖҒжҹұдёҠгҒ«гҖҢеӨ§ж–—пјҲгҒ гҒ„гҒЁвҖҰвҖҰ

ж–—з№°(гҒЁгҒҗгӮҠ)

еәҠгҒ®й–“(гҒЁгҒ“гҒ®гҒҫ)
еә§ж•·йЈҫгӮҠгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеәҠжҹұгғ»еәҠжЎҶгғ»еәҠз•ігҒҫгҒҹгҒҜеәҠжқҝгғ»иҗҪжҺӣгғ»еәҠеӨ©дә•зӯүгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжҺӣи»ёгҒЁдёүе…·и¶іпјҲиҠұ瓶гҖҒзҮӯеҸ°гҖҒйҰҷзӮүпјүгӮ’йЈҫгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®з©әй–“гҖӮе®Өз”әз„ЎжҷӮд»ЈгҒ®дёҠж®өгҒҫгҒҹгҒҜжҠјжқҝеәҠгӮ’еҺҹеҪўгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гғҲгӮ№гӮ«гғјгғҠејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒЁгҒҷгҒӢгғјгҒӘгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)
Tuscan orderгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«з„ЎиЈ…йЈҫгҒӘгҖҢгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮўгҖҚд»ҘеӨ–гҒҜгғүгғӘгӮ№ејҸгҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҹұиә«гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸ гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

еңҹи”өйҖ (гҒ©гҒһгҒҶгҒҘгҒҸгӮҠ)
йӘЁзө„гҒҝгҒҜжңЁйҖ пјҲжңЁйӘЁпјүгҒ§гҖҒеӨ–йғЁгҒҜеңҹеЈҒгҒ§еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгҒҰжҹұгғ»жўҒгҒӘгҒ©гҒ®жңЁйғЁгӮ’йңІеҮәгҒ•гҒӣгҒӘгҒ„еӨ§еЈҒгҒЁгҒ—гҖҒеҶ…йғЁгҒҜжңЁйғЁгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢзңҹеЈҒгҒЁгҒ—гҒҹж§ӢйҖ гҒ§гҖҒеЈҒеҺҡгҒҜ20пҪһ30гӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©гҒ«гҒӘгӮӢйҖ гӮҠж–№гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеЈҒд»•дёҠгҒ’гҒҜжјҶе–°еЎ—гҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„вҖҰвҖҰ

йЈӣзҹі(гҒЁгҒігҒ„гҒ—)
еәӯең’еҶ…гӮ’жӯ©гҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹзҹігҒ§гҖҒжҷҜиүІгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж„ҸеҢ зҡ„гҒӘиҰҒзҙ гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮжҷ®йҖҡгҖҒдёҠйқўгҒҢе№ігӮүгҒӘиҮӘ然зҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҲҮзҹігӮ„дјҪи—ҚзҹіпјҲгҒҢгӮүгӮ“гҒ„гҒ—пјқеҜәйҷўзӯүгҒ®зӨҺзҹігӮ’и»ўз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгӮҢгҒ«дјјгҒӣгҒҹзҹіпјүгҖҒиҮјзҹігҒӘгҒ©еҠ е·ҘвҖҰвҖҰ

еңҹеәҮ(гҒ©гҒігҒ•гҒ—гҖҒгҒӨгҒЎгҒігҒ•гҒ—)
ең°йқўгҒ«жҹұгӮ’з«ӢгҒҰгҖҒж·ұгҒҸејөгӮҠеҮәгҒ•гҒӣгҒҹеәҮгҒ§гҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжҹұгғ»жЎҒгҒ§ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҗ№ж”ҫгҒЎгҒ§еәҠгҒҜејөгӮүгӮҢгҒҡгҖҒиҫІе®¶дҪҸе®…гҒ§гҒҜеәҮдёӢгҒҜзёҒеҒҙгҒ«д»ЈгӮҸгӮӢзёҒз©әй–“гҒЁгҒ—гҒҰиҫІдҪңжҘӯгҒ®е ҙгҒЁгӮӮгҒӘгӮӢгҖӮиҢ¶е®ӨгӮ„ж•°еҜ„еұӢе»әзҜүгҒӘгҒ©гҒ§гҒҜзҺ„й–ўе…ҘеҸЈйҖҡи·ҜгӮ„жӯ©е»ҠгҒЁгҒ•вҖҰвҖҰ

еңҹй–“(гҒ©гҒҫ)
еұӢеҶ…гҒ§гҖҒеәҠгҒҢең°йқўгҒ®гҒҫгҒҫгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдёүе’ҢеңҹпјҲгҒҹгҒҹгҒҚпјүгҖҒз ӮеҲ©ж•·гҖҒзҹіејөгҖҒгӮҝгӮӨгғ«ејөгҖҒгғўгғ«гӮҝгғ«еЎ—гҖҒгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲжҠјгҒҲзӯүгҒ§ең°йқўй«ҳгҒ•иҝ‘гҒҸгҒ§д»•дёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

з•ҷи“Ӣз“Ұ(гҒЁгӮҒгҒ¶гҒҹгҒҢгӮҸгӮү)
еҪ№зү©з“ҰгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒйӣЁд»•иҲһгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«йҡ…жЈҹгҒ®е°»йғЁеҲҶпјҲи»’е…ҲгҒӢгӮүиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„еҒҙпјүгӮ’иҰҶгҒҶз“ҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз«ӢжөӘжЁЎж§ҳгҖҒзҚ…еӯҗгҖҒйі©гҖҒжӨҚзү©гҒӘгҒ©гҒ®йЈҫгӮҠгҒҢд№—гҒӣгӮүгӮҢгҖҒиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігӮӮгҒӮгӮҸгҒӣжҢҒгҒӨгҖӮе…ҘжҜҚеұӢеұӢж №гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҷҚгӮҠжЈҹгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲвҖҰвҖҰ

е·ҙж–Ү(гҒЁгӮӮгҒҲгӮӮгӮ“)

гғҲгғ©гӮӨгӮўгғігғ•гӮЎгғ«гӮўгғјгғҒ(гҒЁгӮүгҒ„гҒӮгӮ“гҒөгҒҒгӮӢгҒӮгғјгҒЎ)
triumphal archгҖӮеҮұж—Ӣй–ҖгҖӮ

гғҲгғ©гғҗгғјгғҒгғі(гҒЁгӮүгҒ°гғјгҒЎгӮ“)
travertineгҖӮгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮиҷ«гҒ«жөёйЈҹгҒ•гӮҢгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе°ҸгҒ•гҒӘеӯ”зҠ¶гҒ®еӮ·гӮ’жңүгҒҷгӮӢгҖҒж·ЎиӨҗиүІжҲ–гҒ„гҒҜиҢ¶иӨҗиүІгҒ®еӨ§зҗҶзҹігҖӮгҒқгҒ®еӨҡеӯ”иіӘгҒ«и¶ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒиЈ…йЈҫз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢзҹізҒ°иҸҜгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ

гғҲгғ©гғігӮ»гғ—гғҲ(гҒЁгӮүгӮ“гҒӣгҒ·гҒЁ)
transeptгҖӮиў–е»ҠпјҲгҒқгҒ§гӮҚгҒҶпјүгҖӮзҝје»ҠгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒ«зӣҙдәӨгҒҷгӮӢе»ҠгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰеҚҒеӯ—еҪўпјҲгғ©гғҶгғіеҚҒеӯ—пјүгҒ®е№ійқўгӮ’еҪўдҪңгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®и…•гҒ®йғЁеҲҶгҖӮ
еҫ“гҒЈгҒҰгҖҒеҚ—еҢ—гҒ«иө°гӮӢгҒ“гҒ®е»ҠгҒҜгҖҒеҚ—гҒ®иў–е»ҠгҒЁдәӨе·®вҖҰвҖҰ

гғүгғӘгӮ№ејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ©гӮҠгҒҷгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)
Doric orderгҖӮжңҖгӮӮжңҹйҷҗгҒ®еҸӨгҒ„ гӮӘгғјгғҖгғј гҒ§гҖҒеҶҶжҹұгҒ«зӨҺзӣӨпјҲжҹұеҹәпјүгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„зӮ№гҒҢзӢ¬зү№гҖӮжҹұй ӯгҒҜз„ЎиЈ…йЈҫгҒ§гҖҒжҹұиә«гҒ«гҒҜ гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гғүгғӘгғғгғ—гӮ№гғҲгғјгғі(гҒ©гӮҠгҒЈгҒ·гҒҷгҒЁгғјгӮ“)
dripstone, weather mouldingгҖӮйӣЁжҠјгҒҲзҹігҖӮгӮўгғјгғҒгғ»зӘ“гғ»еҮәе…ҘеҸЈгҒ®дёҠйғЁгҒ«йӣЁж°ҙгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢ гғўгғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гҖӮ

гғҲгғӘгғ“гғҘгғјгғі(гҒЁгӮҠгҒігӮ…гғјгӮ“)
tribuneгҖӮеҸӨд»ЈгғӯгғјгғһгҒ®жҢҮжҸ®е®ҳгғҲгғӘгғ—гғҢгӮ№гҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢиӢұиӘһгҒ®гӮ«гӮҝгӮ«гғҠиЎЁиЁҳгҒ§гҖҒгғҗгӮ·гғӘгӮ« гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖй«ҳиЎҢж”ҝе®ҳгҒ®еёӯгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢи»ўгҒҳгҒҰдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢжј”еЈҮгҖҚгӮ’жҢҮгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүеҶ…гҒ®гҖҢгӮ°гғ©гғігғүгғ»гӮўгғјгӮұгғјгғүгҖҚгҒЁвҖҰвҖҰ

гғҲгғ¬гғјгӮөгғӘгғј(гҒЁгӮҢгғјгҒ•гӮҠгғј)
traceryгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзӘ“йқўгӮ’зҙ°еҲҶеҢ–гҒҷгӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘзө„еӯҗйғЁжқҗгҖҒгҒқгҒ®жүӢжі•гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
гҒӘгҖңгҒ®

еҶ…еӨ–йҷЈеўғ(гҒӘгҒ„гҒ’гҒҳгӮ“гҒ–гҒӢгҒ„)

еҶ…йҷЈ(гҒӘгҒ„гҒҳгӮ“)
гҖҢйҮ‘е ӮгҖҚгғ»гҖҢжң¬е ӮгҖҚе»әзҜүгҒ®е№ійқўж§ӢжҲҗгҒ®еӨ§гҒҫгҒӢгҒӘеӨүйҒ·гӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ
е…ҲгҒҡгҖҒжі•йҡҶеҜәйҮ‘е ӮгҒҜгҖҒеҶ…йғЁгҒ«зӨјжӢқз©әй–“гӮ’жҢҒгҒҹгҒҡгҖҒзӨјжӢқиҖ…гҒҜеҶ…йғЁгҒ«з«ӢгҒЎе…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҚ—еәӯгҒ«жҚ®гҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҖҢзӨјжӢқзҹігҖҚгӮ„гҖҢеӣһе»ҠгҖҚгҒ§д»ҸдәӢгҒҢиЎҢвҖҰвҖҰ

еҶ…йҷЈжҹұ(гҒӘгҒ„гҒҳгӮ“гҒ°гҒ—гӮү)

еҶ…и—ӨеӨҡд»І(гҒӘгҒ„гҒЁгҒҶгҒҹгҒЎгӮ…гҒҶгҖҒ1886~1970)
дҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ гҒ«её«дәӢгҖӮжҲҰеүҚгӮҲгӮҠж•°гҖ…гҒ®ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҖҒгҖҢиҖҗйңҮж§ӢйҖ гҒ®зҲ¶гҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеұұжўЁзңҢеҮәиә«гҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰеҚ’гҖӮжҲҰеҫҢгҒҜгҖҒйӣ»жіўеЎ”гғ»иҰіе…үеЎ”гҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҖҢеЎ”еҚҡеЈ«гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒж—§еӨ§йҳӘе•ҶиҲ№зҘһжҲёж”Ҝеә—вҖҰвҖҰ

еҶ…гҖ…йҷЈ(гҒӘгҒ„гҒӘгҒ„гҒҳгӮ“)

дёӯеӮҷ(гҒӘгҒӢгҒһгҒӘгҒҲ)

дёӯеЎ—гӮҠз•ҷгӮҒ(гҒӘгҒӢгҒ¬гӮҠгҒ©гӮҒ)
гҒӘгҒӢгҒ¬гӮҠгҒ©гӮҒ

й•·йҮҺе®Үе№іжІ»(гҒӘгҒҢгҒ®гҒҶгҒёгҒ„гҒҳгҖҒ1867пҪһ1937)
иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒ®ејҹеӯҗгҖӮжҳҺжІ»еҫҢеҚҠгғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮж–°жҪҹзңҢй«ҳз”°еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӨ§йҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮж•°гҖ…гҒ®йҠҖиЎҢе»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҖҒеҸӨе…ёдё»зҫ©ж§ҳејҸгӮ’жҘөгӮҒгӮӢгҖӮжҷ©е№ҙгҒҜгҖҒзҘһи©ұгҒ®дё–з•ҢгҒҫгҒ§йҒЎгӮҠгҖҒгғ—гғ¬гғ»гғҳгғ¬гғӢгғғгӮҜж§ҳејҸгӮ’еҶҚзҸҫгҒҷгӮӢгҖӮ1917е№ҙвҖҰвҖҰ

дёӯжқ‘йҺ®(гҒӘгҒӢгӮҖгӮүгҒҫгӮӮгӮӢгҖҒ1890пҪһ1933)
ж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲжҠҖиЎ“гҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮгҖҢдёӯжқ‘ејҸгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜж§ӢйҖ гҖҚгҒ®зҷәжҳҺиҖ…гҖӮпјҲйҖҡз§°гҖҢйҺ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢпјүзҰҸеІЎзңҢзіёеі¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еҹәзқЈж•ҷеӣЈжң¬йғ·вҖҰвҖҰ

дёӯжқ‘ијҝиіҮе№і(гҒӘгҒӢгӮҖгӮүгӮҲгҒ—гҒёгҒ„гҖҒ1880пҪһ1963)
жҳҺжІ»жңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжңқй®®гӮ„ж—§жәҖе·һеҸҠгҒійқҷеІЎзңҢгҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®йҠҖиЎҢгӮ„е…¬е…ұе»әзҜүгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮйқҷеІЎзңҢжөңжқҫеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺи‘ӣиҘҝе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ«е…ҘжүҖгҖӮеҫҢе№ҙзӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜвҖҰвҖҰ

й•·еұӢй–Җ(гҒӘгҒҢгӮ„гӮӮгӮ“)
иҝ‘дё–жӯҰ家гӮ„еә„еұӢзӯүгҒ®еұӢж•·гҒ®й–ҖеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮжЁӘй•·е»әзү©гҒ®дёӯеӨ®д»ҳиҝ‘гӮ’йҖҡгӮҠжҠңгҒ‘гҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒй–ҖйғЁеҲҶгҒ®дё»ж§ӢйҖ гҒҜжЎҹжўҒгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҶ жңЁгҒЁдәҢжң¬гҒ®иҰӘжҹұгҒ§гҖҒдәҢжһҡгҒ®й–ҖжүүгҒЁжҪңгӮҠжҲёгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮжүүи„ҮгҒ®йғЁеұӢгҒҜ家иҮЈгӮ„дёӢеғ•гҒ®еұ…жүҖгғ»зү©зҪ®зӯүгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

жөҒйҖ (гҒӘгҒҢгӮҢгҒҘгҒҸгӮҠ)
зҘһзӨҫжң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮеҲҮеҰ»йҖ гҒ§е№іе…ҘгҒ®еүҚжөҒгӮҢгҒҢгӮ„гӮ„й•·гҒҸ延гҒігҒҰеҗ‘жӢқгҒЁгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮжӯЈйқўдёӯеӨ®гҒ«жқҝжүүгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒд»–гҒ®жҹұй–“гӮ’жЁӘзҫҪзӣ®жқҝејөгӮҠгҒЁгҒ—гҖҒе‘ЁгӮҠгҒ«еӢҫ欄д»ҳгҒҚгҒ®зёҒгӮ’гӮҒгҒҗгӮүгҒ—гҒҰйҡҺж®өеҸҠгҒіжөңеәҠгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮе®ҮжІ»дёҠзҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҒҜгҒқгҒ®жңҖеҸӨдҫӢгҖӮ

жҠ•жҺӣгҒ‘жўҒ(гҒӘгҒ’гҒӢгҒ‘гҒ°гӮҠ)
е°ҸеұӢжўҒгҒ®дёҖгҖӮжўҒй–“гҒ®дёӯеӨ®д»ҳиҝ‘пјҲжЎҒиЎҢж–№еҗ‘пјүгҒ«йҖҡгҒ—гҒҹж•·жўҒгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҖҒеүҚеҫҢгҒӢгӮүжһ¶гҒ‘гҒҰж•·жўҒдёҠгҒ§з¶ҷгҒҗгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ

й•·жҠј(гҒӘгҒ’гҒ—)
гҖҢй•·гҒҢжҠјгҒ—пјҲгҒӘгҒҢгҒҠгҒ—пјүгҖҚгҒ®з•ҘгҖӮе®ҹгҒҜгҖҒдёӯеӣҪгғ»йҹ“еӣҪгҒ«гҒҜгҖҢй•·жҠјгҖҚгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢйғЁжқҗгҒҜз„ЎгҒҸгҖҒжҲ‘гҒҢеӣҪзӢ¬иҮӘгҒ«зҷәйҒ”гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
йЈӣйіҘеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®жңЁйҖ е»әзҜүгҒ®жҹұгҒ«гҒҜгҖҒжҹұй ӯгҒ«иҗҪгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖҢй ӯиІ«пјҲгҒӢгҒ—гӮүгҒ¬гҒҚпјүгҖҚгҒЁвҖҰвҖҰ

жіўжұҹжӮҢеӨ«(гҒӘгҒҝгҒҲгӮ„гҒҷгҒҠгҖҒ1885пҪһ1965)
еӨ§йҳӘгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’еҫҢгҖҒзүҮеІЎе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’зөҢгҒҰгҖҒеӨ§йҳӘеёӮ営繕е»әзҜү家иӘІй•·гҒ«е°ұд»»гҖӮеҫҢгҒ«жіўжұҹжӮҢеӨ«е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖй–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§йҳӘжҜҺж—Ҙж–°иҒһжң¬зӨҫпјҲзүҮеІЎе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ§еҹәжң¬вҖҰвҖҰ

еҸҢе Ӯ(гҒӘгӮүгҒігҒ©гҒҶ)
гҒ“гҒ®гҖҢжӯЈе ӮпјҲгҒ—гӮҮгҒҶгҒ©гҒҶпјүгҖҚгҒЁгҖҢзӨје ӮпјҲгӮүгҒ„гҒ©гҒҶпјүгҖҚгҒ®гҖҢеҸҢе ӮгҖҚгҒ®еҪўејҸгҒҢзҷәеұ•гҒ—гҖҒдёҖгҒӨгҒ®еӨ§еұӢж №гҒ«зҙҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢжң¬е ӮгҖҚеҪўејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒ„гҖӮжқұеӨ§еҜәжі•иҸҜе ӮгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ§еұӢж №гӮ’жһ¶гҒ‘гӮӢжҠҖиЎ“гҒҢгҒҫгҒ жңӘжҲҗзҶҹгҒ§гҒӮвҖҰвҖҰ

新家еӯқжӯЈ(гҒ«гҒ„гҒ®гҒҝгҒҹгҒӢгҒҫгҒ•гҖҒ1857пҪһ1922)
жұҹжҲёз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰж ЎйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮе®®еҶ…зңҒгғ»йҖ“дҝЎзңҒгҖҒеҫҢгҒ«ж—Ҙжң¬еңҹжңЁдјҡзӨҫпјҲеӨ§жҲҗе»әиЁӯгҒ®еүҚиә«пјүгҒ«е…ҘзӨҫгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеұұзёЈжңүжңӢеҲҘйӮё/з„Ўй„°еәөжҙӢйӨЁгҖҒж—§еӯҰзҝ’йҷўеҲқзӯү科жӯЈе ӮпјҲйҮҚж–Ү/жҲҗз”°еёӮгҒ«з§»зҜүпјүгҖҒжқұдә¬еӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁ/иЎЁж…¶йӨЁпјҲзүҮеұұжқұвҖҰвҖҰ

д»ҒзҺӢй–Җ(гҒ«гҒҠгҒҶгӮӮгӮ“)
еҜәйҷўгҒ®й–ҖеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮе·ҰгҒ«еҜҶиҝ№йҮ‘еүӣгҖҒеҸігҒ«йӮЈзҫ…延йҮ‘еүӣгҒ®дәҢдҪ“гҒ®еғҸгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢдёүй–“дёҖжҲёгҒ®й–ҖеҪўејҸгҖӮеұӢж №еҪўејҸгӮ„еұӢж №жқҗж–ҷгҒҜдёҖе®ҡгҒӣгҒҡгҖҒдёҖйҮҚгӮӮдәҢйҮҚгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдёҖйҮҚгҒ®йҡӣгҒҜе…«и„ҡй–ҖгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮзҘһзӨҫгғ»е»ҹгҒ®йҡҸиә«еғҸгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢйҡҸиә«й–ҖгҒЁйЎһдјјгҒҷгӮӢгҖӮ

иҘҝжқ‘дјҠдҪң(гҒ«гҒ—гӮҖгӮүгҒ„гҒ•гҒҸгҖҒ1884пҪһ1963)
ж—Ҙжң¬гҒ®ж•ҷиӮІиҖ…гҒ§ж–ҮеҢ–еӯҰйҷўгҒ®еүөе§ӢиҖ…гҖӮеӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гғ»з”»е®¶гғ»йҷ¶иҠёе®¶гғ»и©©дәәгғ»з”ҹжҙ»ж–ҮеҢ–з ”з©¶е®¶гҖӮе’ҢжӯҢеұұзңҢж–°е®®еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжҜҚж–№гҒ®иҘҝжқ‘家пјҲеҘҲиүҜзңҢдёӢеҢ—еұұжқ‘гғ»е’ҢжӯҢеұұзңҢеҢ—еұұжқ‘дёҖдҪ“гҒ®еұұжһ—зҺӢпјүгҒ®еҪ“дё»гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеәғеі¶зңҢгҒ®вҖҰвҖҰ

иҘҝжқ‘еҘҪжҷӮ(гҒ«гҒ—гӮҖгӮүгӮҲгҒ—гҒЁгҒҚгҖҒ1886пҪһ1961)
旧第дёҖйҠҖиЎҢгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®йҠҖиЎҢе»әзҜүгӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгғ»жё…ж°ҙзө„гӮ’зөҢгҒҰ第дёҖйҠҖиЎҢе»әзҜүиӘІй•·гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒ旧第дёҖйҠҖиЎҢзҶҠжң¬ж”Ҝеә—пјҲзҸҫгғ”гғјгӮЁгӮ№зҶҠжң¬гӮ»гғігӮҝгғјпјүгҖҒ旧第вҖҰвҖҰ

иәҷеҸЈ(гҒ«гҒҳгӮҠгҒҗгҒЎ)

гғӢгғғгғҒ(гҒ«гҒЈгҒЎ)
nicheгҖӮеЈҒйҫ•пјҲгҒёгҒҚгҒҢгӮ“пјүгҖӮеЈҒгӮ’еҮ№зҠ¶гҒ«жҠүгҒЈгҒҹйғЁеҲҶгҒ§гҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гӮўгғјгғҒгӮ„еҚҠгғүгғјгғ гҒ§иҰҶгӮҸгӮҢгҖҒгӮЁгғҮгӮЈгӮӯгғҘгғ©гӮ„иҠұ瓶гҒӘгҒ©гҒ®зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢеЈҒгҒ®зӘӘгҒҝгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

дәҢж–№е·®гҒ—(гҒ«гҒ»гҒҶгҒ•гҒ—)
иғҙе·®гӮ„е·®йҙЁеұ…гӮ„и¶іеӣәгӮҒзӯүгҒ®еӨ§ж–ӯйқўжЁӘжһ¶жқҗгҒЁжҹұгҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡж–№жі•гӮ’иЎЁгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжҹұгҒЁдәҢйқўжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜдәҢж–№е·®гҒ—гҒЁе‘јгҒігҖҒдёүйқўгӮ„еӣӣйқўд»ҘдёҠжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒҜдёүж–№е·®гҒ—гҖҒеӣӣж–№е·®гҒ—гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

иІ«ж§Ӣжі•(гҒ¬гҒҚгҒ“гҒҶгҒ»гҒҶ)
йЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҒ®д»Ҹж•ҷе»әзҜүгҒ®жёЎжқҘгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®й•·гҒ„еҺҹе§ӢгҒ®зң гӮҠгҒӢгӮүгҒ®зӣ®иҰҡгӮҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҪ“жҷӮгҒ®е»әзү©гҒҜгҖҒгҖҢй ӯиІ«пјҲгҒӢгҒ—гӮүгҒ¬гҒҚпјүгҖҚгӮ„гҖҢйЈӣиІ«пјҲгҒІгҒ¬гҒҚпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒҜз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжЁӘеҠӣгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиҖғж…®гҒ—гҒӘгҒ„гҖҒгҖҢжҹұгҖҚвҖҰвҖҰ

жӢӯжқҝж•·(гҒ¬гҒҗгҒ„гҒ„гҒҹгҒҳгҒҚгҖҒгҒ—гҒҚгҒ„гҒҹгҒҳгҒҚ)
ж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүгҒҜзҙ жңЁпјҲгҒ—гӮүгҒҚпјүгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҖҒгҒқгҒ®д»•дёҠгҒ’гҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒҜжҳ”гҒӢгӮүж—Ҙжң¬дәәгҒ«еҘҪгҒҫгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮи„ұйқҙгҒ—гҒҰгҖҒзҙ и¶ігҒ§гҒқгҒ®дёҠгӮ’жӯ©иЎҢгҒ—гҖҒи¶іиЈҸгҒ®ж„ҹиҰҡгӮ’йӢӯж•ҸгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮпјҲи„ұйқҙгӮ’гҒ—гҒӘгҒ„欧зұігҒ®ж–ҮеҢ–гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјүжңЁвҖҰвҖҰ

еёғж•·(гҒ¬гҒ®гҒ—гҒҚ)

жҝЎзёҒ(гҒ¬гӮҢгҒҲгӮ“)

гғҚгӮӨгғ–(гҒӯгҒ„гҒ¶)
naveгҖӮиә«е»ҠгҖӮж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёӯеӨ®гҒ®зҙ°й•·гҒ„еәғй–“гҒ®йғЁеҲҶгҖӮгғ©гғҶгғіиӘһгҒ§гҖҢиҲ№гҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢnavisгҒӢгӮүеҮәгҒҹиӘһгҖӮгҖҢгғҠгғ“гӮІгғјгӮ·гғ§гғіпјҲиҲӘжө·гғ»иҲӘжө·иЎ“пјүгҖҚгӮӮеҗҢзҫ©иӘһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҚгӮӘгӮҜгғ©гӮ·гӮ·гӮәгғ ж§ҳејҸ(гҒӯгҒҠгҒҸгӮүгҒ—гҒ—гҒҡгӮҖгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Neo-Classicism styleгҖӮж–°еҸӨе…ёдё»зҫ©ж§ҳејҸгҖӮ18дё–зҙҖгҒ«гҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜгӮ„гғӯгӮігӮігҒ®е…ёйӣ…гҒӘи¶Је‘ігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҸҚеӢ•гҒЁгҒ—гҒҰиҲҲгӮҠгҖҒ19дё–зҙҖеүҚеҚҠжңҹгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҹе»әзҜүгҒ®еӢ•еҗ‘гҒ§гҖҒеҸӨе…ёеҸӨд»ЈгҒ®еҶҚиӘҚиӯҳгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮгғӯгғһгғівҖҰвҖҰ

гғҚгӮӘгӮ°гғӘгғјгӮҜж§ҳејҸ(гҒӯгҒҠгҒҗгӮҠгғјгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Neo-Greek styleгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«еҸӨд»ЈгӮ®гғӘгӮ·гғЈе»әзҜүгҒ®еҫ©иҲҲгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷеӢ•гҒҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ18дё–зҙҖгҒӢгӮү19дё–зҙҖеүҚеҚҠжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰиө·гҒЈгҒҹж–°еҸӨе…ёдё»зҫ©гҒ®дёҖгҒӨгҖӮиӢұеӣҪгҒ®J.гӮҪгғјгғігҖҒзӢ¬еӣҪгҒ®K.F.гӮ·гғігӮұгғ«гҒҜгҒқгҒ®д»ЈиЎЁе»әзҜү家гҖӮгҖҢвҖҰвҖҰ

гғҚгӮӘгӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸ(гҒӯгҒҠгҒ”гҒ—гҒЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Neo-Gotjhic styleгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«дёӯдё–гӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ®еҫ©иҲҲгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷеӢ•гҒҚгҒ®ж§ҳејҸгҖӮзІҫзҘһеҸІзҡ„гҒ«гҒҜгғӯгғһгғідё»зҫ©гҒ®дёҖгҒӨгҒ®еҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе»әзҜүж§ҳејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҢгғ”гӮҜгғҒгғЈгғ¬гӮ№гӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒ«еҢ…гҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®иө·жәҗгҒҜиӢұеӣҪвҖҰвҖҰ

гғҚгӮӘгғҗгғӯгғғгӮҜж§ҳејҸ(гҒӯгҒҠгҒ°гӮҚгҒЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Neo-Baroque styleгҖӮ欧е·һгҒ®19дё–зҙҖеҫҢеҚҠжңҹгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢиҠёиЎ“гҒ®дёҖеӮҫеҗ‘гҒ§гҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜзҡ„гҒӘеӢ•ж„ҹиұҠгҒӢгҒӘиЎЁзҸҫгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгӮӮгҒ®гҖӮж–°еҸӨе…ёдё»зҫ©гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҸҚжҠ—гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӣһгҒҢгғ»еҪ«еҲ»гғ»е·ҘиҠёгҒ®еҗ„еҲҶйҮҺгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢеӢ•еҗ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒвҖҰвҖҰ

гғҚгӮӘгғ«гғҚгӮөгғігӮ№ж§ҳејҸ(гҒӯгҒҠгӮӢгҒӯгҒ•гӮ“гҒҷгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Neo-Renaissance styleгҖӮ19дё–зҙҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгғҚгӮӘгӮ°гғӘгғјгӮҜгҖҚгҖҢгғҚгӮӘгғҗгғӯгғғгӮҜгҖҚгҒӘгҒ©дёҖйҖЈгҒ®дёҖзЁ®гҒ®жӯҙеҸІдё»зҫ©зҡ„еӢ•еҗ‘гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒгғ«гғҚгӮөгғігӮ№е»әзҜүгҒ®еҫ©иҲҲгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгӮӮгҒ®гҖӮF.v.гӮІгғ«гғҲгғҠгғјгӮ„G.гӮјгғігғ‘гғјгҒӘвҖҰвҖҰ

ж №еӨӘеӨ©дә•(гҒӯгҒ гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)
民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒӨгҒ—дәҢйҡҺзӯүгҒ®еӨ§еј•гӮ„ж №еӨӘгҒ«еҺҡгҒ„еәҠжқҝгӮ’ејөгҒЈгҒҰйҡҺдёӢгҒ®еӨ©дә•гҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮиёҸгҒҝеӨ©дә•гҒЁгӮӮе‘јгҒ¶гҖӮз°ҖеӯҗеӨ©дә•гҒҜгҖҒз«№гӮ’дёҰгҒ№гҒҰз·ЁгҒҝгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«и“ҶгӮ’ж•·гҒ„гҒҰзІҳеңҹгӮ’ијүгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеұӢж №иЈҸгҒ®йҳІзҒ«дёҠгҒ®е·ҘеӨ«гҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

иғҪиҲһеҸ°(гҒ®гҒҶгҒ¶гҒҹгҒ„)
иғҪжҘҪгӮ’жј”гҒҳгӮӢиҲһеҸ°гҖӮдә¬й–“дёүй–“еӣӣж–№гҒ®жң¬иҲһеҸ°гҒ®еҘҘгҒ«дёҖй–“еҚҠдёүй–“гҒ®еҫҢеә§гҖҒеҸіи„ҮгҒ«еҚҠй–“дёүй–“гҒ®ең°и¬Ўеә§гӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒйҸЎгҒ®й–“гҒЁеҫҢеә§гҒЁгҒ®й–“гҒ«ж–ңдәӨгҒҷгӮӢж©ӢжҺӣгӮҠгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮжң¬иҲһеҸ°гғ»ж©ӢжҺӣгӮҠгғ»жҘҪеұӢгҒӘгҒ©гҒҜеұӢж №жҺӣгҒ‘гҖҒиҰӢжүҖгҒҜйңІеӨ©гҒ®гҒҫгҒҫгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

и»’е”җз ҙйўЁ(гҒ®гҒҚгҒӢгӮүгҒҜгҒө)
е®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ®еӨ§йҳӘгҒ®зҘһзӨҫе»әзҜүгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢи»’е”җз ҙйўЁгҖҚгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢдҪ•ж•…гҒӢеӨҡгҒ„гҖӮгҖҢж„ҸиіҖзҫҺпјҲгҒҠгҒҢгҒҝпјүзҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҖҚгҖҢйҢҰз№”пјҲгҒ«гҒ—гҒ”гҒҶгӮҠпјүзҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҖҚгҖҢеӨҡжІ»йҖҹжҜ”еЈІпјҲгҒҹгҒҳгҒҜгӮ„гҒІгӮҒпјүзҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҖҚгҒқгҒ—гҒҰгҖҢиҰіеҝғеҜәиЁ¶жўЁеёқжҜҚпјҲгҒӢгӮҠгҒҰгҒ„гӮӮпјүвҖҰвҖҰ

йҮҺеҸЈеӯ«еёӮ(гҒ®гҒҗгҒЎгҒҫгҒ”гҒ„гҒЎгҖҒ1869пҪһ1915)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҒдҪҸеҸӢ営繕гҒ®еҹәзӨҺгӮ’зҜүгҒ„гҒҹдәәзү©гҖӮ姫и·ҜеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ еҪўеӯҰ科еҚ’гҖӮ欧е·һиҰ–еҜҹгҒ§гҖҒгғӯгғігғүгғігҒ®еҫҢжңҹгғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўж§ҳејҸгӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§йҳӘеәңз«ӢеӣіжӣёйӨЁпјҲеәңз«Ӣдёӯд№Ӣеі¶еӣіжӣёйӨЁ/еў—зҜүйғЁиЁӯвҖҰвҖҰ

йҮҺз”°дҝҠеҪҰ(гҒ®гҒ гҒЁгҒ—гҒІгҒ“гҖҒ1891пҪһ1929)
еӨ§жӯЈжңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҖҒе®ҳе…¬еәҒзі»гҒ®иҒ·е ҙгҒ«еҘүиҒ·гҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮиҝ‘д»Јж—Ҙжң¬е»әзҜүеҸІдёҠгҒ§гҒҜгҖҢе»әзҜүйқһиҠёиЎ“и«–гҖҚгҒӘгҒ©гӮ’и‘—гҒ—гҒҹи«–е®ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҒҙйқўгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҪјгҒ«иҠёиЎ“гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҗҶи§ЈгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹиЁігҒ§гҒҜжұәгҒ—гҒҰгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®дё»ж—ЁгҒҜгҖҒиЈ…йЈҫгӮ’жҺ’гҒ—гҒҹвҖҰвҖҰ

жҳҮгӮҠеӢҫ欄(гҒ®гҒјгӮҠгҒ“гҒҶгӮүгӮ“)

йҮҺзү©(гҒ®гӮӮгҒ®)

йҮҺеұӢж №(гҒ®гӮ„гҒӯ)
гҒҜгҖңгҒ»

гғҸгғјгғ•гғҶгӮЈгғігғҗгғјж§ҳејҸ(гҒҜгғјгҒөгҒҰгҒғгӮ“гҒ°гғјгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
half-timber construction styleгҖӮгӮўгғ«гғ—гӮ№д»ҘеҢ—гҒ®ж¬§е·һпјҲиӢұгғ»зӢ¬гғ»д»ҸпјүгҒ®жңЁйҖ е»әзҜүгҒ«еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢжҠҖжі•гҒ§гҖҒзү№гҒ«15дё–зҙҖгҒӢгӮү17дё–зҙҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиӢұеӣҪгҒ®дҪҸе®…гҒ«еӨҡз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҢеҚҠжңЁйӘЁйҖ гҖҚвҖҰвҖҰ

й…Қд»ҳеһӮжңЁ(гҒҜгҒ„гҒӨгҒ‘гҒ гӮӢгҒҚ)

жӢқж®ҝ(гҒҜгҒ„гҒ§гӮ“)

гғ‘гӮӨгғӯгғі(гҒұгҒ„гӮҚгӮ“)
pylonгҖӮеЎ”й–ҖгҒЁиЁігҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®зҘһж®ҝгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«гҒӮгӮӢй–ҖгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәҢгҒӨгҒ®еҸ°еҪўзҠ¶гҒ®е»әйҖ зү©гӮ’зөҗгӮ“гҒ ж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣ гҒҝгҒ«гҖҒе·ҘдәӢзҸҫе ҙгҒ§иҰӢгҒӢгҒ‘гӮӢгҖҢгӮігғјгғігҖҚгҒ®жӯЈејҸгҒӘеҗҚз§°гҒҜгҖҢгғ‘гӮӨгғӯгғігғ»гӮігғјгғігҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгӮҰгғҸгӮҰгӮ№(гҒ°гҒҶгҒҜгҒҶгҒҷ)
BauhausгҖӮ1919е№ҙгҖҒзӢ¬еӣҪгҒ®гғҙгӮЎгӮӨгғһгғ«гҒ«W.гӮ°гғӯгғ”гӮҰгӮ№пјҲ1926гҖҒгғҗгӮҰгғҸгӮҰгӮ№ж ЎиҲҺпјүгӮ’ж Ўй•·гҒЁгҒ—гҒҰеүөиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪз«ӢгҒ®йҖ еҪўеӯҰж ЎгҖӮжҖҘйҖІзҡ„гҒӘж•ҷиӮІзҗҶеҝөгҒ®ж•…гҒ«гҖҒгӮ„гҒҢгҒҰеҸіеӮҫеҢ–гҒҷгӮӢж”ҝжғ…гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§еӯҳз¶ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒвҖҰвҖҰ

йҡҺйҡ (гҒҜгҒ—гҒӢгҒҸгҒ—)

з«Ҝе–°жҲё(гҒҜгҒ—гҒ°гҒҝгҒ©)

гғҗгӮ·гғӘгӮ«(гҒ°гҒ—гӮҠгҒӢ)
basilicaгҖӮеҸӨд»ЈгғӯгғјгғһжҷӮд»ЈгҒ«гҖҒиЈҒеҲӨгӮ„е•ҶеҸ–еј•гҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹе…¬е…ұе»әзҜүзү©гҖӮйҖҡеёёгҒҜзҙ°й•·гҒ„зҹ©еҪўгҒ®е№ійқўгӮ’жҢҒгҒӨе»әзү©гҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒҜеҲ—жҹұгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёүгҒӨгҒ®е»ҠдёӢзҠ¶гҒ®з©әй–“гҒ«еҲҶеүІгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжңҖгӮӮеҘҘгҒ®гҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°еҚҠеҶҶеҪўгҒ«зӘҒеҮәгҒ—вҖҰвҖҰ

й•·и°·йғЁйӢӯеҗү(гҒҜгҒӣгҒ№гҒҲгҒ„гҒҚгҒЎгҖҒ1885пҪһ1960)
ж—Ҙе»әиЁӯиЁҲгҒ®жҜҚдҪ“гҒ®й•·и°·йғЁз«№и…°е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ®еүөжҘӯиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮжңӯе№Ңз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒдҪҸеҸӢгғ“гғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјҲеӨ§йҳӘпјүгҖҒжіүеұӢеҚҡеҸӨйӨЁгҖҒж—Ҙжң¬з”ҹе‘Ҫдҝқйҷәжң¬зӨҫгҖҒгӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜиҠҰеұӢж•ҷдјҡгҖҒеӨ§йҳӘгӮ«гғҶгғүгғ©гғ«иҒ–гғһгғӘгӮўеӨ§иҒ–вҖҰвҖҰ

ж’Ҙжқҹ(гҒ°гҒЎгҒҘгҒӢ)

е…«е№ЎйҖ (гҒҜгҒЎгҒҫгӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)
зҘһзӨҫжң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮдёүй–“дәҢй–“гҒ®жң¬ж®ҝгҒ®еүҚгҒ«дёүй–“дёҖй–“гҒ®еүҚж®ҝгӮ’е»әгҒҰгҖҒгҒқгҒ®й–“гӮ’зӣёгҒ®й–“пјҲеҗҲгҒ®й–“гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶпјүгҒЁгҒ—гҒҰеүҚеҫҢеҲҘгҖ…гҒ®еұӢж №гӮ’жһ¶гҒ‘гҒҰдәҢжЈҹгӮ’дёҖжЈҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жүұгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮд»Ҹе ӮгҒ®еҸҢе ӮгҒЁеҗҢи¶ЈгҖӮд№қе·һгҒ®е®ҮдҪҗзҘһе®®жң¬ж®ҝгҒҜгҒ“гҒ®д»ЈиЎЁдҫӢгҖӮ

е…«и§’еҶҶе Ӯ(гҒҜгҒЈгҒӢгҒҸгҒҲгӮ“гҒ©гҒҶ)
е№ійқўгҒҢе…«и§’гҒ®д»Ҹе ӮгҒ®з·Ҹз§°гҖӮжі•йҡҶеҜәеӨўж®ҝгҖҒж „еұұеҜәе…«и§’еҶҶе ӮгҖҒиҲҲзҰҸеҜәеҢ—еҶҶе ӮгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеӨҡгҒҸгҒҜж•…дәәгҒ®йңҠгӮ’гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢеЎ”е»ҹгҒ®жҖ§ж јгӮ’жҢҒгҒӨгҖӮеұӢж №гҒҜе…«гҒӨгҒ®жөҒгӮҢгҒ§е…«жіЁгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒе№ійқўгҒҢе…ӯи§’гҒ®д»Ҹе ӮгӮ’е…ӯи§’е ӮгҒЁе‘јгҒігҖҒдҫӢгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮвҖҰвҖҰ

жі•е Ӯ(гҒҜгҒЈгҒЁгҒҶ)
д»Ҹжі•гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢзҰ…е®—е»әзҜүгҒ®дёҖгҖӮд»–е®—гҒ®и¬ӣе ӮгҒ«зӣёеҪ“гҖӮдёүй–Җгғ»д»Ҹж®ҝгғ»жі•е ӮгҒ®й ҶгҒ«дёҖи»ёз·ҡдёҠгҒ«дёҰгҒігҖҒеҪўж…ӢгҒҜд»Ҹж®ҝгҒЁеҗҢдёҖгҒ§гҖҒд»Ҹж®ҝгӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮж–№дёүй–“гҒ®иә«иҲҺгҒ®еӣӣе‘ЁгҒ«дёҖй–“йҖҡгӮҠгҒ®иЈійҡҺгӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒеҶ…йғЁгҒҜеңҹй–“еәҠгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№(гҒ°гҒЈгҒЁгӮҢгҒҷ)
buttressгҖӮжҺ§еЈҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒеЈҒгҒ«еҠ гӮҸгӮӢеҒҙең§гҒ«иҖҗгҒҲгҒҰгҒқгҒ®еҖ’еЈҠгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеЈҒгҒӢгӮүзӘҒеҮәгҒ—гҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиЈңеј·з”ЁгҒ®еЈҒгҖӮгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒдё»гҒЁгҒ—гҒҰиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷд»ҳжҹұгӮ’жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒгӮҙгӮ·гғғгӮҜж•ҷдјҡе ӮвҖҰвҖҰ

гғ‘гғҶгӮЈгӮӘ(гҒ°гҒҰгҒғгҒҠ)
patioгҖӮгӮ№гғҡгӮӨгғігӮ„гғ©гғҶгғігӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®дҪҸе®…гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖҒеҷҙж°ҙгӮ„жӨҚж ҪгҒӘгҒ©гӮ’й…ҚгҒ—гҒҹдёӯеәӯгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮйЈҹе ӮгӮ„еҝңжҺҘе®Өгғ»еұ…й–“гҒӘгҒ©гҒ«йҖЈз¶ҡгҒҷгӮӢеұӢеӨ–з©әй–“гҒ§гҖҒеәҠгҒҜгӮҝгӮӨгғ«ејөгӮҠгҒ§еҶ…йғЁгҒЁдёҖдҪ“зҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮўгғјгӮұгғјгғү гӮ„еҲ—жҹұе»ҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰвҖҰвҖҰ

йј»йҡ (гҒҜгҒӘгҒӢгҒҸгҒ—)

жЎ”жңЁ(гҒҜгҒӯгҒҺ)
ж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒдёӢгҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢеҢ–зІ§жқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®и»’еӨ©гҒЁгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҢйҮҺзү©пјҲгҒ®гӮӮгҒ®пјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж§ӢйҖ жқҗгҒЁгҒҢгҖҒе№іе®үжҷӮд»Јжң«жңҹгҒ”гӮҚгҒ«еҲҶйӣўгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢеҲҘгҖ…гҒ«ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеұӢж №вҖҰвҖҰ

гғ‘гғ“гғӘгӮӘгғі(гҒұгҒігӮҠгҒҠгӮ“)
pavilionгҖӮе…ғгҒҜгҖҒе»әзү©гҒӢгӮүзӘҒеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгӮ„гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘе»әзү©гҒӢгӮүеҲҶйӣўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе»әзү©гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеҫҢгҒ«гҖҒеәӯең’гғ»е…¬ең’гғ»гғ¬гӮҜгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғіж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢи»Ҫеҝ«гҒӘиЈ…йЈҫзҡ„ж§ӢзҜүзү©гӮ„гҖҒеҚҡиҰ§дјҡгҒ§еҖӢгҖ…гҒ®еҮәеұ•иҖ…гҒ«гӮҲвҖҰвҖҰ

з ҙйўЁ(гҒҜгҒө)
йҖҡеёёгҖҒгҖҢз ҙйўЁжқҝгҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҰ»еҒҙгҒ«гҒӮгӮӢд»ҳеұһзү©гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒз·Ҹз§°гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢз ҙйўЁгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ
еұӢж №еҪўејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢеҲҮеҰ»з ҙйўЁгҖҚгҖҢе…ҘжҜҚеұӢз ҙйўЁгҖҚгҖҢеҲҮз ҙйўЁгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҢз ҙйўЁжқҝгҖҚгҒ®еҪўзҠ¶гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢзӣҙз ҙйўЁпјҲгҒҷгҒҗгҒҜгҒөпјүгҖҚвҖҰвҖҰ

з ҙйўЁгҒ®з«ӢжүҖ(гҒҜгҒөгҒ®гҒҹгҒҰгҒ©гҒ“гӮҚ)

жөңеәҠ(гҒҜгҒҫгӮҶгҒӢ)
зҘһзӨҫгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжң¬ж®ҝгҒӘгҒ©гҒ®еҗ‘жӢқдёӢгҒ«гҒӮгӮӢдҪҺгҒ„зёҒгҖӮе®®еҸёдјәеҖҷгҒ®е ҙгҖҒгҖҢжөңзёҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ民家гҒ§гҒҜзёҒеҸ°гӮ„зёҒеҒҙгҖҒејҸеҸ°зӯүгӮ’жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
вҖҰвҖҰ

гғҗгғ©гӮ№гӮҝгғј(гҒ°гӮүгҒҷгҒҹгғј)
balusterгҖӮ欧е·һгҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжүӢж‘әгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢжүӢж‘әеӯҗгғ»жүӢж‘әжқҹгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮйҖҡеёёгҒҜгҖҒж–ӯйқўгҒҢеҶҶеҪўгҒ§з№°еһӢпјҲгғўгғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжӨ…еӯҗгҒ®иғҢеҮӯгӮҢгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢеһӮзӣҙжқҗгӮӮгҖҢгғҗгғ©гӮ№гӮҝгғјгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гғ‘гғ©гғҡгғғгғҲ(гҒұгӮүгҒәгҒЈгҒЁ)
parapetгҖӮиғёеЈҒгҖҒжү¶еЈҒгҒЁиЁігҒҷгҖӮжң¬жқҘгҒҜгҖҒе»әзү©гҒ®еұӢдёҠгӮ„еҗ№ж”ҫгҒ—е»ҠдёӢгҒ®жүӢж‘әеЈҒгҖҒж©ӢгҒ®ж¬„е№І гӮ’жҢҮгҒҷиӘһгҖӮзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜгҖҒйҷёеұӢж №гҒ®еұӢдёҠгҒ®еӨ–е‘ЁгҒ«жІҝгҒЈгҒҰз«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҖҒйҳІж°ҙеұӨгҒ®з«ҜйғЁгҒ®зҙҚгҒҫгӮҠдёҠгҒ®еҪ№еүІгӮ’гҒҜгҒҹгҒҷи…°еЈҒгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

и–”и–ҮзӘ“(гҒ°гӮүгҒҫгҒ©)
rose windowгҖӮдёёзӘ“гҒ®дёҖеҪўж…ӢгҖӮгҒқгҒ®гҖҢгғҲгғ¬гғјгӮөгғӘгғјгҖҚгҒҢи–”и–ҮгҒ®иҠұгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҖ гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҗҚз§°гҖӮзү№гҒ«12пҪһ13дё–зҙҖгҒ®гӮҙгӮ·гғғгӮҜж•ҷдјҡе ӮгҒ§гҒҜгҖҒиҘҝжӯЈйқўгҒ®иә«е»ҠеҸҠгҒіеҚ—еҢ—гҒ®иў–е»ҠгҒ®жӯЈйқўгҒ«гҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒӘгӮ№гғҶвҖҰвҖҰ

ејөд»ҳеЈҒ(гҒҜгӮҠгҒӨгҒ‘гҒӢгҒ№)

гғҗгғ«гғҖгғғгӮӯгғјгғҺ(гҒ°гӮӢгҒ гҒЈгҒҚгғјгҒ®)
baldacchinoгҖӮеӨ©и“ӢгҖӮгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷж•ҷдјҡе ӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёӯеӨ®зҘӯеЈҮгҒ®дёҠж–№гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиҰҶгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ4жң¬гҒ®жҹұгҒ§ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҖҒйӯ”гӮүгҒҜйҺ–гҒ§еҗҠгӮӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гғҗгғӯгғғгӮҜж§ҳејҸ(гҒ°гӮҚгҒЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Broque styleгҖӮ1600е№ҙй ғгҒӢгӮү1730е№ҙй ғгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰ全欧гҒ«еәғгҒҫгҒЈгҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгҖҢгғҗгғӯгғғгӮҜпјҲжӯӘгӮ“гҒ зңҹзҸ пјүгҖҚгҒ®иӘһгҒҢзӨәгҒҷйҖҡгӮҠгҖҒиҚҳйҮҚз«ҜжӯЈгҒӘгғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒ®еҸӨе…ёдё»зҫ©е»әзҜүгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжөҒеӢ•зҡ„гҒӘгғӘгӮәгғ ж„ҹгҖҒиұӘиҸҜзөўзҲӣгҒҹгӮӢвҖҰвҖҰ

еҚҠеҶҶгӮўгғјгғҒ(гҒҜгӮ“гҒҲгӮ“гҒӮгғјгҒЎ)
semi-circular archгҖӮгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒ®дёҖгҒӨгҖӮеҚҠеҶҶеҪўгҒ®гӮўгғјгғҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еҝ…然гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҹұгҒ®й–“йҡ”гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮөгӮӨгӮәгҒҢжұәгҒҫгӮҠгҖҒз•°гҒӘгӮӢй–“йҡ”гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгҒ®й«ҳгҒ•гҒҢжҸғгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдёҚйғҪеҗҲгҒҢз”ҹвҖҰвҖҰ

зүҲзҜү(гҒҜгӮ“гҒЎгҒҸ)
з ӮгҒЁзІҳеңҹпјҲзҹізҒ°гӮ’ж··гҒңгҒҹиүҜиіӘгҒӘзІҳеңҹпјүгҒЁгӮ’дәӨдә’гҒ«еұӨзҠ¶гҒ«гҒ—гҒҰзӘҒгҒҚеӣәгӮҒгӮӢе·Ҙжі•гҒ§гҖҒеҸӨд»ЈгӮҲгӮҠеҹҺеЈҒгӮ„е»әзҜүзү©гҒ®еҹәеЈҮгҖҒеңҹеЎҖгҒ®ж§ӢзҜүгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮдёҖж–№гҖҒз“ҰгҒЁзІҳеңҹгӮ’дәӨдә’гҒ«з©ҚйҮҚгҒӯгҒҰйҖ гҒЈгҒҹеңҹеЎҖгҒҜз·ҙеЎҖгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒеҜәйҷўгӮ„民家гҒ«гҒқгҒ®дҫӢгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮвҖҰвҖҰ

еҚҠй•·жҠј(гҒҜгӮ“гҒӘгҒ’гҒ—)

гғҸгғігғһгғјгғ“гғјгғ (гҒҜгӮ“гҒҫгғјгҒігғјгӮҖ)
hammer beamгҖӮе®ӨеҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеЈҒгҒ®дёҠз«ҜгҒӢгӮүзӘҒеҮәгҒ—гҒҹзүҮжҢҒгҒЎжўҒгӮ’жҢәеҮәгҒ•гҒӣгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«з«ӢгҒӨгӮўгғјгғҒжқҗгҒ§жЈҹжңЁгӮ„жўҒгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸеұӢзө„гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
жҹұгҒ®гҒӘгҒ„еәғгҒ„з©әй–“гӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иӢұеӣҪгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢжңЁйҖ вҖҰвҖҰ

гғ“гғјгғү(гҒігғјгҒ©)
beadгҖӮзҺүзёҒйЈҫгӮҠгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе…Ҙйҡ…йғЁгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢеҚҠзҗғзҠ¶гҒ®з№°еһӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

гғ”гӮў(гҒҙгҒӮ)
pierгҖӮеҚҳдёҖйғЁжқҗгҒҫгҒҹгҒҜзҹӯгҒ„еҶҶзӯ’зҠ¶йғЁжқҗгӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҹеҶҶеҪўж–ӯйқўгҒ®гҖҢеҶҶжҹұпјҲгӮігғ©гғ пјүгҖҚгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҗ„еұӨгҒ”гҒЁгҒ«ж•°еҖӢгҒ®йғЁжқҗгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгҖҒж–ӯйқўгҒҢжӯЈж–№еҪўгғ»еӨҡи§’еҪўгғ»еҶҶеҪўжҲ–гҒ„гҒҜгҒ“гӮҢгӮүгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹиӨҮйӣ‘гҒӘеҪўгӮ’жҢҒгҒӨеӨӘвҖҰвҖҰ

йЈӣжӘҗеһӮжңЁ(гҒІгҒҲгӮ“гҒ гӮӢгҒҚ)

гғ”гӮҜгғҒгғЈгғ¬гӮ№гӮҜ(гҒҙгҒҸгҒЎгӮғгӮҢгҒҷгҒҸ)
picturesqueгҖӮе…ғжқҘгҒҜиҠёиЎ“гғ»з”ҹжҙ»еӮҷе“ҒгҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒд»–гҒ®жҷӮд»Јгғ»з’°еўғгғ»жөҒиЎҢгҒӘгҒ©гҒ®йӣ°еӣІж°—гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢзҫҺзҡ„гҒӘж„ҹиҰҡгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®ж§ҳејҸгӮ’жҢҮгҒҷгҒҢгҖҒе»әзҜүгҒ§гҒҜзү№гҒ«гҖҒ18дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ®иӢұеӣҪгҒ§иө·гҒ“гҒЈгҒҰ19дё–зҙҖдёӯй ғгҒҫгҒ§е…Ёж¬§гӮ„вҖҰвҖҰ

еәҮ(гҒІгҒ•гҒ—)
гҖҖ

иӮҳжңЁ(гҒІгҒҳгҒҚ)
еҪўзҠ¶гғ»з№°еҪўгҒ®гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зү№еҫҙгӮ’еҲ—иЁҳгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮгҖҢе’Ңж§ҳиӮҳжңЁгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёӢз«ҜгҒ®з№°гӮҠдёҠгҒ’жӣІйқўгҒҢгҖҒгҖҢжңЁеҸЈпјҲеҲҮгӮҠеҸЈпјүгҖҚгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§зёҰгҒ«еҲҮгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢжңҖгӮӮеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ®е»әзү©гҒҜгҖҒгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠз«ҜгҒ«гҖҢвҖҰвҖҰ

иҸұжӣІгӮ’гҒЁгӮӢ(гҒІгҒ—гҒҗгҒӣгӮ’гҒЁгӮӢ)

жӯӘй«ҳеЎҖйҖ (гҒІгҒҡгҒҝгҒҹгҒӢгҒёгҒҘгҒҸгӮҠ)

ж—Ҙй«ҳиғ–(гҒІгҒ гҒӢгӮҶгҒҹгҒӢгҖҒ1875пҪһ1952)
ж—§дҪҸеҸӢиІЎй–ҘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е»әйҖ зү©гӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјж§ҳејҸ гҒ®зҘһжң¬зҗҶй«Әеә—пјҲзҸҫеӯҳгҒӣгҒҡпјүгҒ®иЁӯиЁҲгӮ„гҖҒдҪҸеҸӢгғ“гғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гҒ®е»әиЁӯгҒ®з·ҸжҢҮжҸ®гӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’вҖҰвҖҰ

дёҖзӯӢеӯҗжҢҒгҒЎйҡңеӯҗ(гҒІгҒЁгҒҷгҒҳгҒ“гӮӮгҒЎгҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)

гғ”гғҠгӮҜгғ«(гҒҙгҒӘгҒҸгӮӢ)
pinnacleгҖӮе°Ҹе°–еЎ”гғ»йЈҫгӮҠе°–еЎ”гҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢгғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№пјҲжҺ§еЈҒпјүгҖҚгҒ®й ӮйғЁгӮ„йЈҫгӮҠз ҙйўЁгҒ®дёЎеҒҙгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒ«иЈ…йЈҫгҒ•гӮҢгҒҹе°ҸгҒ•гҒӘеЎ”гҖӮгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ гҒ®жЁӘең§гӮ’еқҮиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«дҝқгҒӨзӣ®зҡ„гҒ§иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮвҖҰвҖҰ

йЈӣиІ«(гҒІгҒ¬гҒҚ)

иЎЁзҸҫдё»зҫ©(гҒІгӮҮгҒҶгҒ’гӮ“гҒ—гӮ…гҒҺ)
ExpressionismгҖӮзҫҺиЎ“гҒ®гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзү№гҒ«з¬¬дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеүҚгҒ®зӢ¬еӣҪгӮ’дёӯеҝғгҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҹиҝ‘д»ЈзҫҺиЎ“гҒ®дёҖеӮҫеҗ‘гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ1905е№ҙгҒ«гҖҒгғүгғ¬гӮ№гғҮгғігҒ§E.гӮұгғғгғҳгғ«гҖҒE.L.гӮӯгғ«гғ’гғҠгғјгӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзө„з№”гҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгғ–гғӘгғҘгғғгӮұвҖҰвҖҰ

з“ўз®ӘзҢӘгҒ®зӣ®(гҒІгӮҮгҒҶгҒҹгӮ“гҒ„гҒ®гӮҒ)

ж—ҘеҗүйҖ (гҒІгӮҲгҒ—гҒҘгҒҸгӮҠгҖҒгҒІгҒҲгҒҘгҒҸгӮҠ)
зҘһзӨҫжң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮеӨ§жҙҘеёӮеқӮжң¬гҒ®ж—ҘеҗүеӨ§зӨҫгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮдёүй–“дәҢй–“гҒ®иә«иҲҺгҒ®еүҚж–№гҒЁе·ҰеҸігҒ®дёүж–№гҒ«еәҮгҒҢгӮҒгҒҗгӮүгӮҢгҖҒдёҖгҒӨгҒ®еұӢж №гҒ®дёӢгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжӯЈйқўгҒҜе…ҘжҜҚеұӢйҖ е№іе…ҘгҖҒиғҢйқўгҒҜеәҮгҒҢгҒӘгҒҸиўҙи…°йўЁгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§иҒ–еёқйҖ гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮвҖҰвҖҰ

гғ”гғ©гӮ№гӮҝгғј(гҒҙгӮүгҒҷгҒҹгғј)
pilasterгҖӮиЈ…йЈҫз”Ёд»ҳгҒ‘жҹұгҖӮжҹұеһӢгҖӮеЈҒйқўгӮҲгӮҠе№ҫеҲҶзӘҒеҮәгҒ—гҒҹж–№еҪўж–ӯйқўгҒ®жҹұгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

е№іжһ—йҮ‘еҗҫ(гҒІгӮүгҒ°гӮ„гҒ—гҒҚгӮ“гҒ”гҖҒ1894пҪһ1981)
ж„ӣзҹҘзңҢиұҠеұұз”әз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе№іжһ—家гҒ®йӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮҠжқұдә¬гҒ«з§»дҪҸгҖӮжқұдә¬й«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫжқұдә¬е·ҘжҘӯеӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮй«ҳж©ӢиІһеӨӘйғҺгҖҖгҒ®еӢ§гӮҒгҒ§еҶ…еӢҷзңҒгҒ«е…ҘзңҒгҖӮеҫҢгҒ«е®®еҶ…зңҒгҒ«з§»гӮҠгҖҒеҗҢеғҡгҒ гҒЈгҒҹеІЎжң¬йҰЁгҒЁгҒ®йҖЈеҗҚгҒ§еӨ§йҳӘеәңеәҒиҲҺгҒ®гӮігғігғҡгҒ«еҝңеӢҹгҒ—дёҖзӯүеҪ“йҒёвҖҰвҖҰ

е№іжқҫиӢұеҪҰ(гҒІгӮүгҒҫгҒӨгҒІгҒ§гҒІгҒ“гҖҒ1894пҪһ1928)
жқұдә¬й«ҳијӘз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжӯҰз”°дә”дёҖ гҒ«её«дәӢгҖӮеӨ§жһ—зө„гҒ®е»әзҜүиЁӯиЁҲиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҖҒжң¬еә—гҒ®еӨ–иҰіж„ҸеҢ гҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҒӘгҒ©е°ҶжқҘгӮ’еҳұжңӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢ34жӯігҒ®иӢҘгҒ•гҒ§йҖқеҺ»гҒ—гҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒҜгҖҒж—§еӨ§жһ—зө„жң¬зӨҫеұӢгҒ®еӨ–иЈ…ж„ҸеҢ пјҲвҖҰвҖҰ

й°ӯ(гҒІгӮҢ)

еәғзёҒ(гҒІгӮҚгҒҲгӮ“)
еҸӨгҒҸгҒҜгҖҢеҜқж®ҝйҖ гҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҢжҜҚеұӢгҖҚгҒЁгҖҢеәҮгҖҚгҒ®еӨ–еҒҙгҒ«гҖҢеӯ«еәҮгҖҚгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖҢеәғеәҮпјҲгҒІгӮҚгҒігҒ•гҒ—пјүгҖҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮ
гҖҢжҜҚеұӢгҖҚгҒЁгҖҢеәҮгҖҚгҒҜгҖҒеҗҢдёҖгҒ®гғ¬гғҙгӮ§гғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҖҢеәғеәҮгҖҚгҒҜгҖҢеҲҮзӣ®й•·жҠјгҖҚдёҖж®өеҲҶгҒ гҒ‘дҪҺгҒҸгҖҒиә«еҲҶгҒ®дҪҺгҒ„иҖ…гҒҢвҖҰвҖҰ

еәғе°ҸиҲһ(гҒІгӮҚгҒ“гҒҫгҒ„)
ж•°еҜ„еұӢеӨ§е·ҘпјҲдҪҸе®…зі»пјүгҒҢгҖҢеәғе°ҸиҲһгҖҚеҸҠгҒігҖҢж·ҖгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶йғЁжқҗгӮ’гҖҒе®®еӨ§е·ҘпјҲзӨҫеҜәе»әзҜүзі»пјүгҒҜгҖҢиҢ…иІ гҖҚеҸҠгҒігҖҢиЈҸз”ІпјҲгҒҶгӮүгҒ”гҒҶпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гӮӮгҒ®гҒЁзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮҲгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
е°ҡгҖҒгҖҢе°ҸиҲһпјҲжңЁиҲһпјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒйҖҡгҒ—гҒ§з”ЁгҒ„гӮӢзҙ°й•·гҒ„и§’жңЁгҒ®гҒ“гҒЁвҖҰвҖҰ

гғ”гғӯгғҶгӮЈ(гҒҙгӮҚгҒҰгҒғ)
д»Ҹ/pilotisгҖӮеҺҹзҫ©гҒҜгҖҒе»әзү©гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢжқӯгҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮе»әзү©гӮ’ж”ҜжҢҒгҒҷгӮӢзӢ¬з«ӢжҹұгҒҢдёҰгҒ¶еҗ№ж”ҫгҒЎгҒ®з©әй–“гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ
1926е№ҙгҖҒгғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§ гҒЁгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гӮёгғЈгғігғҢгғ¬гҒҢжҸҗе”ұгҒ—гҒҹиҝ‘д»Је»әзҜүгҒ®дә”еҺҹеүҮгҖҢгғ”гғӯгғҶгӮЈгғ»еұӢдёҠеәӯең’вҖҰвҖҰ

жӘңзҡ®и‘ә(гҒІгӮҸгҒ гҒ¶гҒҚ)
жӘңгҒ®жЁ№зҡ®гӮ’еұӢж №и‘әжқҗгҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮжӯўж°ҙжҖ§гҒҢгӮҲгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§еұӢж №еӢҫй…ҚгҒҜжҜ”ијғзҡ„з·©гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒеұӢж №е…ЁдҪ“гҒ®е§ҝгҒҢи»Ҫеҝ«гҒ§е„ӘзҫҺгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжқ®и‘әгӮ„жқүзҡ®и‘әзӯүгҒ«жҜ”гҒ—гҒҰиҖҗд№…жҖ§гӮ„йҳІзҒ«жҖ§гӮӮгӮҲгҒ„гҖӮе®®ж®ҝгӮ„зӨҫеҜәе»әзҜүгҒӘгҒ©гҒ«з”ЁдҫӢгҒҢеӨҡгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гғ•гӮЎгӮөгғјгғү(гҒөгҒҒгҒ•гғјгҒ©)
д»Ҹ/faГ§adeгҖӮе»әзү©жӯЈйқўгҖӮйҖҡеёёгҒҜгҖҒжӯЈйқўзҺ„й–ўеҒҙгҒ®з«ӢйқўгӮ’гҒ„гҒҶгҒҢгҖҒеӨ–иҰігҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘйқўгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°еҒҙйқўеҸҲгҒҜиғҢйқўгӮ’гӮӮгғ•гӮЎгӮөгғјгғүгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮеӣ гҒҝгҒ«ж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүгҒ®гғ•гӮЎгӮөгғјгғүгҒҜгҖҒж•·жқЎд»¶дёҠгҒ®еҲ¶зҙ„гҒ®гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠиҘҝйқўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҗ№жҠң(гҒөгҒҚгҒ¬гҒҚ)
еҗ№жҠңгҒҜдёҠдёӢйҡҺгҒ®еәҠгҒ®дёҖйғЁгҒӘгҒ„гҒ—е…ЁйғЁгҒҢжҠңгҒ‘гҒҰгҖҒдёҠдёӢйҡҺгҒҢз©әй–“зҡ„гҒ«дёҖдҪ“гҒЁгҒӘгӮӢзҠ¶ж…ӢгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеҗ№ж”ҫгҒҜгҖҒе»әзү©гҒ®еӨ–е‘ЁйғЁгҒ®жҹұй–“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе°ҸеЈҒд»ҘеӨ–гҒ«е»әе…·гҒӘгҒ©гҒ®жҹұй–“иЈ…зҪ®гҒҢе»әгҒҰиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ

еҗ№еҜ„еһӮжңЁ(гҒөгҒҚгӮҲгҒӣгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

иҰҶијӘ(гҒөгҒҸгӮҠгӮ“)
гҖҖ

иӨҮе»Ҡ(гҒөгҒҸгӮҚгҒҶ)
гҖҖ

и—Өдә•еҺҡдәҢ(гҒөгҒҳгҒ„гҒ“гҒҶгҒҳгҖҒ1888пҪһ1938)
ж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүз’°еўғе·ҘеӯҰгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮдҪҸе®…е»әзҜүгҒ®з§ҖдҪңгҒҢдә¬йҳӘзҘһй–“гҒ«ж®ӢгӮӢгҖӮеәғеі¶зңҢзҰҸеұұеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮз«№дёӯе·ҘеӢҷеә—еӢӨеӢҷгӮ’зөҢгҒҰдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжқ‘еұұйӮёпјҲйҰҷйӣӘзҫҺиЎ“йӨЁеҶ…пјүгҖҒе–ңеӨҡжәҗйҖёйӮёгҖҒиҒҙз«№еұ…вҖҰвҖҰ

иҘ–йҡңеӯҗ(гҒөгҒҷгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҒҳгҖҒгҒөгҒҷгҒҫ)
иҘ–гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮе”җзҙҷйҡңеӯҗгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮжңЁгҒ§йӘЁгӮ’зө„гҒҝдёЎйқўгҒӢгӮүзҙҷгҒҫгҒҹгҒҜеёғгӮ’ејөгӮҠгҖҒзёҒгҒЁеј•жүӢгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹжҲёгҖӮиҘ–зёҒгҒ«гҒҜдёҠдёӢзёҒгғ»з«ӘзёҒгғ»е®ҡиҰҸзёҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеқҠдё»иҘ–гҒҜгҒ“гҒ®иҘ–зёҒгҒ®гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮиҚүеәөж•°еҜ„еұӢпјҲиҢ¶е®ӨпјүгҒ®еӨӘйј“ејөгӮҠиҘ–гҒҢгҒқгҒ®дҫӢгҖӮ

гғӢгҒӨж–—(гҒөгҒҹгҒӨгҒ©)
гғӢгҒӨж–—

дәҢи»’(гҒөгҒҹгҒ®гҒҚ)
дёҠдёӢдәҢж®өгҒ§еҮәгҒ®з•°гҒӘгӮӢеһӮжңЁгҒӢгӮүгҒӘгӮӢи»’гҖӮзӨҫеҜәе»әзҜүгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒдёҠж®өгӮ’йЈӣжӘҗеһӮжңЁгҖҒдёӢж®өгӮ’ең°еһӮжңЁгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮдәҢи»’гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒең°еһӮжңЁгҒ®гҒҝгҒӢгӮүгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’дёҖи»’гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйЈӣжӘҗеһӮжңЁгҒҢдәҢж®өгҒЁгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜдёүи»’гҒЁгҒ„гҒҶгҒҢгҖҒдҫӢгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮвҖҰвҖҰ

зӯҶиҝ”(гҒөгҒ§гҒҢгҒҲгҒ—)
гҖҖ

иҲҹеә•еӨ©дә•(гҒөгҒӘгҒһгҒ“гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)
гҖҖ

иҲҹиӮҳжңЁ(гҒөгҒӘгҒІгҒҳгҒҚ)
гҖҢиҲҹиӮҳжңЁгҖҚгҒҜгҖҒд»Ҹе ӮгӮҲгӮҠгӮӮзҘһзӨҫгғ»е®®ж®ҝгғ»ж–№дёҲгғ»дҪҸе®…гҒӘгҒ©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮжқұзҰҸеҜәеЎ”й ӯж–№дёҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢйҫҚеҗҹеәөгҖҚпјҲзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬жңҖеҸӨгҒ®ж–№дёҲе»әзҜүпјүгҒ«гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒй–ӢеҸЈйғЁгӮ’еәғгҒ’гҒҹеҢ—еҒҙгҒ®е®ӨгҒ®гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҖҢж·»гҒҲжўҒгҖҚгҒ®вҖҰвҖҰ

иёҸиҫјеәҠ(гҒөгҒҝгҒ“гҒҝгҒ©гҒ“)
еәҠгҒ®й–“гҒ®дёҖеҪўејҸгҖӮеәҠжЎҶгҒӘгҒҸең°жқҝгҒ®дёҠз«ҜгӮ’з•ійқўгҒЁеҗҢгҒҳй«ҳгҒ•гҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’иёҸиҫјеәҠгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮз°Ўжҳ“гҒӘеәҠеҪўејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒи№ҙиҫјеәҠгҒҜең°жқҝгӮ’гӮ„гӮ„й«ҳгҒҸгҒ—гҒҰз•ійқўгҒЁгҒ®й–“гҒ«и№ҙиҫјжқҝпјҲеӨҡгҒҸгҒҜйҠҳжңЁпјүгӮ„з«№гҒӘгҒ©гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

гғ•гғ©гӮӨгғігӮ°гғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№(гҒөгӮүгҒ„гӮ“гҒҗгҒ°гҒЈгҒЁгӮҢгҒҷ)
flying buttressгҖӮйЈӣжҺ§гҒҲгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®ж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиә«е»ҠйғЁгӮ’иҰҶгҒҶ гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ гҒ®еҒҙең§гӮ’еӨ–еҒҙгҒ® гғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№ гҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҒҙе»ҠгҒ®еұӢж №гҒ®дёҠгҒ«жһ¶гҒ‘жёЎгҒ•гӮҢгҒҹзҹійҖ гҒ®гӮўгғјгғҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

гғ•гғ©гғігӮҜгғ»гғӯгӮӨгғүгғ»гғ©гӮӨгғҲ(гҒөгӮүгӮ“гҒҸгғ»гӮҚгҒ„гҒ©гғ»гӮүгҒ„гҒ© Frank Lloyd Wright 1867пҪһ1959)
зұіеӣҪгҒ®е»әзҜү家гҖӮгҖҢиҝ‘д»Је»әзҜүдёүеӨ§е·ЁеҢ гҖҚгҒ®дёҖдәәгҖӮL.H.гӮөгғӘгғҙгӮЎгғігҒ®гӮӮгҒЁгҒ§еғҚгҒ„гҒҹеҫҢзӢ¬з«ӢгҖӮеҲқжңҹгҒ®дҪҸе®…е»әзҜүгҒҜгҖҒж—ўгҒ«зӢ¬иҮӘгҒ®з©әй–“ж§ӢжҲҗгӮ’зӨәгҒ—гҖҢеӨ§иҚүеҺҹж§ҳејҸгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮгӮ·гӮ«гӮҙгҒ®гғӯгғ“гғјйӮёгҒҜгҒқгҒ®й ӮзӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжқұдә¬гҒ®ж—§еёқеӣҪгғӣгғҶвҖҰвҖҰ

гғ•гғӘгғјгӮә(гҒөгӮҠгғјгҒҡ)
friezeгҖӮгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў гҒ® гӮігғјгғӢгӮ№ гҒЁ гӮўгғјгӮӯгғҲгғ¬гғјгғ– гҒ®й–“гҒ®еёҜзҠ¶гҒ®йқўгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

гғ•гғӘгғјгӮәгӮҪгғ¬гӮӨгғҰ(гҒөгӮҠгғјгҒҡгҒқгӮҢгҒ„гӮҶ)
brise-soleilгҖӮе…ғжқҘгҒҜгҖҒгҖҢж—ҘйҷӨгҒ‘гҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮд»Ҡж—ҘгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙз…§иӘҝж•ҙгҒ®жүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгӮ’е»әзҜүеҢ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮгғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§ гҒҢз©ҚжҘөзҡ„гҒ«дҪңе“ҒгҒ«з”ЁгҒ„гҒҹгҖӮгҖҢгғ«гғјгғҗгғјгҖҚгҒҜгҒқгҒ®йғЁжқҗеҗҚз§°гҖӮ

гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°(гҒөгӮӢгғјгҒҰгҒғгӮ“гҒҗ)
flutingгҖӮжәқеҪ«гӮҠгҖӮеҸӨд»Је»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҹұиә«гҒ«зёҰж–№еҗ‘гҒ«еҲ»гҒҫгӮҢгҒҹжәқгҖӮгғүгғӘгӮ№ејҸгӮӘгғјгғҖгғј гҒ§гҒҜгҖҒжәқгҒЁжәқгҒ®пј©гҒ гҒҢйӢӯи§’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгӮӨгӮӘгғӢгӮўејҸгӮӘгғјгғҖгғј гҒ§гҒҜгҖҒжәқгҒ®й–“гҒ«е№ізёҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮжҹұгҒ®еһӮвҖҰвҖҰ

гғ–гғ«гғјгғҺгғ»гӮҝгӮҰгғҲ(гҒ¶гӮӢгғјгҒ®гғ»гҒҹгҒҶгҒЁ Bruno Julius Florian Taut 1880пҪһ1938)
зӢ¬еӣҪеҮәиә«гҖӮиЎЁзҸҫдё»зҫ©е»әзҜүгҒ§еҗҚгӮ’йҰігҒӣгӮӢгҖӮгғҠгғҒгӮ№гҒ®иҝ«е®ігҒ«гӮҲгӮҠж—Ҙжң¬гҒ«дәЎе‘ҪгҖӮж—Ҙжң¬е»әзҜүгҒ®дјқзөұзҫҺгӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҖҢжЎӮйӣўе®®гҖҚгҖҢеҗҲжҺҢйҖ гӮҠгҖҚгҒӘгҒ©гӮ’дё–з•ҢгҒ«зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮпјҲгҒқгҒ®жЎҲеҶ…дәәгҒҜгҖҒйҖ“дҝЎзңҒгҒ®гҖҖеҗүз”°йү„йғҺгҖҖгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢпјүе®ҹжҘӯ家ж—Ҙеҗ‘вҖҰвҖҰ

еҗүеЎҡжӯЈжІ»(гҒөгӮӢгҒҘгҒӢгҒҫгҒ•гҒҜгӮӢгҖҒ1892пҪһ1976)
йҳӘзҘһй–“гғўгғҖгғӢгӮәгғ гӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢе»әзҜү家гҒ®дёҖдәәгҖӮе…өеә«зңҢиҘҝе®®еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе®®еҶ…зңҒеҶ…еҢ еҜ®еӢӨеӢҷгҖӮеҫҢгҒ«иҘҝе®®гҒ§е»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮзҘһжҲёй«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫзҘһжҲёеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁпјүи¬ӣеё«е°ұд»»гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжӯЈеҸёвҖҰвҖҰ

еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ(гҒ¶гӮ“гӮҠгҒҜгҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸгҒӢгҒ„)
еӨ§жӯЈ9е№ҙпјҲ1920пјүгҒ«жқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹпј–дәәгҒҢзөҗжҲҗгҒ—гҒҹгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҖҒгҒқгҒ®жҙ»еӢ•гҒҜж—Ҙжң¬гҒ§еҲқгӮҒгҒҰгҒ®иҝ‘д»Је»әзҜүйҒӢеӢ•гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҪјгӮүгҒҜиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®зҗҶжғігҒ®е»әзҜүеғҸгӮ’гҖҒзҷҫиІЁеә—гҒӘгҒ©гҒ§гҒ®еұ•иҰ§дјҡгҒЁеҮәзүҲзү©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдёҖиҲ¬е…¬вҖҰвҖҰ

гғҷгӮӨгғ»гӮҰгӮЈгғігғүгӮҰ(гҒ№гҒ„гғ»гҒҶгҒғгӮ“гҒ©гҒҶ)
bay windowгҖӮејөеҮәгҒ—зӘ“гҖӮй•·ж–№еҪўгӮ„еӨҡи§’еҪўгӮ’гҒӘгҒ—гҒҰеЈҒйқўгҒӢгӮүзӘҒеҮәгҒ—гҒҰгҖҒж•°йҡҺйҖҡгҒ—гҒ§иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮеј“еҪўгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҢгғңгӮҰгғ»гӮҰгӮЈгғігғүгӮҰгҖҚдёҠйҡҺгҒ®гҒҝгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҢгӮӘгғјгғӘгӮЁгғ«гғ»гӮҰгӮЈгғігғүгӮҰгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

е№іиЎҢеһӮжңЁ(гҒёгҒ„гҒ“гҒҶгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

е№Ји»ё(гҒёгҒ„гҒҳгҒҸ)
гҖҢжқҝжүүгҖҚгҒЁгҖҢжһ пјҲйЎҚзёҒпјүгҖҚгҒ®зҙҚгҒҫгӮҠгҒ«гҒҜгҖҒе®ҡгҒҫгҒЈгҒҹеҪўејҸгҒҢгҒӮгӮӢиЁігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮеҸӨејҸгҒҜгҖҒгҖҢе”җжҲёйқўгҖҚгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгҖҢе№Ји»ёгҖҚгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒжі•йҡҶеҜәйҮ‘е ӮгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҖҢиҫәйҷ„пјҲгҒёгӮ“гҒӨгҒ‘пјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҹ©еҪўгҒ®гҖҢдә”е№іпјҲгҒ”гҒІгӮүпјүгҖҚгҒ®жқҗгӮ’гҖҢвҖҰвҖҰ

е№іең°дјҪи—Қ(гҒёгҒ„гҒЎгҒҢгӮүгӮ“)
еұұең°дјҪи—ҚпјҲеҜҶж•ҷзӯүпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе‘јз§°гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®еҸӨд»ЈеҜәйҷўгӮ„гҒқгҒ®еҫҢгҒ®йҺҢеҖүж–°д»Ҹж•ҷпјҲзҰ…е®—зӯүпјүд»ҘйҷҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҒқгҒ®йЎһгҒ«еұһгҒҷгӮӢгҖӮдё»гҒЁгҒ—гҒҰе№іеқҰең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰи»ёз·ҡдёҠгҒ«дё»иҰҒгҒӘе»әзҜүзү©гҒҢеҜҫз§°зҡ„гҒ«ж•ҙ然гҒЁгҒ—гҒҹй…ҚзҪ®гӮ’иҰӢгҒӣгӮӢдјҪи—ҚеҪўж…ӢгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

е№Јж®ҝ(гҒёгҒ„гҒ§гӮ“)
гҖҖ

гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ(гҒәгҒ§гҒғгӮҒгӮ“гҒЁ)
pedimentгҖӮеҲҮеҰ»еұӢж №гҒ®дёүи§’з ҙйўЁгҖҒж°ҙе№ігҒ® гӮігғјгғӢгӮ№ гҒЁеӮҫж–ңгҒ—гҒҹгғ¬гғјгӮӯгғігӮ°гӮігғјгғӢгӮ№гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӣІгҒҫгӮҢгҒҹдёүи§’еҪўгҒ®еҲҮеҰ»еЈҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҸӨе…ёдё»зҫ©д»ҘеӨ–гҒ§гҒҜгҖҢгӮІгӮӨгғ–гғ«гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гғҡгғҮгӮ№гӮҝгғ«(гҒәгҒ§гҒҷгҒҹгӮӢ)
pedestalгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҹұгӮ’ијүгҒӣгӮӢеҸ°гҖӮеҸ°еә§гҖӮжҹұзӨҺгҖӮ

гғҡгғігғҖгғігғҲ(гҒәгӮ“гҒ гӮ“гҒЁ)
еһӮйЈҫгӮҠгҖӮеӨ©дә•гӮ„еұӢж №гҒӢгӮүдёӢж–№гҒ«зӘҒеҮәгҒҷгӮӢгҒӢеһӮгӮҢдёӢгҒҢгӮӢзҙ°й•·гҒ„йЈҫгӮҠгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮзҸҫд»ЈгҒҜгҖҒиЈ…иә«е…·гӮ„еҗҠгӮҠдёӢгҒ’ејҸз…§жҳҺеҷЁе…·гӮӮгҒқгҒҶе‘јгҒ¶гҒҢгҖҒиӘһжәҗгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®pendereпјҲеһӮгӮҢдёӢгҒҢгӮӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҳгғігғӘгғјгғ»гӮӯгғ©гғ гғ»гғһгғјгғ•гӮЈгғј(гҒёгӮ“гӮҠгғјгғ»гҒҚгӮүгӮҖгғ»гҒҫгғјгҒөгҒғгғј Henry Killam Murphy 1877пҪһ1954)
зұіеӣҪгҒ®е»әзҜү家гҖӮзұіеӣҪеҢ—жқұйғЁгҖҒдёӯеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж•°еӨҡгҒҸгҒ®дҪҸе®…гҖҒеӯҰж Ўж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮзұіеӣҪгӮігғҚгғҒгӮ«гғғгғҲз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгӮӨгӮ§гғјгғ«еӨ§еӯҰеҚ’гҖӮгғӘгғҒгғЈгғјгғүгғ»гғҳгғігғӘгғјгғ»гғҖгғҠгҒЁе…ұеҗҢгҒ§иЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒз«Ӣж•ҷеӨ§вҖҰвҖҰ

гғқгғјгғҒ(гҒҪгғјгҒЎ)
porchгҖӮдҪҝз”ЁзҜ„еӣІгҒ®еәғгҒ„иӘһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…ғжқҘгҒҜгҖҒй–Җгғ»е…ҘгӮҠеҸЈгғ»йҖҡи·ҜгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ
е»әзү©гҒ®жң¬дҪ“гҒЁгҒҜеҲҘгҒ®гҖҒйӣЁгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢеәҮгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒеЈҒдҪ“гҒӢгӮүзӘҒеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе»әзү©гҒ®е…ҘгӮҠеҸЈйғЁгӮ’жҢҮгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгӮігғӯгғҚгғјгғүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҹұгҒ«ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҹвҖҰвҖҰ

ж–№еҪўйҖ (гҒ»гҒҶгҒҺгӮҮгҒҶгҒҘгҒҸгӮҠ)
ж–№еҪўйҖ гҒЁгҒҜгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢеұӢж №еҪўзҠ¶гӮ’иЎЁгҒҷиЁҖи‘үгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе№ійқўгҒҢжӯЈж–№еҪўгҒ®е ҙеҗҲеӣӣйқўгҒЁгӮӮеҗҢгҒҳеҪўзҠ¶гҒ§гҖҒй ӮзӮ№гҒҢдёҖгҒӨгҒ«йӣҶгҒҫгӮӢеұӢж №еҪўзҠ¶гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеӣӣжіЁйҖ гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮе№ійқўеҪўзҠ¶гҒҢе…«и§’еҪўгҒ®е ҙеҗҲгҒҜе…«жіЁйҖ гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ

ж–№дёҲ(гҒ»гҒҶгҒҳгӮҮгҒҶ)
зҰ…е®—еҜәйҷўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰй•·иҖҒгӮ„дҪҸжҢҒгҒ®з§Ғе®ӨгҒҫгҒҹгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҗ«гӮҖдҪҸеұӢгҖӮж–№дёҲгҒҜдҪҸеұ…гҖҒжҺҘе®ўгҖҒгҒҠгӮҲгҒідҝ®иЎҢзӯүгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдјҪи—ҚгҒ®гҒҶгҒЎжі•е ӮиғҢеҫҢгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒЁгҖҒеЎ”й ӯеҶ…гҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжқұзҰҸеҜәгҒ®з«ңеҗҹжЎҲгҖҒеӨ§еҫіеҜәгҒ®еӨ§вҖҰвҖҰ

е®қзӣёиҸҜж–Үж§ҳ(гҒ»гҒҶгҒқгҒҶгҒ’гӮӮгӮ“гӮҲгҒҶ)
е®қзӣёиҸҜгҒЁгҒҜиҸҜйә—гҒӘиҠұгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸгҖӮе”җиҚүжЁЎж§ҳгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒдёӯеӣҪгҒ®е”җжҷӮд»ЈгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜеҘҲиүҜжҷӮд»Јгғ»е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘжЁЎж§ҳгҖӮжҸҸгҒӢгӮҢгҒҹжӨҚзү©гҒҜжһ¶з©әгҒ®жӨҚзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжүүгҒ®е…«еҸҢйҮ‘зү©гҒӘгҒ©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ж–№з«Ӣ(гҒ»гҒҶгҒ гҒҰ)
гҖҖ
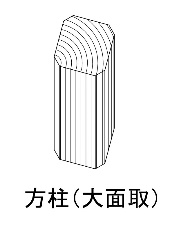
ж–№жҹұ(гҒ»гҒҶгҒЎгӮ…гҒҶ)
жӯЈж–№еҪўгҒ®жҹұгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеҸӨе»әзҜүгҒ§гӮҲгҒҸеҮәгҒҰгҒҸгӮӢж–№пјҲгҒ»гҒҶпјүгҒҜжӯЈж–№еҪўгӮ’иЎЁгҒҷгҖӮж–№жҹұгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘжӯЈж–№еҪўгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗ„и§’гҒҜйқўеҸ–гӮҠгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйқўеҸ–гӮҠгҒҜж•°гҖ…гҒ®зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨ§йқўеҸ–гӮҠгҖҒе”җжҲёйқўгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

ж–№ж–—(гҒ»гҒҶгҒЁ)
гҖҖ

е®қеЎ”(гҒ»гҒҶгҒЁгҒҶ)
гҖҖ

жһ¶жңЁ(гҒ»гҒ“гҒҺ)
й«ҳ欄гҒ®дёҖз•ӘжңҖдёҠйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’жһ¶жңЁгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮпјҲй«ҳ欄гҒЁгҒҜгҖҒзёҒгҒ«е·ЎгӮүгҒӣгҒҹжүӢж‘әзҠ¶гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶпјүжһ¶жңЁгҒ®дёӢгҒ«гҒҜе№іжЎҒгӮ’йҖҡгҒ—гҖҒдёӢйғЁгҒҜең°иҰҶгӮ’йҖҷгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮ

жҙһеәҠ(гҒ»гӮүгҒ©гҒ“)
гҖҖ

е ҖеҸЈжҚЁе·ұ(гҒ»гӮҠгҒҗгҒЎгҒҷгҒҰгҒҝгҖҒ1895пҪһ1904)
жқұеӨ§еҗҢзӘ“з”ҹгҒЁзөҗжҲҗгҒ—гҒҹ еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ®ж§ӢжҲҗе“ЎгҒ®дёҖдәәгҖӮгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ®иЁӯиЁҲгҒ®еӮҚгӮүгҖҒж•°еҜ„еұӢе»әзҜүгҒ®дёӯгҒ«зҫҺгӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҖҒдјқзөұж–ҮеҢ–гҒЁгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ®зҗҶеҝөгҒЁгҒ®зөұеҗҲгӮ’еӣігӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүгҒЁеәӯең’гҒ®й–ўдҝӮгӮ’гҖҢз©әй–“ж§ӢжҲҗгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲвҖҰвҖҰ

жң¬иҹҮиӮЎ(гҒ»гӮ“гҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)
гҖҖ

жң¬з“Ұи‘ә(гҒ»гӮ“гҒҢгӮҸгӮүгҒ¶гҒҚ)
еҜәйҷўгҒ«еӨҡгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢз“ҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе№із“ҰгҒЁдёёз“ҰгӮ’дәӨдә’гҒ«гҒ«з”ЁгҒ„гҒҰз“ҰгӮ’и‘әгҒҸгҖӮдёёз“ҰгҒ®и»’е…Ҳе…Ҳз«ҜгҒ«гҒҜе·ҙз“ҰгҒ§д»•иҲһгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®з“ҰгҒҜеҘҲиүҜзңҢгҒ®е…ғиҲҲеҜәгҒ«гҒӮгӮӢиЎҢеҹәи‘әгҒҚгҒ®з“ҰеұӢж №гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЎҢеҹәи‘әгҒҚгӮӮжң¬з“Ұи‘әгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёёз“ҰгҒҢдёҠвҖҰвҖҰ

жң¬ж®ҝ(гҒ»гӮ“гҒ§гӮ“)
е…ғжқҘгҒҜгҖҒзҘӯзӨјгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҖҒдёҖе®ҡжңҹй–“гҒ«йҷҗгӮҠгҖҒзҘһеҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰд»®гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹж–ҪиЁӯгҒ«зҘһйңҠгҒ®йҷҚдёӢгӮ’д»°гҒҺгҖҒзҘӯзӨјгҒ®еҫҢгҒ«еҸ–гӮҠеЈҠгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢеӨ§еҳ—зҘӯгҖҚгҒ®гҖҢжӮ еҹәпјҲгӮҶгҒҚпјүгҖҚгҖҢдё»еҹәпјҲгҒҷгҒҚпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢйҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢжң¬ж®ҝвҖҰвҖҰ

жң¬е Ӯ(гҒ»гӮ“гҒ©гҒҶ)
гҖҖ

жң¬й–“д№ҷеҪҰ(гҒ»гӮ“гҒҫгҒҠгҒЁгҒІгҒ“гҖҒ1892пҪһ1937)
еӨ§жӯЈжңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢејҸгҒ«еӨ§йҳӘгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе…өеә«зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬й«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫжқұдә¬е·ҘжҘӯеӨ§еӯҰпјүе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӨ§йҳӘеёӮз«ӢйғҪеі¶е·ҘжҘӯй«ҳж Ўе»әзҜү科еҳұиЁ—ж•ҷе“ЎгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§иҠқиҳӯиҲҺ家ж”ҝеӯҰең’пјҲзҸҫиҠқе·қгғ“гғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гҖҒж„ҸеҢ жӢ…еҪ“гҖҒвҖҰвҖҰ

жң¬жЈҹйҖ (гҒ»гӮ“гӮҖгҒӯгҒҘгҒҸгӮҠ)
жң¬жЈҹйҖ гҒҜгҖҒй•·йҮҺзңҢгҒ®дёӯдҝЎең°ж–№гҒӢгӮүеҚ—дҝЎең°ж–№гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰеҲҶеёғгҒҷгӮӢ民家гҒ®еҪўејҸгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒеә„еұӢгӮ„жң¬йҷЈгҒӘгҒ©гҒ®еҪ№дәәеұӨгҒ®дҪҸеұӢеҪўејҸгҒ§еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮеҲҮеҰ»йҖ гӮҠжқҝи‘әгҒҚгҒ§еҰ»е…ҘгӮҠгҖӮз·©гҒ„еұӢж №еӢҫй…ҚгӮ„йӣҖгҒҠгҒ©гҒ—гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжЈҹйЈҫвҖҰвҖҰ
гҒҫгҖңгӮӮ

иҲһиүҜжҲё(гҒҫгҒ„гӮүгҒ©)
дёӯдё–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҲқгӮҒгҒҰзҸҫгӮҢгҒҹжқҝжҲёгҒ®еҪўејҸгҖӮиҲһиүҜжҲёгҒҜжқҝгҒ®дёҠгҒ«иҲһиүҜеӯҗгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҙ°гҒ„жЎҹгҒЁжЁӘж–№еҗ‘гҒ«дёҖе®ҡгҒ®й–“йҡ”гҒ§еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҲһиүҜеӯҗгҒ®й–“йҡ”гӮ„дёҰгҒ№ж–№гҒ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҗ№еҜ„иҲһиүҜжҲёгҖҒз№ҒиҲһиүҜжҲёгҒӘгҒ©гғҗгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮӢгҖӮ

еүҚе·қеңӢз”·(гҒҫгҒҲгҒӢгӮҸгҒҸгҒ«гҒҠгҖҒ1905пҪһ1986)
гғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§гҖҒгӮўгғігғҲгғӢгғігғ»гғ¬гғјгғўгғігғү гҒ«её«дәӢгҖӮгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ®ж——жүӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®ж—Ҙжң¬е»әзҜүз•ҢгӮ’гғӘгғјгғүгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮж–°жҪҹзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеІёз”°ж—ҘеҮәеҲҖгҖҖй–ҖдёӢз”ҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ«зңҹжӯЈгҒ®иҝ‘д»Је»әзҜүгӮ’вҖҰвҖҰ

еүҚз”°еҒҘдәҢйғҺ(гҒҫгҒҲгҒ гҒ‘гӮ“гҒҳгӮҚгҒҶгҖҒ1892пҪһ1975)
жҲҰеүҚгҒӢгӮүжҲҰеҫҢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒЁгҒҜдёҖз·ҡгӮ’з”»гҒ—гҒҹдҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгҖҢгӮігғігғҡгҒ®еүҚеҒҘгҖҚгҒ®з•°еҗҚгӮ’гҒЁгӮҠгҖҒеёқеӣҪиӯ°дәӢе Ӯгғ»еӨ§йҳӘеёӮзҫҺиЎ“йӨЁгғ»зҘһжҲёеёӮе…¬дјҡе Ӯгғ»ж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰеӨ§йҡҲиЁҳеҝөе Ӯгғ»дә¬йғҪеёӮзҫҺиЎ“йӨЁгҒЁеӨҡгҒҸгҒ®иЁӯиЁҲгӮігғігғҡгҒ§дёҖзӯүвҖҰвҖҰ

еүҚеҢ…(гҒҫгҒҲгҒҘгҒӨгҒҝ)
гҖҖгҖҢе…ҘжҜҚеұӢз ҙйўЁгҖҚгҖҢгӮ„гҖҢеҚғйіҘз ҙйўЁгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®гҖҢзӢҗж јеӯҗпјҲгҒҚгҒӨгҒӯгҒ”гҒҶгҒ—пјүгҖҚпјҲжңЁйҖЈж јеӯҗ/гҒҚгҒҘгӮҢгҒ”гҒҶгҒ—пјүгҒ®дёӢз«ҜгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎеұӢж №гҒ®зӣҙдёҠгҒ«й…ҚгҒ•гӮҢгӮӢж°ҙе№ігҒ®жЁӘжңЁгӮ’гҖҢеүҚеҢ…гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҸӨејҸгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢеүҚеҢ…гҖҚгӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҢзӢҗж јеӯҗгҖҚгҒ®гҖҢзёҰвҖҰвҖҰ

е·»ж–—(гҒҫгҒҚгҒЁ)
гҖҖ

е·»йј»ж®өжқҝ(гҒҫгҒҚгҒ°гҒӘгҒ гӮ“гҒ„гҒҹ)
иҘҝжҙӢе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҡҺж®өгҒ®дёҖж®өзӣ®гӮ’жӣІз·ҡеҪўгҒ«еәғгӮҒгҒ«гҒЁгӮҠгҖҒзүҮеҒҙжҲ–гҒ„гҒҜдёЎеҒҙгҒ®з«ҜйғЁгӮ’еҶҶеҪўгҒ«жӢЎејөгҒ—гҒҰгҖҒиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘиҰӘжҹұгӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸеҢ дёҠгҒ®е·ҘеӨ«гӮ’ж–ҪгҒҷгҖӮгҒқгҒ®йғЁдҪҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

жҘЈ(гҒҫгҒҗгҒ•)
гҖҖ

жһ•жҚҢгҒҚ(гҒҫгҒҸгӮүгҒ•гҒ°гҒҚ)
й•·жҠјгҒ§еәҠжҹұгӮ’дёүж–№гҒҫгӮҸгҒҷдәӢгӮ’жһ•жҚҢгҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеәҠжҹұгҒ®иЈҸйқўгҒҫгҒ§й•·жҠјгӮ’еӣһгҒҷгҒЁгҖҒжһ•жҚҢгҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒҢгҖҒиЈҸйқўгҒҫгҒ§еӣһгҒ•гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜзүҮжҚҢгҒҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮжһ•жҢҹгҒҝгҖҒжһ•иўҙгҖҒе·»иЈҸжҚҢгҒҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ

еӯ«еәҮ(гҒҫгҒ”гҒігҒ•гҒ—)
гҖҖ
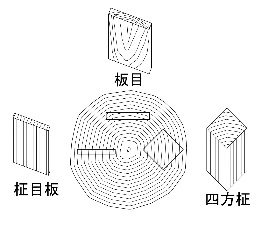
жҹҫзӣ®(гҒҫгҒ•гӮҒ)
жҹҫзӣ®гҒЁгҒҜжңЁжқҗгҒ®з№Ҡз¶ӯгҒҢж–№еҗ‘гҒ«гҒқгӮҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжңЁзӣ®гҒ®йқўгӮ’жҹҫзӣ®гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжңЁжқҗгҒ®дёӯеҝғгҒӢгӮүе№ҙијӘгҒ«зӣҙиЎҢж–№еҗ‘гҒ«жқҝгӮ’гҒЁгӮӢгҒЁжҹҫзӣ®гҒ®жқҝгҒҢеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮжҹұгҒӘгҒ©гҒ§еӣӣйқўгҒҢжҹҫзӣ®гҒ®жңЁзӣ®гӮ’еӣӣж–№жҹҫгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҹҫзӣ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„жңЁзӣ®гӮ’жқҝзӣ®гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

еў—з”°еҸӢд№ҹ(гҒҫгҒҷгҒ гҒЁгӮӮгӮ„гҖҒ1914пҪһ1981)
зӢ¬еүөзҡ„гҒӘе»әзҜүз©әй–“и«–гӮ’зўәз«ӢеҫҢеӨўзӘ“з–ҺзҹігҒ®зҰ…зҡ„гҒӘе»әзҜүз©әй–“и«–з ”з©¶гҒӢгӮүгҖҒжңүеҪўгҒ®дҪңе“ҒгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰйҒ“е…ғгҒ®е§ӢзҘ–зҺӢзҡ„дё–з•ҢгҒ«жҳҮиҸҜгҒ—гҖҒгғҸгӮӨгғҮгғғгӮ«гғјгҒ®е»әзҜүеӯҳеңЁи«–гҒёгҒЁеұ•й–ӢгӮ’иҰӢгҒӣгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮе…өеә«зңҢеҚ—гҒӮгӮҸгҒҳеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰвҖҰвҖҰ

гғһгғғгӮ№(гҒҫгҒЈгҒҷ)
д»Ҹ/masseгҖӮгҖҢеЎҠгҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮзөөз”»гғ»еҪ«еҲ»гғ»е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®дёӯгҒ§дёҖгҒӨгҒ®гҒҫгҒЁгҒҫгӮҠпјҡгҒЁгҒ—гҒҰжҠҠжҸЎгҒ•гӮҢгӮӢйғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз©әй–“гҒ®дёӯгҒ§дёҖеЎҠгӮҠгҒЁжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢз·ҸдҪ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

жқҫе®ӨйҮҚе…ү(гҒҫгҒӨгӮҖгӮҚгҒ—гҒ’гҒҝгҒӨгҖҒ1873пҪһ1937)
дә¬йғҪгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгғҚгӮӘгғ«гғҚгғғгӮөгғігӮ№ж§ҳејҸгҒ®еҗҚе»әзҜүгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢдә¬йғҪеәңеәҒиҲҺж—§жң¬йӨЁгҒ®иЁӯиЁҲиҖ…гҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲе®ҹ家гҒҜгҖҒжқҫе°ҫеӨ§зӨҫгҒ®зҘһе®ҳгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢ家系пјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮдә¬йғҪеәңжҠҖеё«гҖҒй–ўжқұйғҪзқЈеәңжҠҖеё«гҒӘвҖҰвҖҰ

гғһгғӢгӮЁгғӘгӮ№гғ (гҒҫгҒ«гҒҲгӮҠгҒҷгӮҖ)
ManД“rismeгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒзҫҺиЎ“гӮ„ж–ҮиҠёгҒ®еҲ¶дҪңгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰи‘—гҒ—гҒҸж—ўжҲҗгҒ®жүӢжі•гҒ«дҫқеӯҳгҒ—гҒҰж–°й®®е‘ігӮ’ж¬ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒи»Ҫи”‘зҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®гҖҢгғһгғігғҚгғӘгӮәгғ гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®зӣӣжңҹгғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒЁгғҗгғӯгғғгӮҜгҒ®й–“гҒ®жҷӮжңҹгҖҒвҖҰвҖҰ

з–ҺеһӮжңЁ(гҒҫгҒ°гӮүгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

дёёз•і(гҒҫгӮӢгҒ гҒҹгҒҝ)
гҖҖ

гғһгғігӮөгғјгғүеұӢж №(гҒҫгӮ“гҒ•гғјгҒ©гӮ„гҒӯ)
иӢұ/mansard roofгҖҒзұі/gambrel roofгҖӮдёҠйғЁгҒҢз·©еӢҫй…ҚгҒ§дёӢйғЁгҒҢжҖҘеӢҫй…ҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдәҢйҮҚеӢҫй…ҚгӮ’жҢҒгҒӨеұӢж №гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®з©әй–“гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰеұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮд»ҸеӣҪгҒ®е»әзҜү家F.гғһгғігӮөгғјгғ«пјҲиҮӘеӣҪгҒ®дјқзөұгҒ®дёҠвҖҰвҖҰ

жӣјиҚјзҫ…жқҝ(гҒҫгӮ“гҒ гӮүгҒ„гҒҹ)
гҖҖеҜҶж•ҷеҜәйҷўгҒ®гҖҢеҶ…йҷЈгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе·ҰеҸігҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢиҘҝгҖҚгҒ«гҖҢйҮ‘еүӣз•ҢжӣјиҚјзҫ…гҖҚгҖҒгҖҢжқұгҖҚгҒ«гҖҢеӨ§жӮІиғҺи”өз”ҹжӣјиҚјзҫ…гҖҚгӮ’жҺІгҒ’гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮүгҒ®жқҝеЈҒгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢжӣјиҚјзҫ…жқҝгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҖҢй ҲејҘеЈҮгҖҚгҒҜгҖҢеҢ—гҖҚгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҖҢйҮ‘еүӣз•ҢгҖҚгҒ®дёҠвҖҰвҖҰ

гғҹгғјгӮ№гғ»гғ•гӮЎгғігғ»гғҮгғ«гғ»гғӯгғјгӮЁ(гҒҝгғјгҒҷгғ»гҒөгҒҒгӮ“гғ»гҒ§гӮӢгғ»гӮҚгғјгҒҲ Ludwig Mies van der Rohe 1886пҪһ1969)
зӢ¬еӣҪеҮәиә«гҒ®зұіеӣҪдәәгҖӮгҖҢиҝ‘д»Је»әзҜүдёүд»Је·ЁеҢ гҖҚгҒ®дёҖдәәгҖӮ20дё–зҙҖгҒ®гғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢе»әзҜү家гҖӮP.гғҷгғјгғ¬гғігӮ№гҒ®дәӢеӢҷжүҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮ1920е№ҙд»Јд»ҘйҷҚгҖҒе»әзҜүз©әй–“гҒ®еҮҰзҗҶгҒ®дёҠгҒ§гғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘжүҚиғҪгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҰгҖҒиҝ‘д»Је»әзҜүгҒ®й–ӢжӢ“иҖ…гҒ®вҖҰвҖҰ

з‘һеһЈ(гҒҝгҒҡгҒҢгҒҚ)
зҘһзӨҫгҒҠгӮҲгҒіеҸӨеўіжҷӮд»ЈгҒ®зҡҮеұ…гҒ«е·ЎгӮүгҒ—гҒҹеһЈгҖӮеҪўејҸгҖҒжқҗж–ҷгҒӘгҒ©гҒҜе•ҸгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮдјҠеӢўзҘһе®®гҒ®е ҙеҗҲгҒҜжңҖгӮӮеҶ…еҒҙгҒ®еһЈгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮдёҖиҲ¬гҒ®зҘһзӨҫгҒ§гҒҜеһЈгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«дәҢйҮҚгҒ§еҶ…еҒҙгӮ’з‘һеһЈгҖҒеӨ–еҒҙгӮ’зҺүеһЈгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮзҺүеһЈгӮӮз‘һеһЈгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгҖҒеҪўејҸгҖҒжқҗж–ҷгҒҜе•ҸгӮҸгҒӘвҖҰвҖҰ

дёүж–—(гҒҝгҒӨгҒ©)
гҖҖ

з®•з”І(гҒҝгҒ®гҒ“гҒҶ)
жӣІйқўзҠ¶гҒ®гҖҢз®•з”ІгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢжӘңзҡ®и‘әгҖҚгҖҢжқ®и‘әгҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҢжң¬з“Ұи‘әгҖҚгҒ§гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҢз“Ұи‘әгҖҚгҒ®е ҙеҗҲгҖҒж•°жқЎгҒ®дёёз“ҰгҒЁе№із“ҰгҒЁгӮӮгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢиҰҸж јеӨ–гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҪ№зү©з“ҰгҒ«иҝ‘гҒ„зҙҚгҒҫгӮҠгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҒ®гӮӮгҒ®гӮ„иҝ‘д»ЈгҒ®гӮӮгҒ®вҖҰвҖҰ

и“‘жқҹ(гҒҝгҒ®гҒҘгҒӢ)
гҖҖ

гғҹгғҺгғ«гғ»гғӨгғһгӮөгӮӯ(гҒҝгҒ®гӮӢгғ»гӮ„гҒҫгҒ•гҒҚ еұұеҙҺеҜҰгҖҒ1912пҪһ1986)
ж—Ҙзі»зұіеӣҪдәәе»әзҜү家гҖӮгғҜгӮ·гғігғҲгғіе·һгӮ·гӮўгғҲгғ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҜгӮ·гғігғҲгғіеӨ§еӯҰ件е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖҒгғӢгғҘгӮҰгғЁгғјгӮҜеӨ§еӯҰйҷўгҒ§дҝ®еЈ«еҸ–еҫ—гҖӮзҙҶдҪҷжӣІжҠҳгҒ®дҝ®иЎҢжҷӮд»ЈгӮ’зөҢгҒҰзӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеңЁзҘһжҲёзұіеӣҪй ҳдәӢйӨЁпјҲж—Ҙжң¬е»әзҜүеӯҰдјҡдҪңе“ҒиіһпјүгҖҒгғҜгғјгғ«гғүгғҲгғ¬гғјгғүвҖҰвҖҰ

иө·гӮҠз ҙйўЁ(гӮҖгҒҸгӮҠгҒҜгҒө)
гҖҖ

иө·гӮҠеұӢж №(гӮҖгҒҸгӮҠгӮ„гҒӯ)
зӨҫеҜәгғ»е®®ж®ҝгғ»еҹҺйғӯе»әзҜүгҒӘгҒ©гҒ«гҒҜгҖҢз…§гӮҠеұӢж №пјҲеҸҚгӮҠеұӢж №гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶпјүгҖҚгҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒеҸӨејҸгӮ’дјқгҒҲгӮӢзҘһзӨҫжң¬ж®ҝгӮ„зҸҫд»ЈдҪҸе®…гҒҜгҖҢзӣҙз·ҡеұӢж №гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢиө·гӮҠеұӢж №гҖҚгҒҜжҜ”ијғзҡ„гҒ«жӯҙеҸІгҒҢжө…гҒҸгҖҒиҝ‘дё–гҒ®дҪҸе®…гӮ„й–ўиҘҝең°ж–№гҒ®ж°‘家гҒӘгҒ©гҒ«еӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸвҖҰвҖҰ

иҷ«зұ зӘ“(гӮҖгҒ—гҒ“гҒҫгҒ©)
дә¬йғҪгҖҒеӨ§йҳӘгҖҒеҘҲиүҜгҒ®з”әеұӢгҒ®еҺЁеӯҗдәҢйҡҺгҒ®йҒ“и·ҜеҒҙгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҒзёҰж јеӯҗгҒ®гҒӮгӮӢзӘ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҷ«зұ зӘ“гҒ®ж јеӯҗгҒҜиҷ«зұ ж јеӯҗгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒеӣӣеҜёи§’гҒ®жқҗгӮ’е…ӯеүІгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ«гҖҒзё„гӮ’е·»гҒҚд»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’зёҰж јеӯҗгҒЁгҒ—гҖҒеңҹгӮ’еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгҒҰгҒӨгҒҸгӮӢгҖӮжҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ«вҖҰвҖҰ

з„ЎеҸҢзӘ“(гӮҖгҒқгҒҶгҒҫгҒ©)
з„ЎеҸҢйҖЈеӯҗзӘ“гҒ®з•ҘгҒ§гҖҒе№…гҒ®гҒӮгӮӢйҖЈеӯҗгӮ’зёҰгҒ«зө„гӮ“гҒ зӘ“гҒ®еҶ…еҒҙгҒ«еҗҢеҪўејҸгҒ®йҖЈеӯҗгҒ®еј•гҒҚжҲёгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҖҒдёҖж–№гҒ«еј•гҒ‘гҒ°гҖҒзӘ“йҖЈеӯҗгҒ®йҡҷй–“гҒҢгҒөгҒ•гҒҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮеҶ…еҒҙгҒ«йҖЈеӯҗгҒ®еј•гҒҚжҲёгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢдәӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒй–ӢгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒиҰ–з·ҡвҖҰвҖҰ

жЈҹй–Җ(гӮҖгҒӯгҒӢгҒ©гҖҒгӮҖгҒӘгӮӮгӮ“)
гҖҖ

жқ‘йҮҺи—Өеҗҫ(гӮҖгӮүгҒ®гҒЁгҒҶгҒ”гҖҒ1891пҪһ1984)
жҲҰеүҚгғ»жҲҰеҫҢгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒй•·гҒҚгҒ«жёЎгӮҠж•°еӨҡгҒҸгҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒҷгҖӮдҪҗиіҖзңҢе”җжҙҘеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮпјҲе…ҘеӯҰжҷӮгҒҜйӣ»ж°—е·ҘеӯҰ科пјүжёЎйӮҠзҜҖ е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ«е…ҘжүҖгҖӮж—Ҙжң¬иҲҲжҘӯйҠҖиЎҢжң¬еә—гҖҒгғҖгӮӨгғ“гғ«жң¬йӨЁгҖҒз¶ҝжҘӯдјҡйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®иЁӯиЁҲгҒ«вҖҰвҖҰ

еҘіжўҒ(гӮҒгҒҶгҒӨгҒ°гӮҠгҖҒгӮҒгҒ°гӮҠ)
гҖҖ

еҸ¬еҗҲгҒӣ(гӮҒгҒ—гҒӮгӮҸгҒӣ)
е»әе…·еҗҢеЈ«гӮ’й–үгӮҒгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒҢжҺҘгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҒөгҒҷгҒҫгҒӘгҒ©гҒ®еј•гҒҚжҲёгҒ®еҸ¬еҗҲгҒӣгҒ«гҒҜе®ҡиҰҸзёҒпјҲгҒҳгӮҮгҒҶгҒҺгҒ¶гҒЎпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢйғЁжқҗгҒ§йҡҷй–“гӮ’иҰӢгҒҲгҒӘгҒҸгҒҷгӮӢгҒҠгҒ•гҒҫгӮҠгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮе®ҡиҰҸзёҒгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҸ¬еҗҲгҒӣжЎҶпјҲгӮҒгҒ—гҒӮгӮҸгҒӣгҒӢгҒҫгҒЎпјүгҒӘвҖҰвҖҰ

гғЎгғҖгғӘгӮӘгғі(гӮҒгҒ гӮҠгҒҠгӮ“)
medalionгҖӮзҙӢз« гҖӮеӨ§еһӢгҒ®гғЎгғҖгғ«гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

йқўзҡ®жҹұ(гӮҒгӮ“гҒӢгӮҸгҒ°гҒ—гӮү)
гҖҖ

йқўжҲё(гӮҒгӮ“гҒ©)
гҖҖ

гғўгғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°(гӮӮгғјгӮӢгҒ§гҒғгӮ“гҒҗ)
mouldingгҖӮеҲігӮҠеҪўгҖҒз№°гӮҠеҪўгҖӮе»әзҜүгғ»е®¶е…·гғ»еҷЁзү©гҒӘгҒ©гҒ®зёҒгҒ®йғЁеҲҶгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҮ№гӮ“гҒ§еҲігҒЈгҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹзү№еҫҙгҒ®гҒӮгӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘеҪўгҖӮйҷ°еҪұгӮ’д»ҳеҠ гҒҷгӮӢиЎЁзҸҫжүӢжі•гҒ®дёҖгҒӨгҖӮйҖҡеёёгҖҒеҗҢгҒҳеҪўгҒ®ж–ӯйқўгҒҢйҖЈз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮжҲ‘гҒҢеӣҪгҒ®еҸӨе»әзҜүгҒ«гӮӮгҖҒйқўвҖҰвҖҰ

гғўгӮӨгӮ»гӮӨжІіжқ‘дјҠи”ө(гӮӮгҒ„гҒӣгҒ„гҒӢгӮҸгӮҖгӮүгҒ„гҒһгҒҶгҖҒ1865пҪһ1940)
ж„ӣзҹҘзңҢеҚ—зҹҘеӨҡз”әз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮзҘһз”°й§ҝжІіеҸ°гҒ®жӯЈж•ҷдјҡи© йҡҠеӯҰж ЎгҒ«еӯҰгҒ¶гҖӮжӯЈж•ҷдјҡгҒ®иҒ–иҒ·иҖ…гҒ§гҖҒжҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ«еҗҢеҚ”дјҡгҒ®е–¶з№•гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮжІіжқ‘гҒ«гҒҜе»әзҜүгҒ®еҝғеҫ—гҒҜз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжқұдә¬еӨ§иҒ–е ӮпјҲгғӢгӮігғ©гӮӨе ӮпјүгӮ„жқҫе®Өең°жҜӣеҜҶиЁӯиЁҲгҒ®дә¬йғҪгғҸгғӘгӮ№гғҲжӯЈж•ҷвҖҰвҖҰ

иЈійҡҺ(гӮӮгҒ“гҒ—)
гҖҖ

жҢҒйҖҒгӮҠ(гӮӮгҒЎгҒҠгҒҸгӮҠ)
зӨҫеҜәе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢжҢҒйҖҒгӮҠгҖҚгҒ®е…ёеһӢзҡ„гҒӘдҫӢгҒҜгҖҒгҖҢжқұеӨ§еҜәдәҢжңҲе ӮгҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢдёүж®өж§ӢгҒҲгҒ®иұӘеЈ®гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»–гҒ«гӮӮгҖҒгҖҢеҗүеӮҷжҙҘзҘһзӨҫгҖҚгҒ®гҖҒиҲ№гҒ®е§ҝгӮ’жЁЎгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгҖҢзёҒгҖҚгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҢжҢҒйҖҒгӮҠгҖҚгӮӮгҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒ§гҒӮгӮҠдёҖй–“гҒ®дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢвҖҰвҖҰ

жң¬йҮҺзІҫеҗҫ(гӮӮгҒЁгҒ®гҒӣгҒ„гҒ”гҖҒ1882пҪһ1944)
еӨ§жӯЈжңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰдә¬йғҪгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжӯҰз”°дә”дёҖ гҒ«дә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰж ЎпјҲзҸҫдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰпјүж•ҷжҺҲгҒ«жӢӣгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

гғўгғҺгғӘгӮ№(гӮӮгҒ®гӮҠгҒҷ)
monolithгҖӮдёҖжң¬зҹігҖӮдёҖжң¬зҹігҒ§дҪңгҒЈгҒҹжҹұгғ»иЁҳеҝөзў‘гҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гӮӘгғҷгғӘгӮ№гӮҜгҖӮ

жҜҚеұӢ(гӮӮгӮ„)
гҖҢжҜҚеұӢпјҲгӮӮгӮ„пјүгҖҚпјҲеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒҜгҖҢзңҹеұӢпјҲгҒҫгӮ„пјүгҖҚпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢеҲҮеҰ»еұӢж №е»әзү©гҒ®дёӯеӨ®йғЁеҲҶгҒ®еӣӣе‘ЁгҒ«гҖҢеәҮгҖҚз©әй–“гҒҢеҸ–гӮҠд»ҳгҒ„гҒҹеҪўејҸгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеұӢж №гҒ®жҺҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«ж®өгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢйҢЈи‘әеұӢж №пјҲгҒ—гҒ“гӮҚгҒ¶гҒҚгӮ„гҒӯпјүгҖҚгҖҒ
ж®өгӮ’д»ҳвҖҰвҖҰ

жЈ®з”°ж…¶дёҖ(гӮӮгӮҠгҒҹгҒ‘гҒ„гҒ„гҒЎгҖҒ1895пҪһ1983)
еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ®ж§ӢжҲҗе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»еӢ•гӮ’е§ӢгӮҒгӮӢгҒҢгҖҒиҘҝжҙӢе»әзҜүгҒ®жӯҙеҸІзҡ„з ”з©¶гӮ’зөҢгҒҰгҖҒгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһгҒ®еҸӨе…ёзІҫзҘһгӮ’жҺўжұӮгҒ—гҖҒе»әзҜүи«–з ”з©¶гҒ«гӮӮеҠӣгӮ’жіЁгҒ„гҒ е»әзҜү家гҖӮеҗҚи‘—гҖҢиҘҝжҙӢе»әзҜүе…Ҙй–ҖгҖҚпјҲжқұжө·еӨ§еӯҰеҮәзүҲдјҡпјүгҒ®и‘—иҖ…гҖӮжЈ®з”°гҒ®и¶Јж—ЁгҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

жЈ®еұұжқҫд№ӢеҠ©(гӮӮгӮҠгӮ„гҒҫгҒҫгҒӨгҒ®гҒҷгҒ‘гҖҒ1869пҪһ1949)
ж—Ҙжң¬зөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ®еҸ°ж№ҫгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеӨ§йҳӘеёӮе№ійҮҺз”әз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲеҸ”зҲ¶гҒҢдә”д»ЈеҸӢеҺҡпјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒ«её«дәӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒз·ҸзқЈе®ҳйӮёпјҲзҸҫеҸ°еҢ—иі“йӨЁпјүгҖҒеҸ°еҢ—е·һеәҒпјҲзҸҫеӣҪз«ӢеҸ°ж№ҫж–ҮеӯҰйӨЁпјүгҖҒд№…ж…Ҳе®®йӮёпјҲзҸҫвҖҰвҖҰ

дёЎжҠҳжҲё(гӮӮгӮҚгҒҠгӮҢгҒ©гғ»гӮӮгӮҚгҒҠгӮҠгҒ©)
гҖҖ
гӮ„гҖңгӮҲ

и–¬еҢ»й–Җ(гӮ„гҒҸгҒ„гӮӮгӮ“)
йҺҢеҖүжҷӮд»Јжң«жңҹгҒӢе®Өз”әжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ®гҖҒжӯҰ家гҒҫгҒҹгҒҜ公家гҒ®еұӢж•·гҒӘгҒ©гҒ«зҸҫгӮҢгӮӢй–ҖеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮгҖҢжң¬жҹұгҖҚгҒЁгҖҢжҺ§жҹұгҖҚгҒ«иҚ·йҮҚгҒҢеҲҶж•ЈгҒ•гӮҢж§ӢйҖ дёҠгҒ®е®үе®ҡгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҒӢгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜж–Ҫе·ҘжҖ§гҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒеҫҢгҒ«еҹҺйғӯгӮ„зӨҫеҜәгҒ«гӮӮеәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲвҖҰвҖҰ

и–¬её«еҜәдё»иЁҲ(гӮ„гҒҸгҒ—гҒҳгҒӢгҒҡгҒҲгҖҒ1884пҪһ1965)
еІЎеұұзңҢз·ҸзӨҫеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮйҷёи»ҚзңҒжҠҖеё«гӮ’зөҢгҒҰгҖҒеҖүж•·зө№з№”ж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲзҸҫгӮҜгғ©гғ¬пјүгҒ®еҸ–з· еҪ№гҒ«е°ұд»»гҖӮеӨ§еҺҹ家гҒ«й–ўгӮҸгӮӢж–ҪиЁӯгӮ’дёӯеҝғгҒ«е»әзҜүиЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеҫҢгҒ«ж ӘејҸдјҡзӨҫи—ӨжңЁе·ҘеӢҷеә—зӣЈжҹ»еҪ№гӮӮеӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«вҖҰвҖҰ

е®үдә•жӯҰйӣ„(гӮ„гҒҷгҒ„гҒҹгҒ‘гҒҠгҖҒ1884пҪһ1955)
еӨ§йҳӘгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҒгҖҢзңҹгҒ«гҒ—гҒҰзҫҺгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҖҚгӮ’иҝҪжұӮгҒҷгӮӢиҮӘз”ұж§ҳејҸгӮ’жЁҷжҰңгҒҷгӮӢгҖӮеҚғи‘үзңҢдҪҗеҖүеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科е®ӨгҖӮйҮҺжқ‘иІЎй–ҘгҒ®еүөе§ӢиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢйҮҺжқ‘еҫідёғгҒ®еҫҢжҸҙгҒҢгҒӮгӮҠе®үдә•е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

дҝқеІЎеӢқд№ҹ(гӮ„гҒҷгҒҠгҒӢгҒӢгҒӨгӮ„гҖҒ1877пҪһ1942)
дёүиҸұгҒ®дёёгҒ®еҶ…иөӨз…үз“ҰгӮӘгғ•гӮЈгӮ№иЎ—гҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҒ»гҒӢгҖҒе…Ҳй§Ҷзҡ„гҒӘдҪҸе®…иЁӯиЁҲгҒ§гӮӮзҹҘгӮүгӮҢгӮӢе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӯҰй•·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒ«её«дәӢгҖӮеІ©пЁ‘д№…ејҘзӨҫй•·гҒ®дёүиҸұеҗҲиіҮдјҡзӨҫпјҲзҸҫдёүиҸұең°жүҖпјүгҒ«вҖҰвҖҰ

еұұз”°е®Ҳ(гӮ„гҒӘгҒ гҒҫгӮӮгӮӢгҖҒ1894пҪһ1966)
йҖ“дҝЎе»әзҜүгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҒ§гҖҒеҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ®ж§ӢжҲҗе“ЎгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҒ®еҫ©иҲҲж©ӢжўҒгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮжүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮж»‘гӮүгҒӢгҒӘжӣІз·ҡгҒёгҒ®жӢҳгӮҠгҒ«гғүгӮӨгғ„ иЎЁзҸҫдё»зҫ© гҒ®еҪұйҹҝгҒҢиүІжҝғгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеІҗйҳңзңҢзҫҪеі¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әвҖҰвҖҰ

зҹўж©Ӣиіўеҗү(гӮ„гҒ°гҒ—гҒ‘гӮ“гҒҚгҒЎгҖҒ1869пҪһ1927)
жҳҺжІ»е»әзҜүз•ҢгҒ®дёүеӨ§е·ЁеҢ гҒ®дёҖдәәгҒЁзӣ®гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеІҗйҳңзңҢеӨ§еһЈеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮеӨ§еҖүзңҒгҒ§ еҰ»жңЁй јй»„ гҒЁеҮәдјҡгҒ„гҖҒгҒқгҒ®зүҮи…•гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еұұеҸЈзңҢеәҒиҲҺгғ»зңҢдјҡиӯ°е ӮпјҲзҸҫеұұеҸЈзңҢж”ҝиіҮж–ҷйӨЁпјүгҖҒжһўеҜҶйҷўеәҒиҲҺпјҲзҸҫвҖҰвҖҰ

зҹўйғЁеҸҲеҗү(гӮ„гҒ№гҒҫгҒҹгҒҚгҒЎгҖҒ1888пҪһ1941)
жҳҺжІ»жң«жңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжЁӘжөңгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжЁӘжөңеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮеҰ»жңЁй јй»„ гҒ®е…ғгҒ§иЁӯиЁҲгҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҖӮеҫҢгҒ«гғҷгғ«гғӘгғіе·Ҙ科еӨ§еӯҰгҒ«е°ұеӯҰгҒ—гҒӘгҒҢгӮүR.гӮјгғјгғ«гҒ«её«дәӢгҖӮжЁӘжөңеёӮеҶ…гҒ«е»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’вҖҰвҖҰ

еұұе·қйҖёйғҺ(гӮ„гҒҫгҒӢгӮҸгҒ„гҒӨгӮҚгҒҶгҖҒ1889пҪһ1962)
еӨ§йҳӘеәңй«ҳзҹіеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе…өеә«зңҢз«Ӣе·ҘжҘӯе°Ӯй–ҖеӯҰж ЎпјҲ姫и·Ҝе·ҘжҘӯеӨ§еӯҰгҒӢгӮүзҸҫе…өеә«зңҢз«ӢеӨ§еӯҰпјүж©ҹ械科еҚ’гҖӮгғҡгғігӮ·гғ«гғҗгғӢгӮўе·һз«ӢеӨ§еӯҰгҒ®иҒҙи¬ӣз”ҹгҖӮй«ҳеё«жөңгҒ®дјҪзҫ…ж©Ӣең’гҒ®иЁӯиЁҲиҖ…гғ»ж–Ҫе·ҘиҖ…гғ»зөҢе–¶иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еұұе·қ家дҪҸе®…гҖҒиөӨеҹҺе®—жҲҗ家дҪҸвҖҰвҖҰ

еұұеҸЈеҚҠе…ӯ(гӮ„гҒҫгҒҗгҒЎгҒҜгӮ“гӮҚгҒҸгҖҒ1858пҪһ1900)
еі¶ж №зңҢжқҫжұҹеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеӣҪз«Ӣгғ‘гғӘдёӯеӨ®е·ҘиҠёеӯҰж ЎеҚ’гҖӮж–ҮйғЁзңҒ営繕еңЁзұҚжҷӮгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®еӯҰж Ўе»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮе®ҹеӢҷгҒ®еӮҚгӮүгҖҒе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүгҒ§ж•ҷйһӯгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒ第дёүй«ҳзӯүдёӯеӯҰж ЎеҜ„е®ҝиҲҺпјҲзҸҫдә¬йғҪеӨ§еӯҰеҗүз”°еҜ®пјүгҖҒж—§жқұдә¬йҹіжҘҪвҖҰвҖҰ

еұұеҸЈж–ҮиұЎ(гӮ„гҒҫгҒҗгҒЎгҒ¶гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1902пҪһ1978)
1930пҪһ60е№ҙд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹиҝ‘д»Јж—Ҙжң¬е»әзҜүйҒӢеӢ•гҒ®гғӘгғјгғҖгғјгҒ®дёҖдәәгҖӮгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁеҗҢжҷӮгҒ«е’ҢйўЁе»әзҜүгҒ®еҗҚжүӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжқұдә¬жө…иҚүз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮзҘ–зҲ¶гҒҜе®®еӨ§е·ҘгҖҒзҲ¶гҒҜжё…ж°ҙзө„пјҲзҸҫжё…ж°ҙе»әиЁӯпјүгҒ®еӨ§е·ҘжЈҹжўҒгҖӮжқұдә¬й«ҳзӯүе·ҘжҘӯвҖҰвҖҰ

еұұдёӢе•“ж¬ЎйғҺ(гӮ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒ‘гҒ„гҒҳгӮҚгҒҶгҖҒ1868пҪһ1931)
жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮй№ҝе…җеі¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮдјҠжқұеҝ еӨӘ гҒЁеҗҢзӘ“гҒ§гҖҒдә”еӨ§зӣЈзҚ„гӮ’иЁӯиЁҲгҖӮгӮёгғЈгӮәгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ®еұұдёӢжҙӢиј”гҒҜеӯ«гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еҚғи‘үзӣЈзҚ„гҖҒж—§й•·еҙҺзӣЈзҚ„гҖҒж—§йҮ‘жІўзӣЈзҚ„гҖҒж—§й№ҝе…җеі¶зӣЈзҚ„гҖҒж—§еҘҲиүҜзӣЈзҚ„вҖҰвҖҰ

еұұдёӢеҜҝйғҺ(гӮ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гӮҚгҒҶгҖҒ1888пҪһ1961)
еұұеҪўзңҢзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдёүиҸұеҗҲиіҮдјҡзӨҫпјҲзҸҫдёүиҸұең°жүҖпјүгҒ«е…ҘзӨҫгҖӮеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—еұұдёӢеҜҝйғҺе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖпјҲзҸҫеұұдёӢиЁӯиЁҲпјүгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬иҲҲжҘӯйҠҖиЎҢжң¬еә—гҖҒе®үз”°з”ҹе‘Ҫдҝқйҷәзӣёдә’жң¬зӨҫгҖҒе®®еҹҺзңҢж°‘дјҡйӨЁгҖҒд»ҷвҖҰвҖҰ

еұұз”°йҶҮ(гӮ„гҒҫгҒ гҒҳгӮ…гӮ“гҖҒ1884пҪһ1969)
дҪҸе®…дҪң家гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йҒ“гӮ’жӯ©гҒҝгҖҒе’ҢжҙӢжҠҳиЎ·дҪҸе®…гӮ’зҷәеұ•гҒ•гҒӣгҒҹе»әзҜү家гҖӮеӯҗжҒҜгҒ®з—…гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒеҒҘеә·дҪҸе®…гӮ’з ”з©¶гҒ—жҸҗе”ұгҒ—гҒҹе…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮеҹјзҺү家秩зҲ¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮпјҲз«№и…°е»әйҖ гғ»иҘҝжқ‘еҘҪжҷӮгғ»еұұдёӢеҜҝйғҺгғ»вҖҰвҖҰ

еӨ§е’ҢжЈҹ(гӮ„гҒҫгҒЁгӮҖгҒӯ)
гҖҢеӨ§е’ҢжЈҹгҖҚгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈжңҹд»ҘйҷҚгҖҒд»Ҡе’Ңж¬ЎйғҺгҒӘгҒ©гҒ®ж°‘ж—ҸеӯҰиҖ…гҒ«гӮҲгӮҠе”ұгҒҲгӮүгӮҢгҒҹеҗҚз§°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжҳ”гҒӢгӮүгҒ®е‘јгҒіеҗҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜгҖҢй«ҳеЎҖйҖ гҖҚгҒЁжӣёгҒҚгҖҢгҒҹгҒӢгҒёгғ»гҒҘгҒҸгӮҠгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮй–ўиҘҝгҒ§гҒҜгҖҢеЎҖгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢгҒёгҒ„гҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸвҖҰвҖҰ

йҒЈйүӢ(гӮ„гӮҠгҒҢгӮ“гҒӘ)
зҸҫд»ЈгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢеҸ°йүӢгҒҢеҮәзҸҫгҒҷгӮӢд»ҘеүҚгҒ®еҸӨд»ЈгҒ®йүӢгҖӮйҒЈйүӢгҒҜжҹ„гҒ®е…ҲгҒ«ж§Қе…ҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲғзү©гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹйүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ®е®®еӨ§е·ҘгҒ®иҘҝеІЎеёёдёҖжЈҹжўҒгҒҢеҶҚзҸҫгҒ—гҒҰе®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҒЈйүӢгҒ§еүҠгҒЈгҒҹеҫҢгҒҜгҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒӘе№ійқўгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҮ№еҮёгҒҢвҖҰвҖҰ

гғҰгғјгӮІгғігғҲгӮ·гғҘгғҶгӮЈгғјгғ«(гӮҶгғјгҒ’гӮ“гҒЁгҒ—гӮ…гҒҰгҒғгғјгӮӢ)
JugendstilгҖӮгҖҢгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгҖҚгҒ®гғүгӮӨгғ„гғ»гӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе‘јгҒіеҗҚгҖӮ1896е№ҙгҖҒгғҹгғҘгғігғҳгғігҒ§зҷәеҲҠгҒ•гӮҢгҒҹйӣ‘иӘҢгҖҢгғҰгғјгӮІгғігғҲгҖҚгҒ«еӣ гӮҖеҗҚз§°гҖӮ

зөҗз¶ҝ(гӮҶгҒ„гӮҸгҒҹ)
гҖҖ

жңүж©ҹзҡ„е»әзҜү(гӮҶгҒҶгҒҚгҒҰгҒҚгҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸ)
organic architectureгҖӮе»әзҜүзү©гӮ’иҮӘ然гҒ®йӣ„еҢ—гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөұдёҖдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жңүж©ҹзҡ„е»әзҜүгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒ гҒҢжңүж©ҹзҡ„гҒЁгҒ„гҒҶиӘһгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дҪҝгҒҶдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®жҰӮвҖҰвҖҰ

йҒҠйӣўе°ҫеһӮжңЁ(гӮҶгҒҶгӮҠгҒҠгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

з“”зҸһ(гӮҲгҒҶгӮүгҒҸ)
гҖҖ

жЁӘжІіж°‘иј”(гӮҲгҒ“гҒӢгӮҸгҒҹгҒҝгҒҷгҒ‘гҖҒ1864пҪһ1945)
жҳҺжІ»гҒ®е»әзҜү家гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йү„йӘЁе»әзҜүгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒжЁӘжІігӮ°гғ«гғјгғ—гӮ’еүөжҘӯгҒ—гҒҹе®ҹжҘӯ家гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳҺзҹіеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰж ЎйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеёқеӣҪеҠҮе ҙгҖҒдёүи¶ҠгҖҒжқұдә¬йҠҖиЎҢйӣҶдјҡжүҖгҖҒж—Ҙжң¬е·ҘжҘӯеҖ¶жҘҪйғЁгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮвҖҰвҖҰ

еҗүз”°дә”еҚҒе…«(гӮҲгҒ—гҒ гҒ„гҒқгӮ„гҖҒ1894пҪһ1956)
жҳӯе’ҢжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҖҒе’ҢйўЁгҒ®ж„ҸеҢ гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢж•°еҜ„еұӢе»әзҜүгҖҚгӮ’зӢ¬иҮӘгҒ«жҠҪиұЎеҢ–гғ»иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲзҲ¶гҒҜеӨӘз”°иғғж•ЈгҒ®еүөжҘӯиҖ…гҖӮеҗүз”°гҒҜжҜҚж–№гҒ®е§“пјүжқұдә¬зҫҺиЎ“еӨ§еӯҰпјҲзҸҫжқұдә¬иҠёиЎ“еӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮеІЎз”°дҝЎдёҖйғҺ гҒ«её«дәӢгҖӮжҜҚж ЎгҒ®ж•ҷеЈҮгҒ«з«ӢвҖҰвҖҰ

еҗүжӯҰй•·дёҖ(гӮҲгҒ—гҒҹгҒ‘гҒЎгӮҮгҒҶгҒ„гҒЎгҖҒ1879пҪһ1953)
еұұеҸЈзңҢйҳІеәңеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҡгғігӮ·гғ«гғҗгғӢгӮўе·Ҙ科еӨ§еӯҰгҒ§е»әзҜүгӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮж—§жқ‘дә•йҠҖиЎҢжң¬ж”Ҝеә—гӮ„ж•ҷдјҡе»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮгҖҢжқ‘дә•е®¶гҒ®гҒҠжҠұгҒҲе»әзҜү家гҖҚгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжқ‘дә•йҠҖиЎҢдёғжқЎж”Ҝеә—пјҲзҸҫгҒҚгӮҮгҒҶгҒЁе’ҢгҒҝйӨЁSECONDHOUSEиҘҝвҖҰвҖҰ

еҗүз”°йү„йғҺ(гӮҲгҒ—гҒ гҒҰгҒӨгӮҚгҒҶгҖҒ1894пҪһ1956)
йҖ“дҝЎе»әзҜүгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®гғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮи‘—жӣёгҒ®гҖҢж—Ҙжң¬гҒ®дҪҸе®…гҖҚгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұе»әзҜүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒзӢ¬гғ»иӢұиӘһгҒ«иЁігҒ•гӮҢгҒҹдёӯгҒ§жңҖгӮӮеҪұйҹҝгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹеҮәзүҲзү©гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ®д»–гҖҢж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүгҖҚгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®еәӯең’гҖҚвҖҰвҖҰ

еҗүжқ‘й Ҷдёү(гӮҲгҒ—гӮҖгӮүгҒҳгӮ…гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1908пҪһ1997)
ж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұж–ҮеҢ–гҒЁгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ®иһҚеҗҲгӮ’еӣігҒЈгҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬зҫҺиЎ“еӯҰж ЎпјҲзҸҫжқұдә¬и—қиЎ“еӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮеңЁеӯҰдёӯгҖҒе®ҹжё¬гҒЁиҰіеҜҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒ®еҸӨе»әзҜүгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҖӮгӮўгғігғҲгғӢгғігғ»гғ¬гғјгғўгғігғү гҒ«её«дәӢгҒ—гҖҒгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгӮ’дҪ“еҫ—вҖҰвҖҰ

еҜ„жЈҹйҖ (гӮҲгҒӣгӮҖгҒӯгҒҘгҒҸгӮҠ)
еҜ„жЈҹеұӢж №гӮ’жҢҒгҒӨе»әзү©гҒ®еҪўејҸгҖӮеҜ„жЈҹеұӢж №гҒЁгҒҜе№ійқўгҒҢй•·ж–№еҪўгҒ§гҖҒеӣӣйҡ…гҒ«дёӢжЈҹгӮ’жҢҒгҒӨеұӢж №еҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе№ійқўгҒҢжӯЈж–№еҪўгҒ§еӣӣйҡ…гҒ®дёӢжЈҹгҒҢдёҖзӮ№гҒ«йӣҶдёӯеұӢж №еҪўзҠ¶гҒҜж–№еҪўеұӢж №гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

еӣӣи„ҡй–Җ(гӮҲгҒӨгҒӮгҒ—гӮӮгӮ“)
дәҢжң¬гҒ®еҶҶжҹұгҒ®еүҚеҫҢгҒ«еӣӣжң¬гҒ®ж–№и§’гҒ®жҺ§гҒҲжҹұгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹй–ҖгҒ®еҪўејҸгӮ’еӣӣи„ҡй–ҖгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеұӢж №гҒҜеҲҮеҰ»еұӢж №гҒ§гҖҒз“Ұи‘әгҒҚгӮ„гҖҒжқ®и‘әгҒҚгҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮй–ҖгҒ®ж јејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжңҖгӮӮй«ҳгҒ„гҖӮпјҲгҒ—гҒҚгӮғгҒҸгӮӮгӮ“гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶпјү
гӮүгҖңгӮҚ

зӨје Ӯ(гӮүгҒ„гҒ©гҒҶ)
гҖҖ

зӨјжӢқзҹі(гӮүгҒ„гҒҜгҒ„гҒӣгҒҚ)
гҖҖ

гғ©гғігӮ»гғғгғҲгӮўгғјгғҒ(гӮүгӮ“гҒӣгҒЈгҒЁгҒӮгғјгҒЎ)
lancet archгҖӮгҖҢйӢӯе°–гӮўгғјгғҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ® е°–й ӯгӮўгғјгғҒ гҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒгӮўгғјгғҒгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢеҶҶеј§гҒ®еҚҠеҫ„гҒҢгӮ№гғ‘гғігӮҲгӮҠй•·гҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒжҹұгҒ®й–“йҡ”гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮзӮ№гҒ®й«ҳгҒ•гӮ’жҸғгҒҲвҖҰвҖҰ

гғ©гғігӮҝгғі(гӮүгӮ“гҒҹгӮ“)
lanternгҖӮгғүгӮҘгғјгғўзҠ¶гҒ®еұӢж №гҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®й ӮйғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒиҮӘ然е…үгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҖҒжҸӣж°—гҒ®еҪ№еүІгӮӮжһңгҒҹгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®жҺЎе…үеЎ”гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҫҢгҒ«еҪўзҠ¶гҒ®йЎһдјјжҖ§гҒӢгӮүгҖҒгғқгғјгӮҝгғ–гғ«гҒӘз…§жҳҺеҷЁе…·гҒ®е‘јз§°гҒЁгӮӮгҒӘгӮӢгҖӮ

欄間(гӮүгӮ“гҒҫ)
еӨ©дә•гҒЁйҙЁеұ…гҒЁгҒ®й–“гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹй–ӢеҸЈйғЁгҒ§гҖҒйҡңеӯҗгҖҒзө„еӯҗгҖҒеҪ«зү©гҒӘгҒ©гҒҢгҒҜгӮҒиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮжҺЎе…үгҒҠгӮҲгҒійҖҡйўЁгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ欄間иҮӘдҪ“гҒҢиЈ…йЈҫгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзӯ¬ж¬„й–“гҖҒз«№гҒ®зҜҖ欄間гҒӘгҒ©гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘж„ҸеҢ гҒ®ж¬„й–“гҒҢгҒӮгӮӢвҖҰвҖҰ

гғӘгғҚгғігғ•гӮ©гғјгғ«гғүгғ»гғ‘гғҚгғ«(гӮҠгҒӯгӮ“гҒөгҒүгғјгӮӢгҒ©гғ»гҒұгҒӯгӮӢ)
linenfold panelгҖӮиӢұеӣҪгҒ®гғҒгғҘгғјгғҖгғјзҺӢжңқжҷӮд»ЈгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе®ӨеҶ…еЈҒйқўгҒ®иЈ…йЈҫеҪўејҸгҖӮжңЁиЈҪгҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒ«гҖҒеёғгҒ®жҠҳгӮҠзӣ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒІгҒ жЁЎж§ҳгҒҢзёҰгҒ«еҲ»гҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

гғӘгғ’гғЈгғ«гғҲгғ»гӮјгғјгғ«(гӮҠгҒІгӮғгӮӢгҒЁгғ»гҒңгғјгӮӢ Richard Seel 1854пҪһ1922)
зӢ¬еӣҪдәәгҒ®е»әзҜү家гҖӮзӢ¬еӣҪгӮЁгғ«гғҗвҖ•гғ•гӮ§гғ«гғҲз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮE.гғҷгғғгӮҜгғһгғідәӢеӢҷжүҖгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®ҳеәҒйӣҶдёӯиЁҲз”»гӮ’еҸ—жіЁгҖҒгӮјгғјгғ«гӮӮжқҘж—ҘгҖӮжқұдә¬иЈҒеҲӨжүҖпјҲзҸҫжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјүгҖҒеҸёжі•зңҒпјҲзҸҫжі•еӢҷзңҒпјүгҒ®еәҒиҲҺгӮ’иЁӯиЁҲгҖӮеҫҢгҖҒеӣҪеҶ…гҒ«е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒвҖҰвҖҰ

гғӘгғігғҶгғ«гӮ№гғҲгғјгғі(гӮҠгӮ“гҒҰгӮӢгҒҷгҒЁгғјгӮ“)
lintel stoneгҖӮжҘЈзҹігҖӮзҹійҖ гҒ®жҘЈгҖӮзө„з©ҚйҖ гҒ®й–ӢеҸЈйғЁгҒ®дёҠйғЁиЈңеј·гҒ«гӮўгғјгғҒгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«жҘЈгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢжҘЈејҸж§ӢйҖ гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§(гӮӢгғ»гҒ“гӮӢгҒігӮ…гҒҳгҒҮ Le Corbusier гҖҒCharles-Edouard Jeanneret-Gris 1887пҪһ1965)
гӮ№гӮӨгӮ№з”ҹгҒҫгӮҢгҒ®д»ҸеӣҪдәәгҖӮгҖҢиҝ‘д»Је»әзҜүдёүеӨ§е·ЁеҢ гҖҚгҒ®дёҖдәәгҖӮгғ‘гғӘгҒ®A.гғҡгғ¬гҒ®дәӢеӢҷжүҖгҒ§е»әзҜүж§ӢйҖ гӮ’еӯҰгҒігҖҒP.гғҷгғјгғ¬гғігӮ№гҒ®дәӢеӢҷжүҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮж—©гҒҸгҒӢгӮүгғүгғҹгғҺж–№ејҸгҒ®дҪҸе®…гӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҖҒдҪҸе®…гҒ®йҮҸз”ЈеҢ–гҒёгҒ®ж„Ҹж¬ІгӮ’зӨәгҒҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘеёӮз«Ӣж”№йҖ вҖҰвҖҰ

гғ«гғҚгӮөгғігӮ№ж§ҳејҸ(гӮӢгҒӯгҒ•гӮ“гҒҷгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Renaissance styleгҖӮ15дё–зҙҖгҒӢгӮү16дё–зҙҖгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®гғ«гғҚгӮөгғігӮ№жҷӮд»ЈгҒ«гҖҒе…ҲгҒҡгӮӨгӮҝгғӘгӮўгӮ’дёӯеҝғгҒ«иө·гӮҠгҖҒ全欧гҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҹеҸӨе…ёдё»зҫ©зҡ„гҒӘе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮеҸӨд»ЈгғӯгғјгғһгҒ®иҚҳйҮҚгҒӘж§ҳејҸгӮ’зҗҶжғігҒЁгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гӮўгғјгғҒгғ»гғҙгӮ©гғјгғ«вҖҰвҖҰ

гғ«гғҚгғғгғҲ(гӮӢгҒӯгҒЈгҒЁ)
д»Ҹ/lunetteгҖӮгӮўгғјгғҒгҒ®еңҹеҸ°гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжҹұгҒ®дёҠгҒ«ж°ҙе№ігҒ®гҖҢгӮігғјгғӢгӮ№гҖҚгӮ’е·®гҒ—жёЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®дёҠйғЁгҒ®гӮўгғјгғҒгҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢеҚҠеҶҶеҪўгҒ®йғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гғ«гғҚгғғгғҲпјҲжңҲеҪўпјүгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒқгҒ®гғ«гғҚгғғгғҲгҒҢжҺЎе…үз”ЁгҒ®зӘ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙвҖҰвҖҰ

з…үз“Ұз©Қ(гӮҢгӮ“гҒҢгҒҘгҒҝ)
brick masonryгҖӮз…үз“ҰгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒеЈҒгӮ„еЎҖгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮпј”зЁ®йЎһгҒ®з©ҚгҒҝж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
в‘ гҖҒз…үз“ҰгҒ®й•·жүӢгҒ гҒ‘гҒ®ж®өгҒЁгҖҒе°ҸеҸЈгҒ гҒ‘гҒ®ж®өгӮ’дёҖж®өгҒҠгҒҚгҒ«з©ҚгӮҖж–№ејҸгӮ’гҖҢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№з©ҚгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮв‘ЎгҖҒдёҖж®өгҒ«з…үз“ҰгҒ®й•·жүӢгҒЁе°ҸеҸЈгӮ’вҖҰвҖҰ

йҖЈеӯҗзӘ“(гӮҢгӮ“гҒҳгҒҫгҒ©)
зҙ°гҒ„и§’жқҗгӮ’зёҰгҒҫгҒҹгҒҜжЁӘгҒ®гҒҝгҒ«дёҰгҒ№гҒҹзӘ“гҒ®еҪўејҸгӮ’йҖЈеӯҗзӘ“гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮи§’жқҗгӮ’зёҰгҒ«дёҰгҒ№гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҒзёҰйҖЈеӯҗзӘ“гҒЁгҒ„гҒ„гҖҒжЁӘгҒ«дёҰгҒ№гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жЁӘйҖЈеӯҗзӘ“гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеӨҡгҒҸгҒҜзёҰйҖЈеӯҗзӘ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ®еӣһе»ҠгҒ«гӮӮгҒҝгӮүгӮҢгӮӢеҸӨгҒҸгҒӢгӮүгҒӮгӮӢзӘ“гҒ®еҪўејҸгҒ§гҒӮгӮӢвҖҰвҖҰ

жҘјй–Җ(гӮҚгҒҶгӮӮгӮ“)
зӨҫеҜәе»әзҜүгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢжҘјеҪўејҸгҒ®й–ҖгҖӮпјҲдәҢйҮҚй–Җгғ»гҒ«гҒҳгӮ…гҒҶгӮӮгӮ“гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶпјүдәҢйҡҺе»әгҒҰгҒ§гҖҒдёӢеұӨгҒҜеұӢж №гҒӘгҒ—гҖҒдёҠеұӨгҒҜеҲҮеҰ»йҖ гӮҠгҒ®еұӢж №гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒдәҢйҡҺгҒ®зёҒгҒ«гҒҜй«ҳ欄гҒҢеҸ–гӮҠд»ҳгҒҸгҖӮеұӢж №жқҗж–ҷгҒҜзү№гҒ«е®ҡгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮй–“еҸЈгҒҢдёүй–“дёҖжҲёгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜвҖҰвҖҰ

гғӯгӮігӮіж§ҳејҸ(гӮҚгҒ“гҒ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Rococo styleгҖӮ1730е№ҙй ғгҒӢгӮү1770е№ҙй ғгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰ全欧гҒ«ж „гҒҲгҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгғӯгӮігӮігҒЁгҒ„гҒҶиӘһгҒҜгҖҒе…ғжқҘгҖҢгғӯгӮ«гӮӨгғҰпјҲиІқж®»иЈ…йЈҫпјүгҖҚгӮ’дё»иҰҒгғўгғҶгӮЈгғјгғ•гҒЁгҒҷгӮӢиЈ…йЈҫж§ҳејҸгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮдё»гҒЁгҒ—гҒҰж•ҷдјҡе ӮгӮ„е®®ж®ҝгғ»йӮёйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®вҖҰвҖҰ

гғӯгғғгӮёгӮў(гӮҚгҒЈгҒҳгҒӮ)
loggiaгҖӮеҗ№ж”ҫгҒ—е»ҠдёӢгҖӮдјҠеӣҪгҒ§з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹе»әзҜүж„ҸеҢ гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғ•гӮЎгӮөгғјгғү гҒ«еҲ—жҹұжҲ–гҒ„гҒҜз„ЎжҹұгҒ§еӨ–гҒ«й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹе»ҠдёӢгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮгҖҢй–Ӣе»ҠгҖҚгҖҢж¶јгҒҝе»ҠдёӢгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
ең°дёҠйҡҺгҒ«гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢеӣһе»ҠгҖҚгҒЁвҖҰвҖҰ

гғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜж§ҳејҸ(гӮҚгҒҫгҒӯгҒҷгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)
Romanesque styleгҖӮ 10дё–зҙҖжң«гҒӢгӮү13дё–зҙҖгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰиҘҝ欧全еңҹгҒ«еәғгҒҫгҒЈгҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮиҒ–е ӮгҒҜдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢгғ©гғҶгғіеҚҒеӯ—еҪўгҖҚгҒ®гҖҢдёүе»Ҡ гғҗгӮ·гғӘгӮ« еҪўејҸгҖҚгӮ’гӮӮгҒЎгҖҒгҒқгҒ®еүҚгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®е№ігӮүгҒӘжңЁйҖ еӨ©дә•гҒҜгҖҒзҹійҖ гҒ®гҖҢеҚҠеҶҶвҖҰвҖҰ

гғӯгғігғҗгғ«гғүгғҗгғігғү(гӮҚгӮ“гҒ°гӮӢгҒ©гҒ°гӮ“гҒ©)
Lombardo bandгҖӮгғӯгғігғҗгғ«гғҮгӮЈгӮўгғҗгғігғүгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гғӯгғігғҗгғ«гғҮгӮЈгӮўең°ж–№гҒ§зҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҖҢгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜе»әзҜүгҖҚгҒ«зү№еҫҙзҡ„гҒӘеЈҒйқўгҒ®иЈ…йЈҫеҪўејҸгҖӮ
еӨ–еЈҒгҒ®дёҠйғЁгҒ®зёҒгҒ®йғЁеҲҶгҒ«иҰҸеүҮзҡ„гҒ«д»ҳжҹұпјҲгғ”гғ©гӮ№гӮҝгғјпјүгӮ’е»әгҒҰдёҰвҖҰвҖҰ
гӮҸ

и„Үйҡңеӯҗ(гӮҸгҒҚгҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)
еӣһгӮҠзёҒгҒ®зөӮз«ҜгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҒжқҝгҒ®дәӢгӮ’и„ҮйҡңеӯҗгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҸӨгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒҜгҖҒзҫҪзӣ®жқҝгҒ«жҘөеҪ©иүІгҒ®иҠұйіҘгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮ„гҖҒи–„иӮүгҒ®еҪ«еҲ»гӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮйӮёе®…гҒ§и„ҮйҡңеӯҗгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзҫҪзӣ®жқҝгӮ’иүҜиіӘгҒӘжҹҫзӣ®гҒ®з„ЎеһўжқҝгҒЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲвҖҰвҖҰ

жёЎиҫәд»Ғ(гӮҸгҒҹгҒӘгҒ№гҒҳгӮ“гҖҒ1887пҪһ1973)
жқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеҸӨе…ёдё»зҫ©гҒӢгӮүиЎЁзҸҫжҙҫе»әзҜүгғ»еёқеҶ ж§ҳејҸгғ»еҲқжңҹгғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒҫгҒ§гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иҮӘеңЁгҒ«дҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒ—гҖҒиЁҳеҝөзў‘зҡ„гҒӘдҪңе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒгғӣгғҶгғ«гғӢгғҘгғјгӮ°гғ©гғігғүгҖҒж—©зЁІз”°е°ҸеӯҰж ЎвҖҰвҖҰ

жёЎйӮҠзҜҖ(гӮҸгҒҹгҒӘгҒ№гҒӣгҒӨгҖҒ1884пҪһ1967)
иҝ‘д»Јж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜү家гҒ§гҖҒеҸӨе…ёдё»зҫ©гӮ’гғҷгғјгӮ№гҒЁгҒ—гҒҹж§ҳејҸе»әзҜүгӮ’иҮӘеңЁгҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҖҒиҝ‘з•ҝгӮ’дёӯеҝғгҒ«е•ҶжҘӯгғ“гғ«гҒ®з§ҖдҪңгӮ’еӨҡгҒҸж®ӢгҒ—гҒҹгҖӮй–ҖдёӢз”ҹгҒ«гҖҖжқ‘йҮҺи—ӨеҗҫгҖҖгҒҢгҒ„гӮӢгҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮйү„йҒ“йҷўгӮ’зөҢгҒҰзӢ¬з«ӢеӨ§йҳӘгҒ«иЁӯиЁҲдәӢеӢҷвҖҰвҖҰ

ијӘеһӮжңЁ(гӮҸгҒ гӮӢгҒҚ)
гҖҖ

ијӘйҒ•ж–Үж§ҳ(гӮҸгҒЎгҒҢгҒ„гӮӮгӮ“гӮҲгҒҶ)
ијӘгӮ’дәҢгҒӨд»ҘдёҠзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰдҪңгҒЈгҒҹжЁЎж§ҳгҒ®дёҖзЁ®гҖӮдәҢгҒӨијӘйҒ•гҖҒдёүгҒӨијӘйҒ•гҖҒеӣӣгҒӨијӘйҒ•гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжЈҹз“ҰгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҹеҒҙйқўгҒҢијӘйҒ•жЁЎж§ҳгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҚҠеҶҶеҪўгҒ®з“ҰгӮ’дёҠдёӢдә’гҒ„гҒ«з©ҚгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹз“ҰгӮ’ијӘйҒ•з“ҰгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

е’Ңж§ҳ(гӮҸгӮҲгҒҶ)
еәғзҫ©зҡ„гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘж§ҳејҸгғ»еҪўејҸгҒӘгҒ©гӮ’зӨәгҒҷз·Ҹз§°гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢз”ЁиӘһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
йЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҖҒдёӯеӣҪгҒ®е”җгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢж§ҳејҸгҒҢзӣҙијёе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹеҲқжңҹгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫҗгҖ…гҒ«еӣҪйўЁеҢ–гҒҢйҖІгҒҝгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒеӣҪвҖҰвҖҰ

и—Ғеә§(гӮҸгӮүгҒ–)
зҰ…е®—ж§ҳе»әзҜүгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢжүүгҒ®и»ёеҸ—гҒ‘гҒ®дәӢгӮ’и—Ғеә§гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮзҰ…е®—ж§ҳд»ҘеүҚгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҒ§гҒҜгҖҒдёӢйғЁгҒҜең°иҰҶй•·жҠјгҒ«дёҠйғЁгҒҜй•·жҠјгҒ«и»ёеҸ—гҒ‘гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒи—Ғеә§гҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзҰ…е®—ж§ҳејҸгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒең°иҰҶй•·жҠјгҒӘгҒ©гҒ®йғЁжқҗгҒ®е№…гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢвҖҰвҖҰ

и•ЁжүӢ(гӮҸгӮүгҒігҒҰ)
гҖҖ

и—Ғи‘ә(гӮҸгӮүгҒ¶гҒҚ)
гҖҖ

еүІжқҹ(гӮҸгӮҠгҒҘгҒӢ)
гҖҖ

еүІжӢқж®ҝ(гӮҸгӮҠгҒҜгҒ„гҒ§гӮ“)
е№іе®үжң«жңҹгҒ“гӮҚгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹжӢқж®ҝгҒ®еҪўејҸгҖӮжЁӘй•·гҒ®е№ійқўгҒ®дёӯеӨ®гӮ’еңҹй–“пјҲйҰ¬йҒ“гғ»гӮҒгҒ®гҒ©гҒҶпјүгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰйҖҡи·ҜгҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
ж§Ӣжі•гғ»зҙ°е·Ҙ

зӣёжұәгӮҠ(гҒӮгҒ„гҒҳгӮғгҒҸгӮҠ)
жқҝгӮ’ејөгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒд№ҫзҮҘгҒ—гҒҰгӮӮйҡҷй–“гҒҢгҒӮгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҡЈгӮҠеҗҲгҒҶжқҝгҒ®еҺҡгҒҝгӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢеҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮжҺҘеҗҲгҒҷгӮӢжңЁжқҗгӮ’еҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣёж¬ гҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

и¶ій§„ж¬ (гҒӮгҒ—гҒ гҒҢгҒ’)

иҹ»з¶ҷгҒҺ(гҒӮгӮҠгҒӨгҒҺ)
жңЁжқҗжҺҘжүӢгҒ®дёҖгҖӮдёҖж–№гҒ®з«ҜгҒ«йғЁжқҗгҒ«йі©е°ҫзҠ¶пјҲиҹ»еҪўпјүгҒ®зӘҒеҮәзү©гҖҒд»–ж–№гҒ®з«ҜгҒ«еҗҢеҪўгҒ®з©ҙгӮ’жҺҳгӮҠзөҗеҗҲгҒ•гҒӣгӮӢгҖӮеј•ејөеҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҠөжҠ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖҒз°ЎеҚҳгҒ§еәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢжҺҘжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҹ»гӮҲгӮҠгӮӮеј•ејөгӮҠеј·еәҰгҒҢеӢқгӮӢгҒҢгҖҒжҺҘеҗҲй•·гҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢйҺҢзҠ¶гҒ®вҖҰвҖҰ

зҹіе ҙе»әгҒҰ(гҒ„гҒ—гҒ°гҒ гҒҰ)
民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзӨҺзҹігҒ®дёҠгҒ«зӣҙжҺҘжҹұгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢе·Ҙжі•гҖӮжҹұгӮ’зӣҙжҺҘең°дёӯгҒ«еҹӢгӮҒгҒҰиҮӘз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢжҺҳз«ӢгҒҰе»әгҒҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘһгҖӮзӨҺзҹігҒЁжҺҘи§ҰгҒҷгӮӢжҹұдёӢз«ҜгӮ’зҹігҒ®еҗҲз«ҜгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮзҸҫеңЁгҒ®еҹәжә–жі•гҒ§гҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзҹігҒЁжҹұгҒ®ж‘©ж“ҰеҠӣгҒҢжңүеҠ№гҒ«еғҚгҒҸгҖӮ

жө®йҖ гӮҠ(гҒҶгҒҘгҒҸгӮҠ)
гҖҖ

жҠҳзҪ®зө„(гҒҠгӮҠгҒҠгҒҚгҒҗгҒҝ)
е°ҸеұӢжўҒгҒ®з«ҜйғЁгҒ®зҙҚгӮҒж–№гҒ®дёҖгҖӮжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«зӣҙжҺҘе°ҸеұӢжўҒгӮ’жһ¶гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«и»’жЎҒгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮеҸӨд»ЈгҒӢгӮүз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йҖҶгҒ§гҖҒжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«гҒҫгҒҡжЎҒгӮ’жёЎгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«е°ҸеұӢжўҒгӮ’гҒ®гҒӣгӮӢзҙҚгӮҒж–№гӮ’дә¬е‘Ӯзө„гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

йҙЁеұ…(гҒӢгӮӮгҒ„)
иҝ‘з•ҝең°ж–№гҒ®иҫІе®¶гҒ«гҒҜгҖҒдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸгҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдёҠеә§гҒ®еә§ж•·еҒҙгҒ гҒ‘гӮ’гҖҢй•·жҠје·»пјҲгҒӘгҒ’гҒ—гҒҫгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжҷ®йҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гҖҒеә§ж•·еҒҙгҒ®гҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгӮ’ж¬ гҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҖҢйҮҝеҗҚж —пјҲгҒЎгӮҮгҒҶгҒӘгҒӘгҒҗгӮҠпјүгҖҚгӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒе·Ұе®ҳгҒ§вҖҰвҖҰ

жҢҝиӮҳжңЁ(гҒ•гҒ—гҒІгҒҳгҒҚ)
жқұеӨ§еҜәеҚ—еӨ§й–ҖгҒ®ж–ӯйқўеӣігӮ’гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еӯ”гӮ’з©ҝпјҲгҒҶгҒҢпјүгҒЎжҢҝгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖҢжҢҝиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠгҒ«гҖҢж–—гҖҚгӮ’жҚ®гҒҲгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«гҖҢжҹұгҖҚгӮ’иІ«йҖҡгҒ—гҒҰдјёгҒігҒҰгҒҸгӮӢгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгҒҹгҖҢйҖҡиІ«пјҲгҒЁгҒҠгҒ—гҒ¬гҒҚпјүгҖҚгӮ’д№—гҒӣгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҢж–—гҖҚгҒ®вҖҰвҖҰ

жү йҰ–(гҒ•гҒҷ)
еұӢж №гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢе°ҸеұӢзө„гҒ®дёҖгҒ§гҖҒгҖҢж•·жЎҒпјҲиҷ№жўҒпјүгҖҚгҒЁзҷ»жўҒгҒ§гҒӮгӮӢдәҢжң¬гҒ®гҖҢеҗҲжҺҢпјҲжү йҰ–з«ҝпјүгҖҚгҒЁгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢдәҢзӯүиҫәдёүи§’еҪўгҒ®еҚҳзҙ”гҒӘгғҲгғ©гӮ№еҪўејҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҖҢж•·жЎҒгҖҚгҒ«гҖҢжү йҰ–з«ҝгҖҚгҒ®е…Ҳз«ҜгӮ’гҖҒж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҢжү гҒҷпјҲжҢҝгҒҷпјүгҖҚгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—вҖҰвҖҰ

жү йҰ–з«ҝгғ»жү йҰ–жқҹ(гҒ•гҒҷгҒ–гҒҠгғ»гҒ•гҒҷгҒҘгҒӢ)
гҖҖ

ж•·еұ…(гҒ—гҒҚгҒ„)
гҖҖ

жүӢж–§(гҒЎгӮҮгҒҶгҒӘ)

жҠ•жҺӣгҒ‘жўҒ(гҒӘгҒ’гҒӢгҒ‘гҒ°гӮҠ)
е°ҸеұӢжўҒгҒ®дёҖгҖӮжўҒй–“гҒ®дёӯеӨ®д»ҳиҝ‘пјҲжЎҒиЎҢж–№еҗ‘пјүгҒ«йҖҡгҒ—гҒҹж•·жўҒгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҖҒеүҚеҫҢгҒӢгӮүжһ¶гҒ‘гҒҰж•·жўҒдёҠгҒ§з¶ҷгҒҗгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ

жҘЈ(гҒҫгҒҗгҒ•)
гҖҖ
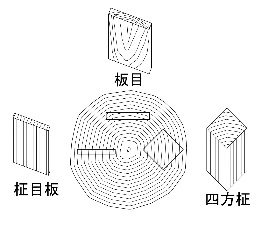
жҹҫзӣ®(гҒҫгҒ•гӮҒ)
жҹҫзӣ®гҒЁгҒҜжңЁжқҗгҒ®з№Ҡз¶ӯгҒҢж–№еҗ‘гҒ«гҒқгӮҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжңЁзӣ®гҒ®йқўгӮ’жҹҫзӣ®гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжңЁжқҗгҒ®дёӯеҝғгҒӢгӮүе№ҙијӘгҒ«зӣҙиЎҢж–№еҗ‘гҒ«жқҝгӮ’гҒЁгӮӢгҒЁжҹҫзӣ®гҒ®жқҝгҒҢеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮжҹұгҒӘгҒ©гҒ§еӣӣйқўгҒҢжҹҫзӣ®гҒ®жңЁзӣ®гӮ’еӣӣж–№жҹҫгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҹҫзӣ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„жңЁзӣ®гӮ’жқҝзӣ®гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

йҒЈйүӢ(гӮ„гӮҠгҒҢгӮ“гҒӘ)
зҸҫд»ЈгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢеҸ°йүӢгҒҢеҮәзҸҫгҒҷгӮӢд»ҘеүҚгҒ®еҸӨд»ЈгҒ®йүӢгҖӮйҒЈйүӢгҒҜжҹ„гҒ®е…ҲгҒ«ж§Қе…ҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲғзү©гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹйүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ®е®®еӨ§е·ҘгҒ®иҘҝеІЎеёёдёҖжЈҹжўҒгҒҢеҶҚзҸҫгҒ—гҒҰе®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҒЈйүӢгҒ§еүҠгҒЈгҒҹеҫҢгҒҜгҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒӘе№ійқўгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҮ№еҮёгҒҢвҖҰвҖҰ

дәҢж–№е·®гҒ—(гҒ«гҒ»гҒҶгҒ•гҒ—)
иғҙе·®гӮ„е·®йҙЁеұ…гӮ„и¶іеӣәгӮҒзӯүгҒ®еӨ§ж–ӯйқўжЁӘжһ¶жқҗгҒЁжҹұгҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡж–№жі•гӮ’иЎЁгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжҹұгҒЁдәҢйқўжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜдәҢж–№е·®гҒ—гҒЁе‘јгҒігҖҒдёүйқўгӮ„еӣӣйқўд»ҘдёҠжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒҜдёүж–№е·®гҒ—гҖҒеӣӣж–№е·®гҒ—гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

иІ«ж§Ӣжі•(гҒ¬гҒҚгҒ“гҒҶгҒ»гҒҶ)
йЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҒ®д»Ҹж•ҷе»әзҜүгҒ®жёЎжқҘгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®й•·гҒ„еҺҹе§ӢгҒ®зң гӮҠгҒӢгӮүгҒ®зӣ®иҰҡгӮҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҪ“жҷӮгҒ®е»әзү©гҒҜгҖҒгҖҢй ӯиІ«пјҲгҒӢгҒ—гӮүгҒ¬гҒҚпјүгҖҚгӮ„гҖҢйЈӣиІ«пјҲгҒІгҒ¬гҒҚпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒҜз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжЁӘеҠӣгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиҖғж…®гҒ—гҒӘгҒ„гҖҒгҖҢжҹұгҖҚвҖҰвҖҰ
е»әзҜү家гғ»и‘—еҗҚдәәгҒ®з”ҹе№ҙиЎЁ
- 1823еӢқжө·иҲҹ
- 1824A.гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҖҒB.гӮ№гғЎгӮҝгғҠ
- 1825еІ©еҖүе…·иҰ–гҖҒпјӘ.гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№в…Ў
- 1826
- 1827е°Ҹж —дёҠйҮҺд»Ӣеҝ й Ҷ
- 1828иҘҝйғ·йҡҶзӣӣ
- 1829з«Ӣзҹіжё…йҮҚ
- еӨ©дҝқе…ғе№ҙ1830еӨ§д№…дҝқеҲ©йҖҡгҖҒеҗүз”°жқҫйҷ°
- 1831еӯқжҳҺеӨ©зҡҮ
- 1832
- 1833жңЁжҲёеӯқе…ҒгҖҒY.гғ–гғ©гғјгғ гӮ№
- 1834иҝ‘и—ӨеӢҮгҖҒE.гғүгӮ¬
- 1835еІ©пЁ‘ејҘеӨӘйғҺгҖҒзҰҸжІўи«ӯеҗүгҖҒеңҹж–№жӯідёүгҖҒC.C.гӮөгғігӮөгғјгғігӮ№
- 1836дә”д»ЈеҸӢеҺҡгҖҒеқӮжң¬йҫҚйҰ¬
- 1837еҫіе·қж…¶е–ңгҖҒжқҝеһЈйҖҖеҠ©
- 1838еӨ§йҡҲйҮҚдҝЎгҖҒеұұзёЈжңүжңӢгҖҒT.B.гӮ°гғ©гғҗгғј
- 1839E.A.гғҗгӮ№гғҶгӮЈгӮўгғігҖҒP.гӮ»гӮ¶гғігғҢгҖҒй«ҳжқүжҷӢдҪңгҖҒB.гғ“гӮјгғјгҖҒM.гғ гӮҪгғ«гӮ°гӮ№гӮӯгғј
- 1840жёӢжІўж „дёҖгҖҒC.гғўгғҚгҖҒP.гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҖҒA.гғӯгғҖгғі
- 1841дјҠи—ӨеҚҡж–ҮгҖҒP.A.гғ«гғҺгӮўгғјгғ«гҖҒA.гғүгғҙгӮ©гғ«гӮ¶гғјгӮҜ
- 1842T.гӮҰгӮ©гғјгғҲгғ«гӮ№
- 1843D.C.гӮ°гғӘгғјгғігҖҒE.гӮ°гғӘгғјгӮ°
- ејҳеҢ–е…ғе№ҙ1844H.гғ«гӮҪгғјгҖҒR.гӮігғ«гӮөгӮігғ•
- 1845G.гғ•гӮ©гғјгғ¬
- 1846W.R.гғҹгғјгғү
- 1847C.F.гғһгғғгӮӯгғ гҖҒT.гӮЁгӮёгӮҪгғі
- еҳүж°ёе…ғе№ҙ1848P.гӮҙгғјгӮ®гғЈгғі
- 1849иҘҝең’еҜәе…¬жңӣ
- 1850
- 1851
- 1852гӮёгғ§гӮөгӮӨгӮўгғ»гӮігғігғүгғ«гҖҒжҳҺжІ»еӨ©зҡҮгҖҒгӮўгғігғҲдәҢгғ»гӮ¬гӮҰгғҮгӮЈ
- 1853жӣҪзҰ°йҒ”и”өгҖҒзүҮеұұжқұзҶҠгҖҒS.гғӣгғҜгӮӨгғҲгҖҒV.V.гӮҙгғғгғӣгҖҒгғ•гӮ§гғҺгғӯгӮөгҖҒеҢ—йҮҢжҹҙдёүйғҺ
- е®үж”ҝе…ғе№ҙ1854иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫгҖҒR.гӮјгғјгғ«
- 1855
- 1856жІіеҗҲжө©и”өгҖҒдҪҗз«Ӣдёғж¬ЎйғҺгҖҒжө…дә•еҝ гҖҒL.гӮөгғӘгғҙгӮЎгғі
- 1857J.гӮ¬гғјгғҮгӮЈгғҠгғјгҖҒ新家еӯқжӯЈгҖҒE.W.гӮЁгғ«гӮ¬гғј
- 1858еұұеҸЈеҚҠе…ӯгҖҒJ.гғ—гғғгғҒгғјгғӢ
- 1859еҰ»жңЁй јй»„гҖҒеқӘеҶ…йҖҚйҒҘ
- дёҮ延е…ғе№ҙ1860A.гғҹгғҘгӮ·гғЈгҖҒG.гғһгғјгғ©гғјгҖҒI.гғ‘гғҮгғ¬гғ•гӮ№гӮӯгғј
- ж–Үд№…е…ғе№ҙ1861R.гӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғҠгғј
- 1862G.гӮҜгғӘгғ гғҲгҖҒC.гғүгғ“гғҘгғғгӮ·гғјгҖҒжЈ®йҙҺеӨ–гҖҒеІЎеҖүеӨ©еҝғ
- 1863иҢӮеә„дә”йғҺгҖҒи‘ӣиҘҝиҗ¬еҸёгҖҒE.гғ гғігӮҜ
- е…ғжІ»е…ғе№ҙ1864жЁӘжІіж°‘иј”гҖҒе®—е…өи”өгҖҒR.гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№
- ж…¶еҝңе…ғе№ҙ1865гғўгӮӨгӮ»гӮӨжІіжқ‘дјҠи”өгҖҒJ.гӮ·гғҷгғӘгӮҰгӮ№
- 1866йҒ и—Өж–јиҸҹгҖҒR.гӮЁгӮ№гғҲгғҷгғӘгҖҒW.гӮ«гғігғҮгӮЈгғігӮ№гӮӯгғјгҖҒE.гӮөгғҶгӮЈгҖҒеӯ«ж–Ү
- 1867й•·йҮҺе®Үе№іжІ»гҖҒгғ•гғ©гғігӮҜгғ»гғӯгӮӨгғүгғ»гғ©гӮӨгғҲгҖҒдјҠжқұеҝ еӨӘгҖҒеӨҸзӣ®жјұзҹігҖҒжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҒе№ёз”°йңІдјҙгҖҒE.гӮ°гғ©гғҠгғүгӮ№гҖҒA.гғҲгӮ№гӮ«гғӢгғјгғӢ
- жҳҺжІ»е…ғе№ҙ1868еұұдёӢе•“ж¬ЎйғҺгҖҒдёӯжўқзІҫдёҖйғҺгҖҒC.R.гғһгғғгӮӯгғігғҲгғғгӮ·гғҘгҖҒP.гғҷгғјгғ¬гғігӮ№гҖҒе°ҫеҙҺзҙ…и‘үгҖҒеҺҹдёүжё“
- 1869йҮҺеҸЈеӯ«еёӮгҖҒзҹўж©ӢиіўеҗүгҖҒжЈ®еұұжқҫд№ӢеҠ©гҖҒH.гғһгғҶгӮЈгӮ№
- 1870йҲҙжңЁзҰҺж¬ЎгҖҒжЎңдә•е°ҸеӨӘйғҺгҖҒгӮўгғүгғ«гғ•гғ»гғӯгғјгӮ№гҖҒиҘҝз”°е№ҫеӨҡйғҺгҖҒйҲҙжңЁеӨ§жӢҷгҖҒV.гғ¬гғјгғӢгғі
- 1871еӣҪжңЁз”°зӢ¬жӯ©гҖҒJ.W.гғЎгғігӮІгғ«гғҷгғ«гӮҜ
- 1872жӯҰз”°дә”дёҖгҖҒG.D.гғ©гғ©гғігғҮгҖҒP.гғўгғігғүгғӘгӮўгғігҖҒеі¶еҙҺи—Өжқ‘гҖҒжЁӢеҸЈдёҖи‘ү
- 1873жқҫе®ӨйҮҚе…үгҖҒе°Ҹжһ—дёҖдёүгҖҒS.гғ©гғ•гғһгғӢгғҺгғ•гҖҒдёҺи¬қйҮҺйү„е№№
- 1874A.гӮ·гӮ§гғјгғігғҷгғ«гӮҜгҖҒW.гғҒгғЈгғјгғҒгғ«
- 1875ж—Ҙй«ҳиғ–гҖҒжҹіз”°еңӢз”·гҖҒM.гғ©гғҙгӮ§гғ«гҖҒF.гӮҜгғ©гӮӨгӮ№гғ©гғј
- 1876зүҮеІЎе®үгҖҒйҮҺеҸЈиӢұдё–гҖҒB.гғҜгғ«гӮҝгғјгҖҒP.гӮ«гӮ¶гғ«гӮ№
- 1877еӨ§зҶҠе–ңйӮҰгҖҒдҝқеІЎеӢқд№ҹгҖҒH.K.гғһгғјгғ•гӮЈгғј
- 1878дҪҗи—ӨеҠҹдёҖгҖҒдёҺи¬қйҮҺжҷ¶еӯҗгҖҒI.гӮ№гӮҝгғјгғӘгғі
- 1879еҗүжӯҰй•·дёҖгҖҒеңӢжһқеҚҡгҖҒз”°иҫәж·іеҗүгҖҒеӨ§жұҹж–°еӨӘйғҺгҖҒж°ёдә•иҚ·йўЁгҖҒж»қе»үеӨӘйғҺгҖҒA.гӮўгӮӨгғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҖҒO.гғ¬гӮ№гғ”гғјгӮ®гҖҒP.гӮҜгғ¬гғјгҖҒеӨ§жӯЈеӨ©зҡҮ
- 1880B.гӮҝгӮҰгғҲгҖҒW.гғҙгӮ©гғјгғӘгӮәгҖҒдҪҗйҮҺеҲ©еҷЁгҖҒи‘ӣйҮҺеЈ®дёҖйғҺгҖҒдёӯжқ‘ијҝиіҮе№ігҖҒжұҹе·қдёүйғҺе…«
- 1881зҪ®еЎ©з« гҖҒP.гғ”гӮ«гӮҪгҖҒB.гғҗгғ«гғҲгғјгӮҜ
- 1882д№…йҮҺзҜҖгҖҒжң¬йҮҺзІҫеҗҫгҖҒе°Ҹе·қе®үдёҖйғҺгҖҒйқ’жңЁз№ҒгҖҒI.гӮ№гғҲгғ©гғҙгӮЈгғігӮ№гӮӯгғјгҖҒF.гғ«гғјгӮәгғҷгғ«гғҲ
- 1883еІЎз”°дҝЎдёҖйғҺгҖҒйҳҝйғЁзҫҺжЁ№еҝ—гҖҒW.гӮ°гғӯгғ”гӮҰгӮ№гҖҒеҝ—иіҖзӣҙе“үгҖҒV.гӮҝгғјгғӘгғ’гҖҒB.гғ гғғгӮҪгғӘгғјгғӢ
- 1884жңЁеӯҗдёғйғҺгҖҒжёЎйӮҠзҜҖгҖҒе®үдә•жӯҰйӣ„гҖҒиҘҝжқ‘дјҠдҪңгҖҒи–¬её«еҜәдё»иЁҲгҖҒеұұз”°йҶҮгҖҒM.гғўгғҮгӮЈгғӘгӮўгғӢ
- 1885еҶ…з”°зҘҘдёүгҖҒй•·и°·йғЁйӢӯеҗүгҖҒжіўжұҹжӮҢеӨ«гҖҒE.G.гӮўгӮ№гғ—гғ«гғігғүгҖҒжӯҰиҖ…е°Ҹи·Ҝе®ҹзҜӨ
- 1886еҶ…и—ӨеӨҡд»ІгҖҒгғҹгғјгӮ№гғ»гғ•гӮЎгғігғ»гғҮгғ«гғ»гғӯгғјгӮЁгҖҒиҘҝжқ‘еҘҪжҷӮгҖҒзҹіе·қе•„жңЁгҖҒеұұз”°иҖ•дҪңгҖҒи°·еҙҺжҪӨдёҖйғҺгҖҒW.гғ•гғ«гғҲгғҙгӮ§гғігӮ°гғ©гғј
- 1887жёЎиҫәд»ҒгҖҒгғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§гҖҒE.гғЎгғігғҮгғ«гӮҫгғјгғігҖҒM.гӮ·гғЈгӮ¬гғјгғ«гҖҒе°ҸеҮәжҘўйҮҚгҖҒA.гғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҖҒи’Ӣд»Ӣзҹі
- 1888A.гғ¬гғјгғўгғігғүгҖҒи—Өдә•еҺҡдәҢгҖҒзҹўйғЁеҸҲеҗүгҖҒG.T.гғӘгғјгғҲгғ•гӮ§гғ«гғҲгҖҒеұұдёӢеҜҝйғҺгҖҒз«№и…°е»әйҖ гҖҒJ.V.W.гғҗгғјгӮ¬гғҹдәҢвҖ•гҖҒд»Ҡе’Ңж¬ЎйғҺгҖҒA.гӮөгғігғҶгғӘгӮўгҖҒG.D.гӮӯгғӘгӮігҖҒиҸҠжұ еҜӣгҖҒд№қй¬је‘ЁйҖ гҖҒF.гғ©гӮӨгғҠгғј
- 1889йҒ и—Өж–°гҖҒеұұе·қйҖёйғҺгҖҒ笹е·қж…ҺдёҖгҖҒL.гғҙгӮЈгғҲгӮІгғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҖҒе’Ңиҫ»е“ІйғҺгҖҒA.гғ’гғҲгғ©гғј
- 1890е°Ҹжһ—жӯЈзҙ№гҖҒдёӯжқ‘йҺ®гҖҒE.гӮ·гғјгғ¬гҖҒE.гӮҜгғ©гӮӨгғҗгғј
- 1891жқ‘йҮҺи—ӨеҗҫгҖҒйҮҺз”°дҝҠеҪҰгҖҒгӮёгӮӘгғ»гғқгғігғҶгӮЈгҖҒS.гғ—гғӯгӮігғ•гӮЈгӮЁгғ•гҖҒC.гғҹгғігӮ·гғҘгҖҒиҝ‘иЎӣж–Үйәҝ
- 1892й«ҳж©ӢиІһеӨӘйғҺгҖҒжң¬й–“д№ҷеҪҰгҖҒеҸӨеЎҡжӯЈжІ»гҖҒеүҚз”°еҒҘдәҢйғҺгҖҒR.гғҺгӮӨгғҲгғ©гҖҒиҠҘе·қйҫҚд№Ӣд»Ӣ
- 1893еІ©пЁ‘е№іеӨӘйғҺгҖҒеІ©жң¬зҰ„гҖҒC.гӮҜгғ©гӮҰгӮ№гҖҒжҜӣжІўжқұ
- 1894еҗүз”°дә”еҚҒе…«гҖҒеҗүз”°йү„йғҺгҖҒеұұз”°е®ҲгҖҒзҹіжң¬е–ңд№…жІ»гҖҒе№іжһ—йҮ‘еҗҫгҖҒе№іжқҫиӢұеҪҰгҖҒP.гҒёгғӢгғігӮ°гӮ»гғігҖҒK.гғҷгғјгғ
- 1895д»Ҡдә•е…јж¬ЎгҖҒжё…ж°ҙиӢұдәҢгҖҒе ҖеҸЈжҚЁе·ұгҖҒи”өз”°е‘Ёеҝ гҖҒжЈ®з”°ж…¶дёҖ
- 1896дјҠи—ӨжӯЈж–ҮгҖҒйҮҚжЈ®дёүзҺІгҖҒе®®жІўиіўжІ»
- 1897еңҹжөҰдәҖеҹҺгҖҒжұ з”°и°·д№…еҗүгҖҒG.гӮ»гғ«
- 1898гӮўгғ«гғҙгӮЎвҖ•гғ»гӮўгӮўгғ«гғҲгҖҒM.гӮігғғгғӣ
- 1899еІёз”°ж—ҘеҮәеҲҖгҖҒдҪҗи—ӨжӯҰеӨ«гҖҒе·қз«Ҝеә·жҲҗ
- 1900еӨ§еҖүдёүйғҺ
- 1901еқӮеҖүжә–дёүгҖҒгғ«гӮӨгӮ№гғ»гӮ«гғјгғігҖҒпј№.гғҸгӮӨгғ•гӮ§гғғгғ„гҖҒжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮ
- 1902еұұеҸЈж–ҮиұЎгҖҒгғ«гӮӨгӮ№гғ»гғҗгғ©гӮ¬гғігҖҒM.гғ–гғӯгӮӨгғӨгғјгҖҒA.гғӨгӮігғ–гӮ»гғі
- 1903жЈҹж–№еҝ—еҠҹгҖҒйҮ‘еӯҗгҒҝгҒҷгӮһгҖҒA.гғҸгғҒгғЈгғҲгӮҘгғӘгӮўгғігҖҒV.гғӣгғӯгғҙгӮЈгғғгғ„гҖҒE.гғ гғ©гғҙгӮЈгғігӮ№гӮӯгғј
- 1904и°·еҸЈеҗүйғҺгҖҒG.гғҶгғ©гғјдәҢгҖҒS.гғҖгғӘгҖҒе Җиҫ°йӣ„
- 1905зҷҪдә•жҷҹдёҖгҖҒеүҚе·қеңӢз”·гҖҒA.гӮ·гғҘгғҡгғјгӮўгҖҒA.гӮҜгғӘгғҘгӮӨгӮҝгғігӮ№
- 1906гӮ«гғ«гғӯгғ»гӮ№гӮ«гғ«гғ‘гҖҒP.гӮёгғ§гғігӮҪгғігҖҒD.гӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғғгғҒ
- 1907B.гғһгғғгғҲгӮҪгғігҖҒC.гӮӨгғјгғ гӮәгҖҒдёӯеҺҹдёӯд№ҹгҖҒж№Ҝе·қз§ҖжЁ№
- 1908еҗүжқ‘й ҶдёүгҖҒжқұеұұйӯҒеӨ·гҖҒH.V.гӮ«гғ©гғӨгғігҖҒD.гӮӘгӮӨгӮ№гғҲгғ©гғ•/span>
- 1909жөҰиҫәйҺ®еӨӘйғҺгҖҒеӨӘе®°жІ»гҖҒеҸӨй–ўиЈ•иҖҢ
- 1910E.гӮөгғјгғӘгғҚгғігҖҒй»’жҫӨжҳҺгҖҒR.гӮұгғігғҡ
- еӨ§жӯЈе…ғе№ҙ1911жЈ®жңүжӯЈ
- 1912гғҹгғҺгғ«гғ»гғӨгғһгӮөгӮӯгҖҒгғ•гӮЈгғігғ»гғҰгғјгғ«гҖҒеүЈжҢҒеӢҮ
- 1913дё№дёӢеҒҘдёүгҖҒеІ©жң¬еҚҡиЎҢгҖҒеӨ§жұҹе®ҸгҖҒE.B.гғ–гғӘгғҲгӮҘгғі
- 1914еў—з”°еҸӢд№ҹгҖҒз«ӢеҺҹйҒ“йҖ гҖҒH.гӮҰгӮ§гӮ°гғҠгғј
- 1915иҘҝжҫӨж–ҮйҡҶгҖҒH.гғҷгғ«гғҲгӮӨгғӨгғјгҖҒжҹіе®—зҗҶгҖҒS.гғӘгғ’гғҶгғ«
- 1916
- 1917еҗүйҳӘйҡҶжӯЈгҖҒI.M.гғҡгӮӨгҖҒD.гғӘгғ‘гғғгғҶгӮЈ
- 1918清家清гҖҒиҠҰеҺҹзҫ©дҝЎгҖҒеӨ©йҮҺеӨӘйғҺгҖҒP.гғ«гғүгғ«гғ•гҖҒL.гғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғі
- 1919P.гӮҪгғ¬гғӘ
- 1920жұ иҫәйҷҪгҖҒR.гӮёгғ§гӮҙгғ©гҖҒB.гғҹгӮұгғ©гғігӮёгӮ§гғӘ
- 1921й•·еӨ§дҪңгҖҒA.гғһгғігӮёгӮ§гғӯгғғгғҶгӮЈ
- 1922еәғзҖ¬йҺҢдәҢгҖҒзҹідә•дҝ®
- 1923еӨ§й«ҳжӯЈдәә
- 1924еӨ§и°·е№ёеӨ«гҖҒй«ҳж©Ӣйқ—дёҖгҖҒжЁӘеұұе…¬з”·гҖҒе®үеҖҚе…¬жҲҝгҖҒK.гғҺгғјгғ©гғігғү
- 1925еў—жІўжҙөгҖҒзҜ еҺҹдёҖз”·гҖҒеҶ…з”°зҘҘе“үгҖҒеұұжң¬еҝ еҸёгҖҒC.гғ гғјгӮўгҖҒR.гғҙгӮ§гғігғҒгғҘгғјгғӘгҖҒдёүеі¶з”ұзҙҖеӨ«
- жҳӯе’Ңе…ғе№ҙ1926й¬јй ӯжў“гҖҒJ.гӮ№гӮҝгғјгғӘгғігӮ°
- 1927еұұжң¬еҝ й•·гҖҒдёӯжқ‘жҳҢз”ҹгҖҒM.гғӯгӮ№гғҲгғӯгғқгғјгғҙгӮЈгғғгғҒ
- 1928иҸҠз«№жё…иЁ“гҖҒж§Үж–ҮеҪҰгҖҒжұ еҺҹзҫ©йғҺгҖҒжһ—йӣ…еӯҗгҖҒжһ—жҳҢдәҢгҖҒжұ еҺҹзҫ©йғҺгҖҒеІЎз”°ж–°дёҖгҖҒйҳӘз”°иӘ йҖ гҖҒS.гғ«гӮҰгӮЈгғғгғҲ
- 1929йҷҚзұҸе»ЈдҝЎ
- 1930C.гӮҜгғ©гӮӨгғҗгғјгҖҒжӯҰжәҖеҫ№
- 1931зЈҜеҙҺж–°гҖҒеҮәжұҹеҜӣгҖҒжӯҰи—Өз« гҖҒгӮўгғ«гғүгғ»гғӯгғғгӮ·
- 1932е·қеҙҺжё…
- 1933еҶ…дә•жҳӯи”өгҖҒжқұеӯқе…үгҖҒе№іжҲҗеӨ©зҡҮ
- 1934й»’е·қзҙҖз«
- 1935еұұеҙҺеә·еӯқгҖҒжҹіжІўеӯқеҪҰгҖҒеӨ§жұҹеҒҘдёүйғҺгҖҒе°ҸжҫӨеҫҒзҲҫ
- 1936еҺҹеәғеҸёгҖҒе®®и„ҮжӘҖгҖҒC.гӮўгғ¬гӮ°гӮ¶гғігғҖгғј
- 1937йҰҷеұұеЈҪеӨ«гҖҒи—Өжң¬жҳҢд№ҹгҖҒеұұдёӢе’ҢжӯЈ
- 1938жёЎиҫәиұҠе’Ң
- 1939
- 1940зӣҠеӯҗзҫ©ејҳгҖҒе®ӨдјҸж¬ЎйғҺ
- 1941е®үи—Өеҝ йӣ„гҖҒдјҠжқұиұҠйӣ„гҖҒй»’жІўйҡҶгҖҒж—©е·қйӮҰеӨ«гҖҒе…ӯи§’й¬јдёҲгҖҒж°ёз”°жҳҢж°‘
- 1942M.гғқгғӘгғјгғӢ
- 1943й»’е·қе“ІйғҺгҖҒеқӮжң¬дёҖжҲҗ
- 1944
- 1945жқ‘з”°йқ–еӨ«гҖҒеұұжң¬зҗҶйЎ•
- 1946и—ӨжЈ®з…§дҝЎ