ÕŹŚµĄĘķø╗ķēäķ½śķćÄńĘÜ(µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗ’Į×Õ▓ĖķćīńÄēÕć║’╝ē
-

µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ
µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ

µśŁÕÆī20(1945)Õ╣┤µł”ńüĮŃĆüµśŁÕÆī24Õ╣┤Ńü½µł”ńüĮÕŠ®µŚ¦ÕĘźõ║ŗń½ŻÕĘźŃĆüµśŁÕÆī31Õ╣┤Ńü½µö╣ń»ēÕ«īµłÉŃü«Ķ©śķī▓Ńüīµ«ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ
ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ

ķ½śķćÄķēäķüōķ¢ŗµźŁ12Õ╣┤ÕŠīŃü«Õż¦µŁŻÕģāÕ╣┤(1912)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆüķ¦ģÕÉŹŃü»ÕĮōµÖéŃü«µēĆÕ£©Õ£░ÕÉŹŃĆīķøŻµ│óĶŖ”ÕĤńö║ŃĆŹŃüīńö▒µØźŃü©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ
ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ

ķ¦ģŃü«ÕīŚÕü┤Ńü½JRńÆ░ńŖČńĘÜŃü«ķ½śµ×ČŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶŖ”ÕĤµ®ŗķ¦ģŃü©Ńü»300’ĮŹŃü╗Ńü®ķøóŃéīŃéŗŃĆé
-

µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ
µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ

ķ¦ģÕÉŹŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ▓│ÕĘØŃĆīµ£©µ┤źÕĘØŃĆŹŃü»ŃĆüÕ£¤õĮÉÕĀĆÕĘØŃüŗŃéēÕłåÕ▓ÉŃüŚŃü”Õż¦ķś¬µ╣ŠŃü½µ│©ŃüäŃü¦ŃüŖŃéŖŃĆüµ░┤µĘ▒Ńü½µüĄŃüŠŃéīÕÅżŃüÅŃüŗŃéēĶł╣ĶłČŃü«Ķł¬ĶĪīŃüīńøøŃéōŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃĆé

µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ
µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ

Õż¦µŁŻ13Õ╣┤(1924)Ńü½ĶżćńĘÜÕī¢ŃĆüµśŁÕÆī15Õ╣┤(1940)Ńü½µ¢░ķ¦ģĶłÄŃü«õĮ┐ńö©ŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃüŚŃü¤Ńü©Ńü«Ķ©śķī▓ŃüīŃüéŃéŗŃĆé

µ┤źÕ«łķ¦ģ
µ┤źÕ«łķ¦ģ

Õż¦µŁŻ2Õ╣┤(1913)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆéķ¦ģÕÉŹŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕ£░ÕÉŹŃĆīµ┤źÕ«łŃĆŹŃü»ŃĆüÕģāń”äµ£¤Ńü½ķ¢ŗńÖ║ŃüĢŃéīŃü¤ĶĆĢÕ£░ŃĆīµ┤źÕ«łµ¢░ńö░ŃĆŹŃüīńö▒µØźŃü©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé
-

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

ķ½śķćÄńÖ╗Õ▒▒ķēäķüōŃüīÕż¦ķś¬ķ½śķćÄķēäķüōŃü©µö╣ń¦░ŃüŚŃü¤ń┤ä5Ńé½µ£łÕŠīŃü«Õż¦µŁŻ4Õ╣┤(1915)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆé

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ķ¦ģĶłÄŃü«µ¢░Ķ©ŁŃĆüµö╣ń»ēŃü«Ķ©śķī▓ŃüīĶ”ŗÕĮōŃü¤ŃéēŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüķ¢ŗµźŁŃüŚŃü¤Õż¦µŁŻ4Õ╣┤(1915)’╝Öµ£ł18µŚźÕĮōµÖéŃü«ķ¦ģĶłÄŃüīńÅŠÕŁśŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃĆé

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

1924Õ╣┤Ńü½µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗ’Į×µ£©µ┤źÕĘØŃĆü1926Õ╣┤Ńü½Õ▓Ėķćī’Į×Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗŃĆü1930Õ╣┤Ńü½Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗ’Į×µ£©µ┤źÕĘØķ¢ōŃéÆĶżćńĘÜÕī¢ŃĆé

Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗ’╝łÕĘ”’╝ܵ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜ’╝ē
Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗ’╝łÕĘ”’╝ܵ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜ’╝ē

ńÅŠÕ£©Ńü«ńÄēÕć║ÕÅŻõ╗śĶ┐æŃü½ńÄēÕć║ķ¦ģŃüīµśÄµ▓╗40Õ╣┤(1907)ŃĆüµ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜŃü©Ńü«ÕłåÕ▓Éõ╗śĶ┐æŃü½Õ▓ĖŃāÄķćīķ¦ģŃüīÕż¦µŁŻ2Õ╣┤(1913)ķ¢ŗµźŁŃĆé

Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃü«Ńé╣ŃāåŃā│ŃāēŃé░Ńā®Ńé╣
Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃü«Ńé╣ŃāåŃā│ŃāēŃé░Ńā®Ńé╣

ĶÉ®ŃāÄĶīČÕ▒ŗ’Į×ńÄēÕć║ķ¢ōŃü«ķ½śµ×ČÕī¢Ńü½õ╝┤ŃüäŃĆüÕ╣│µłÉ5Õ╣┤(1993)Õ▓ĖŃāÄķćīķ¦ģŃü©ńÄēÕć║ķ¦ģŃéÆń¦╗Ķ©ŁńĄ▒ÕÉłŃüŚŃĆüķ¦ģÕÉŹŃéÆŃĆīÕ▓ĖķćīńÄēÕć║ŃĆŹŃü½Õżēµø┤ŃĆé

µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ
µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ

ÕĮōÕłØŃü«ķ¦ģÕÉŹŃü»ŃĆīķüōķĀōÕĀĆķ¦ģŃĆŹŃüĀŃüŻŃü¤ŃüīŃĆüķ¦ģŃü«ÕīŚÕü┤ŃĆüĶź┐ķüōķĀōÕĀĆÕĘØŃü½µ×ČŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ®ŗŃü«ÕÉŹŃü½ŃüĪŃü¬ŃéōŃü¦ńÅŠÕ£©Ńü«ķ¦ģÕÉŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃĆé

µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ
µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ

µśŁÕÆī20(1945)Õ╣┤µł”ńüĮŃĆüµśŁÕÆī24Õ╣┤Ńü½µł”ńüĮÕŠ®µŚ¦ÕĘźõ║ŗń½ŻÕĘźŃĆüµśŁÕÆī31Õ╣┤Ńü½µö╣ń»ēÕ«īµłÉŃü«Ķ©śķī▓Ńüīµ«ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ
ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ

ķ½śķćÄķēäķüōķ¢ŗµźŁ12Õ╣┤ÕŠīŃü«Õż¦µŁŻÕģāÕ╣┤(1912)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆüķ¦ģÕÉŹŃü»ÕĮōµÖéŃü«µēĆÕ£©Õ£░ÕÉŹŃĆīķøŻµ│óĶŖ”ÕĤńö║ŃĆŹŃüīńö▒µØźŃü©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ
ĶŖ”ÕĤńö║ķ¦ģ

ķ¦ģŃü«ÕīŚÕü┤Ńü½JRńÆ░ńŖČńĘÜŃü«ķ½śµ×ČŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶŖ”ÕĤµ®ŗķ¦ģŃü©Ńü»300’ĮŹŃü╗Ńü®ķøóŃéīŃéŗŃĆé

µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ
µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ

µ░┤ķÖĖķüŗĶ╝ĖŃü«ķĆŻńĄĪŃü«Ķ”üÕ£░Ńü©ŃüŚŃü”ÕĮōÕłØŃéłŃéŖķ¢ŗµźŁŃĆéŃüōŃü«ĶŠ║ŃéŖŃü»ŃĆüĶü¢ÕŠ│Õż¬ÕŁÉŃüīÕøøÕż®ńÄŗÕ»║ŃéÆķĆĀÕ¢ČŃüŚŃü¤ķÜøŃü½ŃĆüĶ½ĖÕøĮŃüŗŃéēńö©µØÉŃéÆķøåń®ŹŃüŚŃü¤ŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆīµ£©µ┤źŃĆŹŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü©ŃüäŃüåŃĆé

µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ
µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ

ķ¦ģÕÉŹŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ▓│ÕĘØŃĆīµ£©µ┤źÕĘØŃĆŹŃü»ŃĆüÕ£¤õĮÉÕĀĆÕĘØŃüŗŃéēÕłåÕ▓ÉŃüŚŃü”Õż¦ķś¬µ╣ŠŃü½µ│©ŃüäŃü¦ŃüŖŃéŖŃĆüµ░┤µĘ▒Ńü½µüĄŃüŠŃéīÕÅżŃüÅŃüŗŃéēĶł╣ĶłČŃü«Ķł¬ĶĪīŃüīńøøŃéōŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃĆé

µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ
µ£©µ┤źÕĘØķ¦ģ

Õż¦µŁŻ13Õ╣┤(1924)Ńü½ĶżćńĘÜÕī¢ŃĆüµśŁÕÆī15Õ╣┤(1940)Ńü½µ¢░ķ¦ģĶłÄŃü«õĮ┐ńö©ŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃüŚŃü¤Ńü©Ńü«Ķ©śķī▓ŃüīŃüéŃéŗŃĆé

µ┤źÕ«łķ¦ģ
µ┤źÕ«łķ¦ģ

Õż¦µŁŻ2Õ╣┤(1913)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆéķ¦ģÕÉŹŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕ£░ÕÉŹŃĆīµ┤źÕ«łŃĆŹŃü»ŃĆüÕģāń”äµ£¤Ńü½ķ¢ŗńÖ║ŃüĢŃéīŃü¤ĶĆĢÕ£░ŃĆīµ┤źÕ«łµ¢░ńö░ŃĆŹŃüīńö▒µØźŃü©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆé

µ┤źÕ«łķ¦ģ
µ┤źÕ«łķ¦ģ

µ┤źÕ«łµ¢░ńö░Ńü«ÕÉŹŃü»ŃĆüÕĮōÕ£░Ķ┐æķÜŻŃü½õ╝صē┐ŃüĢŃéīŃéŗµ┤źÕ«łķĆŻŃĆüµ┤źÕ«łµĄ”ŃĆüŃüŠŃü¤ÕÅżõ╗ŻŃü«Ķź┐µłÉķāĪµ┤źÕ«łķāĘŃü½ŃüĪŃü¬ŃéĆŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃéŗŃüīÕ«ÜŃüŗŃü¦Ńü¬ŃüäŃĆé

µ┤źÕ«łķ¦ģ

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

ķ½śķćÄńÖ╗Õ▒▒ķēäķüōŃüīÕż¦ķś¬ķ½śķćÄķēäķüōŃü©µö╣ń¦░ŃüŚŃü¤ń┤ä5Ńé½µ£łÕŠīŃü«Õż¦µŁŻ4Õ╣┤(1915)Ńü½ķ¢ŗµźŁŃĆé

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ķ¦ģĶłÄŃü«µ¢░Ķ©ŁŃĆüµö╣ń»ēŃü«Ķ©śķī▓ŃüīĶ”ŗÕĮōŃü¤ŃéēŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüķ¢ŗµźŁŃüŚŃü¤Õż¦µŁŻ4Õ╣┤(1915)’╝Öµ£ł18µŚźÕĮōµÖéŃü«ķ¦ģĶłÄŃüīńÅŠÕŁśŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃĆé

Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ
Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗķ¦ģ

1924Õ╣┤Ńü½µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗ’Į×µ£©µ┤źÕĘØŃĆü1926Õ╣┤Ńü½Õ▓Ėķćī’Į×Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗŃĆü1930Õ╣┤Ńü½Ķź┐Õż®õĖŗĶīČÕ▒ŗ’Į×µ£©µ┤źÕĘØķ¢ōŃéÆĶżćńĘÜÕī¢ŃĆé

Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗ’╝łÕĘ”’╝ܵ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜ’╝ē
Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗ’╝łÕĘ”’╝ܵ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜ’╝ē

ńÅŠÕ£©Ńü«ńÄēÕć║ÕÅŻõ╗śĶ┐æŃü½ńÄēÕć║ķ¦ģŃüīµśÄµ▓╗40Õ╣┤(1907)ŃĆüµ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜŃü©Ńü«ÕłåÕ▓Éõ╗śĶ┐æŃü½Õ▓ĖŃāÄķćīķ¦ģŃüīÕż¦µŁŻ2Õ╣┤(1913)ķ¢ŗµźŁŃĆé

Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃü«Ńé╣ŃāåŃā│ŃāēŃé░Ńā®Ńé╣
Õ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģŃü«Ńé╣ŃāåŃā│ŃāēŃé░Ńā®Ńé╣

ĶÉ®ŃāÄĶīČÕ▒ŗ’Į×ńÄēÕć║ķ¢ōŃü«ķ½śµ×ČÕī¢Ńü½õ╝┤ŃüäŃĆüÕ╣│µłÉ5Õ╣┤(1993)Õ▓ĖŃāÄķćīķ¦ģŃü©ńÄēÕć║ķ¦ģŃéÆń¦╗Ķ©ŁńĄ▒ÕÉłŃüŚŃĆüķ¦ģÕÉŹŃéÆŃĆīÕ▓ĖķćīńÄēÕć║ŃĆŹŃü½Õżēµø┤ŃĆé
ÕÉŹń¦░ ÕŹŚµĄĘķø╗ķēäķ½śķćÄńĘÜ(µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗ’Į×Õ▓ĖķćīńÄēÕć║’╝ē/Ńü¬ŃéōŃüŗŃüäŃü¦ŃéōŃü”ŃüżŃüōŃüåŃéäŃüøŃéō µēĆÕ£©Õ£░ TEL/FAX HP https://www.nankai.co.jp/ E-mail Õ╗║ń»ēÕ╣┤õ╗Ż µśÄµ▓╗33Õ╣┤(1900) Õ╗║ńē®ń©«Õłź ńöŻµźŁŃā╗õ║żķĆÜŃā╗Õ£¤µ£© µ¦ŗķĆĀ µ”éĶ”üĶ¬¼µśÄ 通称「汐見橋線」とも呼ばれ、汐見橋駅-岸里玉出駅間の約4.6Kmを運行。明治33年(1900)高野鉄道が大小路駅(現・堺東駅)から道頓堀駅(翌年には汐見橋駅に改称)まで開業。高野山方面への直通運転は汐見橋駅が発着であったが、大正11年(1922)に南海鉄道と合併、大正14年に南海本線と高野線が岸ノ里駅(現・岸里玉出駅)で連絡し難波発着となり、汐見橋線の乗客は激減。かつて和歌山で伐採した木材を鉄道で輸送し木津川駅から近隣の貯木場へ運んだ貨物輸送も昭和46年(1971)に廃止された。汐見橋駅・木津川駅・西天下茶屋駅では、大正・昭和時代に建てられた駅舎が残り、ホーム上屋の構築にはレールが利用されている。
µ¢ćÕī¢Ķ▓Īń©«Õłź ŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃā¬Ńā│Ńé» Ķ”ŗÕŁ” ÕéÖĶĆā 
-
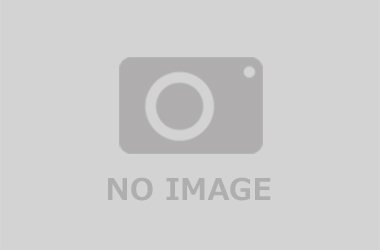
Õ╗║µ░┤Õłåńź×ńżŠ µæéńżŠÕŹŚµ£©ńź×ńżŠŌĆ”
Õ╗║µ░┤Õłåńź×Ńü»Õ╝ÅÕåģńżŠŃü¦ŃĆüµ£¼µ«┐ Ńü»ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü½µīćÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµæéńżŠ Ńü«ÕŹŚµ£©ńź×ńżŠŃü»µźĀµ£©µŁŻµłÉÕģ¼ŃéÆÕŠĪńźŁńź×Ńü©ŃüŚŃĆüµ£¼µ«┐Ńü»µśŁÕÆī’╝æ’╝ōÕ╣┤’╝ł’╝æ’╝Ö’╝ō’╝ś ’╝ēŃü½Õ╗║ń»ēŃüĢŌĆ”
-

ķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ń░Īµ¢ćķż©
ń░Īµ¢ćķż©Ńü»ŃĆü1928Õ╣┤Ńü½Õ╗║ń»ēŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīµŚ¦Õø│µøĖķż©ŃĆŹŃü©ŃĆü1955Õ╣┤Ńü½Õ╗║ń»ēŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīÕååÕĮóÕø│µøĖķż©ŃĆŹŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüńÅŠÕ£©Ńü»ÕŹÜńē®ķż©µ¢ĮĶ©ŁŃü©ŃüŚŃü”õĖĆĶł¼Õģ¼ķ¢ŗŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéŌĆ”
-

ńö¤ķ¦ÆµÖéĶ©łÕ║Ś(ńö¤ķ¦ÆŃāōŃā½ŃāéŃā│Ńé░ŌĆ”
µśŁÕÆīÕłØµ£¤Ńü«ķēäńŁŗŃé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝ŃāłķĆĀõĖŁÕ▒żÕĢåµźŁŃāōŃā½ŃĆéõĖŁÕż«Õī║Õ╣│ķćÄńö║Ńü½µēĆÕ£©ŃĆéõ╗źÕēŹŃü»Õż¦ķś¬Ńü«õĖ╗Ķ”üķüōĶĘ»Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ║ńŁŗŃü©Õ╣│ķćÄńö║ķĆÜŃü«õ║żÕĘ«ńé╣Ńü½ķØóŃüŚŃü”Õ╗║ŃüĪŃĆüµÖéĶ©ł ÕĪö ŌĆ”
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

Õż¦ķś¬Õ║£ń½ŗµĪ£ÕĪÜķ½śńŁēÕŁ”µĀĪÕĪĆ(µŚ¦ŌĆ”
Õż¦ķś¬Õ║£ń½ŗµĪ£ÕĪÜķ½śńŁēÕŁ”µĀĪŃü¦Ńü»µśŁÕÆī’╝ö’╝śÕ╣┤ŃüŗŃéēŃü«µ¢░µĀĪĶłÄÕ╗║Ķ©ŁŃü½Ńü©ŃééŃü¬Ńü䵌¦µĀĪĶłÄŃüīÕÅ¢ŃéŖÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ŃüīŃĆüÕēŹĶ║½Ńü«µŚ¦Ķ▒ŖõĖŁķ½śńŁēÕź│ÕŁ”µĀĪŃüīµśŁÕÆī13Õ╣┤(1938)Ńü½ÕēĄĶ©ŁŌĆ”
-

µ║ÉŃāȵ®ŗµĖ®µ│ēµĄ┤ÕĀ┤
µśŁÕÆī12Õ╣┤’╝ł1937’╝ēŃü½Õ╗║Ńü”ŃéēŃéīŃü¤Õģ¼ĶĪåµĄ┤ÕĀ┤Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéÕĮōÕłØŃü«5Õ╣┤ķ¢ōŃü»ŃĆüõĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃüīŃĆüńÅŠµēƵ£ēĶĆģŃü«ńłČĶ”¬ŃüīŃĆüÕƤÕÅŚŃüæŃü”ÕēĄµźŁŃüĢŃéīŃü¤ŃĆéÕ╗║ńē®Ńü»ŃĆüµ£©ķĆĀŌĆ”
-

õĖŖµ¢░ńö░Õż®ńź×ńżŠµ£¼µ«┐
µŚ¦õĖŖµ¢░ńö░µØæŃü«ķÄ«Õ«łŃü¦ÕŹāķćīŃü«Õż®ńź×ŃüĢŃéōŃü©ŃéłŃü░ŃéīŃéŗŃĆéÕ»øµ░Ė3Õ╣┤(1626)Ńü«õĖŖµ¢░ńö░Ńü«ķ¢ŗńÖ║Ńü©Ńü©ŃééŃü½ÕēĄÕ╗║ŃĆéµ£¼µ«┐Ńü»Ķ▓×õ║½3Õ╣┤(1686)Õ╗║ń½ŗŃü¦ŃĆüõĖĆķ¢ōńżŠµĄüķĆĀŌĆ”
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

µ£½ÕÉēÕ«ČõĮÅÕ«ģõĖ╗Õ▒ŗ
Ķ▒¬ÕĢåŃü«µ£¼Õ«ģŃĆéķĆÜŃéŖŃü½ÕīŚķØóŃüÖŃéŗµ£©ķĆĀÕ╣│Õ▒ŗÕ╗║Ńü¦ŃĆüµĪüĶĪī’╝Ģķ¢ōŃĆüµóüķ¢ō’╝öķ¢ōÕŹŖŃü«ĶĪ©Ńü½Õ║ćŃüīõ╗śŃüÅŃĆéÕłćÕ”╗Õ▒ŗµĀ╣Ńü» µ£¼ńō”Ķæ║ŃĆüÕż¢ÕŻüŃü»Õ£¤ÕŻüŃü¦Ķģ░ŃéÆńĖ”ńŠĮńø«µØ┐Õ╝ĄŃü©ŃüÖŃéŗŃĆéµØ▒Õ”╗Ńü½ŌĆ”
-

Õ░Åµ×Śµ¢░Ķü×ĶłŚÕ║ŚĶłŚÕģ╝õĮÅÕ«ģ
µśŁÕÆī’╝öÕ╣┤’╝ł1929’╝ēŃü«ń½ŻÕĘźŃü¦ŃĆüÕĢåÕ║ŚĶĪŚŃü« ŃéóŃā╝Ńé▒Ńā╝Ńāē Ńü½ÕīŚķØóŃüŚŃü”ŃĆüķēäńŁŗŃé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝Ńāł2ķÜÄŃü«Õ║ŚĶłŚŃü©ŃĆüŃüØŃü«ÕźźŃü½µ£©ķĆĀÕ╣│Õ▒ŗŃü«õĮÅÕ▒ģŃüīµÄźńČÜŃüÖŃéŗŃĆ鵣ŻķØóõĖŁÕż«ŌĆ”
-

ÕŹŚµĄĘķø╗ķēäķ½śķćÄńĘÜ(µ▒ÉĶ”ŗµ®ŗ’Į×Õ▓ĖŌĆ”
ķĆÜń¦░ŃĆīµ▒ÉĶ”ŗµ®ŗńĘÜŃĆŹŃü©ŃééÕæ╝Ńü░ŃéīŃĆüµ▒ÉĶ”ŗµ®ŗķ¦ģ’╝ŹÕ▓ĖķćīńÄēÕć║ķ¦ģķ¢ōŃü«ń┤ä4.6KmŃéÆķüŗĶĪīŃĆ鵜ĵ▓╗33Õ╣┤(1900)ķ½śķćÄķēäķüōŃüīÕż¦Õ░ÅĶĘ»ķ¦ģ(ńÅŠ’ĮźÕĀ║µØ▒ķ¦ģ)ŃüŗŃéēķüōķĀōÕĀĆŌĆ”
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×