
µ£¼ķż©Ńü«Õģ©µÖ»ŃĆĆ’╝łµŁŻķØóŃü½ÕåÖŃéŗŃü«Ńü»ÕŹŚÕīŚµŻ¤’╝ē
µ£¼ķż©Ńü«Õģ©µÖ»ŃĆĆ’╝łµŁŻķØóŃü½ÕåÖŃéŗŃü«Ńü»ÕŹŚÕīŚµŻ¤’╝ē

µ®¤ĶāĮµĆ¦Ńā╗ÕÉłńÉåµĆ¦Ńā╗Õ«¤ńö©µĆ¦ŃéÆĶ┐Įµ▒éŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüÕ£░Õ¤¤Ńü«µĢÖĶé▓ŃéƵŗģŃüåÕŁ”µĀĪÕ╗║ń»ēŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ©üÕÄ│µĆ¦Ńā╗ķćŹÕÄܵƦŃā╗Ķ▒ĪÕŠ┤µĆ¦ŃéÆÕéÖŃüłŃü¤µäÅÕīĀŃü¦ŃüéŃéŗŃĆ鵤▒ŃéÆ’╝ōķÜÄŃüŠŃü¦Õż¢ÕŻüŃü½ķ£▓Õć║ŃüĢŃüøŃĆüµ£ĆõĖŖķā©Ńü«ŃāæŃā®ŃāÜŃāāŃāłŃéÆÕ╣ģÕ║āŃüÅÕĖ»ńŖČŃü½Ńü©ŃéŖŃĆüÕŻüķØóŃéłŃéŖŃééŃüøŃéŖÕć║ŃüŚŃü”µ░┤Õ╣│µ¢╣ÕÉæŃü«Õ║āŃüīŃéŖŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńÄäķ¢óŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬õĖĖń¬ōŃéÆŃüżŃüæŃĆüĶ╗ŖÕ»äŃüøŃü«µ¤▒Ńü»Õå嵤▒Ńü©ŃüŚŃĆüŃéóŃé»Ńé╗Ńā│ŃāłŃéÆŃüżŃüæŃü”ŃüäŃéŗŃĆé
Õż¦ķś¬Õ║£ń½ŗÕøøµóØńĢĘķ½śńŁēÕŁ”µĀĪµ£¼ķż©
-

ÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤
ÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤

µĢÖÕ«żŃā╗Õ╗ŖõĖŗŃü«Õć╣ÕćĖŃéÆŃü¬ŃüÅŃüŚŃĆüµ¤▒ŃéÆ’╝ōķÜÄŃüŠŃü¦Õż¢ķā©Ńü½ķ£▓Õć║ŃĆüń£¤ÕŻüķĆĀŃéŖķó©Ńü©ŃüŚŃĆüÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü»ŃĆüĶ”ŗõ╗śŃüæŃü«ń┤░Ńüäķ╗ÆÕĪŚŃéŖŃü«’ĮĮ’Šü’Į░’ŠÖ’Į╗’Į»’Į╝ŃüÖŃü╣ŃéŖÕć║ŃüŚŃü«ńĖ”ķĢĘń¬ō’╝łńÅŠÕ£©Ńü»’Į▒’ŠÖ’ŠÉ’Į╗’Į»’Į╝Õ╝ĢķüĢŃü½µö╣õ┐«’╝ēŃü¦Õ×éńø┤Ńü«ńĘÜŃéÆÕżÜńö©ŃüŚń½ŗõĮōµä¤ŃéÆÕć║ŃüÖŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüķ½śŃüĢŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃĆéÕĪöÕ▒ŗķā©ÕłåŃü½Ńü»ŃĆüŃéóŃé»Ńé╗Ńā│ŃāłŃü©Ńü¬ŃéŗŃéóŃā╝ŃāüńŖČŃü«ń¬ōŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕż¢ķā©ŃĆĆĶ╗ŖÕ»äŃüøķā©Õłå
ńÄäķ¢óÕż¢ķā©ŃĆĆĶ╗ŖÕ»äŃüøķā©Õłå

ńÄäķ¢óÕåģŃā╗Õż¢ķā©Ńü«ÕŻüķØóŃü»ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣ĶŻĮŃü«Ńé┐ŃéżŃā½ŃüīĶ▓╝ŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüµö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦µ¢░Ńü¤Ńü½ńä╝ŃüŹńø┤ŃüŚŃü¤ŃééŃü«ŃéÆõĮ┐ńö©ŃĆéŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃééŃāÉŃā¬ŃéóŃāĢŃā¬Ńā╝Ńü½µö╣õ┐«ŃĆüÕ║ŖŃü«õĖĆÕ░║Ķ¦ÆŃü«ĶŖ▒Õ┤ŚÕ▓®Ńü»ÕåŹÕł®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéõĖĖń¬ōŃü«õĖŗŃü«ÕŹŖÕååÕĮóŃü«ķēäµĀ╝ÕŁÉŃü»ŃĆüõĮōĶé▓ŃéÆĶŻĖĶČ│Ńü¦ĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¤µÖéõ╗ŻŃü«ĶČ│µ┤ŚŃüäÕĀ┤Ńü«ÕÉŹµ«ŗŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéõ╗ŖŃü»ŃééŃüåµ®¤ĶāĮŃüŚŃü¬ŃüäŃüīŃĆüŃāÜŃāĆŃā½ŃéÆĶĖÅŃéĆŃü©µ░┤ŃüīÕć║Ńéŗõ╗ĢńĄäŃü┐ŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆé

ńÄäķ¢óÕåģķā©
ńÄäķ¢óÕåģķā©

õĖĖń¬ōŃü»ŃéóŃā½Ńā¤ŃéĄŃāāŃéĘŃü½µö╣õ┐«ŃüĢŃéīŃü¤ŃüīŃĆüńÄäķ¢óŃü«µ×ĀŃü©ŃāüŃā╝Ń黵ØÉŃü«µēēŃĆüÕ║ŖŃü«Ńé┐ŃéżŃā½Ńü©õĖŖŃéŖµĪåŃĆüÕ╗ŖõĖŗŃü«Õ║ŖŃü«ń£¤ķŹ«ńø«Õ£░ŃéÆÕ¤ŗŃéüĶŠ╝ŃéōŃüĀõ║║ķĆĀń¤│ńĀöÕć║Ńü»Õ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü«ŃüŠŃüŠŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéõĖĖń¬ōŃü©ńÄäķ¢óŃüŗŃéēķŻ»ńøøÕ▒▒Ńüīµ£øŃéüŃéŗŃéłŃüåŃü½Ķ©ŁĶ©łŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµ¼äķ¢ōŃü«Ńé¼Ńā®Ńé╣Ńü©ŃĆüÕźź’╝Ƶ×ÜŃü«µēēŃü«’╝öķÜģŃüīķØóÕÅ¢ŃéŖŃüĢŃéīŃü¤ÕÄܵØ┐Ńé¼Ńā®Ńé╣ŃééÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆé
-

ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕīŚµŻ¤2EÕ╗ŖõĖŗ
ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕīŚµŻ¤2EÕ╗ŖõĖŗ

Õż®õ║ĢŃü«µóüŃéäķ¢ōõ╗ĢÕłćÕŻüŃü«ŃéóŃā╝ŃāüŃü«ÕĮóńŖČŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüķÜĵ«ĄŃü«µēŗµæ║ÕŻüŃéäń¼Āµ£©ķā©ÕłåŃü½Ńééµø▓ńĘÜŃüīńö©ŃüäŃéēŃéīŃĆüÕż¢ķā©Ńü«ńø┤ńĘÜńÜäŃü¬ŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüÕåģķā©Ńü»Õä¬ńŠÄŃüĢŃéƵä¤ŃüśŃüĢŃüøŃéŗŃĆéķÜĵ«ĄŃüŗŃéēµēŗÕēŹŃüīõĖƵ£¤ÕĘźõ║ŗķā©ÕłåŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéÕ╣│µłÉŃü«µö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦ŃĆü’╝ÆķÜÄŃā╗’╝ōķÜÄŃü«Õ║ŖŃüīķģŹńĘÜŃā╗ķģŹń«ĪŃü«Ńü¤ŃéüŃüŗŃüĢõĖŖŃüÆŃüĢŃéīŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüØŃü«ÕłåŃĆüÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃéłŃéŖŃééÕż®õ║Ģķ½śŃüĢŃüīõĮÄŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü«ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«ż
ÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü«ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«ż

õĖƵ£¤ÕĘźõ║ŗŃü¦Õ«īµłÉŃüŚŃü¤ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«żŃü»’╝ÆķÜÄÕīŚĶź┐Ńü½ŃüéŃéŖŃĆü’╝ōķÜÄķā©ÕłåŃéÆÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéÕīŚÕü┤Ńü«ķ¢ŗÕÅŻŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅŃü©ŃéŖŃĆüÕ«ēÕ«ÜŃüŚŃü¤ÕģēŃéÆÕÅ¢ŃéŖÕģźŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńŠÄĶĪōŃéóŃāłŃā¬Ńé©ŃéÆÕ╝ĘŃüŵäÅĶŁśŃüŚŃü¤Ķ©ŁĶ©łŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüõĖĆķā©Ńü«Õ░éķ¢ĆĶ¬▓ń©ŗŃéÆķÖżŃüäŃü”ŃĆüŃüōŃü«ń®║ķ¢ōŃü«Ķ▒ŖŃüŗŃüĢŃü»ÕĮōµÖéŃü¦Ńü»Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®õŠŗŃéÆĶ”ŗŃü¬ŃüäŃééŃü«ŃüĀŃüŻŃü¤Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃĆéµĪ£Ńü«µÖéµ£¤Ńü»ń¬ōŃüīĶŖ▒Ńü½ŃüŖŃüŖŃéÅŃéīŃü”ńŠÄŃüŚŃüäŃĆé

ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆĆ’╝ÆķÜĵØ▒ń½»Ńü«µĢÖÕ«ż
ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆĆ’╝ÆķÜĵØ▒ń½»Ńü«µĢÖÕ«ż

µĢÖÕ«żŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃü»ŃĆü’╝öķ¢ōX’╝Ģķ¢ōŃéÆÕ¤║µ£¼Ńü½ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéÕ«żÕåģŃü»ń¤│ĶåÅŃāŚŃā®Ńé╣Ńé┐Ńā╝õ╗ĢõĖŖŃüÆŃü©ŃüŚŃĆüŃé╣Ńā®Ńā¢ŃéäµóüÕ×ŗŃü½ńø┤µÄźÕĪŚŃéŖõĖŖŃüÆŃü”ŃüäŃü¤ŃĆéµóüŃü»µ¤▒Ńü«õ╗śŃüæµĀ╣Ńü¦ŃāÅŃā│ŃāüŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅŃü©ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦Õ║ŖŃéÆŃüŗŃüĢõĖŖŃüÆŃüŚŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüń¬ōõĖŗń½»ŃüīõĮÄŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµØ▒Õü┤Ńü«ń¬ōŃüŗŃéēŃü»ŃĆüķŻ»ńøøÕ▒▒ŃüīĶ”ŗŃüłŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕēŹŃü«µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆé
ńÄäķ¢óÕēŹŃü«µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆé

ńĘæĶ▒ŖŃüŗŃü¬Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆéÕÅ│µēŗŃü»ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆéµ£¼ķż©Ńü«Ķ©łńö╗µÖéŃü½Ńü»Õ║£Ńü«Ķ▓Īµö┐ķøŻŃü«ńŖȵ│üõĖŗŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńü¤ŃéüŃü½ŃĆüńĄÉµ×£Ńü©ŃüŚŃü”Ńé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝ŃāłŃü«ÕŹśń┤öŃüĢŃéÆŃüØŃü«ŃüŠŃüŠÕĮóŃü½ŃüŚŃĆüµ®¤ĶāĮŃü©µ¦ŗķĆĀŃüīń┤Āńø┤Ńü½Õż¢Ķ”│Ńü½ĶĪ©ńÅŠŃüĢŃéīŃü¤Õ╗║ń»ēŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃĆé

µ£¼ķż©Ńü«Õģ©µÖ»ŃĆĆ’╝łµŁŻķØóŃü½ÕåÖŃéŗŃü«Ńü»ÕŹŚÕīŚµŻ¤’╝ē
µ£¼ķż©Ńü«Õģ©µÖ»ŃĆĆ’╝łµŁŻķØóŃü½ÕåÖŃéŗŃü«Ńü»ÕŹŚÕīŚµŻ¤’╝ē

µ®¤ĶāĮµĆ¦Ńā╗ÕÉłńÉåµĆ¦Ńā╗Õ«¤ńö©µĆ¦ŃéÆĶ┐Įµ▒éŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüÕ£░Õ¤¤Ńü«µĢÖĶé▓ŃéƵŗģŃüåÕŁ”µĀĪÕ╗║ń»ēŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ©üÕÄ│µĆ¦Ńā╗ķćŹÕÄܵƦŃā╗Ķ▒ĪÕŠ┤µĆ¦ŃéÆÕéÖŃüłŃü¤µäÅÕīĀŃü¦ŃüéŃéŗŃĆ鵤▒ŃéÆ’╝ōķÜÄŃüŠŃü¦Õż¢ÕŻüŃü½ķ£▓Õć║ŃüĢŃüøŃĆüµ£ĆõĖŖķā©Ńü«ŃāæŃā®ŃāÜŃāāŃāłŃéÆÕ╣ģÕ║āŃüÅÕĖ»ńŖČŃü½Ńü©ŃéŖŃĆüÕŻüķØóŃéłŃéŖŃééŃüøŃéŖÕć║ŃüŚŃü”µ░┤Õ╣│µ¢╣ÕÉæŃü«Õ║āŃüīŃéŖŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńÄäķ¢óŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬õĖĖń¬ōŃéÆŃüżŃüæŃĆüĶ╗ŖÕ»äŃüøŃü«µ¤▒Ńü»Õå嵤▒Ńü©ŃüŚŃĆüŃéóŃé»Ńé╗Ńā│ŃāłŃéÆŃüżŃüæŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤
ÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤

µĢÖÕ«żŃā╗Õ╗ŖõĖŗŃü«Õć╣ÕćĖŃéÆŃü¬ŃüÅŃüŚŃĆüµ¤▒ŃéÆ’╝ōķÜÄŃüŠŃü¦Õż¢ķā©Ńü½ķ£▓Õć║ŃĆüń£¤ÕŻüķĆĀŃéŖķó©Ńü©ŃüŚŃĆüÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü»ŃĆüĶ”ŗõ╗śŃüæŃü«ń┤░Ńüäķ╗ÆÕĪŚŃéŖŃü«’ĮĮ’Šü’Į░’ŠÖ’Į╗’Į»’Į╝ŃüÖŃü╣ŃéŖÕć║ŃüŚŃü«ńĖ”ķĢĘń¬ō’╝łńÅŠÕ£©Ńü»’Į▒’ŠÖ’ŠÉ’Į╗’Į»’Į╝Õ╝ĢķüĢŃü½µö╣õ┐«’╝ēŃü¦Õ×éńø┤Ńü«ńĘÜŃéÆÕżÜńö©ŃüŚń½ŗõĮōµä¤ŃéÆÕć║ŃüÖŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüķ½śŃüĢŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃĆéÕĪöÕ▒ŗķā©ÕłåŃü½Ńü»ŃĆüŃéóŃé»Ńé╗Ńā│ŃāłŃü©Ńü¬ŃéŗŃéóŃā╝ŃāüńŖČŃü«ń¬ōŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕż¢ķā©ŃĆĆĶ╗ŖÕ»äŃüøķā©Õłå
ńÄäķ¢óÕż¢ķā©ŃĆĆĶ╗ŖÕ»äŃüøķā©Õłå

ńÄäķ¢óÕåģŃā╗Õż¢ķā©Ńü«ÕŻüķØóŃü»ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣ĶŻĮŃü«Ńé┐ŃéżŃā½ŃüīĶ▓╝ŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüµö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦µ¢░Ńü¤Ńü½ńä╝ŃüŹńø┤ŃüŚŃü¤ŃééŃü«ŃéÆõĮ┐ńö©ŃĆéŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃééŃāÉŃā¬ŃéóŃāĢŃā¬Ńā╝Ńü½µö╣õ┐«ŃĆüÕ║ŖŃü«õĖĆÕ░║Ķ¦ÆŃü«ĶŖ▒Õ┤ŚÕ▓®Ńü»ÕåŹÕł®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéõĖĖń¬ōŃü«õĖŗŃü«ÕŹŖÕååÕĮóŃü«ķēäµĀ╝ÕŁÉŃü»ŃĆüõĮōĶé▓ŃéÆĶŻĖĶČ│Ńü¦ĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¤µÖéõ╗ŻŃü«ĶČ│µ┤ŚŃüäÕĀ┤Ńü«ÕÉŹµ«ŗŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéõ╗ŖŃü»ŃééŃüåµ®¤ĶāĮŃüŚŃü¬ŃüäŃüīŃĆüŃāÜŃāĆŃā½ŃéÆĶĖÅŃéĆŃü©µ░┤ŃüīÕć║Ńéŗõ╗ĢńĄäŃü┐ŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆé

ńÄäķ¢óÕåģķā©
ńÄäķ¢óÕåģķā©

õĖĖń¬ōŃü»ŃéóŃā½Ńā¤ŃéĄŃāāŃéĘŃü½µö╣õ┐«ŃüĢŃéīŃü¤ŃüīŃĆüńÄäķ¢óŃü«µ×ĀŃü©ŃāüŃā╝Ń黵ØÉŃü«µēēŃĆüÕ║ŖŃü«Ńé┐ŃéżŃā½Ńü©õĖŖŃéŖµĪåŃĆüÕ╗ŖõĖŗŃü«Õ║ŖŃü«ń£¤ķŹ«ńø«Õ£░ŃéÆÕ¤ŗŃéüĶŠ╝ŃéōŃüĀõ║║ķĆĀń¤│ńĀöÕć║Ńü»Õ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü«ŃüŠŃüŠŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéõĖĖń¬ōŃü©ńÄäķ¢óŃüŗŃéēķŻ»ńøøÕ▒▒Ńüīµ£øŃéüŃéŗŃéłŃüåŃü½Ķ©ŁĶ©łŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµ¼äķ¢ōŃü«Ńé¼Ńā®Ńé╣Ńü©ŃĆüÕźź’╝Ƶ×ÜŃü«µēēŃü«’╝öķÜģŃüīķØóÕÅ¢ŃéŖŃüĢŃéīŃü¤ÕÄܵØ┐Ńé¼Ńā®Ńé╣ŃééÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤1FÕ╗ŖõĖŗ
ńÄäķ¢óŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤1FÕ╗ŖõĖŗ

Õ╗ŖõĖŗŃü«Õż®õ║ĢŃü«µóüŃü»ŃéóŃā╝ŃāüńŖČŃü½ŃāćŃéČŃéżŃā│ŃüĢŃéīŃĆüńø┤ńĘÜńÜäŃü¬Õ╗║ńē®Ńü«ŃéóŃé»Ńé╗Ńā│ŃāłŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéÕīŚÕü┤Ńü«õĖŁÕ║ŁŃüŗŃéēµ¤öŃéēŃüŗŃü¬ÕģēŃüīÕĘ«ŃüŚĶŠ╝ŃéĆŃĆé

ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕīŚµŻ¤2EÕ╗ŖõĖŗ
ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗÕŹŚÕīŚµŻ¤2EÕ╗ŖõĖŗ

Õż®õ║ĢŃü«µóüŃéäķ¢ōõ╗ĢÕłćÕŻüŃü«ŃéóŃā╝ŃāüŃü«ÕĮóńŖČŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüķÜĵ«ĄŃü«µēŗµæ║ÕŻüŃéäń¼Āµ£©ķā©ÕłåŃü½Ńééµø▓ńĘÜŃüīńö©ŃüäŃéēŃéīŃĆüÕż¢ķā©Ńü«ńø┤ńĘÜńÜäŃü¬ŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüÕåģķā©Ńü»Õä¬ńŠÄŃüĢŃéƵä¤ŃüśŃüĢŃüøŃéŗŃĆéķÜĵ«ĄŃüŗŃéēµēŗÕēŹŃüīõĖƵ£¤ÕĘźõ║ŗķā©ÕłåŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéÕ╣│µłÉŃü«µö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦ŃĆü’╝ÆķÜÄŃā╗’╝ōķÜÄŃü«Õ║ŖŃüīķģŹńĘÜŃā╗ķģŹń«ĪŃü«Ńü¤ŃéüŃüŗŃüĢõĖŖŃüÆŃüĢŃéīŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüØŃü«ÕłåŃĆüÕ╗║Ķ©ŁÕĮōµÖéŃéłŃéŖŃééÕż®õ║Ģķ½śŃüĢŃüīõĮÄŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

ÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü«ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«ż
ÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü«ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«ż

õĖƵ£¤ÕĘźõ║ŗŃü¦Õ«īµłÉŃüŚŃü¤ńŠÄĶĪōµĢÖÕ«żŃü»’╝ÆķÜÄÕīŚĶź┐Ńü½ŃüéŃéŖŃĆü’╝ōķÜÄķā©ÕłåŃéÆÕÉ╣µŖ£Õż®õ║ĢŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéÕīŚÕü┤Ńü«ķ¢ŗÕÅŻŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅŃü©ŃéŖŃĆüÕ«ēÕ«ÜŃüŚŃü¤ÕģēŃéÆÕÅ¢ŃéŖÕģźŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńŠÄĶĪōŃéóŃāłŃā¬Ńé©ŃéÆÕ╝ĘŃüŵäÅĶŁśŃüŚŃü¤Ķ©ŁĶ©łŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüõĖĆķā©Ńü«Õ░éķ¢ĆĶ¬▓ń©ŗŃéÆķÖżŃüäŃü”ŃĆüŃüōŃü«ń®║ķ¢ōŃü«Ķ▒ŖŃüŗŃüĢŃü»ÕĮōµÖéŃü¦Ńü»Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®õŠŗŃéÆĶ”ŗŃü¬ŃüäŃééŃü«ŃüĀŃüŻŃü¤Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃĆéµĪ£Ńü«µÖéµ£¤Ńü»ń¬ōŃüīĶŖ▒Ńü½ŃüŖŃüŖŃéÅŃéīŃü”ńŠÄŃüŚŃüäŃĆé

ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆĆ’╝ÆķÜĵØ▒ń½»Ńü«µĢÖÕ«ż
ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆĆ’╝ÆķÜĵØ▒ń½»Ńü«µĢÖÕ«ż

µĢÖÕ«żŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃü»ŃĆü’╝öķ¢ōX’╝Ģķ¢ōŃéÆÕ¤║µ£¼Ńü½ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆéÕ«żÕåģŃü»ń¤│ĶåÅŃāŚŃā®Ńé╣Ńé┐Ńā╝õ╗ĢõĖŖŃüÆŃü©ŃüŚŃĆüŃé╣Ńā®Ńā¢ŃéäµóüÕ×ŗŃü½ńø┤µÄźÕĪŚŃéŖõĖŖŃüÆŃü”ŃüäŃü¤ŃĆéµóüŃü»µ¤▒Ńü«õ╗śŃüæµĀ╣Ńü¦ŃāÅŃā│ŃāüŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅŃü©ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗŃü¦Õ║ŖŃéÆŃüŗŃüĢõĖŖŃüÆŃüŚŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüń¬ōõĖŗń½»ŃüīõĮÄŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆéµØ▒Õü┤Ńü«ń¬ōŃüŗŃéēŃü»ŃĆüķŻ»ńøøÕ▒▒ŃüīĶ”ŗŃüłŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕēŹŃü«µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆé
ńÄäķ¢óÕēŹŃü«µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆé

ńĘæĶ▒ŖŃüŗŃü¬Õ║ŁÕ£ÆŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµŻ¤ŃéÆĶ”ŗŃéŗŃĆéÕÅ│µēŗŃü»ÕīŚÕü┤µØ▒Ķź┐µŻ¤ŃĆéµ£¼ķż©Ńü«Ķ©łńö╗µÖéŃü½Ńü»Õ║£Ńü«Ķ▓Īµö┐ķøŻŃü«ńŖȵ│üõĖŗŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńü¤ŃéüŃü½ŃĆüńĄÉµ×£Ńü©ŃüŚŃü”Ńé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝ŃāłŃü«ÕŹśń┤öŃüĢŃéÆŃüØŃü«ŃüŠŃüŠÕĮóŃü½ŃüŚŃĆüµ®¤ĶāĮŃü©µ¦ŗķĆĀŃüīń┤Āńø┤Ńü½Õż¢Ķ”│Ńü½ĶĪ©ńÅŠŃüĢŃéīŃü¤Õ╗║ń»ēŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃĆé
ÕÉŹń¦░ Õż¦ķś¬Õ║£ń½ŗÕøøµóØńĢĘķ½śńŁēÕŁ”µĀĪµ£¼ķż©/ŃüŖŃüŖŃüĢŃüŗŃüĄŃéŖŃüżŃüŚŃüśŃéćŃüåŃü¬ŃéÅŃü”ŃüōŃüåŃü©ŃüåŃüīŃüŻŃüōŃüåŃü╗ŃéōŃüŗŃéō µēĆÕ£©Õ£░ Õż¦ķś¬Õ║£ÕøøµóØńĢĘÕĖéķøüÕ▒ŗÕīŚńö║ TEL/FAX HP http://www.osaka-c.ed.jp/shijonawate/ E-mail Õ╗║ń»ēÕ╣┤õ╗Ż µśŁÕÆī9’Į×11Õ╣┤ŃĆĆ/ŃĆĆ1934-1936Õ╣┤ Õ╗║ńē®ń©«Õłź ÕŁ”µĀĪ µ¦ŗķĆĀ ķēäńŁŗŃé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝ŃāłķĆĀ3ķÜÄÕ╗║ µ”éĶ”üĶ¬¼µśÄ 明治36年、小楠公ゆかりの地に、前身の大阪府立四條畷中学校が開校。本館は、昭和9年9月の室戸台風で講堂の倒壊や校舎の破損後,大阪府営繕課の設計により,昭和9年から11年にかけて2期に分けて建設。鉄筋コンクリート造の白亜3層の校舎は府下屈指のものであった。戦時中には陸軍造兵廠によりタールで迷彩が施された。白に再塗装されたのは、昭和28年になってからである。平成14年から16年に改修工事がなされた。 本館は片廊下の__| ̄型で、一期工事の長さ40Mの北側東西棟、2期工事の長さ30Mの南北棟と長さ83Mの南側東西棟からなる。 柱形を露わにした整然とした立面,玄関廻りの庇,円柱 や丸窓の意匠,室内廊下のアーチ状梁形などに特色がある。「質実堅牢」を旨としたモダニズム色の強い昭和初期学校建築の好事例。
µ¢ćÕī¢Ķ▓Īń©«Õłź ÕøĮńÖ╗ķī▓µ£ēÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī ŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃā¬Ńā│Ńé» Ķ”ŗÕŁ” Ķ”ŗÕŁ”õĖŹÕÅ» ÕéÖĶĆā 
-

Õż¦ķüōµŚ¦Õ▒▒µ£¼Õ«ČõĮÅÕ«ģ
Õż¦ķüōµŚ¦Õ▒▒µ£¼Õ«ČõĮÅÕ«ģŃü»ŃĆüŃéÅŃüīÕøĮµ£ĆÕÅżŃü«ÕøĮķüōŃü©ŃééĶ©ĆŃéÅŃéīŃéŗń½╣ÕåģĶĪŚķüōŃü«µ▓┐ķüōŃü½Ńü¤Ńü¤ŃüÜŃéĆŃĆīŃüŗŃéäŃüČŃüŹŃü«ÕÅżµ░æÕ«ČŃĆŹŃü¦ŃĆüÕż¦ÕÆīµŻ¤ Ńü«ÕĮóµģŗŃéÆŃéłŃüŵ«ŗŃüŚŃĆüÕż¦ÕÆīŃü©ÕĀ║ŃéÆńĄÉŃüČŌĆ”
-

Õģēµ╗ØÕ»║
Ķ׏ķĆÜÕ┐Ąõ╗ÅÕ«ŚŃĆüõ╗źÕēŹŃü»Õż®ÕÅ░Õ«ŚĶŗźńÄŗÕ»║µ£½Õ»║Ńü¦ĶæøÕ¤Äõ┐«ķ©ōķüōŃü«ĶĪīÕĀ┤ŃĆéÕóāÕåģŃü½Ńü»µ£¼ÕĀéŃü©ńéŁńä╝õĖŹÕŗĢÕĀéŃā╗Õ║½ĶŻÅŃüīµ«ŗŃéŗŃĆéµ£¼ÕĀéŃü»Õ╗║µø┐ŃéēŃéīŃü¤ŃüīµĪüĶĪī4ķ¢ōÕŹŖŃĆüµóüķ¢ō3ķ¢ōŃĆüµŁŻķØóŌĆ”
-

Õż¦Õ┐ĄõĮøÕ»║µ£¼ÕĀé
Õ╣│ķćÄÕī║Õ╣│ķćÄõĖŖńö║Ńü½ŃüéŃéŗĶ׏ķĆÜÕ┐Ąõ╗ÅÕ«ŚńĘŵ£¼Õ▒▒Õż¦Õ┐ĄõĮøÕ»║Ńü«µ£¼ÕĀéŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéńÅŠÕ£©Ńü«µ£¼ÕĀéŃü»Õ»øµ¢ć’╝ōÕ╣┤Õ╗║Ķ©ŁŃüĢŃéīŃü¤µ£¼ÕĀéŃüīµśÄµ▓╗31Õ╣┤Ńü½ńä╝Õż▒ŃüŚŃü¤ÕŠīŃĆüµśŁÕÆī13Õ╣┤’╝ł193ŌĆ”
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

µŚźµ£¼µ░æÕ«ČķøåĶÉĮÕŹÜńē®ķż©
µŚźµ£¼µ░æÕ«ČķøåĶÉĮÕŹÜńē®ķż©Ńü»ŃĆüĶ▒ŖõĖŁÕĖéŃü«µ£Źķā©ńĘæÕ£░Ńü½ŃüéŃéŖŃĆüµŚźµ£¼ÕÉäÕ£░Ńü«õ╗ŻĶĪ©ńÜäŃü¬µ░æÕ«ČŃéÆń¦╗ń»ēÕŠ®ÕģāŃüŚŃĆüķ¢óķĆŻµ░æÕģĘŃü©ÕÉłŃéÅŃüøŃü”Õ▒Ģńż║ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼µ£ĆÕłØŃü«ķćÄÕż¢ÕŹÜńē®ķż©Ńü©ŃüŚŃü”µśŁŌĆ”
-

ÕÉŹµØæķĆĀĶł╣µēĆÕż¦ķś¬ÕĘźÕĀ┤ĶĘĪÕ£░’╝łŃé»ŌĆ”
ÕīŚÕŖĀĶ│ĆÕ▒ŗŃü»µ£©µ┤źÕĘØŃü«µ░┤ķüŗŃéÆÕł®ńö©ŃüŚŃĆüÕż¦µŁŻµÖéõ╗ŻŃüŗŃéēķĆĀĶł╣µźŁŃüīńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃü¤ŃĆéÕÉŹµØæķĆĀĶł╣µēĆŃü»µśŁÕÆī6Õ╣┤(1931)Ńü½Õż¦ķś¬ÕĘźÕĀ┤(µŚ¦µØæÕ░ŠĶł╣µĖĀÕĘźÕĀ┤)ŃéÆń©╝ÕāŹŃĆéµ£©µ┤źÕĘØŌĆ”
-

Õż¦ķś¬Õż¦ÕŁ”õ╝Üķż©’╝łµŚ¦Õģ▒ķĆܵĢÖĶé▓µ£¼ŌĆ”
µŚ¦ÕłČµĄ¬ķƤķ½śńŁēÕŁ”µĀĪµĀĪĶłÄŃü©ŃüŚŃü”Õż¦ķś¬Õ║£Õ¢Čń╣ĢĶ¬▓Ńü«Ķ©ŁĶ©łŃĆüÕż¦µ×ŚńĄäŃü«µ¢ĮÕĘźŃü¦ŃéŁŃāŻŃā│ŃāæŃé╣Ńü«õĖśŃü«õĖŖŃü½Õ╗║Ķ©ŁŃüĢŃéīŃĆüÕĪöÕ▒ŗõ╗śŃüŹ4ķÜÄÕ╗║Ńü”Ńü«ÕŹŚµŻ¤Ńü½3ķÜÄÕ╗║Ńü”Ńü«ÕīŚµŻ¤ŃüīńČÜŃüÅLŌĆ”
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

Õ»Čµ«┐ńź×ńżŠ
Õ»Čµ«┐ńź×ńżŠŃü»ŃĆüÕ«żńö║µÖéõ╗Żµ▓│ÕåģÕ«łĶŁĘĶüĘŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ńĢĀÕ▒▒µ░ÅŃü«Õ▒ģÕ¤ÄÕ░ÅÕ▒▒ńĀ”(µ┤źÕĀéÕ¤ÄÕ▒▒ÕÅżÕó│)ŃüŗŃéēŃü┐Ńü”ķ¼╝ķ¢ĆŃü«õĮŹńĮ«Ńü½ŃüéŃüŻŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüŃüØŃü«Õ«łĶŁĘńź×Ńü©ŃüŚŃü”ÕēĄÕ╗║ŃüŚŃü¤Ńü©õ╝ØŃüłŃéēŌĆ”
-

µĄģķ”ÖÕ▒▒ńŚģķÖóńÖĮÕĪöŃĆüĶź┐ńŚģµŻ¤
µĄģķ”ÖÕ▒▒ńŚģķÖóŃü»ŃĆüÕż¦µŁŻ11Õ╣┤’╝ł1922Õ╣┤’╝ēŃü½ÕĀ║Ķä│ńŚģķÖóŃü©ŃüäŃüåń▓Šńź×ń¦æŃéÆõĖŁÕ┐āŃü©ŃüÖŃéŗńŚģķÖóŃü©ŃüŚŃü”Ķ©Łń½ŗŃüĢŃéīŃĆüµśŁÕÆī35Õ╣┤’╝ł1960Õ╣┤’╝ēŃü½ńĘÅÕÉłńŚģķÖóŃü©Ńü¬ŃéŖńÅŠÕ£©ŌĆ”
-
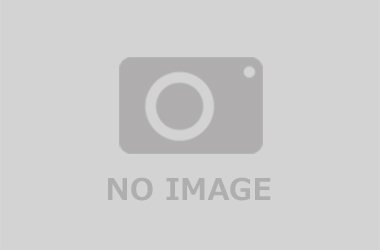
ÕŹŚµ£©ńź×ńżŠ
ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×